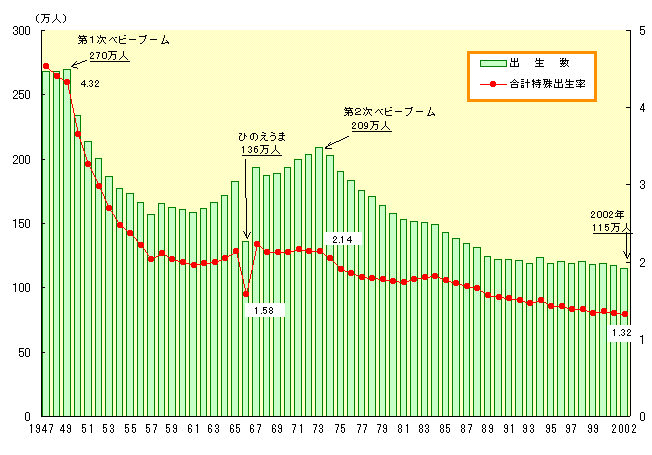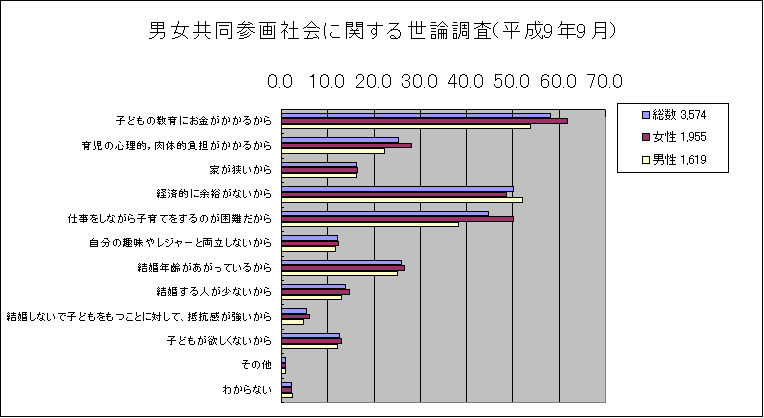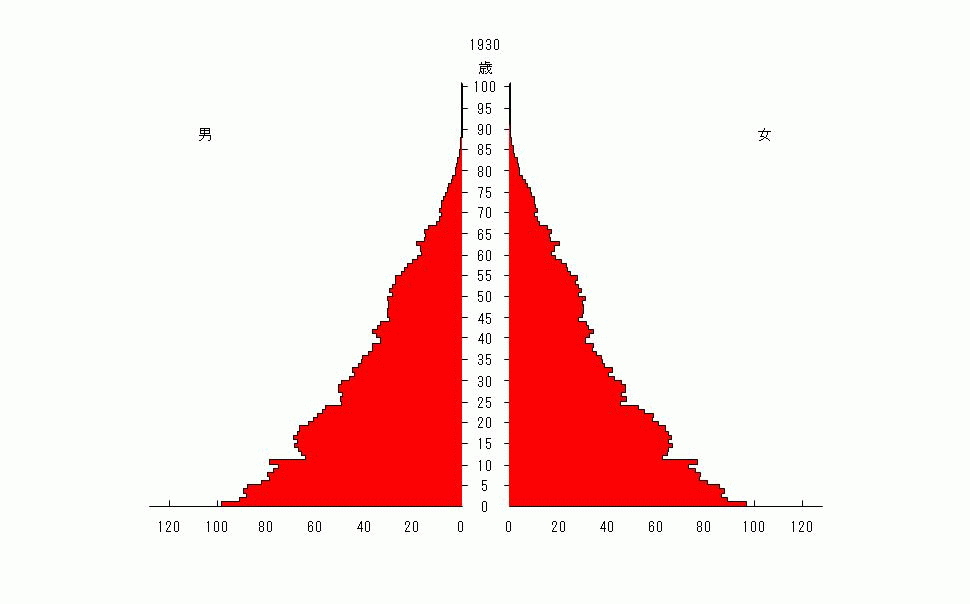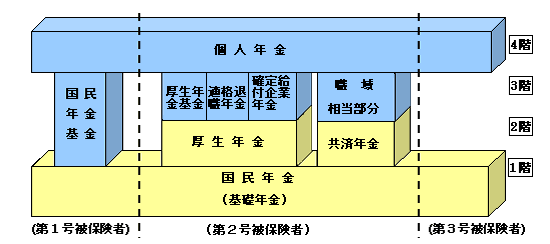THEME 少子高齢化社会を生き抜く
CASE 年金制度の在り方について

松浦
・ 章立て
初めて少子高齢化について知ったのは、小児科を開設する病院が近年少なくなってきているというニュースを通じてであった。その時は医療分野だけの問題だと考えていたが、少子高齢化が実は多岐にわたって社会に大きな影響を及ぼすものであるということが、その後新聞を目にしたり、人から話を聞いたことでわかってきた。その問題の中で一番興味をそそられたのが年金についての問題だった。年金はもらえなくなるのではないか。そんな噂を耳にしていたからだ。そこで私は、少子高齢化がわが国のこれまでの社会保障制度の根幹である年金制度に及ぼす影響を分析して、わが国の近年の年金制度改革の動きを研究し、将来に対するビジョンを養いたい。
第一章 少子高齢化社会到来
第一節 出生率の低下
それではまず日本において少子高齢化がどのように進んできたかを検証する。1970年頃の合計特殊出生率(一人の女性が生涯に出産する子供数の平均値のこと)は2.1を上回っていた。合計特殊出生率に関して、一組の夫婦から二人以上の子供が生まれてはじめて人口はその水準を維持できる。実際には、生まれてくる子供のうち早い段階で死亡する人がいたり、成人後も子供を産まなかったり、または産めなかったりする人がいるため、人口水準に必要な水準は2.07となっている。
1970年頃の出生率は人口を維持していくのに問題のない割合といえよう。この合計特殊出生率が75年には2を割り込んで、以降年々低下しつづけている。そして、95年には1.42まで低下し、2002年にはさらに1.32まで低下し続けた。
下記の図Aを参照にしてもらいたい。実際に生まれる出生率は、1960年の丙牛のときが136万人と極端に少なかったのだが、70年には193万人となっており、当時はだいたい190万人くらいであった。66年の丙牛時の合計特殊出生率は1.58だった。そして70年には2.13。しかしその後出生率の低下に伴い、出生率も95年には約119万人と丙牛のときをさらに下回る状況となった。
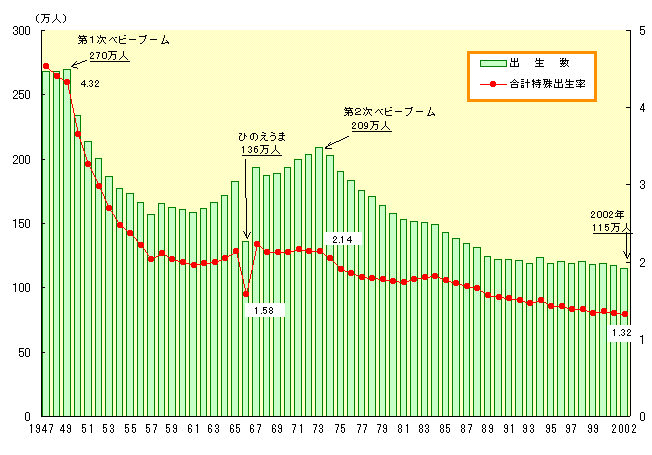
国立社会保障・人口問題研究所によると、合計特殊出生率について、2010年あたりまで低下し続け、その後反転して穏やかに上昇していき、2030年の1.61で、以降横這いで推移すると見られている。
ではなぜここまで出生率が低下したのか。人口問題研究所の「男女共同参画社会に関する世論調査(平成9年)」から男女が子供の数を求めない理由を探ってみる。
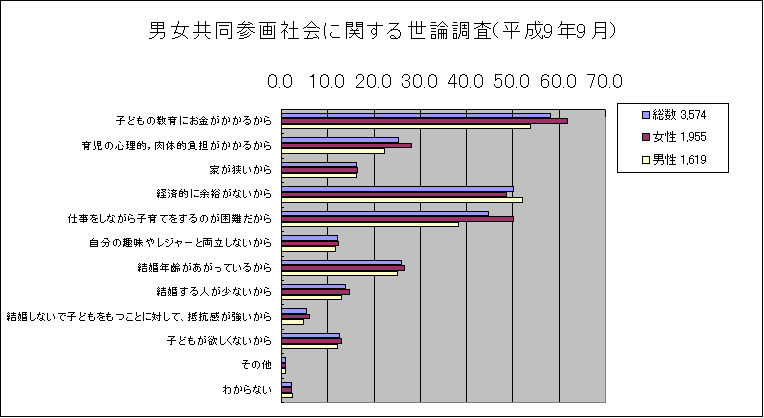
理由として、「子どもの教育にお金がかかるから」(58.2%)や「経済的に余裕がないから」(50.1%)、「仕事をしながら子育てをするのが困難だから」(44.7%)などの指摘が多くなっている。これからわかるのが、日本社会が農耕社会からサラリーマン社会に移行して、学歴社会になり、家族において育児費用が大きな負担になってきているということだろう。さらに不景気がその負担に拍車をかけている。また、「仕事をしながら子育てをするのが困難だから」は多くの女性が挙げている。これから女性の自立化が読み取れる。学歴社会化、経済成長の停滞、女性の社会進出。これら3つが絡む日本の社会構造の変化が、出生率の低下に結びついていると思われる。
第ニ節 高齢化水準の上昇
こうした出生率の低下は高齢化の水準を上昇させる。高齢化の水準を65歳以上人口の比率で見ると、日本は95年の14.6%から急速にその値を高め、2015年には25%を上回るようになり、4人に1人が65歳以上ということになる。その後もその比率は上昇し続け、2025年には27.4%、2038年には30%を超え、2050年には32.3%まで上昇する。このように、21世紀初頭には4人に1人、21世紀の中頃には約3人に1人が65歳以上という高齢社会になることが見込まれている。(全人口の中に占める65歳以上人口が7%を超えた社会を高齢化社会、14%を超えた社会を高齢社会という。この定義は1950年代、国連が国を分類する際に提示したもの)
先進国はいずれの国も高齢化は進んでいるが、これは経済成長による生活水準の安定化、医学の進歩によって長寿化が進み、出生率の低下する中で起こっている。そして、その高齢化の水準は、まさに出生率の動向に関わってくる。
日本の高齢化の水準が特に高いのみならず、その高齢化のスピードが極めて速いという特徴があります。65歳以上人口比率が10%から20%に高まるのにかかる時間を見ると、日本は21年だ。これを他国と比較すると、ギリシャやイタリアでも43年かかっている。日本は、この半分の期間で高齢化が進んでいる。倍のスピードである。
日本の高齢化が急速である理由は、団塊の世代が2005年頃にかけて高齢層に移行していくのに相まって、ここ20年くらい出生率が断続的かつ大きく落ち込んでいるところにある。
第三節 逆さま人口ピラミッド出現
こうして日本の人口形態は大きく変わった。人口問題研究所が作成した動く人口ピラミッドを見てみる。
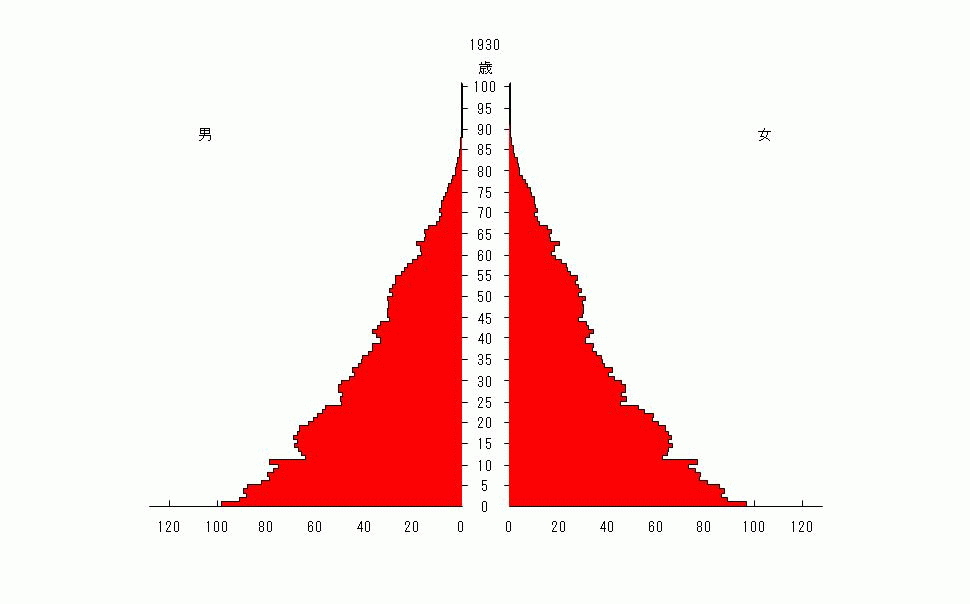
この図は1940年から始まっている。1940年代~1970年代あたりまで完全にピラミッドを形成している。しかしそれ以降、そのピラミッドが、先に述べた出生率の低下からくる少子化、そしてその少子化が起因となる高齢化により崩れ、逆さま状態のピラミッドになっていってしまっている。
こうした人口形態は、家族・家庭、消費、教育、経済・産業構造、土地・住宅、年金・社会保障、雇用・労働などといった社会経済に幅広く、そして大きな影響を及ぼすことが予想される。
これらの少子高齢化において一番興味を抱いている問題が、序章の研究動機でも触れたとおり「年金」だ。次章では少子高齢化が日本の年金政策にどんな影響を及ぼしているのかを検討する。
第二章 年金危機
第一節 日本の年金制度の概要
日本の年金制度は国が全国民を対象として運営する公的年金(下記の図の1階、2階部分)と、国以外が運営の主体となる私的年金(3階部分)に分けられている。
まず、公的年金には、20歳以上60歳未満の全国民が加入する国民年金、企業の従業員が加入する厚生年金、そして公務員等の共済年金があり、老後の収入源として中心的な役割を果たしている。
私的年金には、まず企業がその従業員を対象とする企業年金がある。企業年金には、主として適格退職年金と厚生年金基金があり、内部積立を利用した退職一時年金制度とともに、従業員の老後の生活をより豊かにすることを目的に設けられている。
次に個人が任意に加入する制度として、生命保険会社、銀行、郵便局など、各種金融機関で販売されている個人年金(4階部分)、契約要件を満たせば非課税措置が受けられる財形年金、また、自営業者等が任意に加入する国民年金基金(2階、3階部分)があり、個人がそれぞれの自助努力で老後に備えるものとして近年関心が高まっている。
日本の年金体系の全体像は次の図で表すことができる。
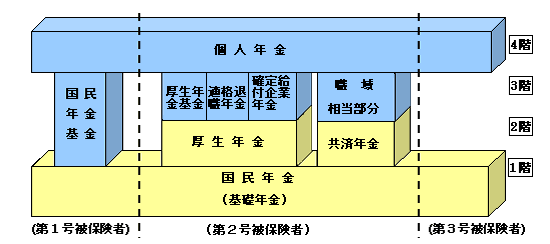
自営業者、学生などの第1号被保険者は1階部分の国民年金しかないので、2階、3階部分に相当する年金として、任意加入の国民年金基金制度が設けられている。ただし、第3号被保険者であるサラリーマンの妻は国民年金基金に加入することができない。
民間のサラリーマンの場合は全部で四階建てになっていて、3階部分が企業年金全部分にあたる。
ちなみにアメリカでは、個人年金を自助努力と見なし、公的年金、企業年金、自助努力の三つを[three-legged stool(三本足)」と呼んでおり、それぞれがバランスよく老後の生活を賄うことが理解されている。
第二節 年金危機
(ⅰ)公的年金
公的年金制度は、老後の生活の拠り所として非常に重要なものだ。高齢者世帯の平均的な内訳を見てみると、総所得の50%以上が公的年金あるいは恩給によるものとなっている。また、公的年金や恩給を受給している高齢者世帯のうちほぼ半数は、それ以外の収入がない、つまり年金(恩給)のみが唯一の収入源であるという世帯になっている。
このように老後の生活にとって公的年金はもはや欠くことのできない存在となっているが、少子高齢化の進展が、この公的年金制度に深刻な影響を及ぼしつつあり、年金財政破綻が危惧されている。
公的年金制度の仕組みには、「積立方式」と「賦課方式」という二つの方法がある。積立方式では、現役世代の支払う保険料が将来の年金給付の原資となる。一方、賦課方式とは、現役世代の保険料がそのまま現在の高齢者の年金として支払われる制度だ。
日本の年金制度は基本的には賦課方式で運営されている。つまり、現在の高齢者の年金は現在の現役世代の保険料から支払われている。こうした制度の下では、少子高齢化が進むと、第一章で触れたように少数の現役世代で多くの高齢者を支えることになるため、年金の給付水準を維持するためには、現役世代の保険料を大幅に引き上げる必要が出てくる。このため、若い世代にとっては、支払った保険料に見合う年金が受け取れなくなってくる可能性が出てくる。
実際のところ、厚生省による厚生年金についての試算によると、世代が若くなるにつれて、年金の受取総額に比べて保険料支払いのほうが多くなってしまうという結果が示されている。例えば1944年生まれの世代は、年金の受取総額が保険料の支払総額より3200万円多いのに対し、1948年生まれの世代は保険料支払いがほうが1000万円も多くなることが予測されている。
保険料のほうが支払いが多くなるのでは、年金を支払う意味がない。本末転倒だ。私たち若年層はこのまま国民年金を始めとする公的な年金制度に身を任せつづけてもいいのだろうか?
(ⅱ)企業年金
では、公的年金に頼れないなら企業年金に頼ればいいのだろうか。
先の公的年金制度を揺るがしている理由として、少子高齢化以外に、不況によってもたらされる低金利、株価の低迷が挙げられる。公的年金制度では保険料全てを高齢者に支払っているわけではなく、小部分ではあるが、積立をし運用させている。だから運用時に低金利、株価低迷が大きく影響するのだ。しかし、これらの要因は公的年金よりむしろ企業年金に大きく影響する。
企業年金は、企業が従業員のために掛け金を拠出し、それと掛金(積立資産)の運用益などをあわせたものによって、将来、退職した従業員に支払う年金を賄うしくみだ。とくに、運用益が占める比重が大きいということ点が、公的年金とは異なる。
企業年金では、将来の年金給付額は、あらかじめ定められた運用利回り(予定利率)を前提に約束されているため(これを確定給付型という)、掛金の実際の運用利回りが(予定利率を下回って)低下すると、企業は負担する掛け金を上げてその分の穴埋めを迫られることになる。1992年度以降、実際の運用利回りが予定利率を下回る年が多かったことから企業の掛金負担は確実に増大している。
バブル崩壊後、このような負担に耐えられず企業年金が解散・廃止に追い込まれ、従業員への年金の分配が十分に行われないというケースも出てきている。
また、株式市況の低迷は、企業年金の積立資産の含み損を増大させていて、これも企業にとっては大きな問題となる。
第三節 公的年金改革の難しさ
こうした状況をうけて、政府も何もしないわけではない。しかし、公的年金制度改革は難しい。
公的年金改革は二つの側面に分けられる。一つは給付額を抑制すること。もう一つは保険料を引き上げること。
保険料を引き上げることは、先にも述べたとおり、保険料が給付額より多くなる可能性がでてくるので、制度破綻を招きかねない。すると必然的に改革は給付額の抑制へと目が向く。
2000年改正では給付額の抑制を調整することが決まった。具体的な抑制策は①報酬比例部分の給付水準を5%適正化する、②支給開始後、65歳以降の年金は原則として物価スライドのみで改定し、賃金スライドをしない、③厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢を60歳から段階的に65歳へ引き上げる(具体的には2013年度から2025年度にかけて3年に一度づつ)、④65歳から69歳までの在職老齢年金を導入する、の4つだ。
厚生年金支給開始年齢を65歳へ引き上げることについてはそう簡単にやっていいものなのか。現在の日本では、定年を設定している会社では定年を60歳に義務づけている。ここで気づくことは、厚生年金支給が65歳になれば、定年した60歳から5年間、所得において空白の期間ができる可能性があるということだ。
このように、年金改革は社会保障の問題だけでなく、労働問題にも関わってくる。非常に複雑で難しい問題だ。
第三章 日本版401K始動
第一節 401Kとは何か
日本の代表的な企業年金である厚生年金基金や適格退職年金では、将来の年金給付額が報酬や勤続年数をもとに一定の計算式により予め決められている確定給付型しか認められていない。これに対して、掛金とその運用益によって将来の年金給付額が事後的に決まる制度を確定拠出型という。確定拠出年金は近年米国の401Kが有名。2001年10月からその401Kをモデルとした日本版401K(確定拠出年金)が導入された。
確定拠出型年金は、①企業が制度を導入し、その従業員が加入する企業型年金と、②自営業者等で国民年金の保険料を納付している人(すなわち免除者、未納者以外)や、他の企業年金(厚生年金基金や適格退職金等、以下同じ)及び企業型年金に加入していない企業の従業員が加入する個人型年金がある。加入対象者の年齢は、いづれも60歳未満となる。また、①、②の条件に該当しない人、つまり、公務員や国民年金の第3号被保険者、あるいは他の企業年金の加入者で、その勤務先が企業型年金を導入しなかった企業の従業員は、確定拠出年金に加入することができない。
第二節 確定拠出型年金と確定給付型年金の違い
確定拠出型年金と確定給付型年金の違いを見てみる。
「確定拠出型年金と確定給付型年金の対比」
| |
確定拠出型年金 |
確定給付型年金 |
| 運用リスク |
従業員が負担 |
企業が負担 |
| 従業員勘定 |
あり |
なし |
| ポータビリティ |
あり |
なし |
| 在職中の引き出し |
あり |
なし |
| 従業員の掛金拠出 |
あり |
なし |
| 従業員の投資先選択 |
あり |
なし |
| 年金数理計算 |
不要 |
必要 |
| 未積立債務のB/Sへの計上 |
不要 |
必要 |
第三節 日本版401K導入の経緯
(ⅰ)アメリカでの401Kの成功
成功の要因は二つある。一つは401Kのサービスが優れていることだ。
401Kの制度事態は企業がつくり、従業員が申し込んで<従業員勘定(個人口座)がつくられる。従業員勘定には、従業員が掛け金を拠出する。さらに企業が上乗せで拠出するのが一般的であり(法律的には企業の拠出は任意)、大きな魅力となっている。
拠出金は従業員が自己責任で運用して増やしていく。運用メニュー(投資商品)は企業によって3種類以上提供される。3種類とは、リスク・リターンの異なる商品(元本確保の安全度や利回りの高低が異なる商品)出なければならない。従業員は運用メニューの中からポートフォリオを組んで(商品を組み合せて)運用する。
401Kの最大の特徴は手厚い優遇課税にある。従業員の掛け金は税引前給与からの天引きで拠出され、給付時まで課税がされない(課税の繰り延べという)。さらに、企業の拠出金と投資した運用益も給付時まで課税繰り延べされる。
退職貯蓄の観点から、一般的には59.5歳より前に引き出すと通常の課税(20%の源泉徴収)に加えて、10%のペナルティ課税がある。
401Kは個別勘定なので、転職時には持っていくことができる(ポータビリティがあるという)。転職先に401Kがない場合や独立する場合、退職後などには、IRA(個人退職勘定)を個人で開設して移管できる。いずれも課税繰り延べのまま移管できる。
米国の401Kの3つの特徴。
・課税優遇:
受給するときまで拠出金や運用収益が課税されない(課税繰り延べ)
・自助努力と自己責任:
自分の口座(個人勘定)を持ち、自己責任で資産を運用する
・ポータビリティ(携帯性):
転職したときには積立金を転職先に移管できる
もう一つの要因は、社会経済構造にあった。
アメリカには日本と同様ベビーブーム世代がいる。1946年から1964年にかけて生まれてきた人たちのことで(日本の場合ベビーブーマはこれほど長期間に渡っていない)、米国民3分の1にあたる7700万人にも上る。この世代が次々に老後準備を始める時期となり、自助努力による退職資金の確保が大きなテーマとなった。このようなときに登場したのが401Kだった。課税優遇といった内容が知られるにつれ、ベビーブーマー世代の退職資金の受け皿として急膨張するようになり、今日までの勢いは衰えていない。
80年代後半には、確定給付型年金制度を維持することが困難になり、401Kに移行する企業が増えたことも、401K拡大に拍車をかけた。
こうして動きがさらに相乗効果をもたらすことになる。投資信託を通して401Kプランの資金が株式市場に大量に流れ込み、株価の上昇を支えたといわれている。1984年には550億ドルだった401Kプランの資産残高は、98年には1兆ドルに達している。そしてそれに合わせてダウ平均も1050ドルから8000ドルに上昇しているのだ。
投資信託の普及は株式と加入者の垣根を低くし、投資対象としての株式の比率を高めた。投資信託は運用をプロに任せられて安心な点や分散投資の商品として向いていることに加え、高利回りの運用実績のファンド(投資信託の商品)が大々的に宣伝されたことにより、老後の資金づくりを急ぐ世代に受け入れられた。
(ⅱ)日本版401Kに対するニーズの増大
主に6つの理由が挙げられる.
①公的年金危機:
先にも述べているが少子高齢化社会という構造変化のもとで制度が成り立たなくなってきている。
②企業年金積み立て不足の深刻化:
企業年金の運用利回りの低下により多額の積立金不足が発生している。
③企業経営の悪化:
長引く不況で企業業績が低迷し、維持コストの安い企業年金が求められている。
④国際会計基準の導入:
2000年4月からの導入により年金債務が企業会計に影響を及ぼさない企業年金が求められている。
⑤雇用構造の変化による流動化の広がり:
転職が一般化しつつある雇用環境に合った新しいタイプの企業年金の必要性
⑥株式市場の活性化:
日本版401Kプランの導入で年金資金を株式市場に流し込み、低迷を続ける株式市場の活性化を期待
以上主な6つの理由で日本版401Kのニーズが高くなっていった。
第四章 401Kプラン導入事例
第一節 日商岩井の場合(401Kと前払い併用)
この章では実際に企業が401Kプランを導入した事例を取り上げ、その機能を検証していきたい。
日商岩井は2002年4月、厚生年金基金を解散し、401Kを中心とする新しい退職金・年金制度を導入した。新制度は401Kと退職金前払い制度の2本立てで構成されている。従来の退職金は退職一時金と厚生年金基金で構成され、両者の比率は基金が2で一時金が1の割合だったが、新たに厚生年金基金部分を401Kに移行し、退職一時金部分は前払い制度に移行している。
401Kと退職金前払い制度は選択制ではなく、全従業員に適用されます。入社後、401Kは個人で運用することになるが、入社後3年以上経過しないと受給権は発生しない。したがって3年以内に退職した場合は積み立てた金額は没収される。
また、401Kの給付は60歳以降だが、給付形態は一時金、5年~20年有期年金、終身年金の3種を用意し、この3種のいずれかもしくは3種の組み合わせを選択できる。同社は運用年金商品の選定と提示に関する運用関連業務を行う運営管理機関を自社で実施している。
制度の運用においては、前提として旧退職金制度の60歳定年時の退職金(退職一時金+基金の年金一時金)水準相当が確保されるように設計している。運用商品は12種18商品。同社独自の判断で定期預金などの元本確保型商品からインデックス型商品、株式・債権型の幅広い商品を取り揃えている。確定拠出型年金の拠出額と前払い退職金の支給額はここの従業員によって異なる。金額は従来の制度で規定しているポイントテーブルを準用。入社時点は10ポイント付与され、以降基本的に入社年次でポイントが増加し、上限は18ポイント。これに2000倍を乗じた額が毎月の拠出額となり、つまり10ポイントで2万円、18ポイントは非課税限度枠の3万6000円となる。
具体的には22歳標準で10ポイント付与され、28歳ぐらいで17ポイント、23歳で上限の18ポイントに到達する。同社の退職金年金制度は安定的な老後の資金の確保という観点から、ポイント制といっても年功的な支給形態になっている。ただし、拠出される金額は同期社員では同じであっても、運用の仕方によって当然ながら受け取る金額は個人によって異なる。
前払い退職金の支給額は基本的にはポイントテーブルと連動し、昇格に応じて支給額が決まる。具体的には22歳入社時点で毎月1万円を支給し、以降昇格するごとに支給額が上がっていく仕組みだ。前払い退職金は毎月給与に上乗せして支払われる。
第二節 日本オラクルの場合(401K全面移行)
コンピューターソフト大手の外資系企業日本オラクルは従来の税制適格年金を廃止し、企業年金を全面的に401Kに移行した。変更した理由は大きく分けて3つある。
一つは従来から進めてきた退職年金の成果主義をもう一歩進め、賃金の後払いとして退職金から、成果に応じた現金払いにしようというものだ。
第二は、転職しても年金の持ち運びができるポータビリティを生かし、人材の流動化に対応しようというものだ。
第三は年金債務の防止だ。同社は平均年齢も約32歳と若く現段階では退職給付債務の負担は小さいのだが、いずれ従業員の勤続年数の上昇とともに年金債務は腫れあがる可能性がある。そうした将来発生する年金債務を事前に防止するという狙いもある。
2000年10月に、従業員代表を集めて説明会を開催。導入に向けた準備をスタートした。
制度対象者は全員従業員だが、401Kへ加入するか、あるいは現金で受け取る「前払い」かの選択ができるようにしている。
同社の401Kへの拠出額は「基準年棒×3.7%」で決まる。運用商品は全部で13本。そのうち元本確保型は2本だ。元本確保型商品から国内株式型のハイリスク・ハイリターン商品まで取りそろえている。
商品を提供する取り扱い金融機関も銀行系、証券系、外資系など運用会社の集中を避けるとともに、第三者機関による格付けでもっとも評価の高い商品を選んだという。また同社の場合、老後の年金に自社単独の株式ファンドを提供するのは良くない、という理由であえてこれを外している。
401Kの実施にあたり、401Kか前払いかの選択を社員に求めたところ、401Kを選択した従業員が4分の3を占めた。
具体的には全従業員1500人のうち、過去の税制適格年金の積み立て分と将来分は401Kに移行した人が50%、すべてを前払いにした人が25%となっている。
この結果には同社自身予想だにしなかったことであり、驚いているという。従業員の商品への投資の割合は当初元本確保型は11%だったが、現在は15%と比率が上がっている。401Kでの給付を実際に受け取るのは60歳以降だが、この結果からは若年世代も老後の年金に対する関心が強いことがわかる。
第三節 すかいらーくの場合(401K+独自年金)
すかいらーくは2002年1月に日本で初めて401Kを導入した。同社では、401Kを通称MAP(My active aging plan)と呼んでいる。
これまでの年金・退職金制度は退職一時金、税制適格年金、それに業界団体でつくる厚生年金基金の3本で構成されていたが、そのうち税制適格年金と一時金の2本をMAPに移行した。
将来は確定給付型年金と退職一時金で、同社の算出したモデル退職金額の8割弱、残りを厚生年金が占めていた。
60歳で受け取る年金・退職金の内訳は2000万円のうち、税制適格年金1000万円、一時金760万円、厚生年金基金が240万円。このうち大半がMAPに移行するが、問題なのは厚生年金基金を残したために企業の非課税拠出限度額は21万6000円(月額1万8000円)しか制度上認められていない。その結果、従業員が一定年齢を超えると会社の拠出額が非課税枠を超えてしまうことになる。
そこで同社は非課税枠の拠出額を「第一口座」、限度額を超える部分を運用するため「第二口座」を設け確定拠出年金を二つに分けている。ただし第二口座の401K分は前払い方式となり、第一口座と違い、途中で引き出すことが可能だ。
同社の運用商品は11種類ある。商品選定においては、主幹事の証券会社やメインバンクの商品に制約されずに、従業員が不利益を受けないようにベストな商品を選択したということらしい。
第一口座の運用商品は11種類。元本確保型の定期預金やミドルリスクタイプの債権型投資信託、ハイリスクの株式型投資信託などを取りそろえている。
また、401Kに移行しても、従来の退職金と受け取る金額がそれほど変わらないことを、従業員に具体的に説明している。
同社の試算では勤続38年従業員の場合、会社の拠出金総額は1170万円。元本確保型の0.05%(定期預金型)で運用した場合、受取総額は約1200万円。3%運用で約1800万円、5%運用で約2500万円になる。現行の確定給付型の総計約2000万円を維持するには、厚生年金基金の240万円を加えるため、3%運用であれば可能だとしている。
第五章 少子高齢化社会を生き抜く
第一節 401Kへの期待
第二章で見たように公的年金、企業年金ともに従来の制度では、いづれ破綻してしまう可能性が高い。保険料を払いつづけ、結局給付をもらうことができなくなってしまうというケースが十分に考えられるのだ。
401Kはアメリカにおいて急伸した。その一つの理由として、株式市場に投資信託を介して401Kの資金が流入し、株価を高めていったところにあった。そして、その背景にあったのがベビーブーマーたちの老後準備だった。大量の401K資金が彼らから放出された。
日本では今まさにベビーブーム世代である50代の人たちが老後を目の前にしている。彼らの多くが401Kを採択すれば、アメリカと同様な景況を実現できるかもしれない。2001年に日本版401K導入されてから、平成15年7月まで企業型年金を導入した企業は455社、個人型年金に加入したのは19、089人。全体の数字から見ればまだまだ増える余地がありそうだ。
401Kにおいてやはり運用リスクがあるから、それで避けてしまうという人も多々いるだろう。しかし、国の年金制度は、人口ピラミッドを見てもわかるように、対処のしようがほとんどない。検討して練りだされた改革案の一つで、厚生年金の支払額を段階的に65歳に引き上げているが、それでは60歳前半の所得獲得はどうすればいいのか。シビアになった経済界で高齢者を雇うほど余裕のある企業はあまりないだろう。結局、「自分」に頼るしかないのだ。それならば、大きなリターンが来る可能性のある401Kで老後の資金を蓄えていったほうがいいのではないか。
第二節 「自己責任」と「自助努力」のスタンスで
現在進行中の日本の少子高齢化社会のもとでは、どうやらわれわれは国や民間の組織に頼っていては生きていけない。個人が自立し、「自己責任」と「自助努力」のスタンスの下で、生きていかなければならない。401Kはそうしたスタンスを助長してくれる制度だ。
話を年金からそらせば、「自己責任」「自助努力」を促す動きを多くの企業がとり始めた。福利厚生の新しいシステムであるカフェテリアプランの導入、年俸制の導入などがそうだ。企業は厳しい競争の中で、従業員と対等な関係を求め始めた。対等な立場でいられる反面、われわれもリスクを背負って生きていかなければならない。「自己責任」と「自助努力」のスタンスを大事にし、生きていこう。
出典
「少子高齢化の恐怖を読む」三菱総合研究所
「少子化 5つの大罪」
「年金のしくみ」みずほ総合研究所
「図解でわかる 401Kプラン」年金問題研究会
「年金革命~老後資金運用の基本テク」溝上憲文
「現代の労働問題第3版」笹島芳雄
終章 研究を終えて
私が感じた日本
窓際の壁には「やると決めたら絶対やる。できなければ水かぶる」、パソコンには「タイムイズマネエ」。そう書かれた紙がそれぞれ張ってある。自分で書いて張ったものだ。自分の意志の弱さにムカついたときにそうした。
しかし、これらを書いて以降も、意志を貫けない、自分の弱さに負けるということは多々あった。今回のゼミ論もそうだし、政策科学の授業もそうだ。先延ばしなどの甘い考えにしばしば犯されていった。それは、他人に頼りすぎたり、また他人に甘えてすぎいるから、そういう生ぬるい人間になっているのかもしれない。しかし、このままの状態でいたら、100%これから社会に出て生きていくことができないだろう。この研究でそれを痛感した。
401Kだけではない。新しい福利厚生であるカフェテリアプラン、賃金体系の変化の現れである年俸制。今までの会社と社員の関係が大分変化したらしい。会社は社員を囲うことをやめた。社員は身動きが取りにくい、スレイブな状態から開放され、自由を得ることができるようになった。しかし、開放された先は大海原だ。得た自由は大海原での自由だ。八方向に舵をきることができる反面、常にリスキーな状態に置かれているのだ。多くの社会人は自立したかんがえを持ち、自己責任のもとに行動していかなければならなくなったのだ。
生ぬるい自分だからこの研究をしている途中、将来について何度も不安になった。でも、ああだ、こうだ、言ってられない。絶対にはちきれて頑張っていこうぜ、自分。