| 研究動機 |
|
私は喫煙者である。 だが、喫煙者では無い人達にとってみれば、喫煙者というのは、非常に迷惑な存在であるように思う。 したがって、法律で禁止されていない以上、喫煙者は各自が責任を持って、喫煙をしなければならない。 そのような事を考えていくうちに、 新聞を読んで、EUではたばこの広告規制を強化する動きがあること、アメリカや日本のメーカーはそれに反発していること、青森県深浦町ではたばこの自動販売機を撤去する条例を出したこと、などを知り、日本の現状は決して世界の常識でも無いし、変える事のできないものでもないことがわかった。 そこで私はEUの規制策を事例として、日本のたばこ規制政策のあり方を考えることにした。そうした考察を通じて、喫煙者としての責任を見つけられれば、と願う。 |
| 章立て |
| 第1章 | EUたばこ規制法 | 第1節:EUたばこ規制法とは? 第2節:日本のたばこ規制の現状と世界との比較 第3節:EUたばこ規制法の「可能性」について考える |
|---|---|---|
| 第2章 | たばこの歴史 | 第1節:たばこの発祥と普及 第2節:歴史から見たたばこの人文学的価値 第3節:日本のたばこ史と日本専売公社について |
| 第3章 | たばこの経済メカニズム | 第1節:たばこの経済的影響(損失) 第2節:たばこ税の意味 第3節:資本主義社会におけるたばこの役割 |
| 第4章 | たばこと健康 | 第1節:喫煙による体への害と警告文 第2節:たばこを吸う理由 第3節:間接喫煙の意味付け |
| 第5章 | たばこと政治 | 第1節:国内的側面から見たたばこ規制策 第2節:現在の日本におけるたばこ規制の問題点 第3節:国際的な側面から見たたばこ規制策 |
| 最終章 | 日本のたばこ政策のあり方 | ⇒EUのたばこ規制策を起点として、多方面にわたる要因の考察を総合しながら、 世界でも遅れていると言われている日本のたばこ規制策について考える。 |
研究の流れ
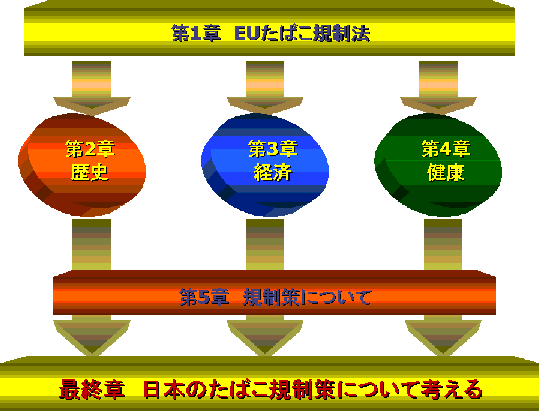
たばこ規制策をただ調べるのでは、ありきたりな研究しかできない。そこで最近EUで成立した「たばこ規制法」が、斬新なものであったので、そこを切り口にすれば、オリジナリティーあるたばこ規制策の研究ができるのではないかと考えた。それでは、そのEUたばこ規制法の斬新さとは一体何なのだろう?そもそも、EUたばこ規制法とは何だろう?という事を、この章で研究する。 第1節 EUのたばこ規制法とは? まずは、「EUたばこ規制法」の記事を紹介したい。 たばこによる健康被害を防ぐため、欧州連合(EU)の議会である欧州議会が5月15日に可決、成立した。たばこ会社に、包装箱の表側30%以上、裏側40%以上を割いて「たばこは死を招く」などの警告文の印刷を義務付けたほか、たばこ一本当たりのニコチン、タールなど含有量の許容値を定めた。タールの含有量は2004年以降、現行の12ミリ・グラムから10ミリ・グラムに減らすよう求めている。上記の記事からうかがえる、EUのたばこ規制法の主な点は、 ①たばこの警告文を厳しくする ②誤解を招くおそれのある、たばこの銘柄の禁止 ③タール・ニコチン含有量の規制 の3点であろう。 この3点において、現在たばこ業界は揺れている。上記の記述にもあるが、「マイルドセブン」の欧州での販売を予定しているJTは、現在抗議中である。たしかにたばこ産業側からしてみれば、大打撃になりかねない政策だろう。 しかし、たばこ規制策としてこのEUの決定を見てみると、これまでのたばこ規制策の壁(後述)を打ち破る「可能性」を秘めているのではないか。特に日本は、たばこの規制が遅れていると言われている。(次節参照)なおさら、このEUの規制策について注目をしてみる必要があるのではないだろうか。 第2節 日本のたばこ規制の現状と世界との比較 日本のたばこ規制が遅れているという主張は、日本の喫煙率の高さからうかがえる。世界保健機関(WHO)の最新の数値(2002年10月15日現在)を挙げると、日本の男性の喫煙率は52.8%であり、先進国の中では群を抜いている。またたばこの輸入量は年間835億本であり、これも群を抜いた高さであると言える。女性の喫煙率は13.4%で先進国(G7に限る)の中では最低を記録したものの、「たばこ大国」というイメージはいまだ払拭できておらず、ジュネーブで始まった「たばこ規制枠組み条約」の交渉においても、拘束力の強いたばこ規制策に対して日本は難色を示しているというのが現状である。 下記の表1とグラフを参考にしてもらいたい。日本における喫煙率は若干の減少をしているものの、目覚ましい減少は記録しておらず、他国に比べていまだに高い数値となっている。また、表2からもわかるように、20年前における喫煙環境(禁煙環境)は改善されてはいるものの、欧米諸国の規制の実態と比較してみると、日本はまだまだ遅れているのがわかる。 表1:日本と欧米諸国の喫煙率
グラフ:日本の喫煙率の推移 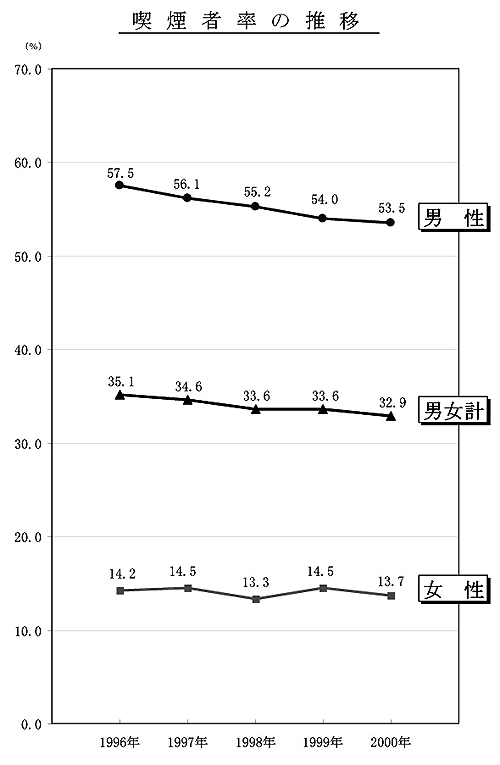 JTホームページより 表2:日本と欧米諸国のたばこ規制比較
第3節 EUたばこ規制法の「可能性」について考える これまでの日本のたばこ規制策は、健康面というあきらかに形となって現れる切り口からしか、なされていなかった。たとえば「健康に良くないので控えましょう」などのPRが主流であったことにうかがえる。だが、たばこがファッションや文化として成り立っている以上、いくら健康面への害を訴えても限界があるのではないだろうか。喫煙者がたばこを吸う理由の一つとして、「かっこいいから」などの精神的な一面がある以上、精神面からのたばこ規制が必要となってくると私は考えるのである。 この点においては、表現の自由における問題も絡んでくるものの、嫌煙者の権利を考える上では致し方ないと言えよう。 EUのたばこ規制法が、たばこのパッケージや銘柄にまで規制の範囲を伸ばすことは、たばこのファッション性や人々が抱くたばこへの価値観といった、精神面にまで規制をかけることができると言える。しかし残念ながら、今回のEUにおけるたばこの銘柄規制が、主に健康面への害を主張しているという点において、私の考えとは多少のズレがある。(もちろん、健康面への被害を訴えることが駄目だとか無駄だとは言っていない)だがたばこ規制法を考える上で、銘柄に規制をかけることは斬新なアイディアであることに違いはない。したがってEUのたばこ規制法を足がかりに、規制の幅を拡大していけるかもしれないという、たばこ規制策の今後の「可能性」がうかがえよう。 EUのたばこ規制法の可決によって、これまでの人々のたばこに対する考え方・姿勢を一変させる道ができた。この規制法を起点に、世界のたばこ規制はどんどん進んでいくものと思われる。したがって、日本におけるたばこの規制も、このEUのたばこ規制法を軸に、考え直してみる必要があるのではないだろうか。 たばこを取り巻く、歴史・経済・健康の3つの側面を考慮したのちに、政治的考察も含めながら、日本のたばこ規制策について本論で考えてみたい。
たばこの規制策について論じる上で、どうしてもこのたばこの歴史について触れてみたかった。なぜならたばこがこれだけ普及したのには、やはりそれだけの意味があるからだと考えたからである。この章はいわば本論とは対をなすような章となるが、そこに生じるパラドックスを見出せれば、と思う。 また、日本においてなぜこれだけたばこが普及したのかということにも疑問を持った。現段階において難航しているたばこ規制策の足がかりを作った、日本専売公社の実態とともに検討してみたい。 第1節 発祥と普及 たばこはアメリカで発祥した。タバコの葉がほとんどアメリカで発見されたからである。しかし、土地によって吸引方法はそれぞれ異なっていた。(吸引方法の種類の紹介は割愛)その後、スペインやポルトガル、オランダなどの侵略によってヨーロッパに伝わる。30年戦争などの国際戦争を経て、たばこ文化は拡大し、融合していったのである。 ここで注目してもらいたいのが、たばこが普及するにあたっての、たばこの役割である。 古代の人々の生活は、当然ながら自然の営みと一体のもので、人々は自然と共生し、自然を敬い畏れ、自然の中に神や精霊たちが宿ると信じていた。そして、神や精霊たちとコミュニケーションを図るためにシャーマンたちは、チョウセンアサガオ、メスカル、ピプタデニアなどのような幻覚性の強い様々な植物を利用していたが、タバコの薬理作用はこれらよりは遥かに穏やかなため、精霊たちの大好物、彼らへの最良の贈り物と考えられていた。アメリカ先住民のたばこの使用例についての報告やたばこに関する神話の中で圧倒的に多いのは、葉たばこやその煙を精霊たちに供えて彼らをなだめ、彼らから力を授かり、彼らの好意を当てにする、といったもので、こうした信仰は南北アメリカを通じて広く行き渡っていった。 上記のたばこの発祥・普及の記述からわかる通り、たばこはもともとアメリカで発祥し、歴史の過程において全世界に普及した。時代的には、大航海時代後の世界レベルでの貿易が開始された頃に普及されている。しかし、たばこは生活において必要なものだとか、直接的に何かの役に立つものだとは考えにくい。それではなぜ、たばこがこれほどまでに普及したのであろうか? 私は人々がたばこによって何を求めたのか、ということに注目してみたい。たばこはもともとアメリカにおいては、お供え物として扱われていたし、ヨーロッパにおいてもはじめは貴族階級においてもてはやされた。アジアにおいても薬として用いられた。 つまりたばこは、神々や貴族に対する羨望の一品などとして始まるが、時代を経て一般大衆のもとに普及し始めた頃から、たばこのイメージは悪くなり始めたものの、いつしか人々が社会への抵抗や現実からの一時的な逃避行を示すものとして、広まったのだろうと私は考える。そして現代においても、喫煙するという行為は若者にとっての一種の社会抵抗なのである。歴史において一貫しているたばこの役割とは、「安らぎ」なのかもしれない。そのような歴史的な過程を見ていくと、次節の人文学的価値が見えてくる。 ここで注意してもらいたいのだが、あくまで私はたばこの規制策について論じる立場の身であり、喫煙に対して肯定的な意見を述べるつもりはない。だが研究対象としてのたばこを語るうえで、一様に否定的な意見を述べてばかりいても、駄目だと思ったのである。たばこがこれほどまでに普及し、今日において規制が困難を極めるということには、それなりにたばこにも価値があると判断したのである。 第2節 たばこの人文学的価値 たばこ規制策の研究をするにあたり、様々なたばこ関連の本を読んだ。禁煙・嫌煙を主張する本が主流の中、なかには愛煙者の本もあった。それらを読んでいくうちに、愛煙者の主張やたばこの価値を見出すことも、スムーズなたばこ規制を行ううえでは必要なことなのではないだろうかと考えた。 たばこは古くから文化・芸能の小道具として用いられてきた。日本では浮世絵にも登場しているし、アメリカの映画では世をときめく俳優がたばこを吸っているシーンが多々登場する。たばこはそれほど文化と密接に歴史を歩んできたのである。 粉川宏氏は、『たかが、煙草 されどたばこ』(イーハトーヴ出版)において次のように語っている。 「たばこは、文学や演劇の作品でも、欠くべからざる小道具として生きているではないか。人生においても、である。」たばこが文化的価値を持つのだとすれば、喫煙者にとってのたばこは精神の領域にまで及んでいると言っていいだろう。極端に言えば、人が生死の境に常に存在していると仮定した時、喫煙という行為は明らかに死の方向に向かう恐れがあるにも関わらず喫煙者が喫煙をやめられないのは、一種のスリルを楽しんでいるからではないだろうか。死へのスリル、社会への抵抗のスリルが、喫煙者に非日常的な感覚をもたらし、たばこをいつしか「安らぎの一品」としている。そのような幻想的・自虐的な効果こそが、たばこが歴史的に文化と深く結びついた理由なのだろう。 そのように考えると、たばこの規制は形だけの外圧的なものでは無駄だといえる。 第3節 日本のたばこ史と日本専売公社 日本の喫煙率は現在、先進国の中でかなり高いものとなっている。このような高い喫煙率となった背景に、日本専売公社が関係しているのでないかと思い、調べてみた。これまでの日本のたばこ規制策が緩いこととも関係しているかどうかも検討してみたい。 現在の日本たばこ産業株式会社(JT)の前身が、日本専売公社である。昭和24年6月に発足した。その発足の背景は、明治時代にまでさかのぼる。明治9年に日本において、煙草税則というものが施行される。これはたばこに対して税金(営業税と印刷税)を課す目的のもであったが、時代が時代なだけに税金の徴収はうまくいかず、国家財政上、意義あるものとはならなかった。だが日清戦争を経て日本の国家財政は窮乏化したため、明治31年に葉煙草専売法が成立する。次第にたばこ税の国家財政に占める割合は拡大していき、日露戦争の勃発した明治37年に煙草専売法が施行された。戦争による支出が激しかったにも関わらず、地租以外の税収がほとんど見込めなかったこの時代に、国にとってたばこによる税収の意味はこの上なく大きかった。 このような仮定を経て、昭和26年6月に日本専売公社が発足する。公務員の労働関係と私企業従業者の労働関係との区別を明確にせねばならなかったこの時代に、日本専売公社は公共企業体(パブリックコーポレーション)という、極めて特異な性格を持つものとなった。終戦後の枯渇した税源において、たばこによる税収は必要なものであったというより、必要なものとしなければならなかった。このように国家目的が要求される以上、国家権力の強力な関与が必要となったのである。そこで、日本専売公社は国家行政組織法上の行政機関ではないものの、事業の国家性に基いて、一般民間の企業とは異なり、特別の制約を受けることになったのである。 日本専売公社が、上記のように国家による介入を受けたことで、たばこは国家による大衆支配の道具となった、とまでは言わないが、たばこが政治の舞台において重要な役割を担ったことは間違いない。このようなたばこと国家の密接な関係が、現在におけるたばこ規制策の諸問題を引き起こしたのである。だが、日本専売公社は民間企業JTとなり、事実上国家とたばこの関係はなくなったはずである。たばこによる税収ばかりを期待しながらの政治は、世界的に見て既に時代遅れのはずだ。先進諸国におけるたばこ税の意味はもはや、税収への期待ではなく、たばこの規制としての意味を持つものとなった。日本も、歴史的なたばこへの関与を早く振り払うべきなのではないだろうか。
第1節 たばこの経済的影響 たばこの値段は日本ではおよそ260円ほどである。この値段をドルに換算してみると、およそ2.47ドルとなる。この値段は、先進各国に比べて低いものである。下記グラフを参照していただければわかるが、イタリアを除くEUの各国はほとんど日本よりも値段は高く、約2倍の値段の国まである。 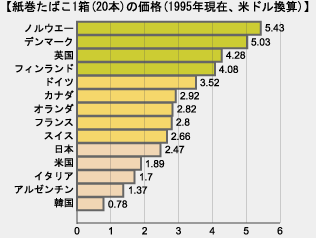
Yahoo!ヘルスケアのホームページより 約3200億本という日本のたばこの消費量を売上高に換算すると、約4兆円となる。これは世界でも第3位のマーケットであり、如何に日本が「たばこ大国」であるかを物語っている。安い値段ほど、消費は増える。この単純な公式はたばこにも当てはまり、現実にたばこの値段の低い国ほど、喫煙率・喫煙本数は少ないのである(下記表参照)。したがって、たばこの値段を吊り上げることが、たばこ規制への最短の道であることは間違いない。だが、日本においては、価格の変更はなかなか難しいものとなっている。その足かせとなっているのが、政府のたばこ税への依存やJTとの密接な関係という、矛盾した構造なのである。
第2節 たばこ税の意味 これほどの売上高を誇る巨大な市場ができあがったのは、第2章で書いたように、政府のたばこ政策によるものと思われる。1000本あたりのたばこには7072円の税金(下記表参照)、つまりたばこ税がかかっている。すると一箱当たり約141円の税金がかかっている計算になり、価格の約56%は税金ということになる。 これを単純計算し、いくらの税収が見込まれるかというと、約2兆3340億円である。ビールの税率が約47%である事を考えると、如何に政府がたばこ税を必要としているかがわかる。
だがこの税収は、実は皮肉な結果を物語っている。 というのも, 実はたばこが原因の病気による医療費は、この税収に迫る勢いなのである。1993年単年度だけで、たばこによる超過医療費は1兆2000億円(国民医療費全体の4%)にも上る。また、これを含む社会損失全体(たばこによる火災・火災保険、山火事、喫煙休憩による労働損失、道路・鉄道などの吸殻清掃に掛る費用など)は5兆4500億円ほどと予想されており、同年のたばこ税収をはるかに上回る額の経済的な損失が発生しているのだ。 世界銀行も、たばこの生産は、短期的には消費者と生産者にそれぞれ快楽と利益という便益を与えるが、長期的には医療費の増加と生産性の低下のため、世界経済に重大な損失がもたらされることから、たばこ生産に新たな貸付を行わないことを決定したほどである。 下記の表は、たばこが原因によるものと思われる病気の医療費の表である。1993年時点の表であるから、現在とは多少違うが、喫煙者の死亡者数は毎年増加傾向にあり、現在の医療費はこの医療費総額を上回り、1兆3000億円~4000億円ほどであると思われる。
このような数値から、たばこによる経済損失はたばこ税ではまかなえないということがわかる。少なくとも、今の税率では医療費をまかなうどころか、喫煙の抑制の効果もさほど期待はできない。目先の税収に期待しているのみのものである。本来ならば、医療費損失<たばこ税収 となるレベルまで税率を上げるのが最低ラインであろう。 ではなぜ日本ではたばこの値段が低い(=税率が低い)のであろうか。これには、アメリカを中心とする資本主義社会の目論見が絡んでくる。 第3節 資本主義社会におけるたばこの役割 日本におけるたばこ市場は、JT(日本たばこ産業)が中心となっているものの、民営化による専売制の廃止、そして輸入の外国たばこに対する関税の全面撤廃で、その優位性は失われつつある。外国たばこは日本市場で売上を伸ばしてきており、それに対してJTも競争心を燃やすことで、結果的に市場は拡大されてきた。実際1985年度には3108億本だったたばこ市場は、93年度には3326億本にまで拡大したのである。しかしながらそれ以上の飛躍的な伸びは無く、嫌煙ブームが世界で巻き起こっている中、JTは日本国内において経営の多角化を図るようになったのである。その一つとして、食品事業がある。 JTのこうした経営の動きは、アメリカにおけるたばこ会社のこれまでの動きと似ている。アメリカにおけるたばこ会社は、ほとんどが巨大多国籍企業である。世界に先駆けて「キャメル革命」(アメリカンブレンド革命)や「フィルター革命」を達成し力を付けていったアメリカのたばこ企業は、互いに国内市場で熾烈な競争を繰り広げながら、積極的に世界各地に進出を果たしていった。「TTCs」とは、たばこ多国籍企業群のことを指し、ほとんどがアメリカ・イギリスの会社であることから、資本主義社会の典型であると言っても過言ではない。このTTCは、各国に対してたばこ専売制の変質を求めていったのである。 日本においても、幾度かの段階を踏みながら、昭和62年4月に製造たばこの輸入関税はゼロとなったのである。そして輸入関税がゼロになった機会を捉え、TTCは売上を一挙に伸ばし、その後も着実に日本のたばこ市場を奪いつづけていくのである。 (外国たばこのシェアは昭和59年度2%であったのが、平成8年度には22%にも達している)まさに、アメリカを中心とする世界を作ろうとする、資本主義社会の典型ではないだろうか。 TTCはアメリカの政治にも影響を及ぼす力を持っている。(その力で各国の輸入関税撤廃を達成してきたわけだが)この政治への圧力は、アメリカにおいてもたばこ規制への障害となっており、議会におけるたばこ規制の法案はまず通らないことが多い。しかし、アメリカ国民における禁煙・嫌煙ブームの煽りを受けて、このTTCも事業の多角化を図るようになったのである。それが、食品事業などであった。 だがTTCは巨大多国籍企業なので、本業であるたばこ販売は、アメリカを飛び出し経済的に貧しい国において進める方針を取っている。まさに「現代の死の商人」と言われる所以ではないだろうか。経済的に貧しい国では、教育が進んでいない事もあり、たばこが害のあるものであるという認識が低い。もちろん政府側も規制策はまだ打ち出していないので、TTCにとっては恰好の市場というわけだ。 JTは、こうしたTTCの戦略をも踏襲している。アジア各国では日本のたばこが売られており、「マイルドセブン」は人気も高い。 したがって、一国の喫煙率やたばこ販売本数が減ったからと言って、単純にたばこの規制が成功しているとは言い難い。たばこ会社の戦略こそが、たばこ規制の障害となっているからだ。実際、たばこ会社から議会の議員への献金はあるし、他国への戦略に関しては自国の政府は何も言えない立場である。政府とたばこ会社の密接な関係は、国の発展に欠かせないものであったかもしれないが、たばこ規制を推進するという観点からは、完全に矛盾したものとなってしまっている。
現在日本で販売されているたばこには、上記の注意書きがたばこの箱に記載されている。また、タール・ニコチンの含有量の記載も義務付けられており、最近ではそれらの数値の低いたばこが人気を集めている。これらの記述や数値ははたして、たばこの規制へとつながっているのかどうかをこの章で調べたい。 第1節 喫煙による体への害と警告文 たばこの煙にはニコチン、種々の発がん物質・発がん促進物質、一酸化炭素、種々の線毛障害性物質、その他多種類の有害物質が含まれています。 喫煙により循環器系、呼吸器系などに対する急性影響がみられるほか、喫煙者では肺がんをはじめとする種々のがん、虚血性心疾患、慢牲気管支炎、肺気腫などの閉塞性肺疾患、胃・十二指腸潰瘍などの消化器疾患、その他種々の疾患のリスクが増大します。 妊婦が喫煙した場合には低体重児、早産、妊娠合併症の率が高くなります。また、受動喫煙により肺がん、虚血性心疾患、呼吸器疾患などのリスクが高くなることも報告されています。 低ニコチン・低タールたぱこの喫煙により健康影響はある程度軽減されますが、肺がん、虚血性心疾患などのリスクは非喫煙者に比べると依然高率です。 たばこによる体への影響(害)は、テレビや新聞などを通して広く知られるようになってはいるものの、具体的な知識に欠けるものが多い。単純に「体に悪い」という認識のみが広まり、「どう体に悪いのか」「どのような影響が予想されるのか」といったことまではあまり知られていない。 たばこの箱に記載されている注意文(上記参照)からも、その曖昧さはうかがえる。海外ではたばこの箱に記載される警告文には様々なものがある。たとえば、カナダの警告文の例を挙げてみよう。
|
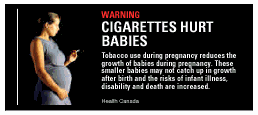 「喫煙は胎児を傷つける」
「喫煙は胎児を傷つける」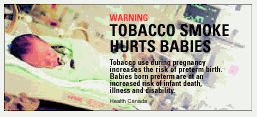 「たばこ煙は赤ん坊に害を与える」
「たばこ煙は赤ん坊に害を与える」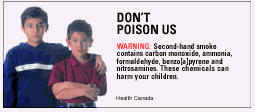 「僕達に毒をもらないで」
「僕達に毒をもらないで」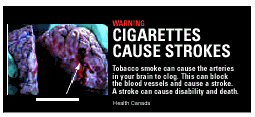 「たばこは卒中の原因になる」
「たばこは卒中の原因になる」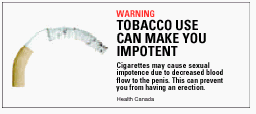 「たばこでインポテンツになる可能性がある」
「たばこでインポテンツになる可能性がある」 「喫煙は歯周病や口内の病気を引き起こす」
「喫煙は歯周病や口内の病気を引き起こす」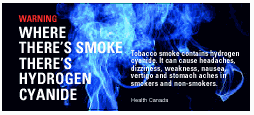 「たばこ煙のあるところに、青酸ガスがある」
「たばこ煙のあるところに、青酸ガスがある」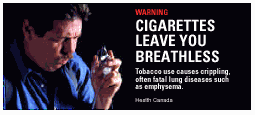 「喫煙はあなたを呼吸困難にする」
「喫煙はあなたを呼吸困難にする」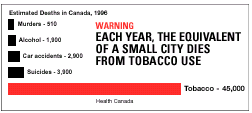 「毎年たばこによって小都市の人口に匹敵する人数が死亡する」
「毎年たばこによって小都市の人口に匹敵する人数が死亡する」