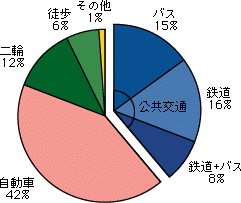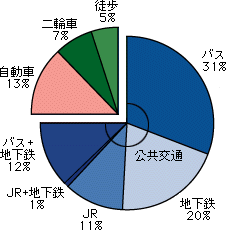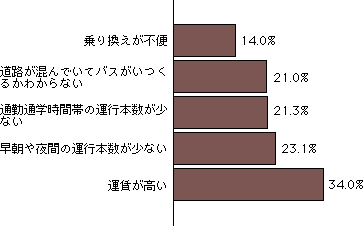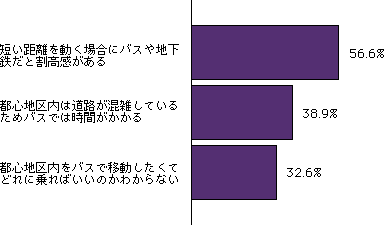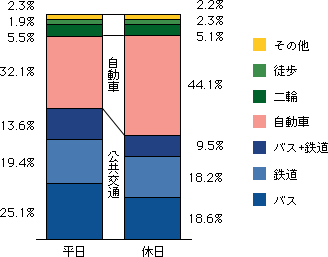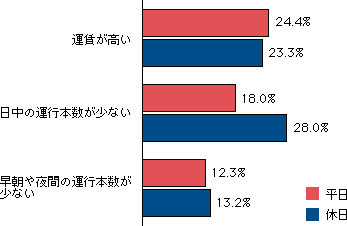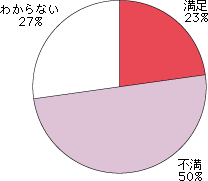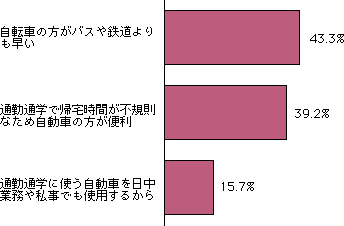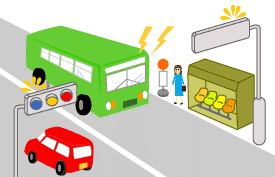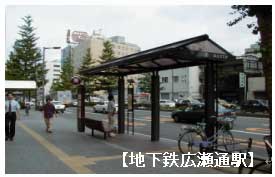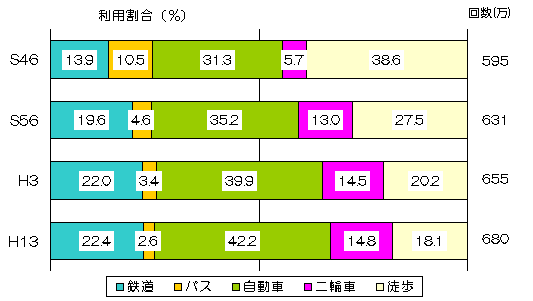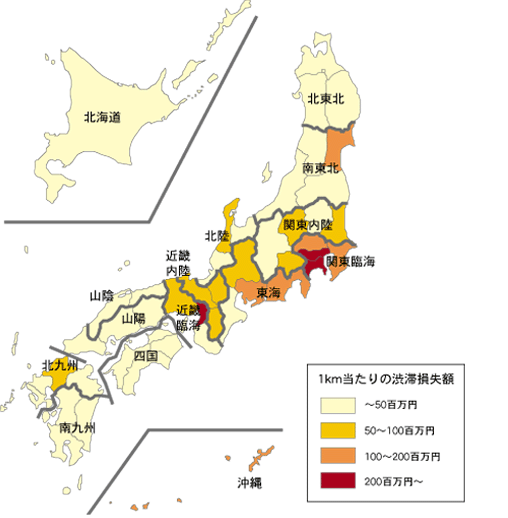
| 順位 | 都道府県名 | 1Km当たりの損失額 (百万円/年間) |
| 1 | 東京都 | 435 |
| 2 | 大阪府 | 338 |
| 3 | 神奈川県 | 237 |
| 4 | 埼玉県 | 171 |
| 5 | 愛知県 | 152 |
| 6 | 千葉県 | 128 |
| 7 | 沖縄県 | 115 |
| 8 | 静岡県 | 108 |
| 9 | 宮城県 | 104 |
| 10 | 京都府 | 95 |
宮城県は全国48都道府県の中で第9位である。
関東圏が上位を占めるが、人口の統計と道路営業キロ数、車両台数の伸びと 合わせて比較するとそれらと同じくらいひどい渋滞都市の顔を見せる(後述) 余談であるが、全国平均は6200万、最も渋滞損失額が低い県は1800万の岩手県である。
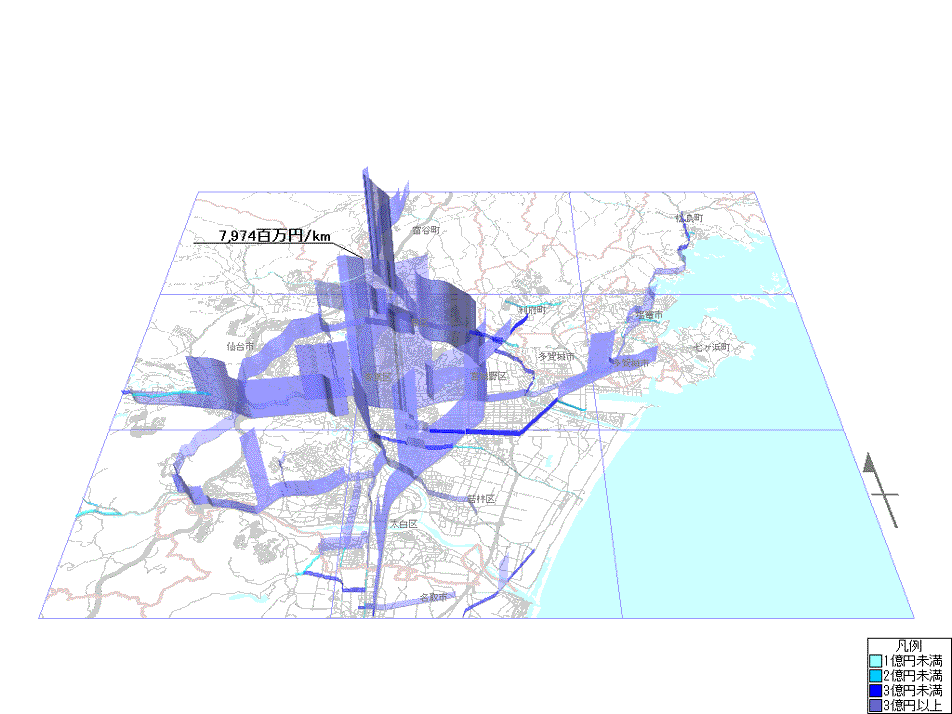
図2-B 仙台市の渋滞損失額3Dマップ
道に色と高さをつけることで損失額を表す3Dマップである。
南北と東西を走る2本の道路を基軸に市の中心街に渋滞が集中していることが よくわかる。仙台市の都市構造は次の節でのべることにして、まずはこの都市が 全国でも有数の渋滞都市であることを押さえてもらいたい。
第二節 渋滞の原因
ここではまず、仙台市の都市構造について大まかに見てみよう。 仙台市は全国で第11番目の政令指定都市で人口は約100万人(平成12年国勢調査による)、 市の中心部は仙台駅周辺であり、ここには県庁や市役所などの行政地域、 オフィスや商店街・国分町などの商業地域が密集している。その周囲を囲むように、泉中央、長町、愛子、原町などを中心に広大な 郊外区域があり、マンションや一戸建て住宅が広範囲に渡っている。(下図参照)
図1-C 仙台市の航空写真に路線図をのせたもの。(上が北) 中心部は、 仙台駅を中心に行政・商業地域となっており、市の「中枢」となっている。その周囲には、 「副都心」や「地域中心拠点」という形で、泉中央(北)、長町(南)、 原町(東)、愛子(西)がある。それらの 周囲には広大に市街・住宅地が広がっており、鉄道の通っていない地域まで広範囲に広がっている。 鉄道上の点は駅で、中心部を中心に東西に伸びている黄色の点線は「東西線」のルート案。
(「みんなで考える仙台の都市計画」より抜粋し、一部を加工)
都市構造の特徴は他にもあるが、話を簡単にするためここでは 中心部と郊外との関係について考えていきたいと思う。 郊外に住んでいるたくさんの住民は、色々な事情で中心部との間 を移動する。バスや鉄道が使える地域ではそれらを使う人もいるが、それを使わない 人や使えない地域の人は当然クルマを使うことになる。ここで注目したいのが「バス や鉄道が使える地域の人でも車を利用する人がいる」という点である。
仙台市の公共交通の利用人員は年々減少の一途をたどっている。市営バスは平成 6~10年度実績で利用人員数19%減、乗車料収入7%減、 南北線地下鉄は乗車人員0.2%増、乗車料収入13%増。 さらに平成11~14年度実績では市営バス利用人員14%減に加え 南北線地下鉄も5%減という惨憺たる状況である。
・市営バス利用状況
・地下鉄南北線利用状況(共に仙台市統計情報より)
その理由の1つとしてあげられるのが料金体系である。 JRの初乗料金が130円であるのに対し、地下鉄南北線は200円(開通当時は160円だった)、 図1-AにもあるようにJRと比べ市営地下鉄は駅間も短く、料金に対する市民の不満は多い。 こうした料金体系の理由は地下鉄建設の赤字経営という市の運営にあり、東西線問題 の根幹を担う重大な問題である。これについては第三章で触れる。
さらにもう一つの理由として渋滞による市営バスの遅延があげられる。 仙台の中心街のほうでは時刻表通りにバスが到着することはめったにない。
そしてワールドカップが行われた利府市(仙台市に隣接している)、イタリア代表が キャンプ地として選んだ北部の泉パークタウンなど、市街地や公共施設の拡大&郊外化が 公共交通より利便性の高い自動車の増加に拍車をかけている。
以上のことから仙台市では、通勤時の交通渋滞によるバス遅延と馬鹿高い料金体系が マイカー利用の増加を引き起こし、更にそれがバス遅延の日常化を 招くという「渋滞悪循環」が起こっていると考えられる。 市街地の郊外化はその悪循環を増幅し、結果として公共交通機関の利用率が低迷し、 公共交通機関の機能が効率的かつ十分に発揮されない状況にあるのである。
・渋滞悪循環を図示したスライド
第三節 市の渋滞認識にいたる経緯
市の行政は市議会を通してその方針が決定される。道路交通問題の場合、市議会 議員の問題への言及をきっかけに、交通局やシンクタンク(総合研究所)などが 調査(前述した走行速度調査など)を行い、対策を立てていく。
そこで市議会議事録や調査結果などを総合して、市が東西線建設を決めるまでに 至った渋滞現状(1987年〔昭和62年〕の地下鉄南北線開業~現在)を示したい。 第一節ではおおまかに実態を示したが、ここでは数値やデータによる客観的な 視点から述べる。
(1)仙台市の車両事情と自動車交通の問題点
仙台市の人口と車両台数についてみてみると、一人当たりの台数は平成元年の 0.34台から平成8年0.43台と増えている。また、道路延長 と車両台数を台数当たりの道路延長と比較すると、平成元年の9.59mから 平成8年には7.61mと車両台数の伸びが道路整備を大きく上回っ ていることがわかる。
また、札幌市、仙台市、広島市、福岡市で道路延長と車両台数の伸びを比較(平成2年と平成8年) すると、車両台数では仙台が1.33で最も高く、道路延長でも1.06と札幌等と並んで高い。
交通事故についてみると仙台市は平成2年と平成7年の比較では車両台数が1.21と増えているの に対して、交通事故の増加は1.04と少なく、仙台近郊と比べても低い水準となっている。 渋滞ポイントは平成4年の26カ所から平成9年の27カ所と微増にとどまっている。 またDID内の一般国道での平均旅行速度を昭和60年、平成2年、平成6年で比較すると、 平成2年より若干上昇しているものの、宮城県内では昭和60年の約9割、仙台市内では約8割 の15.5㎞/hとなっており、交通状況が悪化していることがわかる。さらに平成9年には泉中央~ 都心間が13㎞/h、長町~都心間が11㎞/h となっており、仙台市内の渋滞状況の深刻さを示している。
(2)鉄軌道系交通の利用状況と沿線人口
都市交通研究会の新しい交通システムによると、鉄軌道系交通機関は他の交通機関に比べてエ ネルギー消費量、排気ガス量ともに優位にあることがわかる。
そこで、昭和63年から平成8年までの仙台市の人口と仙台市内におけるJR・地下鉄南北線の 1日当たりの乗車人員を比較すると平成5年以降緩やかにはなっているが増加傾向が継続している。
また、仙台駅を中心として3㎞圏内、5㎞圏内、7㎞圏内、7㎞圏外の乗車人員を比較すると 3㎞圏内が最も多く、離れるほど乗車人員は少なくなっている。乗車人員数の推移は3㎞圏 内、5㎞圏内が類似した傾向をもっており、平成4年以降伸びは緩やかになり、平成6、7年 をピークに減少傾向となっている。これとは対照的に7㎞圏内では継続して高い伸び率を維 持しており、増加傾向が続いている。 しかし平成11年以降乗車人員の数は減少の一途を たどっている。
(3)公共交通機関の現状
バスの運行体系をみると、地下鉄が開通した当時と現在を比較すると、鉄道沿線の仙台市 の郊外を走行する路線が削減され、一方で錦ヶ丘や泉パークタウンなどの新興住宅地に路 線を伸ばしている。また、バスの最終時刻もサービス向上のため地下鉄開業当初と比べて概 ね30分以上の繰り下げが実施されている。
昭和57年から平成4年までの10年間のJR線(東北本線・仙山線・仙石線)のアクセス手段の 変遷を調査すると、全体的に自家用車でのアクセスが増加し、徒歩・二輪車、バスでのアクセ スが減少傾向にあり、都心部では自動車利用が減ってきている。これは、鉄道駅までのアクセ ス手段の整備不足によるものと考えられ、その整備が望まれる。
赤字と下線部は議員による発言など特に強調された部分である。 こうした事実と市民の要望などを踏まえながら対策が論じられる。 市の交通政策に関しては第三章で述べる。
第二章 市民から見た渋滞の問題
第一節 市民アンケート
公共交通に対して市民はどのように思っているのだろうか? 現在の状況を見ると、大方の市民は公共交通に対して大きな不満を持っていると思われる。
一例として、朝日新聞の地方欄に掲載された交通機関に対する主婦の意見を紹介する。
○往復1400円は負担大 通学、自転車で20分、バスだと50分
仙台市泉区 主婦47歳
二人目の子どもが今度高校に入りますが、高校の選択については、学力だけでなく、 通学費用のことも考えなければならず、頭の痛い問題です。
上の子は泉パークタウンから富谷高校まで自転車で二十分足らずで通っていました。 しかし、雨の場合、バスで行くと、一度泉中央まで行って乗り換えるので学校まで五 十分はかかり、料金も往復千四百円ほどかかります。中心部に向かうバスだけでなく、 団地と団地を結ぶような路線がなぜ敷けないのでしょうか。
バスや地下鉄の料金は高いと思います。一人で出かける時は公共交通機関 を利用してもさほど苦になりませんが、家族で出かける時には、車の方が絶対安いの で車を使っています。
天気の悪い日は、学校付近の道路が渋滞します。子どもを車で送迎するた めです。県立高校の授業料も値上げされるので、高い公共交通機関はさらに敬遠され、 渋滞はますますひどくなるのではないでしょうか。 (1999年03月07日朝日新聞紙面より)
新聞の地方欄やタウンマップなどには他にも多くの市民の声が掲載されており、 「車の利用者は、ガソリン代など『金銭的費用』や『時間費用』が、公共交通を使う 乗り継ぎの厄介さやバスの待ち時間など『心理的費用』より低いと判断し、渋滞でも 車を使う。」という細かい心理を分析する意見もあった。 乗車料金と遅延に対する市民の不満は予想以上に大きい。
交通局の交通公共企画室が行った「公共交通利用実態に関する市民1万人アンケート」 には市民の交通利用に関する具体的な行動傾向が示されている。それには今まで 述べてきた内容を裏付ける結果が出ている。 調査概要は以下の通りである。
- 調査対象
住民基本台帳から無作為に抽出した20歳以上の市民1万人
- 調査方法
郵送により送付、回収
- 有効回収数
3,735人(37.5%)
公共交通機関利用実態に関する
市民一万人アンケート調査概要
- 通勤通学手段
全体では、自動車利用が多く42%、
公共交通は39%。卒論大変 都心への通勤通学手段は
公共交通が多く75%、自動車は13%。
- 通勤通学で公共交通を利用する上での不満(複数回答)
- 通勤通学で自動車のみ利用する人の公共交通を利用しない理由
都心への通勤通学者に限ってみると
上表の第1位と第2位が逆転し、それぞれ54%と33%になる。
- 都心への交通手段(通勤・通学目的を除く)
もうやだ - 都心まで公共交通を利用する上での不満
めんどい
平日は公共交通が最も多く59%、自動車利用が32%
休日は公共交通利用が多く、自動車利用が44%と、
平日に比べて自動車利用が多い
- 都心内での公共交通による移動
外国に - 不満の理由(複数回答)
「満足」と答えた方は23%、「不満」は
50%にも達した男性の高齢者、女性の年齢各層で
「バスで移動したくても、 どれに乗ればいいのか
わからない」にも不満がみられる
アンケート調査の結果より、次のことが言える。
通勤・通学の交通手段としては自動車を利用する方が 公共交通を利用する方よりも多いが、都心への通勤に限ると公共交通利用率は75%と高い。 しかし休日や通勤・通学に限らない場合その数字は2割以上下がる。さらに 見逃せない点は、公共交通利用者の半分(三段階評価では なく五段階評価であったら恐らく半分以上だろう)が現在のバス・地下鉄による移動に「不満」 であり、「バスの遅延」「料金の割高感」「運行本数の少なさ」という3点に不満が集中している 点である。このような結果は今までの論述を裏付けるものであると同時に、交通システム に対する市民の分かりやすい要求であると言える。
市は走行速度調査や市民アンケート などの調査を繰り返し、どのような対策を行っているのだろうか。政策を立てるうえで市民の 意識を最重要視するのならただ運賃を下げて運行本数を増やし、バス専用レーンの拡充を はかればいいが、そう単純な話ではない。バランスを考えずに運賃を下げれば財政が圧迫 されるし、本数を増やしたり普通道路をバス専用レーンにすれば渋滞と遅延はさらにひどくなる。 都心に出るにはバスより自転車のほうが早いというわけのわからない交通渋滞に対して、 実際どのような対策を行っているのだろうか?第三章では市の具体的な政策を述べる。
第三章 市の対策とそれに対する政策評価
第一節 都市整備局と交通局
交通政策の計画・実施の担当部署は、扱う内容によって異なる。例えば道路の拡充なら建設局道路計画課、 公共交通政策なら都市整備局公共交通企画室や、バリアフリー対策など総合的交通計画は同局総合 交通政策部交通計画課といった具合である(図3-A参照)。主に都市整備局と交通局の2局ですすめられており、 新地下鉄東西線建設も、交通局東西線建設本部管理課 と都市整備局東西線調整室の2部署が携わっているようだ。
近年の交通政策の歴史 を見るとよく目に付くのが公共バスに関する政策である。定められた区間内なら均一100円 とする「100円パッ区」や「観光シティループバス るーぷる仙台」などユニークな政策が印象的 だ。さらに仙台ではパークアンドライドが試験的に始まり、新たな渋滞対策の一環として 先に述べた東西線建設行われるなど注目する政策が多い。様々な政策が展開されているが、 特に筆者は①公共交通政策②東西線政策に注目しており、この2点について論議を進めたいと思う。
都市整備局 総合交通政策部 交通計画課 調査係 部内事務の連絡調整/総合都市交通計画に関する調査/交通計画に係る国、県その他諸団体との連絡調整/路外駐車場の設置届の受理及び監督指導 計画係 交通施設に係る都市計画の決定/交通施設に係る都市計画の調査及び資料の作成/交通施設に係る都市計画事業認可の手続き 公共交通企画室 公共交通の機能向上及び利用促進に係る総合的な企画及び調整/時差通勤通学の推進 東西線調整室 東西線建設事業に関連する事業の進行管理/東西線建設事業及びこれに関連する事業に係る総合的広報の企画/東西線建設事業に係る連絡調整 交通局 東西線建設本部 管理課 管理係 本部内事務の総合調整及び連絡/本部の予算及び決算の調整/高速鉄道東西線(以下「東西線」という。)建設事業の固定資産の取得、管理及び処分/東西線建設事業の固定資産台帳の保管及び整理/東西線建設事業に係る争訟 推進係 東西線建設事業の総合的な企画及び調整/東西線建設事業の事業許可/東西線建設事業に係る国庫補助に係る関係省庁協議/東西線建設事業に係る広報活動 高速電車部
(南北線)営業課管理係 部内事務の総合調整及び連絡/部の予算及び決算の調整/高速鉄道事業の基本計画の策定及び調整/高速鉄道事業の経営改善計画の策定及び調整/高速鉄道事業の調査及び研究/高速鉄道事業の経営分析/高速鉄道の運賃及び手数料に係る計画、調整、認可申請及び届出/高速鉄道の乗車券の製作、発売及び精算(総務部企画経理課の所管に属するものを除く。)/高速鉄道輸送統計/ 高速鉄道の施設設備の維持管理に係る総合調整/部内所管事項に係る出資法人との業務調整/高速鉄道の乗客誘致/駅構内営業/高速鉄道事業用資産の活用/利用者の要望、相談等の統括/他事業者との連絡運輸及び振替輸送 自動車部 バス事業経営企画課企画係 部内(営業所を除く。)事務の総合調整及び連絡/部の予算及び決算の調整/自動車事業の基本計画の策定及び調整/自動車事業の経営改善計画の策定及び調整/自動車輸送の路線計画の策定/自動車事業の活性化の推進/自動車事業の調査及び研究/自動車事業の経営分析/自動車事業の運賃制度
図3-A 交通政策に関わる主な部署 ( 仙台市HPより )それぞれの政策に関わる部署を色分けした。
公共交通政策は赤、東西線政策は青
第二節 公共交通政策~アクセス30分構想~
公共交通政策の鍵を握るのは都市整備局総合交通政策部 「公共交通企画室」である。仙台市交通局、宮城交通株式会社、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)、 東北運輸局、東北地方整備局といった市内の交通体系と連携し、 バス政策や軌道系関連を始め、道路拡充や市民への呼びかけなど多岐にわたる政策企画を発信している。 公共交通企画室が掲げるテーマ、それは「アクセス30分構想」である。
これは「ひと・まち・環境にやさしい公共交通体系」の実現を目指して掲げられた構想で、 「市街化区域内の居住地から公共交通で都心や主要拠点へ概ね30分で移動できる」ことを 目標にしている。その基本方針として快適な市民生活と多様な都市活動を支える機能的かつ効率的 なまちづくりを目指し、利便性の高い公共交通を中心とした交通体系の整備を図り、交通渋滞 の緩和や高齢者などの移動のしやすさの確保、さらには都市環境の改善といった交通体系の 構築をあげている。公共交通企画室は市民へのPRも積極的に行っており、市民と共に 交通政策を考えていくという意識が高い。上記の基本方針に沿った施策体系は(1) 公共交通による移動時間短縮 (2) 公共交通の利用のしやすさに着目したサービス向上 (3) 市民や企業との協働によるTDM(交通需要管理)の推進 という3点を柱にしている。
■軌道系交通機関の利用圏域の拡大
(1)新たな軌道系の整備
(2)軌道系交通機関相互の結節
(3)既存鉄道の機能強化■結節機能の強化
(1)駅前広場等の整備
(2)駅結節バスの強化・充実
(3)駅へのアクセス道路の整備■新たなバスシステムの導入
(1)幹線バスシステムの導入
(2)快速バスの導入■バスの走行性向上
(1)幹線道路の重点整備
(2)バス優先施策の拡大
(3)バス走行支障箇所の改善
(4)バス路線再編による所要時間の短縮
■公共交通のバリアフリー化等促進
(1)駅施設などのバリアフリー化等促進
(2)バス車両などのバリアフリー化促進■バス交通サービスの向上
(1)バス乗継ぎによるサービス向上
(2)コミュニティバスの導入
(3)運行頻度の改善
(4)運行ダイヤの改善
(5)運賃制度の見直し
(6)バス停施設の改善
(7)環境に配慮したバス車両の導入
アクセス30分構想はバスアンドライド、サイクルアンドライドといった、バス停・駐輪場 と駅のアクセス向上化を図るものや、バス専用レーンの徹底化・バスルート変更といった基本的 なものから、快速電車ならぬ快速バス、バリアフリーを考慮した超低床バスの増台などこれから の交通体系を視野に入れた政策まで抜本的な改革となっている。さらにこれらのうち、バス交通 に関わる施策を着実に推進するのにあたり、平成14年3月に国からの重点的支援が得られる 「オムニバスタウン」の指定を受けている。以下に市民の要求にこたえるもの や、特に筆者が注目すべきだと考えた政策を紹介する。
■市民との協働に基づくTDMの推進
(1)時差通勤など既存施策の強化拡大
(2)パークアンドライドなどの新規施策の展開
(3)複合的施策の展開
(4)市民へのPR等
「公共車両優先システム(PTPS)の導入」
☆ バスレーンを走行するバス車両を感知し、青信号の時間を延長するものである。これによってバス
の走行性向上と定時性の確保を図る。
・ 宮城県警によるシステム整備にあわせ、導入路線を走行するバスに車載器を搭載する
「快適なバス待ち空間の整備とバスロケーションシステムの導入」
・ バス利用者が快適にバス待ちできるよう、上屋やベンチ等を設けたバス停を整備する。
・ 歩道上で現在位置や目的地への経路を音声で知らせることにより、視覚障害者の歩行支援やバス
停等へ案内誘導するシステムの整備を推進し、視覚障害者のバス利用を促進する。
☆ 市内を走行する路線バスの運行情報を、ネット対応型携帯電話やインターネット等を通じて、利用
者にリアルタイムで提供することにより、バス待ちのイライラ感の解消やバスの運行に対する信頼
の回復を図り、利用者の利便性を向上させる。
☆ 公共施設等の近傍バス停の一部には、接近表示機付バス停(20 箇所)を整備する。
・ 鉄道からバスへのスムーズな乗り継ぎを実現するため、JR仙台駅を発車するバスの「のりば」や「発
車時刻」等を案内する情報端末を整備し、利用者の利便性向上を図る。
☆ 中心商店街周辺においては、歩行者を対象に情報端末「i-モビリティセンター」を設置し、バス情報
等を提供する。
「コミュニティバスと100パッ区の導入」
・ 道路が狭く大型車両では運行できない地域や大型車両で運行するほどの需要がない地域等にお
いて、小型車両できめ細かく運行することにより、高齢者をはじめとする地域住民のバス利用を促
進するコミュニティバスの導入について検討を行う。
☆ 都心部において、バス100円均一運賃及びバス幹線道路での走行環境改善実験を実施することに
より、都心部での公共交通の利便性向上と道路渋滞の緩和を図るとともに、郊外で実施している
パーク&ライド等と連携することにより、施策の相乗効果を高め、市全体での公共交通利用促進
及び道路交通の円滑化を図る。
「運賃制度見直し」
☆ エコ切符、カルガモ定期券制度等の実施・ 運賃体系、各種割引切符の検討
(これは未実施である)
こうした施策は実験段階であり、現在進行中のものもあれば未実施のものもある。☆マークがついているのは 第二章でみた市民アンケートの結果を反映している。「運賃」への対策はまだ未実施であるが、「バスでは時間がかかる」 「バスの遅延」「運行本数の少なさ」といった市民の声に対応する施策となっている。こうした試みは一定の成果 をあげており、特に携帯の端末やバス待ち時間表示を利用したバスロケーションシステム(図3-B参照)、100パッ区とそれと 連携しているパーク&ライドはかなりの成果をあげている。
「100円パッ区」・・・仙台市中心部の区域を100円均一区間として、現在運行している市営バス、宮城交通バスの 全路線バスの運賃を100円とするものである。平成13年から始められたが、その成果は上々である。(図3-C参照)
パーク&ライド・・・マイカーをバス営業所や地下鉄沿線の大型スーパーの駐車場に停めて、バスに乗り換え、 都心へ向かう通勤方法である。これは仙台市中心部の渋滞と、市営地下鉄・市バスの赤字を少しでも減らそうと、 行っているものである。実際に行われた例として初期のパークアンドライドとして注目された仙台市南部の長町での 実施をあげる。
1999年1月に仙台市は地下鉄南北 線長町南駅前にある「ザ・モール仙台長町」と協力して、市内に通勤・通学する人を対象に、同店駐車場に車を止め、 地下鉄に乗り換えてもらう「パークアンドライド」を始めた。うまくいけば市の慢性的な悩み二つをいっぺんに解決で きる「妙案」であったが、駐車場の数が少ないため、当時はすぐに効果てきめんというわけには考えられていなかった。 駐車場は百二十八台分あり、午前七時から翌日午前零時半まで使える。地下鉄の定期券と、一カ月につき一万円以上の 同店商品券を買うのが条件。利用者には駐車位置の番号を示したステッカーが交付される。駐車場の入り口に門のよう なものはないが、午前七時から同九時まで市交通局の職員が立ち、車にステッカーがあるかを確認する仕組みである。 以下は実際に利用した市民の声。
朝、車を止めに来た会社員(33歳女性)の声
「以前は八木山から仙台駅近くの会社まで車で通っていましたが、地下鉄は時間が正確だし、いままで会社の近くに 自腹で借りていた駐車場代が浮くので助かります。商品券の購入が条件になっていることに関しても、よく買い物を するので負担にはなりません」
名取市の男性会社員(38歳) 「郊外にもっとこういう駐車場を増やしてほしい」
実際に利用した人々はいい反応を示したようだ。交通局が前年に利用者を募集し、百五十三人が申し込んだが、 以前から最寄りの駅近くに民間駐車場を借りて「自主的なパークアンドライド」をしていた人などは、認められ なかった。担当者は「申し訳ないのですが、地下鉄利用客の増加につながらないし、民業圧迫にもなりますし……」と 語った。そのため、利用者は現在百九人で、市はあと十九台分の募集を行った。また、市にステッカー交付 を申請したのは三十四人だけ。午前九時を過ぎても駐車場はがらがらだった。交通局の佐藤清・企画経理課長は 「市の中心部で借りていた駐車場の契約期間がまだ残っている人が多いのでは」と話し、以降の本格稼働に 期待を寄せた。5年を経た現在では郊外各地にこの動きが拡大し、市や区は駐車場の確保と募集を各地で行っている。
(筆者の実家付近でのパークアンドライド募集)
郊外の駐車場に自家用車を止めて公共交通機関に乗り換える「パークアンドライド」は、都心部 の渋滞対策として米国などで積極的に採り入れられている。5年前の時点で仙台市はすでに、市営地下鉄南北線の南の終着駅である富沢 駅前に二百台分、北の泉中央駅前に七百台分、月決めと時間貸しの駐車場を持ち、契約もほとんどが埋まっていた。 しかし依然として中心部に流入する車の量は増え続け、渋滞の解消に疑問視する声もある。 駐車場というスペースの問題から利用者が一部の市民に限られてしまう点でこの政策には限界がある。 今後の市や区がさらに拡大することで渋滞が軽減するかどうかが決まる。
アクセス30分構想は仙台市の交通政策の問題、特にバス政策に関して一定の効果をみせているようだ。 しかしそれは市民の立場にたった交通体系にしようという動きが実際に見られる点に対してであり、 現実に渋滞が解消されているかどうかには疑問符がつく。現時点では実験段階であり、 一部しか公開されていないデータも多いため、今後の結果に期待したい。さらに、今回は 公共交通政策として渋滞解消対策の中でもその焦点を絞ったが、他には道路拡充もあげられる。 担当は建設局で、従来の計画では、二〇〇五年までの十年間で四十三工区の工事を始める 予定だったが、実際には十工区しかとりかかっていない。 これは東西線建設にあてる費用捻出のため凍結された事業もあるためで、 2000年4月の時点で、整備率は五四・七%にとどまっている。 原因は予算に比べ計画路線が多過ぎるためであり、こうした計画に対する予算の少なさは 次章の東西線計画の問題点にもなっている。
●バスロケーションシステム
ネット対応型の携帯電話を中心としたバス接近情報等の提供。GPSによりほぼ全てのバス運行状況の把握が可能●バス総合案内システム
JR仙台駅を発車するバスの「のりば」等を案内する情報端末を、仙台駅の観光案内所に設置
●PTPS(公共車両優先システム)の導入
朝の道路混雑が激しく、運行便数及び輸送人員の多い県道仙台泉線、国道48号(L=2.6km)に導入●快適なバス待ち空間の整備
バス停への上屋、ベンチ等の設置
現 況: 約350箇所
計 画: 90箇所
図3-B バス政策イメージ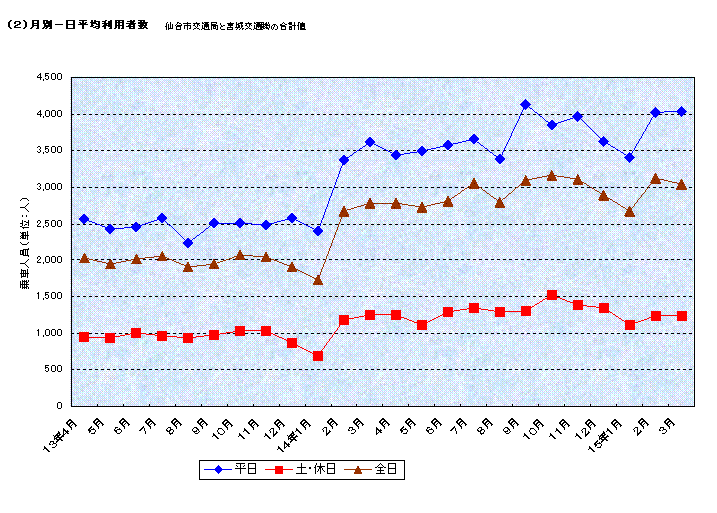
図3-C 百円パッ区利用者動向
第三節 東西線政策
交通政策の柱としてだけではなく、新しい都市構造の形成を目指して 現在計画されているのが東西線政策である。これは現在市内を走っているJR、地下鉄南北線 に続く軌道系の誕生となるものである(路線図は第一章の図1-C参照)。平成12年度~16年度にかけて 測量地質調査・基本設計、実施設計と環境アセスメントにおける影響調査及び評価がなされた。 政府の2003年度予算の財務省原案に補助事業として盛り込まれ、国から「ゴーサイン」が出たこ とで、市は今年度中に事業許可、2003年度に工事施工許可をそれぞれ国に申請して 予定通り2004年度に着工することになりそうだ。開業は2015年度の見通し。 その事業概要は以下のようになっている。
建設区間 八木山地区(青葉山含む)~東部流通業務地区 営業キロ 約14km 予測利用者数 1日あたり約132,000人 建設費 約2,710億円 機種 リニアモーター鉄道
仙台市は東西線建設の理由として交通利便性の向上(目的地到達所要時間の短縮)、 主要な地域間の連結、自動車からの地下鉄の転換による排出ガス軽減・渋滞の緩和・交通事故軽減 などをあげているが、この計画には多くの疑問点がある。 それは乗車人員見込みと採算性・建設費・機種・政策の不透明性・バス政策とのからみの5点である。
(1)乗車人員(需要予測)の見込みと採算性
上の表にあるように、市は一日当たりの需要予測を13万2千人と見積もっている。 (98年度に市がまとめた基本計画に盛り込まれている予測で、利用者が計画通りになった場合、 開業後27年目に累積赤字が解消する。) 市が2000年1月18日の東西線交通軸の調査特別委員会で説明したところによると、 95年度に算定した「2010年度の市の基本計画人口は120万人」を前提に、92年に行われた 現況調査のデータと、92~97年の夜間人口の推移を加えて算定した。 この時点で次の二点に疑問が生じる。
1.2010年度までに市の人口は果たして120万人に達しているだろうか
2.あらかじめ需要のあるところにルートを定めた南北線と異なり、 東西線は沿線周辺の
開発も同時に進める「開発一体型」の地下鉄であるが、 必要不可欠な民間の投資が
見込めるかどうか。
将来人口について市は、1992~2010年にかけて、夜間人口が千人以上増加 すると見込まれる沿線の地域を13カ所示したうえで、その区域で計約3万9千人 増加すると試算している。しかし、92~99年では約3800人の増加にとどまっている。 市営南北線でみると、市は1978年の当初計画で、1日当たりの乗客数 23万5千人と設定していた。しかし、1998年度の1日平均の乗客数は16万3千人と 31%も減っている。もちろん開業以来の乗車人員数は その予測を大きく下回りほぼ半分、そのため累積赤字(01年度決算で約968億円) の解消も当初の予測より21年も遅れて2030年の見込みだ。 しかし、市は南北線で経営改善のためのはっきりとした計画を示さないまま、 東西線の着工に乗り出そうとしている。東西線は累積赤字解消を2037年ころとしているが、 予想乗車人員が達成されなければ南北線に続き赤字経営になるのは必至である。 さらに、南北線は赤字の穴埋めとして運賃上昇を行っており、 前述したようにこれが渋滞悪循環の一つの原因となっている。 「開発一体型」の手法も、当初から需要があった南北線と違いどうなるかわからない 不安定な予測である。特に東地区はJR仙石線と平行して走る形になる。 人口増加の予測と合わせて採算性に疑問が残る。
(2)建設費
市はリニア式地下鉄を想定して、建設費2710億円(うち土木工事費は1310億円)、 関連事業費として道路整備事業に約500億円、駅前広場や駐輪場などの施設整備、 東部地区の市街化促進事業などを合わせて約300億円と見積もっている。市の一般会計 約4300億円の三分の二を占める。市は建設費の財源として、一般会計から1220億円、 国庫補助金から610億円、都市高速鉄道事業債で880億円と見積もっている。 一般会計からの支出額については、六割の732億円が交付税措置で市に戻ってくるため、 実際に負担する金額は488億円になると説明している。しかしここでも市営南北線でみると、 建設費は2164億円の設定だったが、実際には2437億円と設定より13%増えている。 そもそも仙台市の台所事情は2002年12月の時点で税収が5年連続で前年度を 下回るなどかなり苦しい状態である。公共事業でつくった仙台スタジアム (ベガルタ仙台のホームグラウンド)は市民は週2回しか使用できず、年間一億八千万円近い維持 費がかかっている。そのうえ、ワールドカップで建設された「仙台ドーム」も維持費とその建設費の返済 に苦しんでいる。上記で示したように南北線は多額の累積赤字を背負っている。その「お荷物」を抱え込んだ 苦しい財政事情の中で、さらに東西線が必要なのか。予想外の追加工事で事業費がふくらめば 、市の財政を揺るがすことになるだろう。
また第三章第二節の最後で述べたが、東西線建設の影響で、道路の各路線工事の半数以上を 2010年まで凍結することになっている。厳しい財政下で必要性の高い路線に予算を集中させ、 完成までの期間を早めるのが狙いだと言うが、マイカー依存率が高い仙台で確実性の高い 道路拡張策を減らし、予測が不安定な地下鉄に渋滞解消を託せるかどうかはなはだ疑問である。
東西線計画 南北線実績 南北線計画 総建設費(億円) 2,710 2,340 2,164 1km当たり建設費(億円) 190 165 152 1日の利用者(人) 13万2千 16万5千 23万5千
図3-D 地下鉄東西線計画と南北線の比較
(3)機種
東西線の機種はリニアモーター式地下鉄である。リニアモーター地下鉄とは、 車輪で車体を支えながら磁力で進むもので、浮上式と車輪式の2種類がある。 前者はJR東海が開発している時速500キロのあれ、東西線は後者である。 具体的な構造の説明は避けるが、とりあえず本来車輪上にあった大きな回転モーターに とってかわって薄い磁力板がその動力を担うものだと考えていただければいい。 リニアモーター式地下鉄は、すでに東京との大江戸線(都営12号線)、大阪市の 長堀鶴見縁地線(7号線)など各地で実用化されている。
そのメリットとして、①登板能力がある(東西線は高低差100m)②急カーブに対応できる ③低床化によるコスト削減(車体が低くなるためトンネルの直径を狭めて建設コストを抑えられる) があげられる。その一方で、①消費電力が在来線の4割増②車両自体にかかるコストが高い などのデメリットがあげられる。さらに仙台市固有の問題が3点あげられる。まず既存の地下鉄や、 JRとの互換性を失うことによって、将来の仙台都市圏の交通体系に禍根を残す恐れがあることである。 鳴り物入りで開業した多摩都市モノレールも、使い勝手の悪さから、悲願達成の割には不人気で、 「税の無駄遣い」と指摘されているようだ。また、路線が青葉山を通っているために高低差がある わけだが、わざわざ山を経由する必要があったのだろうか。青葉山は観光地として有名である他、 東北大のキャンパスがある。観光客のためならわかるが、それなら「るーぷる仙台」という 仙台駅から青葉山経由で周遊する観光バスがある。使い勝手のよい車やバイクを多用している大学生が 地下鉄に乗り換える可能性があるかどうかも疑問が残る。最後に、機種を検討する会議が密室で行われた 可能性が高い点であるが、これは次の政策の不透明性につながるのでそちらで述べる。
リーモ君
(東西線イメージキャラクター)東京 大阪 神戸
(4)政策の不透明性
市の東西線政策を見ていると、その意志決定過程が不透明な部分が出てくる。 平成11年9月9日、仙台市議会の一般質問にて「リニア地下鉄」想定下での「東西線」について、 採算性や建設費などに対する疑問点が提出された。本来市議会の質問とその答えは 「仙台市議会だより」に載せるのが義務であったが、掲載はなかった。また、 機種の決定は東西線機種等検討会という会議で行われたが、この会議は非公開であったうえ、 検討会の参加メンバーのほとんどが当時リニア地下鉄を推進していた旧運輸省関係者であった という事実もある(日刊建設工業新聞平成11年11月25日記事等)。機種選定等における決定権の 非透明性は、リニアモーター東西線が仙台市に適しているのかどうかを疑問視させる。さらに、 ルートの決定においても市議らの反応は分かれた。「東西線の恩恵を受ける地域は限られる。 98年3月に(ルートと機種を)正式決定したとき、ほかの事業に与えるマイナスの影響も一緒に 説明するべきだった」と市の姿勢に疑問を投げかける議員がいる一方で、「限られた予算の配分 が明らかになり、投資効果があがる」という意見も出た。
(5)バス政策とのからみ
1987年の南北線開業後は、地下鉄利用者の増加を予測して交通局はバス運行本数を減らしている。 しかし結果は、バス利用者の多くが運行本数減少を理由に車に転換、マイカー利用率が11%増加し、 都心への流入部の滞時時間が2倍になってしまっている。東西線が開通すると、バス1本で直通で きた路線が地下鉄の乗り継ぎになり、料金が倍になってしまうところが続出するという見方もある。 東西線開通後に運行本数の見直しをする政策も出ており、30分アクセス構想をはじめとする公共交通 政策の足を引っ張ることにはならないか不安である。
以上、東西線に対する問題点を筆者なりの観点から述べた。これらの要素を考えると、 東西線は渋滞の悪循環にむしろ拍車をかける存在になりかねないのではないか という考えが頭をはなれない。
誤解のないように言っておくと、 東西線に対して大きな期待を抱く市民もいる。 去年の11月に行われた「市民の意見を聞く公聴会」では批判もでたが 計画を推進する仙台商工会議所や、キャンパス付近に青葉山駅が予定されている 東北大の関係者も出席。「毎年多くの東北大生がバイク通学で事故に遭っている」 「都市への交通負荷を軽減するため東西線に期待している」など、賛成意見を発表した。 仙台市の発展を確かなものにするために南北・東西の二つの大動脈が絶対に必要だとする意見もある。 新しくできる地下鉄の駅付近で自営業を営む市民も期待を寄せる。 「郊外の常連客はバスやタクシーを使うが、バス停が遠く不満も多かった。 近くに駅ができればこれが解消される。商売へのメリットは大きい」と話す。 大きな視点から見た軌道系の循環など実際に地下鉄ができてみなければわからない要素 もあり、長い目で見ないと結果を語れないところもある。筆者が今年の1月に仙台に 行った時は、すでに駅建設予定地にバリケードがはってあった。着工は近い。
第四章 他都市との比較から見られる仙台の特色