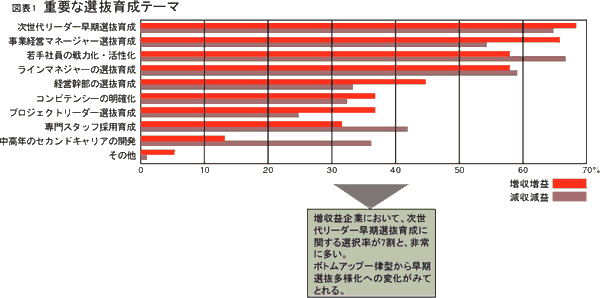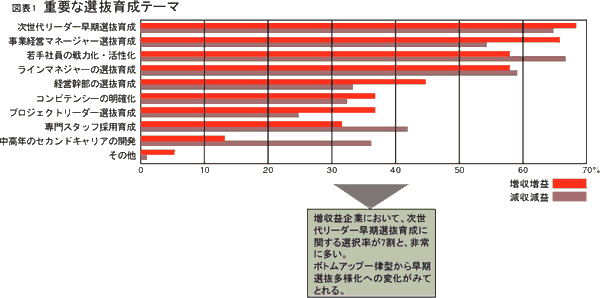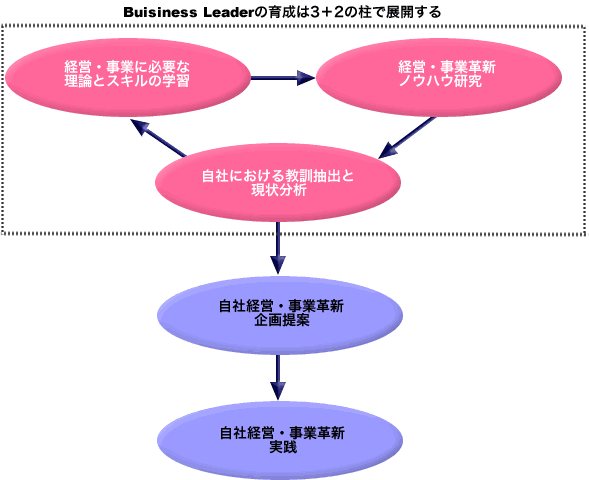�{���@����
(Kohei Miyazato)
����c��w�Љ�Ȋw���@����[�~
�����e�[�}
| ���[�_�[�i�o�c�ҁj�琬������l���� |
�P�[�X
��Ɠ���w�i�R�[�|���[�g���j�o�[�V�e�B�j����
| ��P�� |
��Ɠ���w�Ƃ́H |
��P�߁@���Ă̊�Ɠ���w�̓o��̗��j�Ɣw�i
�@�@
��Q�߁@��Ɠ���w���ݗ����ꂽ�v�� |
| ��Q�� |
�[�l�����E�G���N�g���b�N�iGE�j�̎��� |
�@��P�߁@��Ɠ���w�̐�삯GE�N���g���r��
�@�@
��Q�߁@���[�_�[�琬�̗͂v�� |
�@ | ��R�� |
���[�_�s�݂̎��� |
| ��S�� |
���{�̊�Ɠ�����̗��j�ƌ��� |
��P�߂���܂ł̊�Ɠ�����
�@�@
��Q�ߊ�Ɠ���w�̓o��
��R�߂��ꂼ��̊�Ƃ̎��� |
| ��T�� |
���Ă̔�r�Ɩ��_ |
��P�ߌ��C����̔�r
��Q�ߎQ���҂̑��l��
��R�ߑ����I���� |
| ��U�� |
���{�̎����ナ�[�_�[�̈琬�� |
��P�ߌo�c�҂̃R�~�b�g�����g
��Q�߃��[�_�[�{���ɗ��ӂ���|�C���g
��R�߃��[�_�[�琬��Ɗ�Ɠ���w |
�������@
�����͏����A�Ɨ����u���Ă���B
�����������ݎ����ɂ̓A�C�f�A�Ƃ����̂��Ȃ����A�o�c�ɕK�v�ȃm�E�n�E�Ƃ������̂��Ȃ��B�����ł܂��͊�Ƃɓ���A���̒��ŃA�C�f�A��m�E�n�E�܂��͐l���Ȃǂ�|������Ǝv���Ă���B
���ݓ��{�̓��[�_�[���s�݂ł���ƌ����ċv�����B��ƂȂǂ����ꂩ��̎Љ�Ő����������߂Ɏ�����̌o�c�҂��琬����K�v�ɔ����Ă���B
����ł͈�̊�Ɠ��ł��̂悤�Ȑl�ނ��琬���邽�߂ɂǂ�Ȏ��݂��Ȃ���Ă���̂��Ƃ������ɋ����������A���ׂĂ��������Ɂu��Ɠ���w�v�Ƃ������݂�m�����B
����̓A�����J�̊�Ƃł��Ȃ��������Ă���V�X�e���ŁA���{�ł��ŋߑ��ƂȂǂ�������Ă���B
�����ł��́u��Ɠ���w�v�Ƃ����̂͂ǂ̂悤�ȃV�X�e���ŁA�ǂ̂悤�Ȑl�ނ�����Ă���̂��B����ɂ͂��ꂩ��̊�Ƃ̂�����Ƃ������Ƃ܂ŁA���ꂩ��Љ�ɏo�čs����w���̗��ꂩ��l���Ă��������Ǝv���B
�����Ă܂����̌����������݁A���Z�p�������Ȃ������̖��ɗ��ĂƎv���B
| ��P�� | �@��Ɠ���w�Ƃ́H |
|---|
�@���{�̊�Ɠ���w��_����O�ɂ܂��ݗ����Ă���50�N�̗��j�������Ă̊�Ɠ���w�ɂ��ďڂ������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B
�@
�����ʼn��Ăł͊�Ɠ���w�̓o��܂łǂ̂悤�ȓ���������w�i�Ȃǂ��������̂��B���̏͂ł͂���ȗ��j�Ɣw�i�܂��������Ŋ�Ɠ���w�Ƃ͂��������ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��A���̒�`��ړI�Ȃǂ�_���Ă݂悤�Ǝv���B�@
�@
| ��P�� | �@���Ă̊�Ɠ���w�̗��j�Ɣw�i |
|---|
�ϊv���ɂ����āA�m���͂����ɒ������A����ɑΉ�����@���͂�����Ă��Ȃ��g�D�͎s�ꂩ��̓P�ނ�]�V�Ȃ�����Ă���B�őO���̌���ɂ��A���Ђ̃~�b�V�����A�헪�A�ϗ��A�J���`���[�𗝉����A���̂����Ń��[�_�[�V�b�v��������L�\�Ȑl�ނ����߂��Ă���B�����Č��݁A�����Њ�Ƃł́A�m�I���{�̏d�v���ɒ��ڂ��A����܂łɂȂ��v�V�I�ȕ��@�ŎЈ�����Ɏ��g�ނ悤�ɂȂ��Ă��Ă���B
���̗���̂Ȃ��Ō���Ă����̂��u��Ɠ���w�v�ł���B
������u�r�W�l�X��̃j�[�Y���������i���ׂĂ��E���E�J���E���{����헪�I�Ȓ��j�@�ցv�ƒ�`�ł���B
�@�A�����J�̊�Ɠ���w�́A���Ђ̎Ј��ɒm���������邾���ɂƂǂ܂炸�ڋq�A�T�v���C���[�A���ʊ�ƁA�p�[�g�i�[��Ƃ����Ώۂɔ��W���Ă����B�@
�ŏ��̊�Ɠ���w�͂P�X�T�R�N�A�g�b�v�E�}�l�W�����g�̊�b�P���L�����v�Ƃ��āA�N���g���r���ɔ��������[�l�����E�G���N�g���b�N�̃��[�_�[���C�Z���^�[���Ƃ����Ă���B
�@���̌�U�O�N��ɂ́u�f�B�Y�j�[��w�v�ƃ}�N�h�i���h�́u�n���o�[�K�[��w�v���������B�����ł͑S���E�Ŗ�Q�O�O�O�̊�Ɠ���w�����݂���Ɏ������B�܂����̃y�[�X�ő���������Ƃ���A�Q�O�P�O�N�ɂ̓A�����J�̈�ʑ�w�̂R�V�O�O�Z���Ă��܂����낤�ƌ����Ă���B
| ��Q�� | �@��Ɠ���w���ݗ����ꂽ�v�� |
|---|
��Ɠ���w�̐ݗ��𑣂��v���͕�������Ƃ����Ă���B���̂�����ȂT�̗v���������Ă݂悤�Ǝv���B
�����炭�ő�̗v���Ƃ���Ă���̂��u�m���̒����v����B
���鎞�ɁA�T���E�}�C�N���V�X�e���Y�Ђ̊�Ɠ���w�ł���T���E���j�o�[�V�e�B�����ׂ��Ƃ���A���Ђ̔��グ�̂V�T���ȏオ������N�ȓ��̐��i�Ő�߂�ꂢ���Ƃ����B
���̂悤�ɁA����ł͒m���������Ƃ����Ԃɒ�������X�������܂��Ă��邽�߁A�l�ނ̃X�L�����₦�����j���[�A�����A���t���b�V�����邱�Ƃ����d�v�ɂȂ��Ă��Ă���B
���̗v�����u�w�K���e�Ɛ헪�ڕW�Ƃ̐������v�ł���B
���̗�Ƃ��ẮA�C���t�H�V�X�E�e�N�m���W�[�Y�Ђ��w�K���e�Ɗ�Ɛ헪�𐮍��������i�Ƃ��ĂP�X�X�V�N�ɐݗ������C���t�H�V�X��w����������B�����Ă��̑�w�ƁA���ƖڕW�Ƃ̌��т���[�����邽�߂Ɂu�C���t�H�V�X�헪�ψ���v�����������B�����ŁA�e��w�K�v���O�����ɂ��āi�\�t�g�E�F�A�̊J����i���Ǘ��ȂǂɊւ���j�D�揇�ʂ����߁A�Ј�����ւ̓������ʂ�]�������g�g�݂��߂Ă���B
��O�̗v���́A�ƊE���Łu���E�҂ɑI����Ɓv�ƂȂ�A�`�N���X�̐l�ނ̒��ڂ��W�߁A���E�����Ȃ����Ƃɂ���B�����\������Ƃ��Ă̓n�C�}�[���E�u���[�E�N���X�E�V�[���h�́u�C���t�H���[�V�����E�T�[�r�X�E�O���[�v��w�v����������B���̊�Ƃł͂���܂łP�U�����������E�����A�Q�N�ԂłT���܂łɈ��������邱�Ƃɐ������Ă���B���̂悤�Ɋ�Ɠ��̋��琧�x���[�������邱�Ƃɂ���āA�����l�ނ𑼊�Ƃɗ��o�������A���Ђł�������Ɗm�ۂ�����ʂ������Ă���̂ł���B
��l�̗v���Ƃ��Ắu���[�_�[�w�̌��݂𑝂��v���Ƃ���������B��Ɠ���w����悷��ߒ��ŁA�܂����[�_�[�V�b�v�J���u���̐ݒu���[���ƂȂ邱�Ƃ������̂����̗��R���炾�ƍl������B���[�_�[�V�b�v�u���ł͊e��̃g���[�j���O�E�v���O������R�U�O�x�]���Ƃ������A�]���̂���̋�����@�ɉ����āA���ۂ̉��K�v���W�F�N�g���������ۂ����̂ł���B�Ȃ��A�����̉��K�v���W�F�N�g�́A��u���郊�[�_�[�Ɋ����̃r�W�l�X�E�j�[�Y�ɑ����������������A�����̐��i��T�[�r�X�̍\���ɂ��čl�@�������肷�邱�Ƃ������B
�����čŌ�̗v���Ƃ��ẮA�Г��́u�S���犈���̃u�����h���v��}��A���畔��������I�ȃr�W�l�X�E���j�b�g�Ƃ��ĉ^�c���邱�Ƃł���B����܂Ō��C����͖��v��ȃR�X�g�E�Z���^�[�Ƃ��ĉ^�c����Ă���A���Ɠ��Ƀg���[�j���O�����{���镔�傪�������������B�g���[�j���O�̐��Ƃ��S�̂����邱�Ƃ͂����Ă��A�Г��������r�W�l�X�E���j�b�g�Ƃ��Đ헪�I�ɉ^�c����Ƃ������Ƃ͂قƂ�ǂȂ������̂ł���B
���̂悤�ɃA�����J�ł͂��̌܂̗v���̂��ƂŁA��Ƃ͊�Ɠ���w��ݗ����ϊv�����������߂��߂ɂ��܂��܂ȋ��炪���H����Ă���̂ł���B
| ��Q�� | �@�[�l�����E�G���N�g���b�N(GE)�̎��� |
|---|
| | ��P�� | �@��Ɠ���w�̐�삯GE�N���g���r�� |
|---|
���ɂ��̏͂ł́A�O�͂ł�������Ɠ���w�ݗ��̗v���̂Ȃ��ŁA���[�_�[�w�̌��݂𑝂��A�����ナ�[�_�[�̈琬�ɏd�_��u���Ă����Ƃ̒��ōł��������Ă���Ƃ�����[�l�����E�G���N�g���b�N�̎��݂��ڂ������Ă������Ǝv���B
�@�j���[���[�N�B�N���g���r���ɂ̓W���b�N�E�E�F���`�O��ŗL���ȕă[�l�����E�G���N�g���b�N�iGE�j�Ђ́h���[�_�[�{���@�ցh�ł��郊�[�_�[�V�b�v�J��������������B
�E�F���`������ケ����K���͕̂��ς���1 �T�Ԃ�1 ��B���E���Ŏ��Ƃ�W�J���A30���l�̎Ј�������鑽�Z��CEO���R�l�e�B�J�b�g�B�t�F�A�t�B�[���h�ɂ���{�ЈȊO�ōł��p�ɂɑ����^�ԏꏊ���B���̍ő�̖ړI��GE�Г��ɂ�����D�ꂽ�g���[�_�[�h���Ȃ킿�Ǘ��E�Ɗ������琬���邱�Ƃɂ���B
�N���g���r���̌�������1 �N�Ԃ�11��J�����A�}�l�[�W���[�ȏ�̊Ǘ��E�⊲����ΏۂƂ������C�v���O�������ׂĂɃE�F���`�͎Q������B���ꂼ��3 ���Ԉȏ�ɂ킽����1 �l�́g���t�h�Ƃ��āg���k�h����ɔM�S�ɍu�`����B
�������͓��{�̑�w�ł悭�ڂɂ���悤�ȋ��t���琶�k�ւ̈���ʍs�̎��Ƃł͂Ȃ��B�E�F���`���g���u��i�ɐH���Ă�����悤�Ȗ{���̑Θb��]��ł���v�Ƙb���ʂ�A���k�ł��銲�������́A�E�F���`�ɑ��Ă��M�S�Ɉӌ����Ԃ���B������GE�̎��ۂ̌o�c�ɖ𗧂ǂ��A�C�f�A�����܂ꂽ�炷���Ɏ��s�Ɉڂ����B
�E�F���`�ȊO�ɂ��AGE�̏㋉������r�W�l�X�X�N�[���̋������u�`��S������B��u�҂ɂ́A�O���[�v���ƂɗႦ�u�d�q������v�u�C���^�[�l�b�g�r�W�l�X�v�Ƃ�����GE�������ڂ��Ă���e�[�}���^������B��u�҂�1 �T�Ԃ���1 �J���Ƃ����Ԃ������āA���E���̊�Ƃ���Ƃɘb���A�O���[�v�ŋc�_���d�˂邱�Ƃł��̉������o���B
���C�v���O�����̍Ō�ɂ́A�E�F���`�ȉ�GE�̍ō�����30 �l���������O�Ŗ�2 ���Ԃ̃v���[���e�[�V�������s���B
�@�����������������[�_�[����̎d�g�݂�GE�ɂ��Ƃ��Ƃ��������̂ł͂Ȃ������B�u�N���g���r���������̓E�F���`���g�b�v�ɂȂ�܂Ŏ��H�I�ł͂Ȃ��A�ނ����w�̃r�W�l�X�X�N�[���ɋ߂������v�ƃN���g���r���̌��������̃J�[�͑ł������Ă���B������E�F���`��GE�̌����̉ۑ�����������ɍ��ς����̂��B
�����GE�̃��[�_�[�琬�͂́A�č��̌o�c�Ҏs��ɂ�����GE�o�g�҂ւ̍����]���ɏے��I�ɕ\��Ă���B�č��ŗL�\��CEO��y�o���Ă����ƂƂ��Ă̓R���T���e�B���O���̃}�b�L���[�[�E�A���h�E�J���p�j�[���L�����B
���������{�ł͂��܂�m���Ă��Ȃ����A�č��ɂ�����GE�̓}�b�L���[�[�ƕ��ԗL�͌o�c�҂̈琬�@�ւƂ��ėL�����B
�Ⴆ�AGE�̕��В����o��91 �N����99 �N12 ���܂ŕčq��F���E�����ԕ��i���A�A���C�h�V�O�i����CEO�߂����[�����X�E�{�V�f�B�B�{�V�f�B�͖�8 �N�Ԃ�CEO�ݔC���ɓ��Ђ̊�����1 �N�ԓ����蕽�ς�30 ���ȏ�A�㏸�������B�{�V�f�B��99 �N12���A��������@����n�l�E�G�������A���㍂250 ���h���i2 ��6000 ���~�j�̐V��Ђ̉�ɏA�C�����B
�����ԕ��i���SPX ��CEO�W�����E�u���C�X�g�[���́AGE�ō��v18�N�ԓ������o�������B�u���C�X�g�[����95 �N��SPX��CEO�ɏA�C���đ�_�Ȏ��ƍ\���̉��v��f�s���A���̊�����1 �N�ԓ�����̕��ςŖ�60 ���㏸���Ă���B
98 �N�̔��㍂��30 ���h���i��3000 ���~�j�̍H����X�^�����[�E���[�N�X��CEO�W�����E�g���[�j�A������98 �N�̔��㍂��50 ���h���i��5000 ���~�j�̃O���X�t�@�C�o�[���I�[�G���X�E�R�[�j���O��CEO�ł���O�����E�q���^�[��GE�𑲋Ƃ����L��CEO�ł���B
| ��Q�� | �@���[�_�[�琬�̗͂v�� |
|---|
| �@�Г������łȂ��ЊO�ɂ��L�\�Ȍo�c�҂�y�o����B�����GE�̃��[�_�[�琬�͂̋����͈�̂ǂ��ɂ���̂��낤���B
�@�����łT�̗v�f�������Ă݂����Ǝv���B
���̂P�F�N���o���ɊW�Ȃ��`�����X��^������
�@GE�͔N���o���ɊW�Ȃ��A���[�_�[�Ƃ��č˔\������ƌ����l�ނɃ`�����X���ǂ�ǂ�^���Ă����B�Ⴍ�Ă��L�\�Ȑl�ނ͐ӔC����|�X�g��^������̂ŁA�����̎��͂����������ł���B���������`�����X���Đ��ʂ��グ�邱�Ƃ��ł���A���͂����ƐӔC�̂���d���Ɩ�E���^������B
���̂Q�F������������̃��[�_�[�Ƃ��Ĉ琬����
�@��ʓI�Ɋ�Ƃł́A�o���~�̋����Ǘ��E�������̎蕿������肵����A�����̃��C�o���ɂȂ肻���Ȑl����r�����邱�Ƃ��������Ȃ��B�Ƃ�킯���͋`���d�Ј����m����������������Ƃł́A��i�������̈琬�ɖڂ������Ȃ��Ȃ肪�����B
�����Ȃ�Ȃ��悤�ɁAGE�́u�����������̃��[�_�[���Ƃ��Ĉ琬���邱�Ɓv�����[�_�[�̏����Ƃ��Čf���Ă���B
�@�������ɂ͂�����Ƃ������؋@�\�����݂��Ă���B��i��������]�����邾���łȂ��A��������i��]������g360 �x�]���h�̎d�g�݂��B������i��������̃��[�_�[�琬�ɔM�S���ƁA�����ɕ�������g���[�_�[���i�h�������������Ă��܂��v�Ɠd�̓V�X�e���ȂǕč����̕����̎��ƕ��A�����ăA�W�A����{�Ől����S�����Ă���GE�{�Ђ̕��В��W�����E�\���b�c�H�i48 �j�͋�������
�@GE�ł͓����Ƀ��[�_�[�̕]����Ɂu�`�[�����[�N�v�Ƃ������ڂ�݂��Ă���B���[�_�[����������ɐU�镑�����Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȃ`�F�b�N�@�\�͂ق��ɂ����낢�날��B
�������w�����͎����̕����̔\�͂������o���Ȃ��ƃ`�[���̋Ɛт����߂��Ȃ����߁A�M�S�ɂȂ�͎̂��R�Ƃ���������B�����AGE�͂�������j�ɑ�������p�x����g���h����@�\���������Ă���B
���̂R�F���ՓI�Ȍo�c�X�L��������
GE�͂܂��A�����Ȃ鎖�Ƃɂ��ʗp����u���ՓI�Ȍo�c�X�L���v�������[�_�[�̈琬�ɗ͂����Ă���B11�ɂ��y�ԗl�X�Ȏ��Ƃ�GE�������Ă��邩�炾�B
�Ⴆ�A�N���g���r���������Ō��C����Ǘ��E�����͑S���W�̂Ȃ����Ƃ̏o�g�ғ��m���`�[����g��ŁA���ꂼ��̎��Ƃ�������o�c�ۑ�̉������@���l����B
���̃`�[���͎Ј��ł͂��邪�A�܂�ŎЊO�������Ă����R���T���^���g�W�c�̂悤�Ȃ��̂��B
�`�[���̃����o�[�͏o�g���Ƃɖ߂�������A�i�����P�^���ł���V�b�N�X�V�O�}�̂悤�ȑS�ГI�Ȏ��g�݂ɂ��ĕp�ɂɈӌ�����������B�ǂ����̎��Ƃł������P���Ⴊ����A����������Ɏ����̎��ƂɎ�����邽�߂��B
���̂S�F�D�G�ȃ��[�_�[�قǍ���ȕ����Ŗ���
���{��Ƃł́A���[�_�[�Ƃ��ď��������҂����l�ނ�{���ƌĂ��A�Ȃ�ׂ����s���Ȃ������ő厖�Ɉ�Ă邱�Ƃ����������B
������GE�͗D�G�Ȑl�ނɂ����V�K���Ƃ�s�U�Ɋׂ��Ă��鎖�ƂȂǍ���Ȏd����C����Ƃ������j������B
�D�G�Ȑl�ނ��s�U���Ƃ𐬌��ɓ����Ȃ���A��Ƃ̋����͍͂��܂�Ȃ����炾�B�����Ď��Ƃ��O���ɏ��A�����ɂ܂��ʂ̓���C�����^������B
GE�̑����̃��[�_�[�����̌o�������Ă��A�S�������͕p�ɂɕς���Ă���B�L�\�ȃ��[�_�[�ɂ́A�����Ď��X�Ɍ������C����^���Čo�c�\�͂�����̂��AGE���̃��[�_�[�琬���@�Ȃ̂ł���B
���̂T�F���s���Ă�������ł��҉\
�������Ȃ���A����Ȏd���ɒ��킷�邱�Ƃ�������A���R���s������B����Ȏ��ɁA�������邽�߂̃`�����X���^�����邱�Ƃ�GE�̃��[�_�[��̓������B�`�����X��͂߂A������ł��҉\�Ȏd�g�݂�����B
�@�E�F���`�͂Q�O�O�P�N�Ɉ��ނ���ہu���N�O�����p�҂Ƀo�g���^�b�`���鏀���͂��Ă����B�v�ƌ���Ă���B�ނ�GE������A���܂ł̂悤�Ȑ����͂��������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜���鐺���������B
�����A�E�F���`�̏o�g����ł���v���X�`�b�N���Ƃ�10 �N�ȏ㓭���A���̓N���g���r���̃��[�_�[���C�v���O�����̃}�l�[�W���[�߂Ă���J�����E�I�h�l���͂����b���B�u�W���b�N�i���E�F���`�j����Ă��D�ꂽ���[�_�[���������邩��A�ʒi�S�z�͂��Ă��Ȃ��v�B
�E�F���`��GE�Ɏc�����ő�̈�Y�͗L�\�ȃ��[�_�[�����ݏo��������g�d�g�݁h��������Ȃ��B��Ƃ������������������c���Đ����𑱂��邽�߂ɂ͂ǂꂾ�������̗D�ꂽ���[�_�[������Ă��邩�����ߎ�ƂȂ邩�炾�B
�@GE�ł̓E�F���`�����S�ƂȂ莟���ナ�[�_�[���琬�������A�t�@�C�i���V�����E�^�C���Y�� �iFinancial Times�j�ƃv���C�X�E�H�[�^�[�n�E�X�N�[�p�[�X �iPriceWaterhouseCoopers�j���A���E�̊�Ƃ̍ō��o�c�ӔC��1, 000�l��Ώۂɍs���������Łu���E�ōł����h������Ɓv�ɂ��T�N�A���őI��Ă���B
�܂����[�_�[�V�b�v�_�����Œm����A�W�����E�o�E�R�b�^�[�i�n�[�o�[�h�E�r�W�l�X�E�X�N�[�����_�����j���A�Q�O�O�O�߂����݂���Ă̊�Ɠ���w�ŁA��������Ă���̂͂�͂�f�d���Əq�ׂĂ���B
���̗��R�Ƃ��āAGE�̊�Ɠ���w�̓E�F���`��GE���ǂ̕����ɓ����������Ƃ������Ƃm�Ȏp���őł��o���A�����`���A�������邽�߂ɂ���ꂽ���u�ł��邩�炾�Ƃ����B
| ��R�� | �@���[�_�s�݂̎��� |
|---|
�@ | ���{�̊�Ɠ���w�̍l�@�ɓ���O�ɁA�Ȃ��ߔN���[�_�[���s�݂̎���Ƃ����Ă���̂��A�܂����̗v���Ƃ��Ăǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��w�i�ɂ���̂����܂��͂��߂ɂ��̏͂Ō��Ă������Ǝv���B
�w�b�h�n���e�B���O��Ђ̓����G�O�[�N�e�B�u�E�T�[�`�́A��ɏ㋉�Ǘ��E��ΏۂƂ����Ђł���B�����Ă����ŋ߂̓]�E�s��ŋ��l�̑����Ă���E�킪����Ƃ����B����́u�В��v���B
�ō����s�ӔC�ҁi�b�n�n�j�ȂǎВ��T���̈˗����S�̂̂Q�������Ƃ���B�ŋߓ��ɖڗ��̂́u��Ђ��Č��ł���l�v�B���̐l�ނ����Ȃ��Ƃ����̂��B
�u�헪�����߂Ď��s����B�����Ă��̐ӔC�͕����B����ȌP�����Ă���l���ɂ߂ď��Ȃ��v�i�����t��В��j
�P�X�X�O�N��O���A�č����s�����痧������ߒ��ł́A�o�c�g�b�v�Ƃ��Ď��т̂���Č������l�����������B���{�ł�����A�����������ɖ���Ƃ̏������i�ތ��ʂ������A�o���b�t�B�i���V�����E�A�h�o�C�U���[�E�T�[�r�X�̓c����Y���́u������ƃ��X�N��w�����Ďd�������郊�[�_�[�����Ȃ���Ί�ƍĐ��͂ł��Ȃ��v�ƌx�����Ă���B
�����o�ς̂�����ǖʂō\�����v�𔗂��Ă�����{�B�o�ϓ��F��I�g�����̕i�쐳�����́A���ܕK�v�ȃ��[�_�[�����u�Đ���f����A�S���V�����ڕW��������l�v�ƕ\�����Ă���B����ȉ��v�̒S���肪����Ȃ��̂͂Ȃ����B
���̈�ڂ̗v���Ƃ͔\�͉B���ł���B
�����w�@�̒|���m�����i����Љ�w�j�́u���l�ƈႤ���ƁA�ˏo���邱�Ƃ��悵�Ƃ��Ȃ���㋳��Ɉ��������v�Ƃ݂�B�݂�Ȃ������悤�ȋ�����āA�u�ǂ���Ёv��ڎw���P���Љ�B�u���{�l�͈�̕������ŏ�������郌�[���ɉ������߂��A�\�͂̉肪�E�܂�Ă��܂����v �Ɛ��̋�����@�ɂ��̈��������Ƃ������Ƃ��w�E���Ă���B
�����Ď��Ɂu�ӔC�v������邱�Ƃł���B
��ʌ����̂���������w�Z�ɂ����āA���k��̑I���Ŗ�肪�������������B���t���ǂ�Ȃɓ��������Ă������҂����Ȃ��B���k�����́A�l������O�ɏo��l�Ԃ́u�����߂���v�Ƃ����B���̊w�Z�ł͖��N�A�e�N���X���班�Ȃ��Ƃ�1�l�͌��҂��o�����Ƃɂ����B
�@�@�S���q�ǂ���A����i�����E�����j���A�e�q�ǂ���̃��[�_�[��ΏۂɎ��{����95�N�̒����B�u���炷����Ń��[�_�[�ɂȂ����v�Ɖ����̂͑S�̂�41���ƁA6�N�O�ɔ�ׂ�15�|�C���g�ቺ�����B�l�𑩂ˁA�ӔC�������Ƃ̉��l���}���ɉ������Ă���B
�������������Ƃ����Ȃ��ŁA�W�c�ɐg���䂾�˂Ă��܂��q�ǂ������B���̎p�́A�N������ƏI�g�ٗp�Ɏ���Ă����T�����[�}����A�h����x���c�̂̈ӌ��ɔ���ꂽ����c���ɏd�Ȃ�B
�e�E�ɗǂ����[�_�[��y�o���邽�߂Ɂu�v�Ƃ��Ă̐l�Ԃ�b���鋳���i�߂�C�O�ƁA���͊J�����肾�B
�ă}�T�`���[�Z�b�c�B�A���_�o�[�ɐe�q���̃u�b�V���đ哝�̂����Z������߂������w�Z������B1778�N�A�ēƗ��푈�̂��Ȃ��ɊJ�Z�����t�B���b�v�X�E�A�J�f�~�[�ł́A���t�Ɛ��k�̒���߂������Ŏ��Ƃ��i�ށB�u�č��ƃ��L�V�R�ł͓����l���ł��]�����S���Ⴂ�܂���v�u�����ƂƂ��Ĕނ̂Ƃ����s�����ǂ��v���܂����v�B����Ďj�̎��Ƃŋ��t��6�l�̐��k��ɖ�p�����Ɏ���𗁂т��A�_���̎コ���w�E����B�u�ǂ��K�����ł͂Ȃ��A�ǂ��l����̂���g�ɂ����������v�i�r���Z���g�E�G�C�u���[���������j
�@�قƂ�ǂ̐��k�͋��t�ƂƂ��Ɋw�Z�̕~�n���ɏZ�݁A�������K�͈ӎ����g�ɂ���B�����͂������A�F�l�̏h����ʂ�����ފw�����B�u�A���_�o�[�ōł��M�d�ȑ̌��́A�������g�ɂ��Ēm�������Ƃ��v�B�u�b�V�����哝�͎̂��`�̒��ł��������Ă���B
�@�č��ɂ͂������������w�Z������������B���w�����x���[�����Ă���A�T���ȉƒ�̎q�ǂ��������W�܂�킯�ł͂Ȃ��B���Ɛ��̐i�H�������Ƃ�w�ҁA�X�|�[�c�I��ȂǗl�X���B
�Ƃ�����ΏO���Ɋׂ肪���Ȗ����`�����S�Ɉێ����邽�߁A���L���w���琶�k���W�߁A�����S���l�ނ���Ă�m�b�������ɂ���B
�����{�ł́A����������@�́u�G���[�g����v�Ƃ��ă^�u�[������Ă����B
����̖k���L�ꋳ���i���{�����O���j�j�́u���܂̐����E�̃��[�_�[�s�݂̔w�i�ɂ́A�����ƌ��͂̏W�����������{�l�̍�����������v�Ƃ݂�B�����A���ƕ����Ɍl�̔\�͂�������Ă��܂��ẮA�ϊv��������l�ނ͈炽�Ȃ��B
�@���������i43�j�B�đ��،��S�[���h�}���E�T�b�N�X��19�N�߁A�x���`���[�x����ЁA�l�I�e�j�[�i�����E�`�j��ɍ�N�]���������́A���{�ŋ�������̂͏��w�Z���w�N�����B���O�H������ł��镃�A�����̋߂̊W�ŁA���Ƃ͉p���ƕč��Ŋw�B�u���{�ł݂͂�Ȃ��������_�߂����ċ����Ă������A�č��̍��Z�ł͗l�X�Ȑ�������������邱�Ƃ��w�v
�@�O���[�o���ȑ勣���̂Ȃ��ŁA�������J�����[�_�[���ǂꂾ����Ă邱�Ƃ��ł��邩�B����́A���{�̎Љ���l�̑��l����F�߂��邩�ǂ����ɂ��������Ă���B
�@
| ��S�� | �@���{�̊�Ɠ�����̗��j�ƌ��� |
|---|
| | ��P�� | �@����܂ł̌o�c�ҋ��� |
|---|
���{��Ƃ̔N�����̂��Ƃł́A�����̌o�c�҂��v��I�Ɉ琬���Ă����V�X�e�������߂邱�Ǝ��̍���Ȃ̂�������Ȃ��B�E���̔\�͊J�������ϓI�������ɂ����s���Ȃ��B�����琬���Ǘ��^�̃}�l�W�����g���d������Ă����B�����A�@���Ɍv��E�\�Z�����肵�A�g�D�Ɛl�ނ����p�E�R���g���[�����Ė��ɑΏ����Ă������ɊS������B���[�_�[�V�b�v�Ƃ͂��̂悤�ȃ}�l�W�����g�Ƃ͈قȂ�A�r�W�����Ɛ헪��n�����āA�@���ɑg�D��ϊv���Ă������ł���B
����܂ł̓��{��Ƃɂ�����o�c�����ւ̓o�p�͗v���́A�I�g�ٗp�Ɋ�Â��x�����i�Ɗɂ₩�ȑI����O��Ƃ��Ă��āA�N������^�̏��i�����Ǝ����X�L���̍����l�ނ��d�������X���ɂ������B�����ʂł̔\�͂ƌo�c�I�Ȕ\�͂̈Ⴂ�m�Ɉӎ�����Ƃ������z���A�T���Ă���܂ł͊������Ƃ������Ƃ�������B
�o�c�����ւ̏��i�́A����T�����[�}���l���ɂ�����ŏI�ڕW�ł���A�o�c�̃v����g�D�I�E�̌n�I�ɗ{�����Ă����Ƃ������z��d�g�݂͑��݂��Ȃ������̂ł���B
�����̏ꍇ�A�o�c�S�̂̎��_���玖�ƍ\���𑨂��āA�K�Ȏ����z�����s���Ƃ������\�͊J�����s�[���̂܂܁A����ꂽ�Ɩ�����ł̎��тƌo���Ɋ�Â��Čo�c�҂Ƃ��Ă̒n�ʂɂ��P�[�X�����������B���[�_�[�J���Ƃ����F�����Ȃ������̂ł���B
���{��Ƃɂ����邱��܂ł̈琬�V�X�e���́A�E�\�ʌ��C�ɑ�\�����悤�ɁA�Ј��̏��i�X�e�[�W�̈��̃^�C�~���O�ňꗥ�Ɍ��C��^����������嗬�ł������B���̖ڎw���Ƃ���́A���ʂ̗D�G�ȃ}�l�W���[(�Ǘ���)�̗{���Ɏ�Ⴊ�u����Ă����B���{�ɂ�����T�����[�}���̎Љ�ʔO���猾���Ă��A�ے��╔���ɂȂ邱�Ƃ����̎Љ�I�X�e�[�^�X�ł���A�L�����A���҂̕W���l�Ƃ��čL���F�m����Ă�������ł���B
�������A�ŋ߁A�A�����J��ƂȂǂŌo�c�����̓o�p���c�_�����ۂɏo�Ă���_�_�̈�́A�u�}�l�[�W���[�ł͂Ȃ����[�_�[���v�ł���B�����ł����}�l�[�W���[�Ƃ́A�u�}�l�W�����g������l�v�ł���A�������g�Ŏd��������l�Ƃ��������A���l��g�D�����Ďd����������l�Ԃ̂��Ƃł���B����ɑ��ă��[�_�[�́A���炪���搂�͂��Ď��ɓ�����A���Ȃ̈�A�̍s����ʂ��đg�D�̖ڎw���ׂ������ցA�g�������ă��[�h���闧��̐l�Ԃ̂��Ƃł���B
���t��������A�`���I�ȃ}�l�W�����g�̊�{�ړI���A�����g�D�̑�����O��Ƃ��Ă�������܂��@�\���������鎖�ɂ���̂ɑ��āA���[�_�[�V�b�v�̊�{�@�\�́A���s�g�D�����悢�����֓������߂̕ϊv�̐��i�ɂ���B���̃��[�_�[�V�b�v�ƃ}�l�W�����g�̈Ⴂ�𐳂����F�����邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂ł���B
���̈Ⴂ�𐳂����F�������A�Ђ�����}�l�W���[�̈琬�ɕ��S���Ă������ʂ��A���{��Ƃɂ����Ă̌o�c�Ґl�ޕs���ɂȂ����Ă��܂����Ƃ�������̂ł���B
| ��Q�� | �@��Ɠ���w�̓o��
|
|---|
�o�u������ȍ~�A��Ƃ݂͂�����̌o�c�V�X�e���Ɏ��M�������A�V���ȃ��f����͍����铮�������܂����B����Ƃ̂Ȃ��ŁAMBA�̉��l�����߂ċc�_���꒼������A�����ł��r�W�l�X�X�N�[���^�̃J���L�������蕨�ɂ������ԋ���@�ւ����X�ƒa�����A������悵���w�i�ɂ͂��������S�����������ƍl���Ă������낤�B
�@����A�s���ɂ��������{�o�ς����ڂɁA�č��ł�90�N�㔼�Έȍ~�A���E�ɐ�삯�ăC���^�[�l�b�g�̕��y���i�݁A�r�W�l�X���f�������I�ȕω��𐋂��n�߂��B�ӎv����̐v����������A�K�w�ɂ��Ȃ��v���W�F�N�g�P�ʂ̎d�����r���𗁂т�ɂ��A�]���^�̃}�l�W���[����V�����^�C�v�̃��[�_�[�����߂���悤�ɂȂ����̂ł���B
�����ʼn��̐}�����Ă��炢�����B
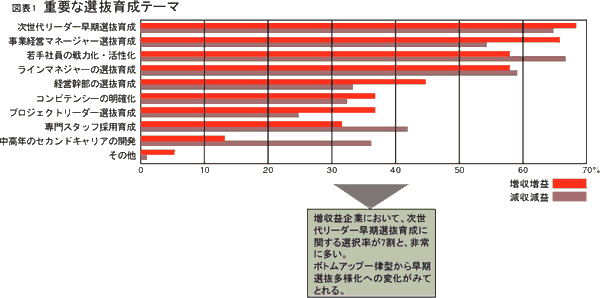
�o���@���N���[�g���[�N�X������
����́A�l���S���������邢�͐l�������ɑ��A����́u�d�v�ȑI���琬�e�[�}�v�ɂ��ĕ��������̂����A�u�����ナ�[�_�[�����I���琬�v�̑I�𗦂͖�V���ɒB���A���ɑ������v��Ƃɂ��Ă͂��̍��ڂ��g�b�v�ƂȂ��Ă���B
���̎�̒����ł͏]���A���C���}�l�W���[�Ȃǃ~�h���}�l�W�����g���^�[�Q�b�g�ɋ�����X���������������A����ł͂���ɉ����Ē����E���N���X�ւ̃V�t�g�����Ď���B�]���́u�{�g���A�b�v�ꗥ�^�v����u�����I�����l�^�v�̐l�ވ琬�ւƁA��Ƃ̐l�ފJ���̗͓_���ω������邱�Ƃ��킩��B
���̂悤�ɓ��{�ł��A����܂ł̉E���オ��̌o�ϋ�Ԃł̔��z�⊵��e���o�c�̂������ʗp���Ȃ�����ƂȂ��Ă����B���̂悤�Ȏ���ɂ͌l�̎����Ɉˑ������\�z�͂Ő헪��`���A�������̓I�Ɏ����ł���悤�Ȑl�ނ��K�v�ƂȂ�B�܂�A���N�����Ă��鎖�ۂ���w�сA����̍\�z�X�y�[�X���g�����邱�Ƃ̂ł���悤�ȃ��[�_�[�V�b�v���������l�ނ����߂��Ă���̂ł���B
���̂悤�ɑO�߂ɏq�ׂ��悤�ȓ��{��Ƃɂ����邱��܂ł̋���V�X�e���Ȃ��A��Ƃ͍��A������̌o�c������g�D�I�E�v��I�Ɉ琬���邱�Ƃɖڊo�߂��̂ł���B�����āu�o�c�̃v���v�����I�E�헪�I�ɔy�o������d�g�݂�n�o���邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����Ɠ���w���o�ꂵ�Ă����̂ł���B
| ��R�� | �@���{�̊�Ƃ̎��� |
|---|
�����܂ʼn��Ă̊�Ɠ���w����{�̊�Ɠ���w�̗��j���ɂ��Č��Ă����B���ɂ��̐߂ł͓��{�̊�Ƃ��ǂ̂悤�ȗ��O�̂��Ɗ�Ɠ���w������A�����łǂ̂悤�Ȏ������H����Ă���̂����ڂ������Ă������Ǝv���B
�@
���R�A�l�ޑI���琬�^��
| �E�\�j�[�̎��� |
�\�j�[�́A������̃r�W�l�X���[�_�[�̔��@�E�琬��ړI�ɁA�Q�O�O�O�N�P�P���ɐݗ����ꂽ�Г�����@�ւƂ����u�\�j�[���j�o�[�V�e�B�v��ݗ������B�ŋߎ��X�Ɛ��܂�Ă����\�ȏ�̐V���Ȍ��C�v���O�������ꊇ���Ď��{����B�e��v���O�����ɑI�ꂽ�\�j�[�Ј����炪�C�m�x�[�V�����G���W���ƂȂ�A�ϊv�̃��[�_�[�Ƃ��Ċ��邱�Ƃ����҂���Ă���Ƃ����B
���̃��j�o�[�V�e�B�̓����́A���ƌ����Ă��o�c�g�b�v�Ƃ́u���ڂ̑Θb�v�ł���B�o��CEO�A����COO���ϋɓI�Ƀv���O�����Ɋ֗^���āA���ڂ̑Θb���d�˂Ȃ��烊�[�_�[�̈琬�ɓw�߂Ă���悤�ł���B�����ナ�[�_�[����Ă�̂ɁA�n�Ǝ҂ł���Ƃ��o�c�g�b�v�Ƃ̉�b���傫�ȗ͂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͐����Ŏ��ɂ���B�����������炢�l�ƒ��ژb���Ǝh���I�ŁA�������̂ł��낤�B��������Ă��Ă͕����͈炽�Ȃ��̂ł���B
�@�\�j�[�̐V�������[�_�[�琬�@�́A���C�Ȃǂ̍��w�����v��I�Ȕz�u�]���ɏd�_��u���Ă���_���������B
�@�S���E��100�̏d�v�Ǝv�����E���߁A���̖�E���ƂɁA�O���l���܂ގ��̊�������4�`5�l�����X�g�A�b�v����B���̌��ʁA�I���҂͍��v��500�l�K�͂ƂȂ錩�ʂ����B100�̖�E�́A�e�J���p�j�[��A��v�O���[�v�q��ЁA�C�O�q��Ђ̃g�b�v�N���X�����S�B���݂��̖�E�ɂ���l����l�����̃X�^�b�t���A30��A40��𒆐S�Ɍ��҂����X�g�A�b�v�A���̃v���t�B�����o�c�g�b�v�ɏW�Ă���B
�@
�I������R�ꂽ�Ј��̃��`�x�[�V�������l�����āA���X�g�̌��J�͍ŏ����ɂƂǂ߂���j�B���ґS���̃��X�g��c�����Ă���̂́A��\�������o���A�������ЁE�В����ō����s�ӔC�ҁiCOO�j�A������v�E���В����ō������ӔC�ҁiCFO�j��3�l�ƁA�l������̖����╔���N���X���l�����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@
���̃����o�[�ɂ���č\������u�G�O�[�N�e�B�u�E�q���[�}���E���\�[�X�E�R�~�b�e�B�[�v���B����͂��̈ψ���N2��W�܂�A���҂̐E������сA�R���s�e���V�[�i�s�������j�Ȃǂf�ޗ��ɔz�u�����߂�B�Ⴆ�A�c�Ǝ��т͔��Q���������̌o�����Ȃ����҂̏ꍇ�A���������ł���|�W�V�����ɔz�]����B�܂��A�}���l��������邽�߂ɁA�����|�W�V�����ɒ����A�������A�V�K���ƕ���Ȃǂɒ��킳����B100�̖�E�́A�o�c���̕ω��ɉ����āA�������Ă����B
�@
���҂̓\�j�[���Q�O�O�P�N�ɐݒu�����A���[�_�[�琬�̂��߂̎Г����C���x�u�\�j�[�E���j�o�[�V�e�B�[�v�ɎQ������B�����ł́A�����Ȃǂ̃}�l�W�����g�X�L�����w�Ԃ����łȂ��A�����O�̈ꗬ��ƃg�b�v�Ȃǂ��������u�`��\�肵�Ă���B�o��������d�ɗ����A�\�j�[�X�s���b�g�̌p���Ɏ��g�ށB�Q���҂ɂ̓O���[�v�̌o�c�ۑ�ɂ��Ă��A�c�_��������B
�@
���������z�u�]���⌤�C�Ȃǂ�ʂ��āA���҂������Ɉ���Ă��邩�A�p���I�Ƀt�H���[����B���҂͌Œ肹���A���N�A�d���̐��ʂ���x�����Ȃǂɉ����Č������B�\�j�[�E���j�o�[�V�e�B�[�ł́A�I�������Ј���Ώۂɂ������̂ƕ��s���āA�Г�����ŏW�߂��Ј��ɂ����l�̌��C���{���B���������Q���҂̒�������A�����ナ�[�_�[�@���Ă����l�����B
�@�]���A�\�j�[�̐l�ވ琬�̍l�����́A�e��̋���v���O������p�ӂ��A���Ƃ͌l�̈ӗ~�ɔC����̂���{�������B�l������̃L�����A�v�������l���A��]�̌��C��ʐM�u���Ȃǂ�I�ԁB���̈Ӗ��ł́A����̎����ナ�[�_�[����́A�\�j�[�����߂āA��Б��̈ӎv�Ől�ނ�I�����A���炷��P�[�X�ƌ�����B
�@�w�i�ɂ́A�l�̎����w�͂ɔC���Ă��ẮA�����ナ�[�_�[�̈琬�͎��ԓI�ɊԂɍ���Ȃ��Ƃ�����@��������B������������A�v��I�ɏd�v�ȐE���ɏA�����A�o�c�m�E�n�E���w����B�Ⴂ��������{�l�Ɏ��o�����A���Ȍ��r�ɗ�܂���_��������B
�E�g���^�����Ԃ̎��� |
���g���^�C���X�e�B�e���[�g�T����
�@
�g���^�����Ԃ͂Q�O�O�Q�N�P���ɁA�g���^�y�т��̊C�O���Ƒ̂��܂߂��O���[�o���g���^�̌o�c�ҁA�~�h���}�l�W�����g���琬����l�ވ琬�@���u�g���^�C���X�e�B�e���[�g�v���Г��g�D�Ƃ��Đݗ������B
�@�g���^�ł͋ߔN�A���Ƃ̒n��I�ȍL����A���Ɨ̈�̊g��ɔ������l�ȉ��l�ς����l�B���g���^�̃I�y���[�V�����ɎQ�悵�Ă��Ă���B�����������A����̃O���[�o���g���^���W�ׂ̈ɂ́A����܂ňÖق̓��ɓ`������Ă����g���^�̌o�c�N�w�A���l�ρA�������s��̎�@���̋��L���}���Ɣ��f�B�{�N�N���ɂ����̍l�������u�g���^�E�F�C�v�Ƃ��č��q�ɂ܂Ƃ߁A�O���[�o���g���^���ɓW�J�����B
�@�X�ɍ���g���^�ł͂��̃g���^�E�F�C�����L���A21���I�̃O���[�o���g���^�̎��ƓW�J��S���l�ނ��m�����p���I�ɔy�o�����悤�A�Г��̐l�ވ琬�Ɋւ��d�g�݂��n�[�h�A�\�t�g���܂ߔ��{�I�Ɍ����������{�B�O���[�o���g���^�̐l�ވ琬�̌�������S���@�ւƂ��āA�g���^�C���X�e�B�e���[�g��ݗ�����B
�@�g���^�C���X�e�B�e���[�g�̏���w���͎В��̒��x�m�v���A�C�B���A�^�c��S�����鎖���ǂ̓O���[�o���l�������������������C�A��C�X�^�b�t�Ȃǂ������P�U���Ŕ����B�܂����N��ɐ�p�{�݂������Ɍ��݂���\��ł��邪�A�Q�O�O�Q�N�t�������̌��C�{�݂𗘗p���v���O���������{����B
�@���̋�̓I�v���O�����́A�O���[�o���g���^�̌o�c�l�ވ琬��ړI�Ƃ���w�O���[�o�����[�_�[�琬�X�N�[���x�ƁA�g���^�E�F�C���H�ׂ̈̎��������ړI�Ƃ���w�~�h���}�l�W�����g�琬�X�N�[���x��ݒu�B�v���O�����̓��e�ɂ��Ă͎ЊO�ꗬ���猤���ҁA����@�ցi�č��y���V���o�j�A��w�E�H�[�g���Z�A�ꋴ��w�Ȃǁj�̋��͂Č��݊J�����ł���B
�@�g���^�͋ߔN��w�̌������𑝂����K�R���y�e�B�V��������ɂ����āA�l�ވ琬���ŏd�v�ۑ�̂ЂƂƑ����Ă���B�g���^�C���X�e�B�e���[�g�͂��̑S���E�I�Ȓ����Ƃ�����̂ŁA�g���^�E�F�C�̋��L�����Ɋe���Ƒ̗̂L�@�I�Ȍ������������āA�O���[�o���g���^�S�̂̌o�c�����̌����ڎw���A���a���鐬���𑱂��Ă��������ƍl���Ă���B
�@ ��ݗ��T�v��
�i�P�j�������̃g���^�C���X�e�B�e���[�g
|
| �i�Q�j�ݗ��̑_�� |
�E
�g���^�E�F�C�̋��L��ʂ��Đ^�̃O���[�o�����𐄐i�B
�E
�O���[�o���g���^�̐l�ވ琬�̌������Ƃ��ċ���̐��̐����𐄐i�B |
| �i�R�j�ݗ����� |
�Q�O�O�Q�N�P�� |
| �i�S�j�{�� |
�O�P�����C�����A�����{�݂ʗ��p�B
�i���N��ɐ�p�{�ݐV�݂̗\��j |
| �i�T�j������e |
�w�O���[�o���g���^�̌o�c�l�ވ琬�x�Ɓw�g���^�E�F�C���H�ׂ̈̎�������x |
| �i�U�j�Ώ� |
�g���^�y�ъC�O���Ƒ̂̃O���[�o�����[�_�[���ҁA�~�h���}�l�W�����g�w |
| �i�V�j�����w |
�g���^�����A��E�A�ЊO�ꗬ����@�֍u�t�� |
| �i�W�j�g�D |
| �w�@�� |
�F �g���^������(��)�@���@�x�m�v�� |
| ������ |
�F �O���[�o���l�������������������C�B
�@ ��C�X�^�b�t�Ȃǂ������A�P�U�l�̐��Ŕ����B |
| �ʒu�t�� |
�F �� ���i�g�D |
|
| �@ |
�O���[�o�����[�_�[�琬�X�N�[�� |
�~�h���}�l�W�����g�琬�X�N�[�� |
| �_�� |
�O���[�o���g���^�̎��_�ŁA���[�_�[�V�b�v�������ł���o�c�l�ނ̈琬 |
�����A�̔����哙�A��v����ʂɊe����̃g���^�E�F�C��̌n�I�ɗ������A���H�ł���}�l�W�����g�̈琬 |
| ���e |
�E
�g���^�E�F�C�Ɋ�Â��w���͂̌���
�E �o�c�m���A�X�L���̋���
�E �O���[�o���l���`�� |
| ��������F |
�g���^�̐������Ƒ̉^�c�S�ʂƐ�������̃g���^�E�F�C�����@�� |
| �̔�����F |
�g���^�̔����O�Ɋ�Â��ŐV�}�[�P�e�B���O��@�̗����@�� |
|
��u
�Ώ� |
�S���E�̏����̃O���[�o�����[�_�[
��P�W�O�l�^�N |
�S���E�̃~�h���}�l�W�����g�R�O�O�l�^�N |
�@
�����@�琬�^��
�E���j�`���[���̎��� |
�@
���j�`���[�����A�o�c�̌�p�҂ƂȂ���̈琬��ړI���u���j�`���[���r�W�l�X�J���b�W�v���Q�O�O�O�N�ɐݗ������B�������]���͑I���Ō��҂�I��ł������A�N�ł�����ł�����含�ɂ��āA�I�����甭�@�ɗ͓_��ς����B�������S�����[�_�[�̈琬�ɖ{�i�I�Ɏ��g�݂����Ƃ����A�n�Ǝҍ�����̋������[�_�[�V�b�v����������Ă���B���̃r�W�l�X�J���b�W���g�b�v�Ƃ̘b�������̏ꂪ����B
�F�u���j�E�`���[���r�W�l�X�J���b�W�v�T�v�F
�E�o�c�Ҍ��̎����f
�@�Ј��̃r�W�l�X�m�������߂�Ӗ��ł́g���{�I�h�ȎГ��X�N�[���͐��������A���j�E�`���[���r�W�l�X�J���b�W�́u�o�c�̌�p�҂ƂȂ���̈琬�Ƃ����ړI�͖��m�B�v���O������ʂ��ē������𗘗p���Č�p�Ҍ��Ƃ��ĕs���Ȏ����̗L���f����v(�������{���l�ފJ��������O���[�v�}�l�[�W���[�E�Ė{�O��)�B���[�_�[�琬�v���O�����Ƃ��Ă��Ȃ蓥�ݍ����e�ƂȂ��Ă���B
�@���Ђ͂���܂Ōo�c�҈琬���x�Ƃ��āu�~�h���E�}�l�W�����g�E�{�[�h�E�I�u�E�f�B���N�^�[�Y(MMBD)�v�����{���Ă������A���j�E�`���[���r�W�l�X�J���b�W�͂��̐��ʂ���{�I�ɂ͎p�����A���Q���҂̎��含���d����������ʼn��ҁE�����������̂Ƃ�����B
�@
MMBD���X�^�[�g�����̂�94�N�B�������S�����[�_�[�̗{���ɖ{�i�I�Ɏ��g�݂����Ƃ��������c��N�В��̈ӌ����Ďn�܂����B�Q���҂͎w�����ŁA�e�E�ꂩ�疈�N15�l��I���B�N��w��35�`40�Α�O���A����30�Α�㔼�Ƃ����̂��ڈ����B
�E�����̌o�c�ۑ肪�f��
�@���Ԃ͖��N4�`12����9�J���ԁB����1��A���E�y�j��2���ԁA���h�`���ōs����B�J���L�������͑O���ƌ㔼�ɕ�����Ă���A�O���̓X�N�[���`���ŁA�o�c�헪��}�l�W�����g�A�A�J�E���e�B���O�A�t�@�C�i���X�Ȃnjo�c�҂Ƃ��ĕK�v�Ȋ�{�I�m������̓I�ȃP�[�X�𒆐S�ɂ������\�b�h�Ŋw�ԁB
�@�㔼�͂���Ύ��K�P���B���j�E�`���[���Ɍ����ɑ��݂��Ă���o�c�ۑ�����グ�A����ɑ����������Ă�12���A�o�c�w�ɓ��\����B�u�o�c�ۑ�ł͂��邪�A�܂��肪�����Ă��Ȃ��e�[�}��I��ł���B���e����ł͒����̂܂܉�Ђ̐헪�ɂȂ�̂ňӋC���݂��Ⴄ�v(�Ė{��)�B����܂łɂ���Ɨ��O�̍���⒆�����Ɛ헪�ȂǂɊւ���e�[�}�ŁAMMBD����̓��\�����s�Ɉڂ���Ă���B
�@MMBD�̑�5�����ł��鑍�����{���Q���A����V���́u���̃J���L���������I����Όo�c�҂ɂȂ��Ƃ������̂ł͂������Ȃ����A�o�c�ɕK�v�Ȓm�����w�Ԃ��Ƃœ���̎d�������鎋�_���ς�����B���Ƃ��Ηʔ̓X�ւ̉c�ƂɃt�@�C�i���X�̒m���͕s�v�ɂ݂��邩������Ȃ����A�����Ӑ�̊�Ƃ�����ڂ͐[���Ȃ�A�o�c�҂ƈ���˂����b���ł���B���̐ςݏd�˂��o�c���o���Ă����̂��Ǝv���v�Ƙb���B
�@
���̃v���O�������́A�Q������Ώ��i���ۏ����Ƃ��������̂ł͂������Ȃ��B�����������ɂ́u��1���̑��Ɛ��͑��������s����(��s)�N���X�ɂȂ��Ă���B�\�͂�ʂŏ�������Ƃǂ����Ă������Ȃ��Ă��܂��v(�Ė{��)�B
�E�I�����甭�@��
�@�����������ʂ܂��A2000�N�t����̑�7���ł́A�`���ɐG�ꂽ�悤�ɖ��̂��u���j�E�`���[���r�W�l�X�J���b�W�v�ƕς��A���e����V�����B��ȕύX�_�͎��̂悤�Ȃ��̂��B
�@
�܂��]���͐l������̎w���������Q���҂��A����2�N�ڈȍ~�̎Ј��Ȃ�N�ł�����\�Ȍ��吧�ɂ����B�u�I�����甭�@�ɐ��x�̗͓_��ς����B�w�Ԉӗ~�⎩���w�͂̐��ʂ̍����l�ނ@�������B�N�ł��@��͋ϓ��A���������ʂ͎s�ꌴ���ɂ���ċϓ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����l������O�ꂵ���v(��)�B
�@����҂�ΏۂɌo�c�Ɋւ����b�m����₤�y�[�p�[�e�X�g��21�l�̎Q���҂����肵���B�Ė{���́u�e�X�g�̌��ʂ����Ă��A��N�܂ł̉�Ўw���̊�Ԃ�����̂��قǂ̃����o�[���W�܂����B�Ј��̈ӗ~�̍������������Ă���v�Ƙb���B
�@��2�̑傫�ȕύX�_�́A�J���L�������̈ꕔ���Г��̎�����⎷�s�������u�t�Ƃ��ĒS�����鐧�x�ɂ������Ƃ��B�O���ɂ͏]�����炠��r�W�l�X�t���[�����[�N�̏K�������ɉ����A�����E���s�����ɂ����H�I�ȍu����݂���B���e�̓}�[�P�e�B���O��o�c�헪(���یo�c)�A�l�E�g�D�A�A�J�E���e�B���O�A�t�@�C�i���X�Ȃǂ�\�肵�Ă���A�����炪�݂�����P�[�X���쐬���A���Ƃ��s���B
�@�u������⎷�s�������P�ɍu����S�����邾���łȂ��A�����̌o�c�җ{���ɐӔC�������A���j�E�`���[���r�W�l�X�J���b�W����̒ɑ��Ă��p���I�ɃR�~�b�g���Ă����̐����\�z����v(�Ė{��)�Ƃ̖ړI�ɉ��������̂��B
�E���͏����Ɍ��т���
�@����܂łɑ��Ɛ��̑��������s�����ɏA�C���Ă��鎖���͂�����̂́A����́u�o�c�Ҋ��o���������l�ɂȂ�܂��傤�A�Ƃ������{�I���i���Z���v���Ƃ͕Ė{�����F�߂�B����������A�n�Ǝ҂ł͂Ȃ����オ�o�c�̑ǎ���S���ƂȂ�A�q�g�E���m�E�J�l�Ƃ����o�c�����S�̂�������\�͂̎�����ł��邱�Ƃ����߂���B���̈Ӗ��Ń��j�E�`���[���r�W�l�X�J���b�W�́u�P�Ȃ�Ј��̋���T�[�r�X�ł͂Ȃ��B�������Ԃ�͏����Ɍ��т��Ƃ����_�̓n�b�L��������v�ƕĖ{���͋�������B
�@����Ɂu�g�I���h�Ƃ������t����l��������ƁA�u���b�N�{�b�N�X�I�ȃC���[�W�����܂�A�I��Ȃ������l�̃����[���_�E���������N�������˂Ȃ��B�����������Ƃ�g�ɂ����A�����������ʂ��o�����l�����j�E�`���[���͔��F����̂��A�Ƃ������Ƃm�ɂ��Ă��������B�w�@��ϓ��A�s�ꌴ���ɂ�錋�ʂ̕s�ϓ��x�Ƃ͂��������Ӗ������߂Ă���v(��)�B
�@���������v��������p�Ҍ��琬�v���O�������ł���w�i�ɂ́A���Ђ��u�n�ƂƊv�V�v�u�I�[�i�[�V�b�v�v�u�`�������W���[�V�b�v�v�u���[�_�[�V�b�v�v�u�t�F�A�v���C�v�Ƃ����u�䂪5�吸�_�v���f���A�n�ƌo�c�҂ł��鍂���В��̂��ƁA�_��ȁu�o��Y�͐������v�g�D�̎�����ڎw���Ď��g��ł������т�����B
�@20�`30�Α�O���̎��Ј����o�c�ۑ�����Čo�c�w�ɒ���u�W���j�A�{�[�h�v�̐��x��X�l�̃L�����A�v������C�t�v�����ɍ��킹�ăL�����A�R�[�X��I�ׂ�u�L�����A�I�𐧓x�v�A�N1��A�l�̃L�����A��X�L�������A�ٓ���]�����Ȑ\������u�L�����A�X�L�������v�ȂǁA�u�v�����ɑg�D���l���镗�y�������Ă����A�o�c�҈琬���x���L���ɋ@�\����_�������Ƃ����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�o�c�����߂�l�ޑ��m�ɂ��A�����ɓ��B�����i�������ŁA��͌l�̎����w�͂Ǝs�ꌴ���ɔC����Ƃ������Ђ̎p���́A���[�_�[�琬���l����ЂƂ̕������������Ă���B
�E���j�E�`���[���r�W�l�X�J���b�W�v���O����
4�`8���̑O���͍����В��̌P���Ɏn�܂�A�o�c�m���̊w�K�A������E���s�����̍u���ɑ����āA����̌o�c�ۑ�̌����ւȂ��鏀����Ƃ��s���B
9�`12��������ے��ŁA��̓I�Ȍo�c�ۑ���O���[�v�Ō������A�ŏI���\���܂Ƃ߂�B���\���F�߂���A�����̎{��ƂȂ��Ď��s�����B
�@
| ��T�� | �@���Ă̔�r�Ɩ��_ |
|---|
�O�͂܂ŁA���Ă��\����GE�̎��݁A�����ē��{�ɂ����鎟���ナ�[�_�[�琬�̕K�v���Ƃ��̔w�i�B����ɂ͓��{��Ƃɂ����邳�܂��܂Ȏ��݂ɂ��Č��Ă����B
���̏͂ł́A���{�̕��y�̖�蓙�܂�����ʼn��Ċ�ƂƔ�r�����A����������{��Ƃ̌���̖��_���l�@���Ă������Ǝv���B
| ��1�� | ���C����̔�r |
|---|
�]�����{��Ƃɂ����錤�C�v���O�����̎�͂́A���ጤ���i�P�[�X�E�X�^�f�B�j�ł���B���ۂ̌o�c����O�ɂ��āu���炪�����҂ł���A�@���Ȃ�����������邩�v����������̂����ጤ�������A���Y���C�Ƀt�B�b�g�����P�[�X�쐬�Ɏ��Ԃ��������ɁA���_�ɂ���č����I�Ȍo�c�ӎv����ɂ������邱�ƂɊ���Ȃ����C�Q���҂ɁA�\����������Ă��Ȃ��̂����łł���B
�A�N�V�����E���[�j���O�́A�P�[�X�E�X�^�f�B������ɐi�߂��`���ŁA��̓I�ɂ́u���Ђ̕�����d����ɂ��W�e����̃��[�_�[�ƃI�[�v���Ȍ`�ŋc�_���A�Ή����ł��o���v���̂ł���B�Ή��g�b�v�ɂ���č̗p�����A��Ď҂����̖������̐ӔC�҂ɔ��F����邱�Ƃ��������Ƃ���A���C�Q���҂����R�^���ɂȂ炴��Ȃ��B�����܂Ŏ��H�I�Ȍ��C�ł��邱�Ƃ��A�f�d���n�߂Ƃ���č��̊�Ɠ����C�̓��F�ƍl������B���̓_�Ń��j�`���[�������݂Ă���A�N�V�����E���[�j���O�͑���Ƃ����������Ă���Ƃ����邾�낤�B
�܂���Ɠ����C�ň�ԏd�v�Ȃ̂́A���C�v���O�����̍쐬�ł��邪�A�����
�@���C�S���҂̖��ӎ�
�A�o�c�`�[���̐ϋɓI�Q��
���̓�Ɋ|���Ă���B�č��ł͎Y�w���͑̐����i��ł��邱�Ƃ���A��w��������ƃT�C�h�̈˗����ċ��ނ��쐬����Ƃ��A�u�`���s���Ƃ�����ʉ����Ă���B����Ɏ��Ƃ��Ă��A���ꂪ�Г����i�Ɏ~�܂邾���ł͖ʔ����Ȃ��Ƃ̎�u�҂̋C���������݂��āA��Ɠ���w�̓���̍u�����C������ƁA������g���Ă����w�̒P�ʂƂ��ĔF�߂鐧�x���X�^�[�g���Ă���B
GE�AIBM�Ȃǂɂ����ẮA�����o�c�����ɂȂ�\���̍����҂��u�n�C�|�e���V�����v�Ƃ��đS�̂�5%���x�I������B���̒��ɂ�20�Α�㔼����30�Α�O���̂�����g���h���������I��顂��̃��X�g�͖��N��������A����ւ����s����B�����ă��X�g�A�b�v���ꂽ�e�l�ɂ��Đ��N�A�ꍇ�ɂ���Ă�5�N�ɘj��L�����A�v�悪���肳���B���̂悤�ȏ����̌o�c�����̌v��I�J���̈�Ƃ��āA���C���g�ݍ��܂�Ă���B���ɏ�����������Ǝv����l��30�ォ��40��ɂ����đI�����A��Ƃ̃g�b�v�ɂȂ邽�߂ɕK�v�ȋ���A�o�����v��I�ɗ^���Ĉӎ��I�Ɉ琬���Ă����B���̃v���Z�X�͐l�����傾���̖��ɗ��܂炸�A�o�c�g�b�v���g���Q�悷��S�ГI�Ȉψ���ɂ����ĉ^�c����Ă���̂����F�ł���B
���{��Ƃ͂���܂Ŗ{�l�̎����ɊW�Ȃ����܂��܂ȋƖ����o�������郍�[�e�[�V�������̐l�����s�ɂ���đ����̃[�l�����X�g�����Ԃ������č���Ă����B�������Ȃ���v���t�F�b�V���i���̌o�c�҂��琬���邽�߂ɂ͑����I�����Ɍ����Đl���V�X�e���̔��{�I�ϊv���K�v�ƂȂ��Ă���B
���{�ɂ�����o�c�җ{���v���O�����͉ʂ����Ă��̂悤�ȕϊv���čs���Ă���ł��낤���B�l������̐������ǂ��ł���A�Q���Ҏ��g�̈ӎ��͓`���I�Ȍ��C���x�̒P�Ȃ鉄�����ɂƂǂ܂��Ă��Ȃ����낤���B�l������̐������ǂ��ł���A�Q���Ҏ��g�̈ӎ��͓`���I�Ȍ��C���x�̒P�Ȃ鉄�����ɂƂǂ܂��Ă��Ȃ����낤���B���ɐl�����傪�u�I���v�Ƃ����Ă��A���O�ɏI����āA���Ԃ͊e���傩�碏����裂��邢�͢�d����s�������ң�Ƃ������ƂɂȂ鋰��͂Ȃ����낤���B�����͍����u�ŃX�^�[�g���Ă��A���{�I�Ȑl���V�X�e���ɕω����Ȃ���A�����o��ɂ�A���x�v�҂̈Ӑ}�ɔ����ė��Ă������̂ł���B
| ��Q�� | �Q���҂̑��l�� |
|---|
�X�ɁA�O���[�o����Ƃ̌o�c�җ{���ɂ����ẮA�Q���҂́u���l���v���d�v�ȉۑ�ł���B���{��Ƃ̑唼�͂���܂œ����Љ��O��Ɍo�c���s�����Ƃ��ł����B����O���[�o���Ȏ��ƓW�J���ƕ����̈قȂ��Ɠ��m�̍����A�A���C�A���X�Ȃǂɂ���Ă��̑O�傫���������B�܂��Ɂu���l���v�̒��łǂ��}�l�W�����g�����邩������Ă���B
�Г��̓��{�l�������Q������v���O���������Ђ̊�ƕ����A��Ɛ헪���l�����ŁA�������Ӗ��͂��邾�낤�B�������Ȃ���A���ꂾ���ł͂��ꂩ��̃O���[�o����Ƃ̌o�c�҂Ƃ��Ă͕�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B�����{���̂��߂̊�Ƒ�w��ݗ��������{��Ƃɂ����Ă��A���ꂾ���Ŗ�������̂ł͂Ȃ��A�Q���҂́u���l���v���m�ۂ����O���@�ւ̊��p�������čl���Ă݂鉿�l������̂ł͂Ȃ����낤���B
| ��R�� | �����I���� |
|---|
���{��Ƃ͍��A�I�y���[�V�����̌��������߂邱�Ƃɂ�荑�ۋ����͂�Nj�����Ƃ������ߋ��̐����̌�����̒E�p�𔗂��Ă���B�����Ă��̂悤�Ȍo�c���̕ω��ɏ]���̃V�X�e���ł͑Ή��ł��Ȃ��Ƃ̐ؔ��������ӎ�����o�c���v��i�߂Ă���B���̌o�c���v�̃e�[�}���g�D�ϊv�Ƃ����n�[�h�̉��v����A��l�ޣ�̖��ɒ��ڂ��ă\�t�g�̉��v�ւƐi��ł��Ă���B
���{��Ƃ͂���܂ŔN������̎v�z��w�i�ɁA���ДN���⌨�����Ɋ�Â��K�w�ʌ��C���قƂ�ǂł������B���A�܂��ɑI�����̋���E���C���x�����āA����̌o�c�҂��ӎ����Ĉ琬���悤�Ƃ����Ƃ������Ă��Ă���B���̂悤�Ȃ���܂łɂȂ��V���ȕ����ɓ��ݏo�����Ɩ͍�����ꕔ��Ƃ̍ŋ߂̓����͒��ڂɒl����B
�����A�����ɂ��̒��Ɏ�̊낤������������B�����A���{��Ƃ̖��_�Ƃ��Ă����Ύw�E����邱�Ƃł��邪�A���Ђ��s���Ă��闬�s�̎�@�������тœ�������X���ł���B�l�������A�В��ȂNJe���x���ł̏������̏�A���邢�̓}�X�R�~����̏���ʂ��čŋ߂̃g�����h���d����A���x��܂��Ƃ���Ή����J��Ԃ��Ă��Ȃ����B���s�������A�ЊO������A���ʎ�`�A�Ȃǂ̓��������s�ɂȂ��Ă��铮���̒��ɂ����̂悤�Ȋ낤����������B�o�c�җ{���V�X�e�����u�I���v�E�u���[�_�[�̈琬�v�ȂNj��ʂ̃L�[���[�h�̂��ƂɁA�e�Г����悤�Ȑ��x�����̂P�A�Q�N�ɓ�������Ă���悤�ł���B
�܂��A�A�����J�Љ�ɂ����Ă͑����I�����Ƃ������x���ʗp���Ă��A���{�ł͎Ј��̃`�������W���_�����܂����ŁA�I��Ȃ������҂̃��������ቺ����Ƃ������O������B���{�ɂ͐̂��畽���ӎ��Ƃ������̂����������A�I�����Ƃ�������Ӗ��Łu�G���[�g����v�Ƃ����鐧�x�̓^�u�[�ƂȂ��Ă������炾�B
���������݂��̃^�u�[�ɗ����������Ƃ������Ă���Ƃ����Ă������낤�B���̂܂܂ł͊�Ƃ͋����͂������A�o�c�҂��Ј������|��ɂȂ��Ă��܂���������Ȃ��B
�����Ń������̒ቺ��h�����߂̕��@�Ƃ��āA���j�`���[�������H���Ă���A�����������Ƃ�g�ɂ����A�����������ʂ��o�����l���킪�Ђ͔��F����̂��A�Ƃ������Ƃm�ɑł��o�����Ƃł���B�w�@��ϓ��A�s�ꌴ���ɂ�錋�ʂ̕s�ϓ��x���̍l�������厖���Ǝv����B
��������Α����̎Ј��́A�G���[�g�Ƃ��đI�ꂽ�����o�[�̋��ʍ���T�����낤�B�܂��A�G���[�g���ǂ�ȋ������̂��ő���ۂ�Ō���邾�낤�B�����Ď��炪�ǂ��s�����ׂ��Ȃ̂��̎������������猩���o�����ɂȂ���̂ł���B
| ��U�� | �@���{�̎����ナ�[�_�[�̈琬�� |
|---|
| ��1�� | �o�c�҂̃R�~�b�g�����g |
|---|
����܂œ��{��Ƃ͑I��Ȃ��҂̃������̒ቺ���x�����āA���̑����I�����S�O���Ă����B���̂悤�ȓ��{��ƂɂƂ��āA�����̌o�c�����ɂ����āu�G���[�g�̈琬�v�Ƃ������{�I���y�ɍł����e��Ȃ��ۑ�A����Ӗ��ł̓^�u�[������Ă������Ƃւ̃`�������W�ɒ��ʂ��Ă���Ƃ�����B
�ߎ��̌o�c�җ{���V�X�e���̓����̖{���I�Ӗ������͂܂��ɂ��̓_�ɋ��߂���B����͈ӎ��̕ϊv�ł�����A���ꂾ���Ɍo�c�Ҏ��炪���߂�o�c�ґ�������܂łɂȂ����m�ɂ��邱�Ƃ��s���ɂȂ��Ă���B����͌o�c�Ҏ��g�̖ڎw�����[�_�[�V�b�v�̃X�^�C���ł�����B�����āu�l������̖��ŁA�������ł�������F����悢�v�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B
�E���オ��̎���ɑ�������ꂽ�u�Ǘ��^�v�̌o�c�ł͂Ȃ��A�u�ϊv�^�v��ڎw���Ƒ����̌o�c�҂͂����B���ꂪ�A�{���ł���Ȃ�A�ϊv�^�̃��[�_�[���ǂ����@���A�ǂ���Ă�悢�����o�c�Ҏ��炪�l���������Ƃ��K�v�ł��낤�B�����̊�Ƃ͌o�c�җ{���v���O�����ɂ��āA�I�������̗p���A�l�����x�ƘA��������Ƃ����B���̍ہA�I������Ƃ��̢�D�G�ȣ�l�ނ̔��f��Ƃ͉����B�]���̂�����u�d�����ł���l�v�ɍ���̑g�D�̕ϊv�����҂ł���̂��B�v���O�����̓��e�����̂悤�Ȏv�z�A�N�w�ɍ��v�������̂��B�܂��ɁA�o�c�Ҏ��炪�v���`�����[�_�[�V�b�v����̌����鐧�x�v�łȂ���A�Q���҂Ɍo�c�҂̢�v�����`���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł��낤�B
���̂��߂ɂ́A���x�v�̃v���Z�X����ю��ۂ̐��x�^�p���̂��̂Ɍo�c�Ҏ��g�����ڐ[���֗^���āA�`�����łȂ��{�C�ł��邱�Ƃ��������Ƃ��ɂ߂ďd�v�ɂȂ�B
GE�̃W���b�N�E�E�F���`�O��́A�o�c�җ{���v���O����������̒������ƂƂ��Đ[���R�~�b�g���A�ߖ��X�P�W���[���̒��ɂ��N��20��O��o�c�����ɑ��Ē��ڍu�`���s���Ă����Ƃ����B���̒��ŎQ���҂ɂ́A�u���������Ȃ�����������GE��CEO�Ȃ����Ƃ���ƁA�ŏ���30���ł��Ȃ��͉������邩�v�Ȃǂ̉ۑ��^���āA�ꏏ�ɓ��c������B
�܂��A�o�c�҂̈琬�͒P�Ɍ��C�A����Ƃ������w�����łł���킯�łȂ��B���F�������Ɍo�c�̌o�����q��ЂȂǂŐς܂���Ȃǂ̐l���V�X�e���Ƒ��܂��āA�͂��߂Č��ʂ����҂ł���B
������{��Ƃɂ����Ă�����܂ł̎q��Аl���̈ʒu�t���{�I�Ɍ������K�v�ɔ����Ă���B���Ŕ��F���ꂽ�o�c�������Ɍo�c�̏C������o�������邽�߂ɁA�q��Ђł̌o�c�o�����L�����A�v�����̒��ɑg�ݍ���ł݂Ă͂ǂ����낤���B���������u�e��Ёv�u�q��Ёv�Ƃ����Ăѕ����̋��ԈˑR���锭�z�Ƃ�����B�ߎ��̃J���p�j�[���A���Љ��̓����͊������Ɍo�c�o���̋@���^����������B�o�c�җ{���v���O���������̂悤�Ȕ��{�I�Ȑl���V�X�e���̉��v�ƘA�������ĉ^�p���A�g�[�^���̌o�c�җ{���V�X�e���̈�Ƃ��Ĉʒu�t���Ă����Ӗ�������̂ƂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
| ��Q�� | ���[�_�[�{���ɗ��ӂ���|�C���g |
|---|
�P�D20�ォ�玩���̔��f�Ŏd����i�߁A���[�_�[�V�b�v������ꂪ�^�����Ă��邱��
GE�Ŏ��H����Ă���悤��20��A30��ȂǎႢ��������C����Ȃǂɐg��u�����ƂŁu���ނ���v�o����������B
�Q�D�َ��Ȃ��̂����e����A�o��Y���ł���Ȃ����R�ȕ��y
�u�o��Y�͑ł��Ȃ��v(�I���b�N�X)�A�u�o��Y�͐������v(���j�E�`���[��)�Ƃ����\���Ɍ�����悤�ɁA�݂�����u�o��Y�v�ɂȂ낤�Ƃ���ӗ~����l�ނ��x�����悤�Ƃ����p����厖�ɂ���B
�R�D�����^�[(�l�܂��̓����^�[�I�ȎЕ�)�̑���
���[�_�[������y�Ƃ������Ƃ��l����Ƃ��A���̎��������l�ނ̑��k����⏕���҂Ƃ��Ẵ����^�[�̑��݂��d�v�ł���B�����ɂ̓����^�[�Ƃ��Ă̌l�̂ق��A�g�D�S�̂Ƃ��Ă��̐l�Ԃ̐����������������A�x�����悤�Ƃ����g�����^�[�I���͋C�h���܂߂Ă������낤�B
�S�D�����I�ȑI���A�L�����A�f�U�C���x���̎d�g�݂����邱��
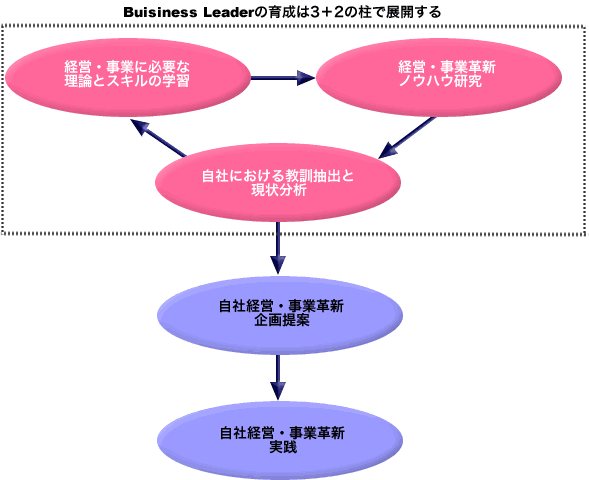
�i�o���@���{�\������}�l�W�����g�Z���^�[�j
��}�̂悤�ȃ��[�_�[�琬�ɕK�v�Ƃ����L�����A�f�U�C���m�ɂ��A�����I�Ɏ��s������B
�T�D�I���Ώێ҂̑I�����@��I�����̌n�I�ɐ�������
�U�D�A�N�V�������[�j���O�̃e�[�}�i���Ђ̌o�c�ۑ�j�̐ݒ�ɏ\���ɒm�b���i���āA�w�K���ʂ̍������̂ɂ���
�V�D��u�҂̃v���O�����C����̐����x�����p���I�Ƀ��j�^�����O���A�ǂ̂悤�ȃ|�X�g�ɔz�u���Čo�����܂��邩�A�X�̎�u�҂̃L�����A���v��I�ɐv���Ă���
| ��R�� | ���[�_�[�琬�Ɗ�Ɠ���w |
|---|
�Q�P���I�͕ϊv�Ɛ헪�̎���ł���B��ƌo�c�̑ǎ����헪�̋�̉����g�D�\�͂̌�����A�l�i�o�c�҂̃��[�_�[�V�b�v�\�́j��ʂ��čs�����͂Ȃ��B
���̈Ӗ��ŁA�Q�P���I�̓��[�_�[�V�b�v�̎���ł���B
�g�D�̒��ɂǂꂾ���D�G�ȃ��[�_�[��I���A�琬���A���p�ł��邩���A���ꂩ��̊�Ƃ̖��^�������Ă���Ƃ����邾�낤�B
���̗���̒��œo�ꂵ�Ă�����Ɠ���w�B�܂����݂Ƃ��Ă͓������߁A���ʂ��o��̂͂܂���̂��ƂɂȂ邩������Ȃ��B
��������������̗��s�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A���ꂩ��̃O���[�o���ȋ����Љ���������߂ɁA���낢��Ȏ��s����̂��Ǝ����ナ�[�_�[�{���@�ւƂ��Ċm�����Ă����Ăق����Ǝv���B
| �I�� | �@�ꌾ |
|---|
�����s����ψ���́A����17�N�x�ɐݒu�����s���̐V��w�ƍ����w�Z�Ƃ̘A�g�ɂ��A���{�̏�����S��������v�^���[�_�[�Ƃ��Ă̎��������l�ނ��琬���邽�߁A����16�N�S���ɓ��������m���J�m����B����͍��Z����ΏۂƂ����@�ւł���B
�܂��Вc�@�l���{�o�ϒc�̘A�����@���c�@�������m���ƂȂ肱��������Z����ΏۂƂ��āA���ē��{�̎����ナ�[�_�[�{���m���J�u����B
���̂悤�Ɋ�Ƃ����łȂ��A�w�����x���ɂ܂Ń��[�_�[�{���̃v���W�F�N�g���}���ƂȂ��Ă��Ă���B
�������A�ŋ߂̗c�t���A���w�Z�ł͓k�����Ȃǂɂ����ď��ʂ�����̂��~�߂�Ƃ����Ƃ��낪�����Ă��Ă���Ƃ������Ƃ����ɂ����B
���ꂩ��̋����Љ�������ׂ�����ɂƂ��āA���̓������t���ƂȂ�Ȃ�������Ɗ肤�B
�Q�l�����F�w�n�[�o�[�g�E�r�W�l�X�E���r���[�x�_�C�������h�Ё@(2002�N12��)�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�\���@��Y�w�O���[�o������̌o�c�҃}�C���h����Ă�x(2003�N)
�@�@�@�@�@�@�@�g�c�@���w�o�c�ҋ���̎���x�@UFJ�����������@(2002�N)�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�����@�P���A�R��@�Ǖ��w���[�_�[�̈�ĕ��x(2000�N)
�@�@�@�@�@�@�@�c�Y�@�����w�I���^�̃��[�_�[�琬�x�쑺�����������@(2003�N)�@
�Q�l�z�[���y�[�W�F���N���[�g���[�N�X�������z�[���y�[�W
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i���j�g���^�����ԃz�[���y�[�W
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i���j�x�m�ʃz�[���y�[�W
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i���j�\�j�[�z�[���y�[�W
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ NIKKEI�@NET�@�z�[���y�[�W
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@UFJ�����������z�[���y�[�W
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�\������}�l�W�����g�Z���^�[�@�z�[���y�[�W