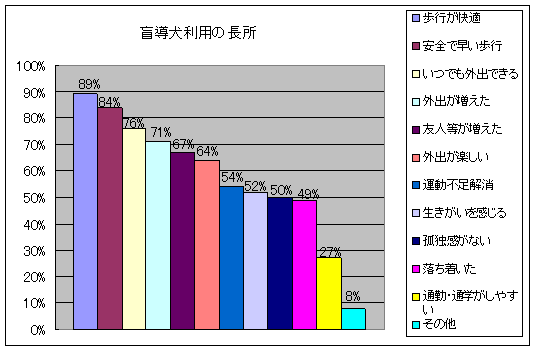
2003/9(財)日本盲導犬協会の調べ
| Last Up Date 2004/02/04 |
| 研究内容 |
| テーマ: |
|
| ケース: | 身体障害者補助犬法の制定と、身体障害者の能力向上の可能性 |
| 序章: 研究動機 | 動物が私たちの生活にもたらすものとは |
| 第1章: 身体障害者補助犬法 | 1.身体障害者補助犬法を知る 2.制定の意義とは 3.制定までの歩みと議論のポイント |
| 第2章: サービス・アニマル | 1.サービス・アニマルとは 2.身体障害者補助犬とは a.盲導犬について b.介助犬について c.聴導犬について 3.諸外国との法制比較 4.ハイテク補助器具との違い |
| 第3章: 日本の障害者の環境 | 1.日本福祉の歴史(思想・法制度) 2.現状の日本の障害者について 3.米国福祉観とアメリカADA法 4.北欧と東南アジアの福祉思想 |
| 第4章: 法制定による変化と課題 | 1.補助犬普及への課題 a.利用者の立場から b.受け入れ側の体制 c.育成団体(訓練士育成) d.政府 e.保険会社など 2.NPOやボランティアへの注目 |
| 第5章: 福祉分野発展への効果 | 1.補助犬法の果たした役割 2.ノーマライゼーションの社会に向けて |
| あとがき:感想 | 私たちが忘れてはならないこと |
| 序章:研究動機 |
私は犬が好きだ。なぜならば、干支が犬ということもあるかもしれないが、物心がついた頃から家族の一員として、生活を共に送っている存在でもあるからである。人も動物であるが、他の動物と共に暮らすことは素晴らしいことだと思う。たとえ言葉が通じなくとも、互いになんとなくでも心で通じ合えていると感じられるときには、心から癒される気持ちになり、人にはない動物の能力に気づいたときなど、彼らから学ぶことも多いからだ。
人間は能力の高い動物だといわれ、科学の発展と共に様々な研究開発をしてきたが、未だに他の動物の能力には敵わない部分もあり、それに頼っている部分も多い。クローン技術開発から麻薬検査、除草の為の利用など多岐にわたってあらゆる分野で動物は利用されているが、盲導犬・介助犬・聴導犬という、ペットとして特に身近である犬が、障害者のサポートをしながら共に活動を営んでいることに興味を持った。
2002年10月1日、身体障害者補助犬法が施行された。これによって、補助犬とされる盲導犬・介助犬・聴導犬が法で認定されることとなる。今までは盲導犬しか法的には認められていなかった背景を考えると、これは非常に大きな動きであり、犬の能力が認められると同時に、彼らと共に生きる障害者へ新たな可能性を与えたといえる。愛犬家の私にとってもとても喜ばしいことであり、人的補助や機械的補助と違う点は何であろうか、犬だからこそできる補助とはいったい何かを探ってみたいと思った。また成立過程を振り返りながら、補助犬に期待されることについて考えることは、様々な社会問題(福祉・住環境・動物愛護など)について捉えることなり、社会科学部という学部を生かしながら学際的に視野を広げることができると考えた。
| 第1章:身体障害者補助犬法 |
第1項:身体障害者補助犬法を知る
2002年5月21日、衆議院本会議において全会一致で可決、成立した法律案がある。「身体障害者補助犬法」だ。これは身体障害者の生活を補助する役割を果たす「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の育成および利用の円滑化、身体障害者の社会参加の促進を定めたものである。まずは、身体障害者補助犬法(以下、補助犬法)の概要を述べよう。
| 厚生労働省法律第49号 身体障害者補助犬法 |
| 第1章:総則(第1条・第2条) |
| 第2章:身体障害者補助犬の訓練(第3条~第5条) |
| 第3章:身体障害者補助犬の使用に係る適格性(第6条) |
| 第4章:施設等における身体障害者補助犬の同伴等(第7条~第14条) |
| 第5章:身体障害者補助犬に関する認定等(第15条~第20条) |
| 第6章:身体障害者補助犬の衛生の確保等(第21条~第24条) |
| 第7章:罰則(第25条) |
| 附則 |
第1章、第1条の目的では、1「身体障害者補助犬の育成」、2「施設等における補助犬の利用の円滑化を図り、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与すること」を挙げている。2条の定義では、この法における「身体障害者補助犬(以下、補助犬とする)」を「盲導犬」「補助犬」「聴導犬」と定めている。
第2章は補助犬の質を確保し、社会的信頼を獲得するための訓練事業者の義務についてである。必要に応じ医療を提供する者、獣医師等との連携を確保をしたり、使用状況の調査や必要に応じた再訓練について、補助犬の訓練に関する決定事項は厚生労働省で定める、以上のことが定められている。
第3章は補助犬を使用する者についての規定である。身体障害者自身に、犬の行動を適切に管理できる能力を求めている。
第4章は、補助犬の同伴についての規定がされている。公の場においては、1「国等(国及び地方公共団体ならびに独立行政法人)が管理する施設等を利用する場合」、2「国等の事業所又は事務所に身体障害者が勤務する場合」、3「国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を私用する場合」について、すべて補助犬の受け入れ義務を負うものと規定している。また公共交通機関における同伴に関しては、同伴によって著しい損害が生じる恐れがある場合などやむを得ない理由がある場合を除いて、補助犬の同伴を拒んではならないとしている。しかし、国等以外の施設、不特定かつ多数の者が利用する施設においては、公共交通機関と同様にやむを得ない場合を除いて同伴を拒んではならないとしいているが、民間が管理する事業所、事務所、住宅等においては、同伴を拒まないように努めなければならないという努力義務になっている。また同伴の際における「身体障害者補助犬」としての表示義務やその制限、6条と関連して補助犬の行動管理を行う義務が定義されている。
第5章は補助犬の認定に関するものである。厚生労働大臣が指定した民法上の財団法人、または社会福祉法人によって補助犬の認定が許可されるというものである。また厚生労働大臣がそれらの認定法人の改善命令権や指定の取り消し権を保持していることや、指定法人に大して業務内容の報告義務や、補助犬認定に関する事項は厚生労働省令で定めるといった委任についての定義がなされている。
第6章は補助犬の取り扱い、衛星の確保、国民理解への措置、国民協力についてが述べられている。国や地方公共団体、国民の両者へ補助犬使用に対する身体障害者への理解を深める努力義務が課せられている。
第7章は19条にて定義された報告義務を怠ったり、虚偽報告を行った場合に、指定法人の役員・職員に20万円以下の罰金が処されるというものである。
附則の内容としては、身体障害者補助犬法の「施行期日」と「経過措置」についてが定められている。「施行期日」に関しては、この法は原則的に平成14年10月1日から施行されるが、今まで認定等について法定義されていなかった介助犬と聴導犬に関する身体障害者への訓練規定の実施についてを半年遅らせ、また民間施設への同伴規定は、準備期間を設けるという考えから1年遅らせる形となった。「経過措置」については、1「道路交通法で認定されている盲導犬について、当分の間はこの法による認定は非適用」、2「介助犬・聴導犬の表示に関して、平成16年9月30日までの間に限り、認定を受けていない犬についても表示が認められる」(新しい認定制度が円滑に運用されるまでに時間がかかるため、これまで未認定の犬を使用していた者の利益を保護するため)、3「施行後の3年後に検討が加えられ措置が施される」という内容である。
また身体障害者補助犬法の成立によって、他の関連法律の一部改正が行われた。 「障害者基本法」では公共施設を利用する障害者の補助を行う犬の同伴について配慮しなければならない故の規定を設けると改正、「社会福祉法」では第2種社会福祉事業に介助犬・聴導犬訓練事業が追加、「身体障害者福祉法」では、身体障害者の社会参加支援を促進する事業に、補助犬支援事業が加わった。
第2項:制定の意義とは
なぜこの法が成立したのか、その理由を衆議院、厚生労働委員会における山本幸三議員の発言を引用すれば、以下のとおりである。
身体障害者補助犬により自立と社会参加を果たすことが可能となる身体障害者は多く、その普及には社会的受け入れ体制の整備と良質な身体障害者補助犬の育成体制の整備が不可欠であります。また、米国を初めとする国々では、身体障害者補助犬の同伴による社会参加を障害者の権利として保障する法律があると承知しております。
しかしながら、我が国においては、五十年近い歴史を持つ盲導犬でさえ道路交通法による規定しかなく、宿泊施設や飲食店で同伴を断られる事態が頻繁に生じております。また、介助犬及び聴導犬については、法的な位置づけがなく、ペットと同様に扱われるため、公共的施設への同伴が困難になっているほか、その犬の質を担保する制度もなく、身体障害者の自立及び社会参加に支障が生じております。
そこで、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与するため、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置等を講ずる必要があります。 (平成14年4月3日 衆議院厚生労働委員会 山本幸三氏の発言)つまり、身体障害者の社会参加を促すために有効な手段とされている、身体障害者補助犬(以下、補助犬)の普及を図り、補助犬の育成体制を整備し、訓練事業者と補助犬使用者それぞれの責務を明確にするとともに、障害者が安心して補助犬を利用できるようにすることで自立と社会参加を保障させるためである。
また、松山大学法文学部教授の田村譲氏によれば、と制定の意義について挙げている。なお(1)については、第5章で私の見解を詳しく述べている。
- 法の制定は、21世紀「共生(バリアフリー)社会実現」の一里塚となり、21世紀初頭に法律が成立した意義は大きい。
- 補助犬(介助犬、盲導犬、聴導犬)の使用者は、法律上の根拠に基づいて(お願いでななく)権利として(胸張って)スーパーや飲食店、ホテルなど、不特定多数の人が利用できる施設や電車・バスなどの交通機関を利用できる。
- 受け入れ側はこれまでの「善意」でなく、法的な義務となる。職場に連れて行くことやマンションなどで飼うことも、事業主や家主は「受け入れに努めなければならない」という規定(努力義務)が設けられた。
- 補助犬使用者にも、認定された犬(多人数が利用する施設で、ほえない、かみつかない、排泄〔はいせつ〕しないなど、適切な行動がとれることが最低限条件)であることがわかる表示と合わせて、補助犬の行動を管理することと衛生に注意することが義務づけられた。
- 補助犬法には、受け入れ拒否者への罰則がないが、介助犬を世間に認知させ、且つトラブル発生による訴訟提起の際には法律が最大の武器(根拠)になる。
第3項:制定までの歩み
次に、法が成立するまでの流れを見ていこうと思う。この法律が制定されるきっかけとなったのは介助犬についても、後で詳しく述べるが、既に1978年に改正された道路交通法において法定義されていた盲導犬と同様に法認定をしてほしいという介助犬利用者の希望運動から始まった。
そのきっかけとして挙げられるのが、介助犬の認識度の低さであった。全国での稼動数が2002年4月30日の段階で27頭と大変少ないこともあるが、世間では介助犬はペットと同様のものとして認識され、交通機関においても乗車拒否、もしくは会社毎に乗車テストをパスしなければ乗車が許されないのを始め、他民間施設においても立ち入りは難しいという介助犬使用者(以下、ユーザー)にとって利用が非常に困難な状況であった。
それに関連して、介助犬の育成者や研究者不足による「専門分野」としての確立が出来ず、「介助犬」の育成法や認定法の統一基準がないことから、世間における信頼性を欠けさせ、利用者の利用困難制や育成費用不足を引き起こしているとも考えられていた。こうした背景の中で、道路交通法によって定義されていた盲導犬と同様に「体の一部が不自由である人をサポートしている」介助犬に関しても、普及が広がっていくような政策を求める動きが強まっていたのである。シンシアという、兵庫県宝塚市に在住の木村佳友さんをサポートしている介助犬がいる。ペットとして飼われてからも適性を認められ介助犬となった犬だ。木村氏は仕事の合間を縫いながら、自ら介助犬の普及活動を行っており、99年の12月のある会議で、宝塚市出身の衆議院議員、中川智子氏が木村氏と知り合い、シンシアと共に国会傍聴へ誘い、参加したことをきっかけに、国会議員の間でも介助犬の認識を広げるきっかけを作った。介助をしていたのが馴染み深い「犬」だったこともあるのだろうか、議員たちの目を引き、興味を持たせることが出来たのではないだろうか。
中川氏が介助犬を連れての社会参加が難しいということを知り、改善していくべきだという思いをきっかけに、1999年には超党派議員による「介助犬を推進する議員の会」が発足され、政治的な動きが始まった。厚生省(現厚生労働省)の動きとして、1998年には介助犬の有効性を研究するために助成がされ、2000年には「介助犬の公的認知に関する検討会」が設置された。そうした中で介助犬だけでなく聴導犬や、盲導犬も含めたサポート犬も提議しようという流れとなり、2001年には議員立法を目的としたワーキングチームが設けられている。議員立法法としては異例の速さで検討され、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び保守党の七派の共同によって提案された2001年5月21日、参議院において全員一致で承認され成立された法なのである。
議員立法とは、「国会において議員により発議される立法」(三省堂デイリー新語辞典)と解されており、政策を法律という形でまとめ国会に提出することを指します。その流れは以下の通り。
| 1【契機】 | 政府案に反対 またはそれが不十分である 社会に新たな問題が発生 市民団体等から提起 |
| 2【整理】 | 問題点の整理・関係者と議論 |
| 3【議論】 | 素案を作り、党内で議論 手続きを経て、党内の合意を得る |
| 4【法律化】 | 法制局で専門的な観点からチェック 条文化 |
| 5【決定】 | 法律の形になったものを最終的に党で決定 |
| 6【提出】 | 国会に提出 |
| 参照:民主党議員 渡辺周氏のHPより |
補助犬法の場合は、【契機】が98年の厚生省による補助犬研究の助成や99年の介助犬の国会傍聴になり、【整理】と【議論】では議員らによる「介助犬を推進する議員の会」の発足や厚生省の「介助犬に関する検討会」、【法律化】は衆院法制局参事の奥克彦氏を中心に進められ、2001年6月の段階で「良質な身体障害者補助犬の育成及びその 利用者の円滑化に関する法律(案)」という名称が「身体障害者補助犬法」とされ、内容ついても【決定】された。そして同年、第153回国会にて【提出】されたのであった。(参照:案審議経過情報)
成立にあたってとくに尽力した人々は、衆議院社会民主党の中川智子議員、内科医で日本介助犬アカデミー専務理事の高柳友子女史、上記にも登場した介助犬シンシア使用者で同じく日本介助犬アカデミー理事の木村佳友氏、全日本盲導犬使用者の会会長の清水和行氏、盲導犬使用者で東京経済大学特認教授の竹前栄治氏といわれている。
こうした議論の中で、最も苦労した点について中川氏は自身のHPエッセーで以下のように述べている。
何よりも障害だったのは、縦割り行政の縄張り意識。関係省庁に要綱案を提示し、要望や意見を聞くことになった。厚生労働省はもちろん、大型店舗を所管する経済産業省、交通機関の国土交通省、そして、盲導犬に対する規定が既に道路交通法にあったので警察庁も呼んだ。この警察庁こそが一番の難敵で、「盲導犬の規定は道路交通法でしているのだから、補助犬法で二重規定されたら混乱しますよ」と憮然として言う。うちの権限には手を出すな、と言わんばかりの態度がありありと出ており、頭を抱えた。
・・・(割愛)
一方、各党の幹事は、それぞれの党にこの法案を持ち帰り、了承を得るという作業を始めた。しかし、そこで出てきたのは、「内容じゃないんだよ。真紀子が絡むものには自民党は誰も協力しないよ」という言葉に代表される「反真紀子勢力」だった。(その後、田中氏が外務大臣のために議員立法の提案者になれないということを理由に会長は橋本龍太郎元首相に)
・・・
超党派の議連といっても、結局は大物議員にすり寄っているだけじゃないかと言う人もいるが、橋本さんは「肢体不自由だったおやじが生きていれば、こんな犬を欲しがったと思う」と言ってくれた。少なくとも、この補助犬法に関しては、同じ思いを共有できる仲間であったと思っている。
障害者の社会参加に関する政策が、社会参加の場のあらゆる場面を想定するために多数の省庁をまたがって議論しなければならないものであったこと、そして盲導犬の規定に関する条文が存在していたために規定が複雑化していたこと、議員立法であるがゆえに政治家同士の関係や国会状況によって立法化への道が左右されやすかったことなどが、立法を進める上で問題になっていたと見ることが出来る。
次に、国会会議録において1993年から2003年までのうち、「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」「身体障害者補助犬」をキーワードに検索し、質問や検討された中で注目すべき発言や、補助犬法の重要ポイントともなった点について挙げてみる。
- ●今までの職業犬の立ち遅れの原因 ~なぜ欧米に比べ日本で盲導犬の数や受入れが進まなかったのか~
- 2002/4/5 衆議院厚生労働委員会における宮路副大臣の発言
- 「欧米と比べて、犬を室内で飼ったり文化の違いがあったこと。補助犬は一般的に大型の犬が適すると言われているが、日本は家屋が比較的狭く、そうした大型犬を飼うのに適した環境にないということ。育成活動への民間の資金協力も余り見られなかったこと。また補助犬に適する犬は、外来種が適しているらしく、日本の在来種は性格や能力の面で必ずしも富んでいないとうことがは関係しているのではないか」
- →犬と人間の文化的背景や生活習慣の違い、育成団体の資金不足(行政としての反省はと何もないと読める)
- なお、この考え方に対して、衆議院議員の児玉健次氏は「障害者と家族の強い願望にもかかわらず、行政と社会がこの分野においての理解が不足し努力も弱かったところに求められると私は考えます。そして補助犬法の成立は立ち後れを取り戻す貴重な契機になることを私は確信するものです。」との発言がある。
- ●補助犬育成の助成制度について ~公的な助成制度はどうするのか~
どの委員会においても、「一頭当たり百五十万円の助成制度が設けられている盲導犬と同様に、介助犬・聴導犬にも育成費用の支援を行う」とし、「育成団体に対する寄附を指定寄附(個人又は法人が共同募金会を通して寄付を行う際に、寄付先を特定の社会福祉法人(または更正保護法人)に指定して行う寄付。法人税上の特典があり、支払った税金が還付(控除を受けられる)される)として取り扱い寄附ができるだけ促進されることを介助犬・聴導犬にも措置する」との前向きな対応。- →盲導犬と同等に扱うという姿勢がみられる
- ●介助犬・聴導犬の認定について ~個人やNPOが資産問題で認定法人なれる見通しが立たない~
- 2002/4/5衆議院厚生労働委員会 高原政府参考人「認定する業務については、適正な認定を確保するため、公益法人または社会福祉法人でなければできない。社会福祉法人については、社会福祉事業という公益性の高い事業を安定的、継続的に経営していくことが求められており、このために一定の資産を備えなければならないとされている。身体障害者補助犬の能力の認定業務の社会的必要性にかんがみ、訓練事業者の実態をも踏まえ、社会福祉法人としての事業の安定性、継続性を確保しつつ、どのような資産要件の緩和を行うことができるのか、引き続き検討。」
- →介助犬・聴導犬についても盲導犬と同レベルの育成体制を取ることが社会信用へ繋がるという判断。この件については、2003年5月には社会福祉法人になるための資産要件が一定の条件(資産要件(基本財産)が1000万円をもつこと・経営年数が5年(NPO法人の場合は、所在地である市町村長が法人格を取得することに対して推薦した場合は3年)以上)・訓練事業所として地方公共団体(都道府県や政令指定都市など)または、民間福祉団体から委託または、助成を受けていたか、また受けているか)の下で緩和され、日本聴導犬協会などが社会福祉法人になった。
議事録を読んだ見解としては、全体的に盲導犬と同レベルの基準で介助犬・聴導犬についても育成を図って行きたいとする政府に対し、現場では盲導犬の状態でもとても満足いく状態とはいえず、なおかつ介助犬・聴導犬の育成は、盲導犬の現状に追いつけるような状況ではないという溝をどう埋めていくべきか、という議員との議論が目に付いた。
- ●受入れを義務化する場所について ~民間も受入れ義務にしなけれな意味がないのではないか~
- 2002/4/5衆議院厚生労働委員会 青山議員「身体障害者が日常生活におきまして頻繁に利用する施設等につきましては、特にその利用が円滑化される必要がある。また一方では、施設等の管理者にとりまして、身体障害者補助犬の受け入れ義務を課されることは一種の負担でもある。「国等」ということには、その身体障害者に係る公共的な責任の重さから、国等は、身体障害者補助犬の受け入れ義務を課した。これに対し国等以外については、必ずしも身体障害者に係る公共的な責任が重いとは言えないというところから、原則として努力義務を課すことにした。しかし、公共交通機関及び不特定多数の者が利用する施設につきましては、身体障害者がその日常生活において利用する必要性が高いことから、その管理者は身体障害者補助犬の受け入れ義務を負うこととした。」
- →民間施設では、受け入れ義務になると負担が生じることもあり、強制まですることができない。かなりの認知度が広がらない限り、個人経営の店などに入店する場合に不安が残る。
| 第2章:サービス・アニマル |
第1項:サービス・アニマルとは
まず「サービス・アニマル」とは、アメリカで主に仕事をする動物を指すもので、「サービス=労働」と「アニマル=動物」を掛け合わせた言葉である。犬に特化したものとしては「ワーキング・ドッグ」とも呼ばれ、これには警察犬、麻薬探知犬をはじめとしてアクティングドッグ(テレビや映画などに出る犬)、アラート犬(シーザー犬・危険予知犬・発作警告犬などとも呼ばれてんかんや糖尿病などの発作を予知して警告する犬) 、AQIS検疫物探知犬(オーストラリアの空港の荷物コンベア乗客荷物の中に検疫の対象となるものが、ないかどうか臭いをかいで調べる犬)、プリズンドッグ(刑務所の中で囚人が介助犬を育成するプログラム。シェルター(日本での保健所)から犬を引き取り囚人たちが世話をすることで自信・意欲・勇気などを感じ社会復帰に反映している)、ガソリン探知犬、癌探知犬、救助犬、軍用犬、酸素犬(盲呼吸器障害者の方のために酸素ボンベを積んだカートを引く犬)、シロアリ探知犬、セラピー犬(孤独な高齢者、精神的な病気を持つ患者などが、抱いたりなでたりすることで安心感が生まれ、人間のストレスや孤独感を和らげる)、船内探知犬(船内で麻薬やけん銃を探し出す特殊技能を持った犬)、ソリ犬、Social Dog(精神的な障害を持つ人のニーズに合わせて訓練を受けた犬。心を穏やかにして社会環境に順応させる助けをする)、追跡犬(容疑者遭難者・行方不明者などの捜索)、ハブ探知犬、、爆発物探知犬、馬車犬、ベアドッグ(熊猟犬)、歩哨犬(自衛隊等で警戒・監視の任にあたる犬)、猟犬などが存在する。(dog data引用)
なお、ここで焦点を当てる補助犬には、世界で「アシスタント・ドッグ」「コンパニオン・ドッグ」「ヘルパードッグ」などの通称がある。日本で言われる「補助犬」という言葉は、国際的に「アシスタンス(補助する)・ドッグ(犬)」の和訳だとされている。
矢口研語「犬の日本史」によれば、犬は人類がもっとも早く家畜化した動物であり、地球上で最も古い家犬の遺物は最低でも約2万年前にもさかのぼるという。イヌ科の動物には、狐、狸、ドール、ヤブイヌ、狼などがあるが、犬の祖先である狼が人間と交渉し始めたのには、人間と共通する2つの理由があからだという。まずは集団で狩りをするということ。次に社会に秩序があり、声や表情・姿勢・動作などでコミュニケーションをとりながらそれを確認しあっていること。人間が攻撃する意思をもっていないことがわかれば、犬たちは人間の群れの近くをうろつき、人間の残飯のおこぼれをあずかるなどして、人間と犬が交渉をし始めたのであろう。そうして、人間に反抗的でなかったり、従順な個体が人為的に選別や淘汰が何千年にもわたって行われてきた結果、家犬としての性質がかたちづくられたのだと考えられている。
日本では、正確にいつから犬が飼われるようになったのかは定かではないが、縄文時代には狩猟、食、祭祀、儀礼に用いる唯一の家畜として飼われていたと遺跡から推定されている。また、日本では犬を社会的に役立てるべく、積極的に改良をしようという思想はほとんどなく、サービスドッグと呼ばれる補助犬など、犬を組織的に人間社会に役立てようとする試みの多くは、いずれも外国に始まったものである。
犬の種類は世界公認犬種で130種前後に及び、ローカルな犬種は500~600種になるともいわれている。同種でもこれだけの変異があるのは犬だけだとされ、この犬種の多様さは、もともと犬が人為的に改良されてきた動物だということも示している。現在日本では畜犬登録で500万匹、未登録の犬も含めると1000万匹の犬がいるのでは、と推定されている。1000万とは、東京都の人口と同じくらいの数になり、どれだけ多くの犬が人間と暮らしているかがわかるだろう。
第2項:身体障害者補助犬とは
身体障害者補助犬(以下、補助犬)とは、補助犬法で定められた「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」のことを指す。障害者の身体の一部機能を補う働きをしており、既に世界でもその有効性が知られている。どのような働きをしているのか順に追っていく。
今回の法律では触れられていなかったが、国際的には「マルチプル・パーパス・アシスタンス・ドッグ」と呼ばれる「多目的補助犬」が存在します。これは、ユーザーの障害によって、聴導犬と介助犬、盲導犬と介助犬など、2つの補助犬の訓練を修了した犬で、今後このような犬も身体障害者補助犬として定義されるのか、注目すべき点でしょう。
a.盲導犬について
盲導犬とは視覚障害者の自立歩行を助ける犬である。ユーザーが歩行を行う際に、障害物を避ける、曲がり角や段差で立ち止まるなどの歩行誘導を行う。視覚障害者は”白杖”を使って歩くことも多いが、杖の先端で点字ブロックや障害物などを確認しながら歩くものの、看板や木の枝など、自身の上部に存在する物を察知することは出来ません。盲導犬はこのような障害物も避けて誘導をすることが出来るため、白杖で歩くよりも安全だとされている。
ユーザーの須貝守男氏の「駅から自宅まで夜歩くと、白杖を使ったら45分くらいかかるが、盲導犬と歩いたら10分で帰宅できた」という経験が語るように、白杖を利用するのに比べスピードが速い。またユーザーの神埼好喜氏の「ゴー(行け)と指示をしても歩かず、変だなあと思った瞬間に、トラックが目の前を通り過ぎるのに気づいた」という命を守ってくれたという体験談もある。(財)日本盲導犬協会の調べによると、盲導犬を取得して満足しているユーザーは99%にも上るといわれている。
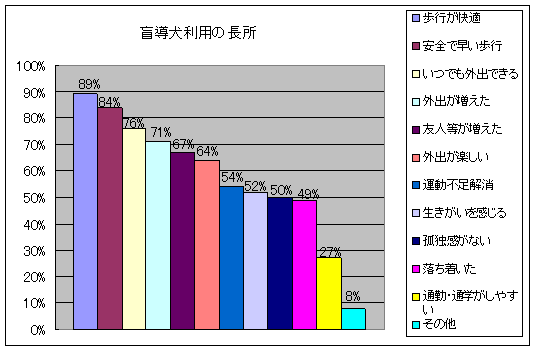
盲導犬の歴史についてだが、古代都市・ポンペイの壁画には、目の見えない男性が犬に導かれて市場を歩いている様子が描かれているという。福祉事業としては第一次世界大戦後のドイツにおいて、失明した兵士たちのために育成されたのが始めとされている。1927年ごろにドイツで働いていた数は、4000頭にも上るそうだ。1938年にアメリカの盲青年が盲導犬を連れて、旅行中に日本に立ち寄ったのがきっかけで、盲導犬が紹介された。翌年にドイツから日本へ盲導犬が輸入されたが死亡、独自訓練で1957年に現アイメイト協会理事長の塩谷健一氏の手によって国産第1号の盲導犬(チャンピィ)が誕生している。(参照:訓練士まるごとガイド)
補助犬法が制定される前に、盲導犬は1978年に改正・施行された道路交通法、第8条<目が見えない者等の保護>の2項において、「道路交通法第14条第1項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。」と法的に定められ、日本における補助犬の中では最も歴史が長い。しかし、社会参加における認知度や理解力が低く、第4章でも述べるが、タクシーや飲食店での入店拒否が数多く起こっていた。
2003年8月末現在、稼動数は927頭であるが、「平成14年度(2002)盲導犬訓練施設年次報告書」によると1998年7月に厚生省(当時)から公表された身体障害者実態調査での全国の視覚障害者(弱視・全盲の合計)は、約30万5千人。そのうち、全盲の方は約10万人といわれている。同年に日本財団が視覚障害者を対象にアンケート調査を行った結果から、盲導犬を必要とする障害者は、「今すぐ希望」と答える希望者が約4700名、「将来希望する」と答えた方も潜在的希望者として加えると、合計で約7800名と推測されると報告している。(引用:日本盲導犬協会資料)これを踏まえても、日本における盲導犬の数は足りないといえる。
また、盲導犬が引退をした場合、一度貸与されたユーザーから優先的に貸与されるために、新規ユーザーがなかなか増えないという実情もある。2003年4月に発行された社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会リハビリテーション部会盲導犬委員会の「盲導犬情報」から「盲導犬育成頭数の新規と代替え 過去10年間の推移」についての記事を引用する。
【盲導犬育成頭数の新規と代替え過去10年間の推移】
新規/代替えの順に記載
1992年度 69/40
1993年度 65/45
1994年度 57/47
1995年度 64/36
1996年度 61/43
1997年度 61/45
1998年度 67/63
1999年度 66/58
2000年度 60/64
2001年度 67/53
(引用 盲導犬情報 第37号)過去10年間の盲導犬育成頭数のうち新規 (初めて盲導犬をもつユーザーの盲導犬となった盲導犬)と代替えの頭数の推移をみてみました。
5年ほど前までは新規と代替えの頭数は、20頭前後の差で新規の方が多かったのに 比べ、1998年度以降は新規と代替えの頭数にあまり差がなくなってきています。すべ ての代替えの人が盲導犬の高齢が原因でリタイアさせたわけではないですが、1998年 度以降に代替えが必要となってきている人の多くは、1986年前後に盲導犬を持ったと 考えられます。
1982年から1990年にかけては盲導犬実働数が大きく増加している頃で した。当時のようには盲導犬育成頭数が増えていかない現状が、年間育成頭数に占め る代替えの比率の増加につながっているものと考えられます。
盲導犬の歩行訓練の様子(ビデオ)
b.介助犬について
介助犬とは、肢体不自由者の方の日常生活を支えるために、障害によって失われた四肢の機能を代行するように訓練された犬である。物を持ってくる、ドアを開ける、身体を動かすのを手伝うなど手足の不自由な人の動作介助をしる。また、ユーザーが車いすから転落して起き上がれないときに、電話を取ってきたり人を呼びにいくなど、命にかかわる緊急時の連絡を手助けする役割も果たしている。ユーザー一人一人に合わせて訓練、指導をされており、ユーザーの障害の度合いによって介助犬の仕事内容も変わってくる、オーダーメイドの補助具である。
介助犬の歴史であるが、1975年にアメリカで誕生したといわれている。1990年にテレビを通じてその活躍ぶりに感動したある障害者が、「自分も介助犬と暮らしたい」と希望し、その思いに賛同した人々によって設立されたのがパートナードッグを育てる会。1992年にアメリカから介助犬が貸与され、アメリカのノウハウを参考に育成が開始され、1995年同協会によって国産第一号の介助犬が誕生したのである。1997年にアメリカ介助犬情報機関「ナショナルサービスドッグセンター」のコーディネーターで介助犬ユーザーのスーザン・ダンカン女史の来日講演が行われ、毎日新聞社が兵庫県宝塚市在住の木村佳友氏と介助犬シンシアを紹介したのをきっかけに、介助犬が注目を集め始めたとされている。
こうした動きもあり、宝塚市では補助犬法の成立以前にも、「シンシアのまち」として介助犬を軸にして福祉の街づくりをしたり、ハーネス購入費の助成制度や相談窓口設置など、県単位での啓発活動に取り組んでいる。京都市では、介助犬使用者の館林千賀子さんが京都市内の大学へ入学したのを期に、動物園と市バスを除くすべての市の施設について、介助犬の同伴利用を可能としたり、介助犬の育成費用の一部を助成する制度を創設した。まだ盲導犬に比べて認知度は低いものの、介助犬利用者が住む地域の政治家や自治体レベルの動きが大きなバックアップともなり、補助犬法が成立したといわれている。
2003年11月17日において、現在38組(暫定犬33組・ 認定5組)の介助犬が活躍中だ。介助犬はけい髄損傷や多発性硬化症、筋ジストロフィーなどに適用例がみられ、木村氏と同レベルのによる肢体不自由者は約1万9000人といわれている。現在の頭数ではとても間に合うはずはない。しかし、大規模な調査は行われていないため、需要がどのくらいあるか正確な数字はつかみにくい。1999年に厚生省事業の一環であった「介助犬の基礎的調査研究班」が全国の障害者102人に意識調査をしたところ、70%を超える72人が「介助犬に興味がある」と回答したが、「欲しい」と答えたのは約25%に過ぎなかった。興味があるのになぜ、持ちたいというまで至らないのか。主な理由は、「犬の世話」(41人)、「住宅事情」(37人)だった。(参照:毎日新聞)
●介助犬の働く様子の動画→リンク(LOOK PAGE介助犬ハッピー)
c.聴導犬について
聴導犬とは聴覚障害者の方のために、音を知らせるよう訓練された犬である。生活の中の様々な音に反応し、ユーザーの体に触れるなどして知らせ、音の発生源までユーザーを誘導する役割を果たしている。電話やFAXの呼び出し音、ドアのチャイムや目覚まし時計の音、やかんや電子レンジの音、赤ちゃんの鳴き声や第三者がユーザーの名前を呼ぶ声も認識をする。聴導犬はユーザーの生活状況に合わせ、必要な音だけを学ぶので常に反応を起こすわけではありません。同時に、ユーザーが聴覚障害者であることに周囲の人が気づきにくいという危険に対しても、その故を聴導犬の存在で知らせることが可能である。
聴導犬の歴史であるが、1975年にアメリカで開発されたと言われている。ペットとして飼っていた犬を、聴覚障害を持つ娘の独立をきっかけに、訓練士に以来をして音を知らせる訓練をさせたのだという。日本では国際障害者年である1981年に、日本小動物獣医師会の提案によって「聴導犬推進委員会」が発足。アメリカからの情報を元に、日本訓練士団体連合会会長だった藤井多嘉史氏らによって1983年までに4頭のモデル犬が育成され、1984年に2頭が2家庭に無料貸し出しされたのが始まりだと言われている。
2003年11月17日現在15組(暫定犬14組・認定1組)の聴導犬が活動中である。日本より1年遅れて訓練を開始した英国聴導犬協会が1団体で850頭の聴導犬を輩出したのに対し、日本では7つの団体があるにもかかわらず、この22年間にわずか25,6頭しか誕生をしていない。民間のボランティアやNPOだけでなく、訓練士による調教を行っていた育成団体もあったために、「聴導犬は高い」というイメージがあったために普及が遅れたのではないか、また他の補助犬と異なり、音を利用したことのない障害者に、音を利用する「聴導犬」の働きを理解してもらいにくい状況があり、聴覚障害者に伝えやすい広報の仕方の模索が重要だ、という(特)日本聴導犬協会会長の有馬もと氏の意見もある。(参照)
聴覚障害者は、「障害者白書」によると34万6千人といわれている。聴導犬を希望する人数などの具体的なアンケートは行われていないが、盲導犬の希望者数から予測したニーズが障害者数の2.6%だと仮定すると、聴導犬の希望者は約9000人との数字が出る。アメリカでは育成私設が20以上もあり、4000頭が、イギリスでは700頭が活躍しているといわれている。日本の現在の稼動数13匹という状況を考えると、まだまだ需要を満たせるだけの環境とは程遠い。なお過去の行政の支援としては、2002年に長野県が(特)日本聴導犬協会へ盲導犬と同様の「聴導犬の育成委託事業」を開始し、1頭当たり30万円の補助金を決定している。
おとなしく待つ聴導犬の美音(ビデオ)
| 盲導犬 | 介助犬 | 聴導犬 | |
| 適応障害 | 視覚障害者 | 肢体が不自由 | 聴覚障害者 |
| 主な役割 | 障害物を避ける、 曲がり角や段差で 立ち止まるなどの 歩行を補助 |
日常生活の介助(モノの 拾い上げ・運搬)、衣類 の着脱の補助、体位の 変換、起立と歩行の支 持、扉の開閉、スイッチ の操作、緊急時の救助 要請など |
ドアのチャイム、お湯が沸い たやかんの音、危険を意味す る音などを聞き分け、必要な 情報を伝える。必要に応じて 音源に誘導する。 |
| 代表的な コマンド |
ゴー(進め)、スト ップ(止まれ)、ヒー ル(横につく)など 約20種類 |
テイク(取れ、持て)、テ イクアップ(上に)、ステイ (待て)、プル(引っ張れ) など約50種類 |
犬が自発的に音を知らせるの で命令はしない |
| 犬の適性 | 体高55cm程度。 おとなしい性格が 望ましい |
好奇心旺盛な性格。もの をくわえて持ってくる動作 が好き。体長、体高は問 わない(障害によって異 なる) |
好奇心が強く、音に敏感 |
| 犬の種類 | ラブラドールレトリバ ー、ゴールデンレト リバーなどの大型犬 |
ラブラドールレトリバーなど 大型犬が中心。コーギー などの中型犬も。 |
犬種は問わない。中型犬が 中心 |
| 団体育成 | 9団体 | 18団体 | 7団体 |
| 実働犬数 | 927頭(2003/8/31) (1993/3は755頭) |
認定5頭 暫定33頭(2003/11/7) |
認定1頭 暫定14頭(2003/11/7) |
| 米国の 活動犬数 |
約10000頭 (英国では約4000頭) |
約3000頭 | 約4000頭 |
| 育成団体 | (財)北海道盲導犬協会 (財)栃木盲導犬センター (財)日本盲導犬協会 (財)アイメイト協会 (財)中部盲導犬協会 (財)関西盲導犬協会 (社)日本ライトハウス (社)兵庫県盲導犬協会 (財)福岡盲導犬協会 |
いわて介助犬を育てる会 日本パートナードッグ協会 茨城介助犬協会 介助犬協会 多摩介助福祉犬協会 トータルケアアシスタント ドッグセンター SALA Network 日本福祉犬育成普及会 東京アシスタンスドッグ協会 山梨県障害介助犬協会 宮下愛犬訓練所 日本介助犬育成の会 介助犬をそだてる会 日本介助犬 トレーニングセンター 中嶋公仁子(個人) 国際介助犬協会 日本介助犬アカデミー (情報提供等) |
聴導犬普及協会 聴導犬育成の会 日本聴導犬協会 日本ヒアリングドッグ協会 徳島の盲導犬を育てる会 ドッグスクール野岳 エンゼル聴導犬協会 |
| 認定団体 | 当面は国家公安委 員会が指定する育 成団体と同じ (自認制度) |
厚生労働相が指定する社 会福祉法人か公益法人 |
厚生労働相が指定する社 会福祉法人か公益法人 |
| 使用者団体 | 全国盲導犬使用者 の会 |
日本介助犬使用者の会 | 全日本聴導犬ユーザーの会 |
| 公的助成制度 (平成14年度) |
都道府県の盲導犬育成事業 (盲導犬の育成団体に委託) に対し厚生労働省が補助金 を交付(年間育成頭数280頭) |
都道府県の介助犬育成事業 (介助犬の育成団体に委託) について15年度予算要求中 一部自治体に介助犬の育成に 対する助成制度有り |
都道府県の聴導犬育成事業 (聴導犬の育成団体に委託) について15年度予算要求中 一部自治体に聴導犬の育成 に対する助成制度有り |
第3項:諸外国との法制比較
日本財団による1999年「盲導犬に関する調査研究報告書」によると、アメリカでは、人権擁護の見地から立法化によって盲導犬使用者の権利保証の徹底化を図っている。立法化に踏み切ったのは盲導犬発祥の地であるニュージャージー州。以後州から州へと拡大し、1970年代に全米の立法化が完了した。ニュージャージー州差別禁止法は視覚障害者が盲導犬を全ての公共施設、職業、公共輸送機関に同伴する権利を保障する。盲導犬を同伴することにより特別料金を徴収されない。上記の権利を侵害した者は、100ドル未満の罰金、各違反について500ドルまでの罰金を科せられる。カルフォルニア州においては、盲導犬の維持費用全額がカリフォルニア州所得税によって医療費として控除される。
カナダでは、全てのカナダの州は、盲導犬使用者が様々な公共施設を利用することを、法的に保護する特別法を制定している。1974年視覚障害者権利法(1960年法の改正)のブリティッシュ=コロンビア州法は視覚障害者が特別に訓練された盲導犬をすべての公共施設に同伴する権利を保障する。盲導犬使用者の権利を不当に差別した者は罪に処せられ、有罪判決の場合、200ドル未満の罰金を科せられる。
スペインの国の法令及び各自治州の法律は、盲導犬を使用する全ての視覚障盲者が、公共施設など自由にアクセスできることを保障するという視点から制定されている。カタルーニャ自治州(抜粋)「盲導犬を同伴する視覚障害者の周囲へのアクセスを規律する法律」(1993年10月8日、法律第10号)では、これに定める違反は、軽度、重度、および最重度に分類され、民間が所有しているが公衆が利用する場所、宿泊施設、施設、区域、および輸送機関に関して、第1条の規定の不履行は、「重度」違反、公有の公共の場所、宿泊施設、施設、区域、および輸送機関に関して、第1条の規定の不履行は「最重度」違反とされ、罰則が科せられている。以下、主な国々の補助犬に関する法規定である。
比較を行うにあたって、2002年4月5日の衆議院厚生労働委員会における 武山百合子氏の発言を引用すると、「日本は盲導犬、聴導犬、介助犬という三つの部分にこの法律が適用されているが、アメリカでは、盲導犬のみならず、もちろん聴導犬、介助犬、このほかに救助犬、シグナルドッグ、その他、障害を補うために特別に訓練されたいかなる動物もサービス動物として認められており、公共の施設、公共の輸送、あらゆるところへのアクセス権として保障されている。これが非常に大きな違いである。
それから、人の集まるところ、あらゆるところでバリアフリーになっている。劇場から、パン屋さんから、食料品店から、コインランドリーから、それから公共のパーキング場、博物館、公園、動物園、レクリエーション、それから教育の機関、あらゆるところがバリアフリーになっているという大きな違いがある。
また、罰則が非常に厳しい。国の法律でも厳しく、そして州法といいまして、日本でいいますと県単位、その州法での罰則もきちっと決まっている。それから権利を侵害された場合、申し出制のように相談の窓口が非常にきちっとしており、権利の回復、損害賠償などの手続をきちっとしてくれる」という特徴がある。
| 国 名 | 施行年 | 内 容 | |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 1990 | 連邦法 『障害を持つアメリカ人法(ADA)』 |
障害を補うために訓練されたあらゆる動物(サービスアニマル)を同伴した障害者が公共の施設や乗り物を利用する権利を保障。違反は初犯が5万ドル(約585万円)、再犯が10万ドル(約1,170万円) |
| スペイン | 1983 | 『視覚障害者のための盲導犬の使用を規律する王令』 | 盲導犬使用者が公共の場所を自由に利用する権利を保障。各自治州法もあり、最高1000万~5000万ペセタ(約660万~3,300万円)の罰金を科した罰則規定もある |
| オーストラリア | 1992 | 『障害者差別禁止法』 | 障害者を援助するために訓練された動物を同伴する障害者を、不利益に取り扱ってはならないと規定。違反すれば6ヶ月以下の禁固刑が科せられる |
| イギリス | 1995 | 『障害者差別禁止法』 | タクシー運転手が盲導犬の同伴者を乗車拒否することを禁じている他の施設を利用する権利は「行為準則」で保障 |
| カナダ | 1974 | 『視覚障害者権利法』 『人権法』 |
各州が『視覚障害者権利法』『人権法』などの州法で、盲導犬使用者が公共施設を利用する権利を保障 |
| ニュージーランド | 1993 1996 |
『人権法』 『犬管理法』 |
盲導犬使用者の権利を二重に保障。違反すれば1年以下の禁固刑などが科せられる |
| 韓国 | 1998 | 『韓国障害者福祉法』 | 障害者援助犬を同伴する障害者が、公共交通機関や公共施設を利用することを正当な理由なく拒否してはならないと規定。違反した事業主には200万ウォン(約18万円)の科料を科される |
第4項:ハイテク補助器具との違い
日本では1990年代中ごろからIT産業が爆発的な台頭をみせ、まさに現代はハイテクノロジーに囲まれた文化であるといえる。もちろん、その流れは障害者の補助器具分野にも影響を受けている。1996年厚生省(現:厚生労働省)と通産省が「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(福祉用具法)を制定し、国が補助を行うことで、新技術の研究を推進しています。技術の進歩あるいは科学マルチメディアの有効活用は、障害者の自立と社会参加にとって非常に重要なことであると認識し、厚生労働省は、点字図書のディジタル化あるいは文字放送デコーダーの給付など、マルチメディアに対応した施策を実施をしてきた。
同時に、世界においても福祉分野におけるハイテク化が進み、2003年には発明家のディーン・ケーマン氏によって、「iBOT」(日本語サイトはこちら)という、本来の車いす機能をさらに進化させた、超スーパー車いすが誕生した。ちなみに価格は$29,000(1/23,1$=106円で換算すると約307万4000円)である。
現在日本で販売されている自動車いす・電動三輪車・電動四輪車の価格は、保健福祉広報協会のデータベースを検索したところ、機能やメーカーによって価格差があるが、20万~100万円台といったところ。補聴器は7万円~28万円より、ハイテクとは少し離れてしまうが、義肢・義具についてはオープン価格が多いため比較しにくく割愛させていただく。
身体障害者福祉法の補装具に関する規定としては、法第20条(補装具)「市町村は、身体障害者から申請があったときは、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。」とし、補助犬の育成と同様に政府による補助制度ができている。
福祉機器の市場規模も、保健福祉広報協会が2000年に行ったアンケート回答企業(156社)の1999年(実績)、2000年(見込)、2005年(見込)の売上高をベースに算出すると、1999年度の売上高合計は、2,268億円。2000年度、2005年度の売上高見込額は、それぞれ、3,422億円、4,021億円。 年平均成長率は、それぞれ2000年度50.9%、2005年度10.0%となり、さらなる市場拡大の期待が見込まれ、研究開発が進んでいるといえよう。
こういった技術革新や市場状況を目の当たりにしていると、補助犬の育成がアナログ的で費用もかかり、非効率だと感じることであろう。同じパーツを用いて一度に大量生産が可能な補助器具とは違い、人間と同じように「性格」が備わっている犬では、素早く合理的に数を増やすことはできないのである。ましてや補助犬の数が増えたものの、その分訓練が疎かになり、補助犬の質が落ちてしまうのは、もっとも望まれない方向であるのは間違いない。しかし、機械では補うことのできない機能を補助犬は備えている。
デルタ協会のスーザン・ダンカン女史によると、1996年の学会発表で「介助犬と暮らすことで、障害者は自尊心や自制力が向上し、学校や職場を休まなくなり、ヘルパーに頼る時間が激減する。」という報告を行っている。(参照)また、介助犬使用者の館林千賀子さんは「アトム(介助犬の名前)が障害を持ち閉ざした心の扉を開くきっかけとなった」と精神的な役割の大きさを唱えている。
犬と一緒にいることで感じる「自分は一人ではない」という安心感や癒し、そして「自分が彼らをコントロールしなければならない」という緊張感。これはなかなか機械では得られることのできない、まさに命を持つものにしか出来ない補助なのである。
また、犬には学習能力があり意思の疎通が図れる(引用)、という違いもある。コンピューターによってプログラミングされた補助器具であれば、長所として通常その機能が低下することもなければ、プログラム以上の作業は行えない。またユーザーが指示を出した場合でも、危険を察知した場合には歩行をしないように訓練されている盲導犬と違い、誤った信号を送ってしまった場合、特別な制御機能等が付帯されているときを除き、命令を取り消さない限りは危険を伴うこともある。しかし、補助犬もいつでも100%ユーザーの思い通りに動かないこともあり、場合によってはそれがユーザーにとってストレスだったり、ニーズに応えることができなければ、自立を妨げる存在になってしまうこともある。
しかし、「補助犬と同じ役割を果たす補助ロボットが出来たら欲しいと思うか?」というシンポジウムでの質問に対して、多くの補助犬利用者たちは「ノー」という答えを出した。あるユーザーは犬と自分が心で繋がっているという「気持ち」が勇気となり、自分にとって大切なものだから、と思いを述べている。
「犬の代替になるものはやっぱり人か?」との問いには、平成14年04月23日に行われた参議院・厚生労働委員会において参考人だった、盲導犬ユーザーの神崎好喜氏は、「最も視覚障害者のアシストとして有用なのは人だろうと思っております。しかし、犬と二年強暮らしているわけですけれども、その中でやはり心の通い合いといいましょうか、和むというのでしょうか、そういうふうなものもございますから、それはそれで捨て難いなというふうに思っております。」と発言している。
もちろん、ハイテク補助器具と補助犬のどちらが優れているか、というのは障害者自身ののニーズや状況がすべて異なるので、論じることは必要ないだろう。「どちらを選ぶか」という選択が出来る状況を作り出すことが、一番すべき事であるからだ。
| ●第3章:日本の身体障害者の支援 |
第1項.日本福祉の歴史
これまでわが国ではどのような福祉政策が行われ、「福祉」というものに対する思想や法制度に変化が現れたのかをてきたのかを振り返ってみる。
まず「社会福祉」という言葉の定義をしよう。これは戦後に「Social Welfare」の訳語として登場した用語で、個人や家族に生じる生活上の困難や生活障害を、社会的な努力や方策によって解決、あるいは軽減する諸活動を総合的に表している。そもそも「welfare」、すなわち「福祉」とは「快い暮らし」とか「より良い生活」といった意味をもっており(引用)、「福祉」は「幸せ」(引用)という解釈もできる。しかし、個人の幸福は多種多様であり、常に社会福祉と一致するとは考えられない。東京都立大学名誉教授、磯村英一氏の「日本人のしあわせ観」の調査によると、自分の思い通りになること、希望が満たされること(=自律・幸福追求)が多いという。これはまさに、憲法13条「個人の幸福を追求する権利」と憲法25条「人間らしく生きる権利」であり、この理念を併せて社会福祉の核心が「人権」である(引用)と断言できよう。
次に、時代をさかのぼりながら社会福祉の歴史的展開をみてみる。
古代には、天皇が行う慈恵的賑恤(じけいてきしんじゅつ:慈しみの心で貧困者・罹災者などに金品をほどこすこと)と、聖徳太子の四箇院や公明皇后の悲田院のような、仏教動機に根ざす慈善九歳が錯綜しながら行われていた。
中世でも、古代のような血縁・地縁による救済が引き継がれるものの、社会は厳しい身分制度の下での封建的なものとなり、慈恵的救済の主体は領主や大名へと移ることになる。また宗教的な慈善活動も仏教を中心に、戦国時代にはキリスト教の伝来も広がって行った。
近世になると、徳川幕藩体制により、宗教は幕府の管理体制に組み込まれて低迷するものの、支配の一翼を担う制度としての慈恵が行われたり、儒教を規範とする名君が現れる。また、五人組制度などによる村落共同体内での相互扶助や住民同士の自発的な相互扶助の発展も見られた。
文明開化の起こった明治時代では、富国強兵、殖産興業を基軸にした近代国家の形成が始まり、明治政府は「恤救規則」という公的な貧民の救済制度を定めたり、欧米の慈善思想が流入し、キリスト教的なヒューマニズムを主軸とする慈善救済事業が開花。末期には感化救済事業という考え方が展開されるようになった。
大正時代に入ると、第一次世界大戦開始以来の米騒動や関東大震災と社会不安の中で、社会事業思想と社会事業理論が発展。政府は取締り強化の中で、軍事救済法や児童保護事業、救療事業などに取り組んだ。
昭和初期には、1929年(昭和4年)には障害や老齢のために働けず生活できないものを対象に救護法が公布され、生活扶助、医療扶助、助産扶助、盛業扶助の4種類の救護を設け、養老院や孤児院などの収容保護を認めていた。
第二次世界大戦が始まる頃になると、国民生活の確保と人的資源の保護育成という目標にかなう事業を中心として、戦時厚生事業が再編されていく。一方で人的資源価値のない老人や障害者の救護は最初に切り捨てられたといわれている。
戦後は、連合国総司令部(GHQ)に先導される形で、戦時厚生事業の解体と民主主義に基づく社会福祉施策の編成が行われた。憲法、生活保護法(昭和21年)、児童福祉法(昭和22年)、身体障害者福祉法(昭和24年)、社会福祉事業法(昭和26年)が主に挙げられる。
高度経済成長期には生産性本位の価値観の元で、精神薄弱者福祉法(昭和35年制定、のち平成11年に「知的障害者福祉法」に改称)、老人福祉法(昭和38年)、母子福祉法(昭和39年制定、のち昭和56年に「母子及び寡婦福祉法」に改称)が制定され、社会福祉サービスの充実が図られた。
昭和48年には、オイルショックにより政府による社会福祉の見直しが進められる。昭和54年には新経済社会7ヵ年計画の中で、個人の自助努力の強化と家族・親族による相互扶助を重視し、社会福祉への歳出抑制、受益者負担の強化、補助金の削減、民間施設などの委託という「日本型福祉社会」を、政府が提案。
昭和50年の終わりからは、日本の社会福祉の法、および財政は世界動向に影響され、大きく改変されている。(引用、一部加筆)特に契機となったのは、1979年の「国際障害者年行動計画」や1981年の「国際障害者年」。国連総会は1982年に「障害者に関する世界行動計画」を採択し、1983年から1993年までを完全参加と平等をテーマとした「国連・障害者の十年」と決定される。1993年からは国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)が採択した「アジア太平洋障害者の十年」がスタート(日本の提唱により十年間期間を延長)。
平成の世の中になると、社会への完全参加と平等が盛り込まれた「障害者基本法」(1993年)、「高齢者、身体障害者つが円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律」(1994年:通称ハートビル法)、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(2000年:通称交通バリアフリー法)が成立と、街づくりの構想にも人権保障の視点が盛り込まれるようになってきている。
| ★富める者が、貧しい者へ、憐れみ・同情として施しを与える慈善救済から、権利としての社会福祉へ (慈善事業→社会事業→社会福祉へ) ★制限を伴った最小限の国家的な救貧から、国民の「いのち・健康・暮らし」を積極的に 総合的に支えていく福祉施策の拡大・展開へ(消費国家→福祉国家へ) ★社会から分断・隔離する施策から、地域の中でくらしていくことの条件・環境づくりへ (施設収容方保護→地域福祉へ) 引用:片居木英人『社会福祉における人権と法』 |
2000年6月に公布された「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」においては、障害者福祉サービスについて「措置制度から契約による利用制度へ」と生活者本位の社会福祉制度へと大きな転換が行われた。この法改正により、盲導犬訓練施設も社会福祉事業に追加されている。そういったサービスの中で、補助犬も一つの身体障害者の補完機能を行う道具として選択できるよう、ますますの普及政策や社会認知を図っていかなければならない。
障害者施策が目標とするのは、障害の有無にかかわらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重支えあう強制社会であり、その実現のためには、政府や地方公共団体等の施策を推進することはもちろん必要であるが、施策の下支えとなる社会のあり方として障害のある人とない人との間の「心のバリアを取り除く」ことが大変重要である。このためには、国民一人一人が障害のある人への理解を深めることが欠かせない、と内閣府の政策統括官、山本信一郎氏は述べている。
しかし、どんなに政府が社会福祉事業に資金を投入し、政策を打ち立てても、国民の我々が正しくメッセージを受け取り、障害者をはじめとするマイノリティーに対する理解を深めない限り、福祉社会はやってこない。
第2項.現状の日本の障害者について
平成13年6月1日における、厚生労働省による「身体障害児・者の実態調査結果」によると、全国の18歳以上の身体障害者数(在宅)は、3,245,000人と推計される。前回調査(平成8年11月)の2,933,000人と比較すると、10.6%増加している。障害の種類別にみると、視覚障害が301,000人、聴覚・言語障害が346,000人、肢体不自由が1,749,000人であり、肢体不自由者が全体の53.9%を占める。年齢階級別に身体障害者数の構成比をみると、70歳以上が45.7%を占めている。また、前回調査と比較すると、60歳以上の割合が67.0%から72.9%に増加しており、高齢化の傾向がうかがえる。身体障害者の人口比は、人口1,000人に対して31.1人であり、前回に比して7.6%の増加である。また、年齢階級別にみた身体障害者の出現率は高年齢になるほど高くなることがわかる。身体障害者の身体障害の原因についてみると、疾病によるものが26.2%、事故によるものが17.0%、加齢によるものが4.7%、出生時の損傷によるものが4.5%である。
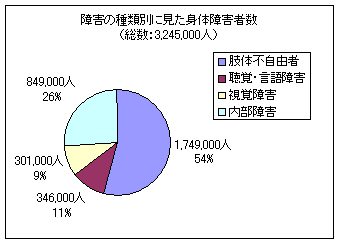 |
また全国の18歳未満の身体障害児数(在宅)は、81,900人と推計される。前回(平成8年11月)及び前々回(平成3年11月)調査の推計数と比較すると、ほぼ横ばいといえる。(3)障害の種類別にみると、視覚障害が4,800人、聴覚・言語障害が15,200人、肢体不自由が47,700人、内部障害が14,200人であり、肢体不自由児が身体障害児総数の約6割を占めている。身体障害児の人口比は、人口1,000人に対して3.6人であり、前回に比して9.1%の増加である。また、年齢階級別にみた身体障害児の出現率は、10~14歳の階級が最も高く、人口1,000人に対して4.5人である。
上記でも述べたが、障害の程度の判定基準は身体障害者福祉法施行規則別表第5号に準拠して1級から7級、級外及び非身体障害者に判定され、身体障害者と判定を受けたものは、自身が障害者であることを証明する「障害者手帳」を持つことが出来る。
第3項.米国福祉観とアメリカADA法
アメリカは人種の坩堝と呼ばれるように、多種多様な人種から成り立つ国という特徴から、障害者に対する特別意識(自分と何かが違う)というものも薄いとされ、また福祉の先進国だといわれている。「法律」が形のみならず日常に浸透しており、「権利意識」についても、日本人に比べて非常に敏感である。「身体障害者補助犬法」と比較されやすい「アメリカADA法」について述べてみたい。
1990年7月26日はアメリカ障害者にとっての”独立宣言の日”といわれている。「American With Disabilitise Act of 1990」(an act to establish a clear and comprehensive prohibitation on the basis of disability)、訳語で「アメリカADA法」(障害に基づく差別の明確で包括的な禁止を設定する法律:以下ADA法)が大統領によって署名され、発効されたからだ。
では、まずアメリカにおける”障害者”の定義とは何か。元全米障害者評議会事務局長レックス・フリーデン氏によれば、(1)生活行動に重大な困難さ、制限を持っている人(2)障害をもっていたという記録がある人(3)周囲の人から障害があると思われている人、である。リハビリテーション法の施行規則から抜粋したものであるが、自己認識のほかに、他者による視点が入っていることが興味深い。障害の程度の判定基準は身体障害者福祉法施行規則別表第5号に準拠して1級から7級、級外及び非身体障害者に判定されている日本に比べて、障害者の範囲が非常に広範囲である。
”差別”という概念については(1)サービスを与えない、拒否する。または何も与えない(2)最も統合された環境の中でサービスが提供されない(3)機会を与えない(4)間接的な差別をする(1~3の行為者を支援するなど)、と考えられている。(引用)
ADA法というのは、雇用、移動・交通、公共的施設、テレコミュニケーションなどで障害者に対する差別をなくすための包括的な法律である。「人間が障害によって差別されてはならない。障害者の持っている力を十分発揮させるようにすることが社会の責任である」(引用)という「公民権」や「平等な機会」についてを厳しく規定している。
アメリカでは1964年に、「社会・政府・企業は肌の色によって差別してはならない」という「Civil Right Act」(公民権法)が成立。1973年には、「政府から補助を受けている団体・組織は、障害を理由として差別してはならない」という「リハビリテーション法504条」が成立し、ADA法の前身といわれている。概念としては”重大な支障”(事業自体の変化など)がない限りは障害者に対して”妥当な配慮”をしなければならないというものだ。ADA法はこの規定を民間にも拡大したいという動きから、1970年代の後半から障害者らによる自立生活運動が始まり、約10年をかけて成立された賜物なのである。
ADA法は、障害があるために建物や乗り物が使えないのは差別であると規定をし、そうならないためには設備をどう変えるべきか、という発想から成り立っている。それに対してハートビル法など日本の法律は高齢の人や障害を持つ人が最近はふえてきたからスロープをつくりましょう、という発想から施されている。
アメリカでは日本で定義されている聴導犬、介助犬、聴導犬の他にも、障害を補うために特別に訓練されたどんな動物でもサービス動物として認められ、公共の施設、輸送など、あらゆるところへアクセス権がて保障されている。では、補助犬やユーザーにとっての環境はどう変化したのか。
「介助犬を伴う障害者の社会的アクセスは格段に改善された。障害者を助ける動物はすべて、サービスアニマル(介助動物)として法的認知を受けた。しかし、介助犬育成団体が乱立し、十分な介助が出来ない犬や好強雨の場で騒ぎを起こす犬が認定される騒ぎが起きている。」と、アメリカの介助犬使用者スーザン・ダンカン氏は意見を寄せている。ADAは障害者の包括的な権利法であり、サービスアニマルの専門法ではなく、従って質や育成制度などについても規定はないからだ。
リーガル・アドボガシー代表理事の川内美彦氏が参考人となった運輸委員会発言から引用すると、ADA法の技術基準の作成はアクセス・ボードという機関が一手に引き受けているそうだ。この機関の26人の理事のうち半数は政府、残りの半数は民間人が選ばれ、民間からの代表者はすべて障害を持つ人である、障害を持っているということが要件になっているという。もちろん、政府関係者の中にも障害を持っている人が含まれているそうだ。これは日本の審議会や委員会のように、障害を持っている人を招いて意見を聞くのではなく、障害を持つ人たちが主体的に自分たちで決めていくという仕組みをつくっているということであり、日本でも仕組みの中に当事者の意見をいかに反映させるかという問題が見えてくる。
また、自治体や企業、NPOにADA法の担当者を置き、その会社の職員とかそれから地域へのトレーニングを行ったり、情報提供、電話相談などを行っている。またADAの管轄である司法省にも窓口を設けて専門の担当者が対応しているという。これらが苦情処理や意見・相談窓口となって、現場ではどんなことが起こっているのかを把握し、パイプ役となって正しいADA法の理解に貢献をしている。
また補助犬法との大きな違いとして、ADA法には罰則規定が設けられている点があげられる。それほどに「人権」を侵すことはしてじはならないことなのだ。補助犬法では、国や地方公共団体、国民の両者へ補助犬使用に対して、身体障害者への理解を深めるあくまでも「努力義務」であり、法としての強制力はほとんどなく、受け入れ側の「理解」にして期待をするままにとどまっている。
忘れてはならないADA法成立の背景として、障害者の「経済的有効性」という視点がある。「差別や偏見は障害を持つ人のみならずアメリカ合衆国にも大きな損失を与える」ブッシュ大統領の演説にもあったように、この法律によって障害を持っていることで経済生産活動の制限を受けている障害者を減らし、年間2000億ドルといわれる公的扶助の受給者数を減らす、という目的だ。補助犬法のように障害の補完機能有効性を増大させることで、障害者の自立を図ろうということではなく、障害者の行動を保障することで経済的チャンスを増やし、障害者の自立を図ろう、という違いがある。
なお、日本にはADA法のような障害者の権利保障法は存在しない。
第4項.北欧と東南アジアの福祉思想
次にアメリカ以外の国々の福祉思想について考えてみる。「障害者に対して必要なのは、福祉ではなく、自分のやりたいことを当然のようにやれる社会環境の整備である」(引用)と考えるアメリカに対し、自由や平等ということを思想の中心を置く北欧民主主義国。
北欧の福祉思想についてであるが、スウェーデンやデンマークなどは高福祉の「モデル国家」として有名である。まずスウェーデンは、民主主義の「平等」の思想と社会民主党の長期政権と結びついて、「揺りかごから墓場まで」、のちに「胎児から死後まで」のスローガンとなって形成された国家とされている。(引用)
高齢者福祉が充実していると言われるスウェーデンでは、(財)滋賀総合研究所研究員、西村秀敏氏のレポートによると、この社会保障制度充実の背景に、1950年代からすでに高齢化率が10%を超えていたこと、女性の社会進出、高齢世帯といえば、夫婦または一人住まいという家族構成等が考えられ、また社会保障制度の理念には自立、そして個人を尊重することにある、という。(引用)
スウェーデンの「障害観・障害者観」というものは、1994年のLSS法(機能障害者に対するサービス援護法)に現れ、その法律の基調には「障害をもった人の権利」によるとされる。権利とは何かを考えるとすれば、スウェーデン人の生活観(生活の中で大切なこと)を挙げれば「住む・働く・余暇」と答えるといわれるように(なお、多くの日本人は「衣・食・住」と答えるそうだ)、これらを実現させること、と解することも出来ようる。そして「体が不自由になった場合ので働けない」ではなく「では何をすれば働けるようになるのか」という発想から福祉サービスが行われる。そして社会福祉法によって保護されている「ISS法(身体障害者に対する援助とサービス法)」に基づき、各コミューンは各種の援助及びサービスを身体障害者に提供しているものである。(引用)
またスウェーデンでは、福祉にボランティアという考え方はなく、福祉は「人を人が助けよう」ではなく「社会がやらなければならないこと」としてあるそうだ。そのために介護などの福祉サービスを行うのは公務員である。そして基本的に視覚障書者が外出する場合、一人では行動せず、必ず介助の人が付くか、盲導犬と一緒に行動をするともいう。(引用)
しかし、スウェーデン政府は2003年7月1日から、長年の経済不況を受け、病気休暇手当て引き下げ実施すしたり、同時に、社会福祉局の発表によれば2010年には、高齢者福祉職員を最低20万人は新規採用が必要と予測しているものの、近年は非常に希望者が少なく、福祉、介護職員の人員確保に不安があるともいう。(引用)また「社会福祉、高齢者福祉が行き渡ったスウェーデンには、ホームレスはいない」というイメージもあるが、ここ数年来の経済不況から、以前にはあまり目立たなかったホームレスが増加していることが判り、2002年度では全国で約1万人程いるとも言われている。(引用)
そして忘れてならないのが、税金も合わせた国民負担率は1999年75.4%(日本は2002年度38.3%引用)であり、高負担との引き換えによって初めて成立する、ということだ。日本でもスウェーデンをお手本に福祉政策を進めていこうという考え方もあるようだが、この考え方は国民の行政に対する高い信頼性がなければ成り立ち得ず、今の日本では到底受け入れられないのではないかと思える。しかし、現実には政府が掲げる理想と現実とは、あまりにかけ離れていることがしばしば見られるということもあり、経済状況と福祉政策のバランスをどうとるかの問題は、日本と共通しているようだ。
発展途上国について触れておくと、全体的に国の経済レベルを上げることが共通の目的であり、「福祉」を国が行う当然のサービスとして考えたり、人権問題として論ずるほどの風潮的な余裕がない状況だといえよう。 タイについて、日本社会事業大学社会事業研究科、萩原康生氏「タイの障害者福祉-その新たな出発-」という海外レポートを元に福祉状況を考察する。
タイは仏教国であり、霊への厚い信仰が見られる。このような社会では、障害は前世の悪行の結果であると一般には信じられている。この考え方は人々の間にふたつの態度を生み出し、一方では人々は障害者を哀れみ、障害者は過保護に扱われる。他方、前世の悪行を恥じる家族は障害者を家の中にひた隠しにしようとする。
社会福祉にかかわる立法の動向をみると、1968年までの立法は、社会問題を抑圧しようとする主として社会秩序の維持を目的とする治安維持的色彩の濃いものが中心であった。1970年代に福祉的立法へと質的転換の図られ、1990年には社会保険法、1991年には障害者社会復帰法が制定されている。これらの社会福祉立法は、都市化や産業化によってもたらされた社会問題を抑圧するのではなく援助することによって問題解決のために対応しようとするものであった。
身体障害者には、車椅子や松葉杖などの供与、自営業を始めるための開業資金の貸与などのサービスが実施されているが、必ずしも満足のできるものではなく、これらの者に対する援助を量的質的に向上させることが望まれているという。また、法整備の中での問題は、法律施行に当たっての省令や規則が未整備であること、障害者に対してのサービスの供与という点が強調されてはいるが、障害者の権利性がまったく等閑に付されていること、広報活動の不徹底ということが挙げられており、障害者の定義、「障害の程度」の定義もできていないという。(参照)
思想を支える宗教の内容を否定することは出来ないが、宗教的な理由で家庭の中に閉じ込められている障害者たちが、一日でも早く、堂々と外を歩ける日はいつだろうか。車いす利用者の木島英登氏は、日本の障害者問題について「日本が全く遅れているとは思いません。」と語る。彼が北欧の福祉先進国といわれる国に行った時、「何で一人で出歩いてるの?」と不思議がられたという。おそらくデンマーク、スウェーデンあたりではないかと思われるが、その国では、車いすの障害者が一人で街に出るのは珍しく、介助者が付き添うのが当たり前で「障害者は保護すべきもの」という思想が色濃く根づいている(引用)と感じたという声もある。
日本が福祉先進国から学ぶことはたくさんある。しかし、そこには文化や宗教といったすぐに変えることができない背景があることを忘れてはならない。日本の福祉政策は遅れ気味だと、一般的に思われがちであるが
| 第4章:法制定による変化と課題 |
第1項.補助犬法の果たした役割
考えられる、補助犬法の果たした役割を見ていきたいと思う。1章の制定の意義の中でも述べたが、まずは身体障害者に対する社会参加の選択肢が一つ増え、受け入れを助長させ、自立を促す役割を果たした。そして、彼らを支える補助犬を、高いレベルで育成するための基盤も作られたといえよう。
日本では歴史の長い盲導犬に関しても、補助犬法を成立させる過程で、既存の法律(盲導犬に関する道路交通法)や通達が、形だけのものになっている事実を知ることができ、施行された法律に関しても、随時、実態調査や見直しを行い、継続的なPRがないと形だけのものになってしまう危険性を再認識させている。この動きがなければ、いくらお役所の会議で盲導犬のさらなる理解などについて関係者が訴えたとしても、さらなる普及や社会認知のために大きな活動は行われなかったであろう。
また補助犬法は議員立法として成立している。地域会議における介助犬ユーザーと衆議院議員の出会いをきっかに、全党から有志者が参加する形で「介助犬の普及を推進する議員の会」が発足され、国会承認されたものであり、まさに市民の声を救う形でスタートし、出来上がった法案だといえる。大物政治家の力なしには到底なしえなかったと推測されるが、マイノリティといわれる市民であっても、その活動や想いに賛同する人々が集まれば、国の法律でさえ作ってしまうことが可能だということを表している。
次に補助犬法は日本の福祉法に関して、「障害者差別禁止法」への立法関心を引き上げた役割を果たしたともいえる。ADA法と比較されることが多かったこともあり、日本でも「障害者差別禁止法」を制定をすべきという考えが広がっている。現在の障害者基本法を見直しや、共生社会を目指した新立法を設立すべき、という法の必要性を求める議員の意見に対して、坂口力厚生大臣は以下のように述べている。
「障害者に対します問題はさまざまな角度から検討していかなければなりません。今まで障害者に対する差別、偏見ということがあったことは、私ももうこれは率直に認めなければならないというふうに思います。だから、それをどうするか。この差別、偏見は法律をつくったからとれるというわけのものではありません。しかし、そこは国の方が毅然とした姿勢をやはり示すということが大事だというふうに思っています。その毅然とした姿勢を示すためにこれからどう構築をしていくか。そのためにさらに努力をしたいというふうに思っております。」
法律を作るだけでは差別や偏見はなくならない、という意見であるが、むしろ法律を作ろうとするプロセスの中で、政府主導で啓蒙活動をさらに行っていこうという考えはできないのだろうか。確かに日本では憲法で「誰もがみな平等」と人権について謳われているが、障害者を社会に受け入れないことが、どれだけ罪が重いかという認識が薄いのは、そういった法律が存在しないという理由も一面にあると思われる。世界主要国の中で障害者差別に関する法がないのは日本だけである。
世界中でも「補助犬」に焦点を当てて、育成や認定基準も含めたユーザーへの理解に対する法律が規定されているのは日本だけであり、今後の補助犬文化を支える国となることが期待されている。福祉文化では後進国とされる日本が、世界から注目されるきっかけも創ったといえよう。世界に先駆けて、自信をもって日本から発信される政策が今後も増えてほしい限りだ。
第1項.補助犬普及への課題
社会的認知を上げたり、障害者が選択できるサービスの一つとして事業を成り立たせるためには、補助犬を普及させ、ユーザーが社会参加をすることが必要だ。では、そうするためにどんな課題があるのかを、まず「身体障害者補助犬法に関する意識調査」を見たあとに、a:補助犬ユーザー、b:受け入れ側、c:育成団体、d:マスコミ、e:政府の5つに分けて考えてみる。
調査は(財)日本盲導犬協会が、補助犬法が施行されて1年経った2003年9月に行った「身体障害者補助犬法に関する意識調査」を参考に問題を見ていく。これは、盲導犬ユーザー(246名)、受け入れ体制側のコンビニエンスストアの店員(1584名)、一般市民(105名)、病院(公立、民間へのアンケート郵送210施設のうち回答54施設)を対象に調査したものである。
介助犬・聴導犬に関しては稼動数が少ないこともあり、このような調査は行われていない。約40年も歴史のある盲導犬が現在どのような状況であり、どうそれらを解決するかが、他の補助犬にとっても普及の鍵になると思われる。
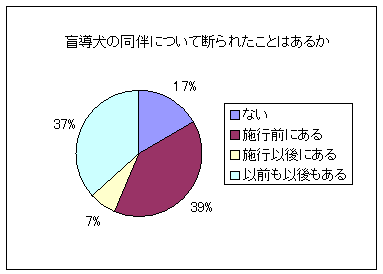 |
まずは下記の盲導犬ユーザーにとったアンケート結果をみてほしい。補助犬法施行の以前も以後も盲導犬を断られたことのあるユーザーが約40%にも上っている。施行以後に断られたケースを含めても約半数のユーザーが同伴拒否の経験があり、一般市民の法律の認知や盲導犬に対する理解がまだまだ低い状況がわかる。 |
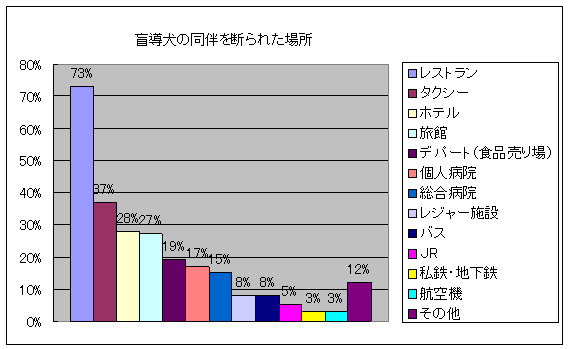 |
盲導犬が断られた場所は、主に不特定多数の人々が集まるために、「衛生面」に配慮が必要とされる場所である。 タクシーは運転手の判断によって異なることが多いという。主な理由は「他の利用客が嫌がる」ため。「犬を入店させている」ことで、他の利用客の店に対する信用を失いたくないということだろう。 拒否理由が「犬」であることに集中しており、ペットと補助犬の違いが正しく理解されない実態が伺える。 しかし東京都福祉局障害福祉部在宅福祉課の高橋晴美社会参加推進係長によると、「補助犬を所有する障害者には、獣医師による検診や健康管理を定期的に行う義務があるので、そこまで心配する必要ない」という。 |
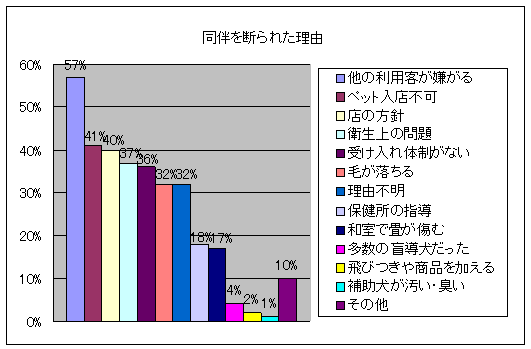 |
下は一般市民へのアンケート結果であるが、店側が「他のお客様」を過敏に気にする一方で、当のお客様とされる人々は補助犬の受入れに対しては95%が賛成、ということで、「店と客」の間にある感覚のギャップをどう埋めていくのかがポイントになろう。 また「障害者の社会参加」に対する権利意識が50%と、最も重要な障害者に対する市民の意識が、それほど高くないように見受けられる。 |
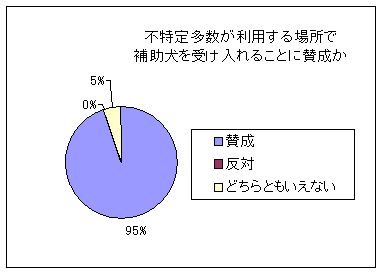 |
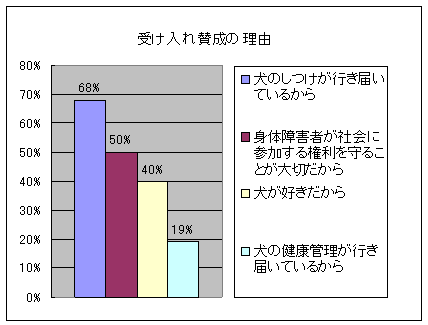 |
このような実態の中で、今までどのような政策がとられてきたのか。受け入れ側の中でも、特に犬が動物であることを理由に断られやすい旅館や飲食店、医療施設に対して、昭和56年1月、平成元年6月に厚生省(現:厚生労働省)から通達で出ている。その内容は、
「盲導犬については、視覚障害者の移動を助ける役割を担っていることはもちろん、その訓練に当たっては、排泄等についても厳しくしつけられており、その衛生上安全上の問題においてもいわゆるペット動物の帯同とは異なること等について、すでに貴管下関係部(局)長に対し、『盲導犬を伴う視覚障害者の旅館、飲食店等の利用について』(昭和56年環指第12号)等の通知が行われているところであるが、近時、盲導犬を伴う視覚障害者が公共施設、公共交通機関をはじめ、旅館、飲食店等の諸施設を利用しようとする機会が増えるにつれ、その利用を断わられる等の事例も発生していると聞いている。ついては、これらの通知の趣旨を踏まえ、さらに関係各方面の理解と協力を得て円滑な受入れが行われるように重ねて格段のご配慮をお願いするものである。」
このように「補助犬≠ペット」であることを、15年ほど前から国が通知をしているのにも関わらず、未だ補助犬がペットと間違えられてしまうが故に入店を拒否されるのは「行政の指導不足」「育成団体、利用者の啓蒙活動不足」「一般市民の認知不足」が考えられる。通達の話をすると、「これは何の強制力もないよと。受け入れてください、協力してくださいということですから、強制力があるならば受け入れるけれども、そうでなければこちらの都合でこのまま盲導犬を受け入れません」というところも現実にあるそうだ。
a.補助犬ユーザー
まず補助犬普及のためにユーザーに求められるものから考えてみよう。まずは、補助犬を責任もって利用することが挙げられよう。補助犬法が施行され、少しずつ社会認知をされるようになったが、補助犬を利用できるようになったことと同時に、ユーザーに対する責任も重くなったといえる。補助犬文化のこれからという時期に、もしも期待はずれの、また迷惑を与える存在だという認識が人々の間に広まってしまったら、これから補助犬をしようしたいという人々の希望をも、結果として摘み取ることになってしまう。
そうならないためにも、何か補助犬について質問をされた際にも正しく答えられるよう、ユーザー自身による補助犬と補助犬法の正しい理解と、継続的な動向把握も求められている。場合によっては、ユーザーの病状や、なぜ障害者になってしまったのかという、常識的に考えて安易にすべきではない質問をされることもあるだろうし、ユーザー自身にとっても、こういった質問をされるのは不快であろう。だが、「なぜ自分にとって補助犬が必要なのか」ということについて、はっきり、分かりやすく答えることができれば、「なぜ社会が補助犬を受け入れなければならないか」という、福祉の「核」となる部分についても、受け入れ側に理解を促すことが出来よう。
まだまだ補助犬の数も少なく、補助犬ユーザーは社会において「目立つ」存在であるかもしれない。意図せずとも人々の視線を集め、ある種の「有名人」になってしまうことさえある。現在のそんな状況でも補助犬を持っているユーザーは、そういった覚悟を持っていたのかもしれない。多くの補助犬ユーザーが、家庭や仕事に追われる中で、積極的に外出をし、イベントへの参加やホームページの公開、マスコミからの取材などを通じて、啓蒙活動を行っている。確かに補助犬を持つことは、自身の自立と社会参加を図ることが目的であって、補助犬をPRするためではない。けれども、そういった姿は障害者だけでなく、障害を持っていない人々に対しても、生きる勇気を与え、自分も頑張ろうというパワーを与えることが出来る。また、これからの日本の福祉環境を一層よりよくしていくためにも、今後とも積極的なPR活動を行っていって欲しいと思う。
b.受け入れ側
補助犬法が施行されてから、今まで犬を入店させたことのない企業はどのように対応をしたらよいのか、混乱しているという。育成協会や、今まで積極的に補助犬を受け入れてきた企業に対して、同業者からの問い合わせが殺到しているという。では、補助犬を連れた障害者を社会ではどのように受け入れたらよいのか。これは状況や場所によって変わってくるものであるが、「補助犬への配慮」について質問をされたときに、(社)日本聴導犬協会の有馬もと氏は「まずは、補助犬ユーザー自身に、お手伝いの必要性をお尋ねください。」また「補助犬のじゃまはしないでください。快く受け入れてください」(引用)と答えるそうだ。
補助犬は、突然人に危害を加えたり、食べ物に興味を示したり、吠えたりしないように訓練されているため、受け入れ側も特別に緊張したり、気を遣う必要はない。補助犬が起こした行動の責任は、そのときに綱を握っていたユーザーの責任となるとあるため、犬よりもむしろ、ユーザー自身に不便がないかどうか気配りをすべきである。このような要望を受けて、日本介助犬アカデミーが「補助犬受け入れマニュアル」を作成し、配布を始めた。お店の入り口で「たぶん迷惑をかけるから」と入店を拒否される補助犬ユーザーが一人でも居なくなるように、また企業側としても補助犬ユーザーのお客様を拒むことのないように、企業姿勢というものも問われるであろう。
特に日本人はかわいい犬を見ると撫でたり触ったりしたがる傾向があるが、補助犬がハーネスをつけているときは仕事中であり、犬の気を紛らわせてしまうことになり、それがユーザーの危険にもつながり、決してしてはいけない。場合によっては、ユーザーの好意で触れ合う許可が出ることもあるだろうが、いずれにしろ、いきなり犬に触ったり大声を浴びせかけたりしてはならない。もちろん、補助犬の汚れがひどかったり、周囲の人々に迷惑をかけるような行為を補助犬がした場合には、ユーザーに注意をすることも必要だ。
「犬が嫌いなお客様がいらっしゃるので、ご入店いただけません。」
これは介助犬ユーザーが交通機関や店舗の利用を交渉する際の、一番の断られ文句だという。補助犬障害者の体の一部である。杖や車椅子、補聴器や眼鏡と何ら変わりない大切な補助具だ。現在の日本で「車椅子は場所をとってじゃまになるので、他のお客様のご迷惑になります」と断られることはないはずである。
左図は一般市民へのアンケート結果であるが、犬が嫌いな人が5%という結果を見る限り、上記のような断り文句は通用しないような気がするだろう。公道を犬が散歩する風景は、日常であたりまえの光景であることを考えると、一般市民は補助犬を受入れ易いと思える。しかし、「万が一問題が起こった際」の予防線を張る、店側はハードルが高い傾向にある。上の、一般市民による「身体障害者補助犬という言葉を知っている」とする人が90%に上るのに対し、右上の法律についての質問になると約70%の人が「知らない」と答えている。
左も一般市民の回答であるが、コンビニエンス・ストアの店員による回答もほぼ同じ割合(知っている=36%、聞いたことはある=26%、知らない=38%)であり、やはり法律の内容まで正しく理解していないと、仮にお客から「なぜ犬が?」と質問された場合に答えられないという不安から、受け入れを断ってしまうケースも考えられる。
「法律が施行された以前も以後も、補助犬の入店を断ったことがある」との結果も約40%とあり、特にコンビニのような大手チェーン店では、本部からの通達や従業員教育が重要であると思われる。
(財)日本盲導犬協会のアンケートの他にも、株式会社電通が、2003年6月下旬に全国10代から60代(高校生以上~65才)までの男女個人1,000名を対象に「身体障害者補助犬法」に関する浸透度調査をインターネットにて実施したアンケートにおいても、補助犬の民間施設へのアクセスを「身体障害者補助犬法」で擁護する必要性は、92%の生活者が支持との結果が出ている。しかし、行政施設、交通機関、食品を扱わない民間商業施設については9割近くの生活者が「不安や抵抗はない」と好意的な回答を寄せているにも関わらず、食品を扱う施設への受容れに関しては、30%の生活者から「衛生上の理由からの不安」が挙げられ、調査が実施された2003年6月時点でのスコアではあるが、74%の生活者が「身体障害者補助犬法」に関する情報発信は不充分との認識しているという。しかし、補助犬の衛生管理については、補助犬法においても厳しい管理を義務付けていることから、殆どの場合に大きな問題は発生しないと思われる。
こうしたアンケートの結果が出ているが、補助犬法の設立以前からも積極的に補助犬ユーザーを受け入れようと、取り組みを実施していた企業も少なくない。社会貢献事業の一つとしての試みであったが、
●企業の取り組み例
流通業界としては、社会貢献事業の一つとして、大手スーパーのダイエーが93年に盲導犬、97年に聴導犬、99年に介助犬の受入れや、店内での補助犬との「ふれあい教室」を実施したり(参照PDF)、コンビニエンスストアのローソンも94年に盲導犬、99年に介助犬、00年に聴導犬の受入れをしてきた。(参照PDF)
左の写真は、玉川高島屋ショッピングセンターの食品売り場入り口のドアに張られた2枚のシールである。左側は「ペット入店不可」の表示であり、右側は「補助犬同伴可」を意味するものである。こうした表示の役目は、補助犬ユーザーに対しての安心だけでなく、一般客への理解を求め、また広告としての役割も果たしている。
また、ホテル業界の動きとして、京王プラザホテルは88年に車椅子での利用が可能な客室15室を設けて以来、障害者を積極的に受け入れ、補助犬を連れた障害者も95年ごろから迎え入れているという。(参照)
このような大手企業の活動は、認知度の向上だけでなく、競合他社に対しても良いプレッシャーを与えることとなる。「補助犬の受入れを拒むような企業には行きたくない」と、一般市民が考え、またそのような対応を目の前にした際には、「法律違反ですよ」「受け入れなければいけないんですよ」と店側に声をかけられるような社会にしたいものである。
また、「犬」を理解するということについては、働く犬を理解する事は、犬本来の本能を知ることである。特に日本は欧米に比べて、飼い主が犬の特性や正しい知識を学んでいこうとする姿勢が低いと言われている。また、その情報や機会を与える場が少ないのも事実である。との見解も見られるよ。ペットとして犬を飼う市民も、「補助犬は頭がいいけど、うちの犬はしつけなんて無理」と。本来犬は社会性の動物とされ、群れという集団の中で生きてきている。犬の社会は縦社会で、争いを避ける上下関係を自然にとってきた。これを人間の暮らしに当てはめると、飼い主が上位に立ってしつけていくことで犬の服従本能や社会化が満たされると考えられている。(引用)
「補助犬の先には人間がいることを忘れないで欲しい」と補助犬関係者は口々に唱える。補助犬と共に社会へ踏み出たユーザーに対し、補助犬を理由に更なるバリアが張られてしまわぬよう、「なぜ補助犬が必要なのか」という原点をまず考えることから始めて欲しい。
c.育成団体
補助犬を普及させるためには、社会的な認知を上げるためにも補助犬の数を増やすことが大きな課題として立ちはだかっている。もちろん、高い「質」も伴っていなければ今後の補助犬文化にも悪い影響を与えかねず、「量」「質」のバランスをとりながらどう育成システムを確立させていくのかが、重要なのである。
そのために必要なことは、まず優秀な訓練士の数を増やす必要がある。補助犬は機械で生産することが出来ないために、「補助犬の育成」と「人材の育成」を同時に行っていかなければならない状況がある。しかし、現在の訓練士の育成システムとしては、50年近く歴史のある盲導犬を例に挙げても、個人に「訓練士」という資格があるわけではなく、国から指定された育成団体に訓練の許可がでている形にとどまっている。
盲導犬訓練士と介助犬・聴導犬訓練士には違いがあるので、まず盲導犬訓練士の現状からみていく。
(財)北海道盲導犬協会によれば「訓練士の資格は個人ではなく、法人に与えられるため、まず全国に9箇所ある盲導犬協会に就職しなくてはなりません。」とある。つまり、採用する際はすべて協会職員としての採用であり、盲導犬訓練士を前提とした採用ではないということである。また各団体も財務状況等から人材を育成できる余裕がないところも多く、毎年必ず訓練士の募集をしているとは限らない。募集を行っていた場合でも、何十倍という競争率で門戸が非常に狭い。
訓練士(「盲導犬訓練士」「盲導犬歩行指導員」)は国家資格ではなく、日本盲導犬協会が認めている資格であるが、盲導犬訓練士の資格を取るには協会に就職し、約3年間の研修を受けることが必要とされ、研修では、3年間に20頭以上の犬を育て、障害者への歩行指導を4週間ほど学ぶ。さらに2年間、先輩の盲導犬歩行指導員について、犬の訓練、犬解剖学、動物心理学などを勉強し、技術、知識が基準に達したと認められると「盲導犬歩行指導員」になることが出来るとされている。
また「盲導犬歩行指導士」になるためには、大学(学部不問)を卒業し、且つ厚生労働省が行う「白杖歩行指導者養成講座」は、あるいは国立リハビリテーションセンター等の専門講座を修了した者にあっては、少なくとも3年間の実務経験が必要とされ、高校を卒業した者においては、5年間の実務経験が必要とされている。(日本盲人社会福祉施設協議会盲導犬委員会策定「盲導犬歩行指導員等養成基準」による)なお、2002年6月における「盲導犬歩行訓練士」の人数は37人(引用)とのことである。
しかし、その一方で訓練士を志す若い人たちの中には「犬」しか目に入らず、何のために犬が必要なのかというユーザーのことを考える前に応募をしてしまう現実があるという。日本ライトハウスでは、このような言葉が記されている。
最近は我々の啓発活動だけでなく、マスコミでも盲導犬の話題が取り上げられることが多くなり、訓練士を目指す人が急増してきました。問い合わせのほとんどが「動物(犬)が好きなので、世話や訓練を通して社会の役に立ちたいという、犬との関わりを前面に押しだした内容のものです。もちろん犬が好きである気持ちは、訓練士として不可欠なものです。ただし、盲導犬は視覚障害者の歩行を助ける機能を果たす手段であり、あくまでも視覚障害者が念頭にあっての盲導犬です。なぜ盲導犬を育成しているのか、という理解が今一つなされていないまま、訓練士を目指そうとされることが気掛かりです。((社福)日本ライトハウス 訓練士を希望される方へ)
また、こういった考えの甘さに起因があるのか、不安定な養成体制に問題があるのか、それとも見習いとしての生活が厳しすぎるのか、訓練士を志した人々の多くが夢を諦めてしまうという。(財)関西盲導犬協会の発表によると、以下のようなデータも出ている。
「指導員養成において、最も大きな問題は、採用しても長く続かないということです。研修修了率(1992~95年平均。日本盲人社会福祉施設協議会盲導犬委員会調べ)は、【初年次 56.3% 2年次 28.2%・・初年次からの修了率 3年次 12.7%・・初年次からの修了率】 とたいへん厳しい状況にあります。」
また、1998年日本財団の「盲導犬に関する調査」において「研修生の平均勤続年月は1年5ヶ月」「基本給月額、現金受給月額ともに「15~20万円」が最も多い」「1ヶ月の休日日数は「4日」が29.3%で最も多く平均では5.7日となっており、宿直は1ヶ月平均4.0回、日直は同2.7回」という数字も出ており、養成・研修に対する満足度は、「非常に満足している」が24.4%、「やや満足している」が、22.0%で、約半数の46.3%が満足者である。一方、満足していない人は、「全く」が4.9%、「あまり」が19.5%で、計24.4%。満足していない理由としては、「養成・研修がシステム化されていない」「分かりにくい」「教員の数が不足」「めざす盲導犬の具体像の提示がない」「養成・研修を受けられる環境がない」などがあげられている、との結果であった。
犬の訓練士を目指す高校生の「もともと犬が好きで、動物に関わる仕事をしたいとは昔から思っていたけど、現実的に何となく思い描いてた職種は全く別の分野でした。」との発言にあるように、インターネットプロバイダー@niftyサイト内にある特集で「動物に関わる職業」で人気第1位という盲導犬訓練士のイメージと現実の差は非常に大きい。こうした補助犬の未来を担おうと希望を持つ若い人たちの意思を、チャンスがないことで諦めざるを得ないことが多い今の状況は非常に勿体無いといえる。
以上は盲導犬訓練士についてだったが、介助犬・聴導犬訓練士に関しては、盲導犬訓練士と事情が異なり、いわゆる犬を指示通りに操ることのできる「訓練士」として技術を取得するか、育成団体に入所しそこで学ぶ、というなり方がある。
介助犬訓練士に関しては採用条件として各介助犬育成団体が指定するカリキュラムに沿った学習をしいることが条件となっている場合が多い。目覚しい動きとしては2003年4月から日本介助犬トレーニングセンター理事長の本岡修二氏が京都市内に「SERVICE DOG PROFESSIONAL TRAINNERS SCHOOL」を開校している。生徒数は非常に少ないが、日本テレビ系列24時間テレビでも紹介されるなど、訓練士候補生たちに注目が集まっている。
また聴導犬に関してであるが、現在のところほとんどの協会において訓練士を必要としていないのが現状だ。よって自ら訓練士学校に通うなどして、技術を取得するしかないといえる。聴導犬訓練士は米国や英国で資格として認定を受けることが可能で、この資格を持ち国内の協会に就職したり、独自に「聴導犬訓練士」としてNPOなどを設立し、育成を行っているところもある。
動物に関する専門学校でも、訓練士コースにおいて取得が見込める資格には(社)日本愛玩動物協会による「愛玩動物飼養管理士」や、その学校内独自の「ドッグ・トレーナー」認定資格しかない状況だ。なお、「愛玩動物飼養管理士」とは「ペットケアアドバイザー」とも呼ばれ、動物関係の法令や保健衛生、犬・猫・鳥の適正飼養管理などまで幅広く知識を修得し『動物の愛護及び管理に関する法律』の趣旨を普及啓発することにたずさわる資格のことだ。(引用)よって、確実に補助犬訓練士になるための道はないといえよう。
現在日本ではペットをしつけたり、また警察犬を育成する「訓練士」の民間資格が存在する。(訓練士になるための必須条件ではない)訓練士、ドッグトレーナー、ドッグインストラクターとも呼ばれるが、(社)日本警察犬協会(NPD)、(社)ジャパンケンネルクラブ(JKC)、日本シェパード犬登録協会(JSV)で行っているものだ。訓練士になる方法としては、訓練所に入り、見習いとして約3~5年間(訓練所に寄って異なる)犬舎のそうじ、糞処理などを主に、担当の犬の世話や扱い方、訓練の知識などを学び、一人前になると独立して、個人で出張トレーニングを始めたりするそうで、一人前になるには、最低でも5~8年はかかるといわれている。(参照)まるで伝統工芸の師弟関係のような状態で、仕事を覚えるといった厳しいものであり、本当に強い意志と体力がなければなれない職業である。
比較として、社会認知や信頼性の高い警察犬についても述べておこう。警視庁が警察犬を犯罪捜査に使い始めたのは昭和27年からであり、(社)日本警察犬協会によると、全国には約1300匹以上(推定)の警察犬がいるという。警察犬には、警視庁直属に育成・管理されている「直轄警察犬」と、民間で育成・訓練された優秀な犬を「嘱託警察犬」として活動させている。よって、警察犬訓練士になる方法は二つあり、一つは警察官になって、刑事部鑑識課に配属されて、警察犬担当者になる方法(直轄警察犬訓練士)、もう一つは、警察犬訓練所に入所して、警察犬の訓練士を目指す方法(嘱託警察犬訓練士)があるという。
2002年9月2日の毎日新聞によると、民間の訓練所では、「警察犬の育成」が主業務ではなく、愛犬家から「しつけ」を頼まれた犬の中から、能力が高かったり愛犬家から希望があった犬を「警察犬」として育てているとされ、
警察犬を育成・訓練するには、最低でも1年以上のトレーニングが必要になり、その費用はひとえにオーナーの
「警察犬を通じて社会の治安維持に貢献する」というボランティア精神に頼っているのが現状(引用)だともいう。補助犬と同様に治安を守る警察犬を一頭育成するにも大変な時間と費用がかかることが理解できる。
盲導犬訓練士の方にインタビューをさせていただいた際にも、「確かに今は生きがいや仕事のやりがいはあるけれども、生活としてはギリギリの状態でいつまで続けられるのかわからない」という話もあり、こうした現状も踏まえながら、補助犬訓練士の教育システムの確立と、現在の訓練士たちの社会的地位や生活水準の向上も図っていくべきだと考えられる。訓練士が満足するような環境を整えることが出来れば、質の高い補助犬の育成にも繋がるのだから。
また、介助犬の研究団体「日本介助犬アカデミー」の高柳友子専務理事は、「補助犬の育成はこれまで、犬の専門家である訓練士に任せきりで、医療や福祉の専門家のかかわりが乏しかった。使用者のニーズに合わせた質のいい補助犬を育成するには、リハビリテーションの専門家などの関与も欠かせない」と指摘する。ユーザーが身体障害者であるという趣旨からも、こうした医療やリハビリテーションとの連携も必要とされているが、補助犬だけでなく、その他の福祉政策についても同様のことが言えよう。
一部の補助犬育成協会に対して、「寄付金の用途が不透明」だという苦情が寄せられている(引用)という実情もあり、収支計算書や貸借対照表などの適切な情報開示を行いながら、より一層の信用に繋がる運営も図っていくべきである。信用の置けないところに、人々は寄付をしようとも思えないはずだ。
最後に、適切なPR活動についてである。私は盲導犬育成団体の主催する見学会へ数回参加させていただいた。参加者は、お年を召されたご夫婦や犬好きな夫婦、小学生くらいの子供を連れた家族が多く、生涯学習の場として利用されているということに気づいた。しかし、「盲導犬は可愛いし賢いしすごい!さわりたーい」という声が多く聴かれ、見学者の多くに囲まれ、触られまくる盲導犬を眺めながら、「ワンワンふれあいコーナー」を思い出してしまった。もちろんこれが福祉を考える入り口であり、重要な役割を果たしている。主催者側も「今日知ったことをお友達に伝えてくださいね!」と、障害者福祉を知るきっかけになればいい、という趣旨から行っているので、あまり初めから難しいことはできないだろう。しかし、PRの仕方によっては「盲導犬は賢い犬」で止まってしまうこともあり、犬の先にいる「人」への関心をどうもたせるか、次のステップに繋がるイベント等の主催を期待したい。
犬は人々の身近な存在として、興味を惹きやすく福祉を理解するためのきっかけ作りに役立っている。社会に受け入れやすい、募金が集まりやすい、声をかけやすいなどそれは補助犬の強みでもある。 それと時に「犬」に対する注目が集まりすぎて(マスコミ紹介のPRなど)、視点がなかなか補助犬を利用する障害者ユーザーに当たらず、普及活動の大きなネックにもなっている。
企業のイベントや教育現場での活動の中で、地域や一般市民との関わりをさらに持ち、さらなる育成団体の発展を期待したい。
d.マスコミの役割
私が始めて補助犬の存在を知ったのは、TV番組の特集を見たことだった。たしか盲導犬がユーザーの目の代わりとなって働く姿が映し出され、ユーザーが盲導犬と生活すること中で起こった感動的な出来事について話をしていた。「犬が目の代わりをするなんて、本当に大丈夫なのかな?」と不思議に思った記憶がある。こういった犬と人間の関係について、日本介助犬アカデミー理事の高柳友子氏が「絵になりやすい」(引用)と警笛を鳴らすように、「感動ドキュメント」で締めくくられやすい傾向がある。それは出版されている本の内容を見てもしかりである。
補助犬をテーマにしたマスコミ作品として、番組特集の一つとしてから、TVドラマ、映画、コマーシャルやポスターなどの広告、少女マンガと非常に幅広い。補助犬がそうした感情を引き出しやすい特徴があるのは事実である。もちろん人間は感動することで、モチベーションが上がったり、生きる勇気が湧いてくるのだから、こういった作品を否定するつもりもないし、すべきでもない。
現在、介助犬シンシアに毎日新聞、介助犬アトムに読売新聞社というビッグなスポンサーがユーザーの日記等を紙上で紹介したり、WEB上で公開をしている。こういった活動は読者に対して介助犬だけでなく補助犬、また福祉に関する興味を惹くといった大きな役割を果たしている。
ただ、特に新聞やテレビは影響の多いメディアであるから、発する情報が間違っていたり、取材された側の意図をや想いを汲み取った上で、取材内容に脚色を加えすぎることはしてはならない。番組内容による制限も出てくるだろうが、取材をする側も取材という意識から一歩踏み込んで勉強をしつつ、感動話で終わらせるだけでなく、問題提議を起こし社会がよりよい方向に向くためのサポートをすべき、と考える。
e.政府
次に政府に期待をしたい点について述べよう。政府はまさに国の方針を決め、私たちを支える存在であるが、福祉の問題について、非常に大きな力を持っている。政府の政策の判断によって、人が動き、企業が動き、社会形成を図っているからである。補助犬については「厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 企画課 社会参加推進室」が窓口となり、補助犬の活動のまとめ役を担っている。国としては補助犬を「障害者が社会参加するための一つの方法」として捉えていることに注目して欲しい。なお、都道府県では「障害福祉担当課」が窓口である。
活動の中でも、国民に対してPRをする役割があるが、「身体障害者補助犬法に、より多くの理解を得るために不足しているものは?」の問いには約80%の盲導犬ユーザーが「行政機関が、もっと啓蒙活動に積極的になること。」と答えているという。2002年10月に法が施行されてから補助犬法に関して、駅ではポスター、TVでもCMを流していたのを私は何度も見かけたが、一般企業が商品をマーケティングするのが非常に難しいこの世の中で、これだけで補助犬の存在を理解することはとても難しい。なぜならば、いくら補助犬が「犬」であることをPRしたとしても、その先には「人」がいて、彼らが主役であることが忘れ去られがちになってしまっているからである。
 |
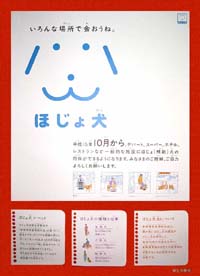 |
国民の意識としては、補助犬を拒否することが、補助犬ユーザーである「人」を拒んでしまっていることに、すぐに結びついていないのではないだろうか。 よりいっそうの理解のためにはその他、「メディアが補助犬法を取り上げる」(68%)「より多くの盲導犬が稼動すること」(63%)が必要だという結果にもなっているが、厚生労働省が中心となって、他の省庁にもPRのための働きかけを進めていって欲しいと思う。
農林水産省では、補助金を出して、繁殖の研究から育種改良、獣医師の養成を行っていたりもするが、特に、文部科学省に対しては「福祉」「道徳」「法律」に関する格好の教育材料になるとも考えられるので、教育プログラムの一環として導入を検討してみても良いかと思われる。補助犬とは少し離れてしまうが、立教女学院小学校では、動物介在教育として、ただ校庭の一部でうさぎを飼育するのとは違った、学校で犬を飼うという教育プログラムを行っている。公立校でこのような試みは難しいと思われるが、地域交流や障害者交流の一つとしてユーザーをゲストにしたり、ビデオを製作するなど、「考える勉強」のきっけかになるであろう。
予算等の面についてであるが、2004年度政府予算では「障害者の社会参加の推進」として62億円の予算が組まれ、この中に「障害者IT総合推進事業を実施するとともに、身体障害者補助犬の育成や視聴覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業の推進を図るなど、障害者の社会参加推進のための事業を総合的に推進する」としている。なお、2003年度政府予算では58億円でありこの予算の中に「視聴覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業を推進するとともに、身体障害者補助犬法の施行に伴い、従来の盲導犬育成に加えて、介助犬と聴導犬の育成にも取り組む」としてある。ITといったデジタル的な事業と、育成というアナログ的な事業が並んでいることに、私たちの日常生活はすべてを科学化できないということを現しているようにも思える。
しかし、2003年5月21日の毎日新聞によると、全国47都道府県と13政令市を対象に、補助犬(介助犬、盲導犬、聴導犬)事業についての取り組みをアンケートしたが、その結果、全体の4割強が介助犬や聴導犬育成のための助成制度を予算化していた一方で、3割弱は予算化の予定すらなく、自治体間の格差が浮き彫りになった、との記事がある。育成団体の有無などによって地方行政の補助犬への関心に差が大きく、これは補助犬希望者がどの地域に住んでいるかということで、福祉サービスの偏りが出てしまうことにもなり、地方行政の間にも柔軟な関係がとられるべきではないかと考える。
次に提言したいのは、福祉業界の健全な拡大のために、国が適切な監視を行うことである。福祉に関する事業は、国が「社会福祉事業」として位置付けながら行っているサービスもあるが、民間で市場競争の中で行われているサービスもある。この両方のバランスを価格の面だけでなくサービス内容、労働条件などでとっていく必要があるだろう。たとえ、障害者自身がゆとりある生活を送ることが出来ても、それを支える人々の労働基準が低いなど苦しむようなことがあるのは疑問を感じる。上記で補助犬訓練士育成の水準を上げる必要性を説いたが、これは福祉業界全体にいえる事ではないかと思われる。
福祉サービスを行う人々の社会的地位を上げ、今よりもよりいっそうやりがいや従事者を増やす努力をすることは、障害者の社会参加だけでなく、高齢化社会にも対応する政策だといえる。また、そういった計画案を作成するときには、参考人として関係者の話を聞き、あとはすべて官僚主導で決定するのではなく、障害者計画を立てる際には、障害をもった人をメンバーに入れるなど、できるだけ国民と近い感覚を持ち合わせ、物事を進める政治を行ってほしいと願うばかりだ。聴導犬ユーザーに「国や行政に期待をしたいことは何か?」と質問をした際に、「当事者の気持ちを理解しようとする人に政治を進めてもらうこと」という答えがあったことも、紹介しておきたい。
またNPOなど、行政がカバーしきれない部分をサポートしようという人々の、頑張ろうとする力の目を摘み取らず、応援することも必要であろう。補助犬の認定業務が「法人」にしか行えなかったということに対し、山本孝史議員が「社会福祉法人あるいは公益法人とNPO法人の間には差があって、NPOは信用できないんだというか、一段格が下なんだというような感じ、あるいはそこに財産的基盤を求めて、財産的基盤がないがゆえに今度は社会福祉法人の基準を下げようというような形を取るというところに、私、筋が少し悪いというふうに思っている。」との発言もある。「信用」というものを、何を基準に判断していくのか、こういった判断力も行政内にも求められている。
最後に、坂口力国務大臣の訓練資格に対する質問の回答を載せておく。
坂口国務大臣「まことに的確な御質問だというふうに思いますが、私も、この法案を前にいたしまして、やはり一番大事なのは、犬を訓練する訓練士をだれが訓練するのかということではないか。ここがやはりしっかりしていないと、どれほど立派な犬でありましても十分に役立つ補助犬になることができない、そこを一体だれが責任を持ってどうするのかということが非常に私もポイントになるというふうに思っております。
ここのところを、例えば資格をつけるとか何かするというようなことが大事なのか、それとも、そういうことではなくて、もう少し、皆さん方に訓練をしていただくことについてはどういうことが大事なのかというふうなお互いに研究をしていただく、そうしたことをつくり上げているのが大事なのか、早急にちょっと検討しなければならないというふうに思っております。
お聞きをするところによりますと、いろいろなやはり流派があって、それぞれおやりだそうでございます。何流、何流というのはあるんだろうと思うんですが、それはそれで、今までの長い歴史の中でいろいろな流儀に従っておやりになっているんだろうというふうに思います。
しかし、共通してこれだけは守ってもらいたい、あるいはこういうことをお願いしたいというようなこともあるんだろうというふうに思いますから、ここは官の方がその中に入り込んでいくというのではなくて、今までそれぞれの中で育ってまいりましたものをどのようにまとめていくか、どのようにそれをまた補助していくかといったことに主眼を置いてこれはやっていかなければならないというふうに思っている次第でございます。」
f.保険会社
補助犬法において、補助犬はユーザーとの関係は法的に「身体障害者の障害を補い、体の機能の一部を補助するもの」として位置づけており、保険手続き上ででは「物」扱いとなっている。「単なる道具として以上の位置づけを与えることはできないのか」という議員の問いがあったが、補助犬というのが一体、物なのか、人の一部として、体の一部として考えていくのか、こういったことも、もう少し考えていっても良いのではないかと思われる。なぜならば、補助犬を連れている人が事故などにあってしまった場合、また事故に遭ってしまい、補助犬を持ちたいと思ったときに場合に保険会社がどういうふうに対応するのか。こういった金銭的な問題も出てくるからだ。
「補助犬の保険扱い」という点ついて、「保険加入者が補助犬に損害を与えた場合の賠償」について損害保険会社5社問い合わせをしてみた。現行上はやはり補助犬は「犬=物的扱い」であり、「犬」そのものの付加価値については、ペットであれ職業犬であれ変わりはないとのこと。しかし、裁判上での手続きで慰謝料や損害額などが発生した場合には、保険会社としては支払う形をとるとのことだった。参考までに2社の回答を掲載しておく。
●東京海上火災保険株式会社
1.補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)に怪我をさせた場合、<対物賠償>によって保険金の支払いは可能か?
→可能でございます。補償対象は主に治療費となりますが、その犬が補助犬としての任務を果たせない場合(期間)には、代替の犬(手段)の費用も補償対象となる可能性がございます。
2.補助犬としての機能を果たせない状態になってしまった場合の賠償金は?
→補助犬の所有者に対する賠償といたしまして、補助犬の時価額(再調達価額)を限度にお支払いできる可能性がございます。●セコム損害保険株式会社
盲導犬、聴導犬等に怪我をさせた等の場合、当然のことながら加害者に法律上の賠償責任が生じますので、任意の自動車保険の対象となります。
はじめに、盲導犬、聴導犬等のみの損害の場合は、対物賠償としての補償となるかと存じます。 その賠償額ですが、これは当該犬の「盲導能力」や「聴導能力」をどう金銭的に測るかということとなり、一概に申し上げることが出来ません。
被害者の方(賠償を受ける側)から主張していただく損害額を賠償側として検討させていただく方法と、何らかの根拠を求めて賠償側が提示する額を、被害者側に検討していただく等により示談にこぎつけるか、最終的には裁判等公の場で決定していただくこととなるのではないかと思っております。
いずれに致しましても、当社として了承させていただきました賠償額が決定した後に、保険金として被保険者にお支払いする、あるいは直接に被害者の方にお支払いすることとなるかと存じます。
また、障害者の方が怪我をされるか亡くなられ、同時に盲導犬、聴導犬等に損害が生じた場合、自賠責保険の支
払対象となっている判例があるようですが、お話をいただいて以降お調べしているものの現在まで確認が出来ておりません。 自賠責の対象となるとすれば、自賠責保険の限度額を超えた賠償額については任意保険の対人賠償の対象となるものと考えております。
現在こうした問題に関する最近の判例としては、介助犬利用者が介助犬の訓練や食事費用についての訴訟(1.毎日新聞 ユニバーサロン 2.レスポンス(車情報サイト))があるので紹介しておこう。この判決では、介助犬の取得費用について「介助犬の存在が原告にとって有益であることは認定するものの、事故当時は介助犬というものが一般的ではなく、この部分についての請求は認められない」(引用)とし、補助犬利用に特化した保険金の賠償は得ることが出来なかった。「交通事故で失明した障害者が盲導犬の費用を請求して認められた判例もある」(引用)とのことで、今後、普及や認知が広まったときに、どう裁判で判決され、保険会社が対応していくのかも、注目すべき点であろう。
また新しいビジネスとして、「ペット共済保険」というものが広がっているのはご存知だろうか。これは人間の健康保険と同じように、ペットが病気や怪我をしたときに、その治療費を保険会社が負担してくれるというものだ。一般に動物の治療費は高価であり、気軽に動物病院に連れて行けない風潮があったのだが、ペットにももっと気軽に医療サービスが受けられるようになってきている。企業によっては、こうした「ペット」保険の会社の中にも、ペットではない補助犬も加入できる会社が数社存在している。
上記は一般市民側の保険問題であったが、もちろん、多くの育成団体では補助犬が他人に危害を与えた場合の補償として、ユーザーへ損害賠償保険に加入することを義務付けたり、また補助犬法でも責任が明確に定義してあり、万が一、問題が起こった場合にも、適切な対処が出来るよう対策が講じられている。たとえば、(特)日本聴導犬協会では、年間約5000円の掛け金で最大4000万円の賠償金がでる保険に加入を義務付けているとのこと。
2項.NPOやボランティアへの注目
1章でも述べたが、補助犬の育成・許可については、補助犬法で「厚生労働大臣が指定した民法上の財団法人、または社会福祉法人によって補助犬の認定が許可される」と規定されているため、NPOは認定はすることはできないが、育成を行うことはできる。補助犬の育成は、すべてボランティアの力から始まってきた。補助犬を育成したい、という意思を持った個人が集まり、NPO(Non Profit Organization=民間非営利組織)として団体が組織され、活動のみならず資金面等でそれを支援する人たちで、長い間運営がなされてきた。(なおアメリカやイギリスではNPOのことを「SCO」(civil society organization=市民社会組織)という呼び方もしている。)こうした流れもあり、今後のNPOやボランティアのあり方についても有益であると考える。
1998年3月にNPO法(特定非営利活動促進法)という法律ができ、市民団体や従来は任意団体、法人格のない任意団体であった市民活動団体が契約主体になれるようになった。法人格を持つことで、信用度が増し、国からの事業委託等の契約ができるようになった。 現在、特定非営利活動促進法における、2003年3月末でのNPO法人の全国の認定数は14657団体(申請は16353団体)となっている。(参照)これは「法人格」のついた団体数であるので、法人となっていない数多くのNPO団体もあることを付け加えておこう。その中でも「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を行っている団体が58.07%とであることに注目してほしい。
少し古いデータであるが、1992年においてアメリカには147万のNPO団体が存在しており、その雇用総数は1511万人、そのうち有給者966万人(68%女性)、またアメリカGDPのNPO事業割合は6.3%にもなるという。平均的な財源としては、寄付収入が20%、行政・公的援助が30%、事業収入が50%といわれている。(引用)
またイギリスの非営利活動について、NPOWEB大学の報告によると、構成団体はイングランドとウェールズでチャリティ団体として登録をしているが約18万8千団体、スコットランドや北アイルランドの団体、非登録団体、草の根団体等を含めると、その数は約60万にも上るとしている。規模として、職員数の総数は全労働人口の2%を占める約563000人(2000年度)で、2001年度のチャリティセクターの総収入は、約156億ポンド(約2兆9640億円)。収入源の内訳は一般からの寄付、会費収入、事業収入で54.1億ポンド(34.7%)、政府からの委託金や補助金等が45.2億ポンド(29%)、投資などによる利益収入などが35.3億ポンド(22.6%)、チャリタブルトラストや財団などの助成金が13.7億ポンド(8.8%)、企業からの寄付が7.6億ポンド(4.9%)と続いている。英国ボランティア団体全国協議会会長のスチュアート・エサリントン氏によると、また全体の60%ぐらいが社会福祉分野のNPOだという。(参照)
このように海外NPOは、代表者が預金をはたいて事業費に充てたり、寄付や援助に頼る日本のNPOのあり方とは違うバランスの良い経営を行っているように思える。活動を継続する上で税制面での優遇措置を望む声も多く、ニーズがあるものの、経済面で問題が生じたためにサービスを止めざるを得ない団体が増加しないよう、政府の政策にも期待をしたい。
イギリス人は人口の65%が定期的に寄付をしていたり、遺産の一部を資金として寄付する(参照)という。日本でも2003年12月8日の日本経済金融新聞によると、「遺言信託での顧客獲得を狙った新サービスとして、みずほ信託銀行は日本盲導犬協会と提携。契約者が死亡後、協会に寄付を希望する場合には遺言信託の手数料を割り引く。公益法人などへの寄付を希望する顧客からの受託を期待。」というように、非営利活動に対して援助を積極的に行うような動きも出始めている。
「福祉」は他分野にわたって大きな影響をもたらすが、こうした部分にもビジネスが台頭してくるのは興味深い。しかし、多くの場合に企業が絡んでくるのは利益が見込める部分であるため、特に「福祉分野」のビジネス化については、合理主義的なコストパフォーマンス重視で目指すべき「福祉」の方向性が崩れぬよう、特に注意を払っていかなければならないだろう。
しかし、政府や企業が行いきれない潜在的な社会ニーズはまだまだ沢山ある。大規模でなければできないこともあるが、NPOのような小規模だからこそできることある。個人の主体性を尊重したこの活動は、阪神淡路大震災をきっかけに日本でも注目されるようになったもので、地域密着型の生活を支援するために地方分権化の進む現在でも、期待をされている。上野千鶴子氏による「ボランティアを行う意識の中には、自分が誰かに必要とされていることを実感したいのかもしれない」との見解は、非常に奥が深い。
補助犬が普及するためには、NPOやボランティアの力が大いに必要である。手軽に行えるものとしては、育成団体への募金や賛助会員になる経済的なもの、団体と提携したクレジットカードの利用、書き損じハガキやタオルなどの送付、イベントなどの手伝いといった作業ボランティアも可能だ。もっと深く関わりたいのであれば、繁殖犬を預かったり(ブリーディングウォーカー)、子犬を1年ほど預かって育てたり(パピーウォーカー)、訓練途中で補助犬に向かなかった犬を引き取ったり(リジェクトウォーカー)、一時的に補助犬を預かる(ステイウォーカー)、引退した補助犬を引き取る(リタイア犬ウォーカー)といった飼育・育成ボランティアもある。(紹介した名称は日本盲導犬協会の使用)
補助犬に特化せずとも、こういった活動がもっと身近に行える社会を目指したいものである。
| 第5章:福祉分野発展への効果 |
1項.補助犬法の果たした役割
私は「福祉」という分野の中でも女性問題については興味をもっていたものの、「障害者福祉」については、特に踏み込みにくかった記憶がある。この障害者福祉について、興味を持ち、知ろうとするきっかけになったのは「犬」の存在だった。「犬」という、障害者よりもある種身近な存在が滑油剤となって、私に障害者福祉を近づけてくれたいたのは事実である。
動物愛護の視点から考えても、犬も他の動物や人間と同じように、より良く生きる権利を持っている。犬にとって暮らしやすい社会とは、障害者にとっても、また高齢者や子供たち、もちろん一般の国民にとっても、安心して過ごせる社会である。
また補助犬が単に頭の良いペットとしてではない、障害者の身体の一部であることを明確にしたこと、「生き物」という新たな補助器具の登場によって、「サポート」に関する新たな概念も生むことにもなった。「動物が人間を補助している」事実と「それが生まれた背景」を私たちはどのように捉えるべきなのだろうか。理想論を述べてしまえば、補助犬や補助器具などに頼らなくても、また存在しなくても障害者の弱い部分を、他の人が支え合いながら生きていける社会が道徳的な観点から見た、あるべき社会であるはずだ。しかし現実的にはそれは非常に困難である。人はそれぞれ個人の世界を持ち、己のアイデンティティの確立を求めながら、自立を目指して自分と闘いながら生きているのではないか。「自分の力で何かをしたい」と考えるのはごく自然なことである。自分に足りないことをするためには、他の誰かに力を補ってもらわなければならない。誰か人の力を借りる以外で、できるだけ自主性を重んじられた方法でそれらを成しえたい考えたときに、多くの人が利用するのは科学の発展と共に発明された道具の数々であろう。補助犬もそんな「道具」の一つなのである。
では、その「道具」をどうやったら便利に使うことができるのか。特に「生き物」を扱っている点で、どうしたら周囲の理解を得ることができ、その機能をより良く発揮できるのか。そうして動物と人間のあり方を再認識するきっかけにもなっている。これは福祉の観点からだけでなく、日常生活上のペットと飼い主のあり方や、動物愛護の観点から捨て犬・捨て猫の問題、環境問題に絡むゴミによカラスの増加や異常発生など、多岐に考えることができる。人間は一人では生きてはいけない。地球上に人間だけでも生きていけない。人間が人間以外の「個を認め合うこと」の必要性、「何かが何かに影響を与え、助けながら生きている」といった生態系上の常識を、日常生活に置き換えて考え直すこともできるのではないか。そう気づくことで、現代の動物と人間の暮らし方について、また自然環境や動物愛護の側面についても見直し、それが補助犬を活かせるフィールド作りにも繋がっていくのだろう。
福祉への理解を進めるにつれ、街づくり、地域環境、
阿部委員の「私どもが生きる二十一世紀というか、これからの子供たちに贈る二十一世紀は、生きとし生けるものへの愛情、命への慈しみということが社会の根幹になってほしい、そうしたことを現実に見せていくための私は大変大事ないい法律だと思います。」という発言が示すように、現代の社会では薄れがちな「いのちの大切さ」ということまで考えさせられるのです。
それと同時に、ペットブームに拍車がかかっている最近だからこそ、より一層しつけやマナーの向上を図っていかなければなりません。補助犬はペットではないけれども、ペットして飼われている犬たちの社会的迷惑行為が減ることになれば、より一層安心して補助犬を受け入れることができる。
また、特別な存在としてとらわれやすい障害者を、どう一般市民と同じように受け容れることが出来るのかを考えてみたい。小浜逸郎氏の著作「『弱者』とはだれか」において、これを「弱者」聖化を超克するためにはと表現し、大事なことは、ある「被差別」感情や「弱者」感情を持つ者と、それを持たないものとの間に、どうやったら橋をかけられるのかである、と表現している。
私はこの「橋」の役割を補助犬が担っていると考えている。もちろん、ユーザー自信の生き様によっても、そうしたきっかけ作りは可能である。しかし、間に犬が入ったことで目をそらしがちな障害者問題についても人々が足を踏み入れやすくなる、そういった側面も持っていると信じている。もちろん主役は補助犬ユーザーであることに変わりはない。しかし、彼らとの心理的な距離感を縮めてくれているのは確かだと思う。補助犬法は補助犬とユーザーを認め、より一層の身体障害者の社会参加を進める中でも、そうしたチャンスを増大させてたという見方も出来るだろう。
「学校の先生が「教える」ということで、生産行為として生活しているのですから、 障害を持つ人が生まれてきたことで、社会とは、人間とは何だろうなと考えさせる作業を促すということでは、まったく同じ事だと思うんです。 つまり、生まれてきたこと事態が生み出す関わりの中で、様々なことを生産しているんだと思う。」(引用)このように障害者の存在を捉えることと同様に、育成にも時間と費用がかかる補助犬の存在についても考えることが出来よう。
2項.ノーマライゼーションの社会に向けて
ノーマライゼーション(nor-malization)とは、1950年代前半のデンマークの発達障害をもつ親の会による「障害者が可能な限り通常な人々に近い生活を実現すること」を新たな原理として施設改革の要求から始まったとされている。この考えは、単に障害者福祉の原理にとどまらず、児童福祉、高齢者福祉、地域福祉など、福祉全般に共通しうる考え方である。
人間は一人では生きていくとは出来ない。人々の自立と依存が複雑に絡み合って成り立つ社会であることを、まず再認識しなければならないだろう。このように、他者への依存が避けられないとしたら、依存をマイナス・イメージでとらえたり、スティグマの感情(恥ずかしい・肩身が狭い感情)を付与したりするのではなく、依存を当然のこととして、むしろ「尊厳ある依存・尊厳を失わない依存」(dependency with dignity)を実現させていくべきである。(引用)それは”自律”を尊重することであり、自分の生き方や人生を自分で決めることに繋がる。
しかし現在の社会では、まだまだ身体障害者にとってもサービスや自律のための選択余地が少ないことはいうまでもない。しかし、「福祉権」(1)福祉サービスを利用するにあたっての情報を受ける権利、(2)福祉サービスを利用しているもののプライバシーが保護される権利、(3)福祉サービスへの接近(access)を容易にされる権利、というものが存在することを、特に情報化が進んだ世の中では忘れてはならない。アドボガシーとは、福祉権が守られなかったり侵されたりした場合、人々の権利を代弁し、権利を回復する行為、つまり障害者の権利擁護を指す。これには「セルフ・アドボガシー」(自分自身のために主張を行い、行動を起こし活動すること)、「シヴィル・アドボガシー」(シチズン・アドボガシーともいい、市民が他者の権利を護るボランティアなどの活動)、「リーガル・アドボガシー」(法律の専門家やソーシャルワーカーによって、裁判等で本人を代理する、以上参照)があるが、我々にはこうした役割も求められていることを忘れてはならない。
たとえば、もし補助犬を連れた障害者が入店拒否をされる場面に遭遇したら、入店が出来るゆえを一言いうだけでもいい。「知っていますが、他のお客様が迷惑ですから」と店員が言うのであれば、それが犬ではなく人を拒否しているることと同じであることに気づいてもらえばいい。知らないことは知ってもらうことで解決することができるが、知っているのにを実行できないのは非常に悲しいことであるし、間違っていると指摘、改善しようとする姿勢が、すこしずつ社会を変えていく。
日本障害者リハビリテーション協会副会長の板山賢治氏は、これから日本が「完全・平等」、つまりノーマライゼーションの行き届いた社会を目指すためには、(1)国内的には法制度に一本筋を通すこと(2)市区町村障害者計画の策定及びその充実の推進(3)障害者運動の活性化(4)アジア・太平洋地域との連帯を推進すること、の必要性を説いている。(1)では各種法制に可能な限り「義務規定」「罰則規定」を明定するよう法改正運動を「国連・人権規約」とも関連して進め、(3)ではそして障害者組織への若い人々の参加による世代交代を実現することを提言している。(参照)
都心ではご近所付き合いもあまりなく、常に時間に追われた生活を送っている結果なのか、自分自身に精一杯で他人に無関心になりがちだ。それでも、千代田区の生活環境条例の改正おいて、歩き煙草の禁止条例が罰則付きで施行された後は、絶大な効果が出ているという。懸命な言葉などによるPRによって問えなかったモラルが、「お金」という罰則が強力に自身のモラルに訴えることができる現代人の傾向を象徴している。
「補助犬に対する社会全体の理解と同意の前進に努めることが現在の主眼である、こういう考えから努力義務規定とし、罰則を設けることはしませんでした」と衆議院議員の発言があったが、この言葉には「まだ日本人には罰則がなくても、人の気持ちを理解しようとする心がある」と、政府でも期待を持っていることが伺える。やはり、人々がみな思いやりを持ちながら、よりよく生きていくという「福祉」本来の目的を考えると、確かに「罰則」いう力を借りたくない、という想いがあるのだろう。
しかし、「罰則がある」→「それはよくないことだから」→「ではなぜだろうか?」と、「罰則規定」によって、本来の意味を問うためのきっかけになるのではないだろうか。今後は、障害者差別に関しても罰則規定を検討すべきであると考える。
いくら頭の中で「障害者も健常者も、老若男女問わず、みんなが平等」であることを理解しても、実生活で実現できなければ、全く意味がない。身体障害者補助犬法は、障害者の自立を促すための一つの方法であり、障害者と身近な「犬」という命を介しながら、私たちに「生きる」ことの意味を問うている。
全章にわたり「障害者」という言葉を用いてきたが、これは身体的特徴によって定義された一つのカテゴリーであり、決して人くくりにすることは出来ない。捉え方によっては文脈上、不適切だと感じられる部分もあっただろう。人には身体の他にも、性格や生活環境、思想や嗜好も異なり、よってAさんはBさんを「障害者」だと思っているが、Bさんは自分を「障害者」だと認識していない場合もある。「NHKハート展」に出品された一つの詩を紹介したい。
| 「僕という人間」 松下大介氏 神奈川県 肢体不自由 僕は僕に「障害」があると 思っていなかった 僕が僕が生きにくい世の中に 障害があると思っていた でも、人は僕のことを 「障害」のある人と言う 僕は僕自身だけれど 「障害」ではない |
東洋大学社会科学部教授の一番ヶ瀬康子氏は、「障害とは何か」という問いの中で、この作品を介しながら「障害」はその人のものではなく、その人が生きにくい世の中、「社会」そのものにあるとうことにあるとし、社会福祉学はこれに気づいたときに始まるのだ、としている。(参照)
では、ノーマライゼーションの社会を目指す中で、障害者にとって、「居心地の良い社会」になるためにはどうしたらよいのか。それは良い意味で「気にされない」存在になることである。そうなるためにも、一般市民は障害者に対して「過剰な意識」や自立を妨げるような「特別待遇」をするべきではないし、障害者自身も出来ることを完全に「依存」したり「甘え」たりしすぎていてはいけない。もちろん障害者であれ、健常者であれ、困っているときに手助けが必要なのは同じである。小浜逸郎氏は弱者(障害者)を差別しないためには、「まず個別の接触体験を深める『慣れる』というところにしかない」としている。そのためにも、多くの障害者が社会に進出できる土台作りが必要なのだ。身体障害者補助犬法もその一つである。
日本は、「神様、仏様、稲尾様」と複数の神に祈る言い回しもあり、年間を通じてお正月、お宮参り、クリスマス、お葬式や教会ウェディングなど、多宗教の文化を寛容に受け容れられる日本。そんなバランス感覚に優れていると思う。それは同時に、補助犬を連れた身体障害者だけでなく、様々なマイノリティーたちも認め合える国だと、私は信じている。
そんな多様性を認められる社会においてならば、障害者たちは補助犬を利用することで身体機能が向上し、家族やヘルパーに頼る機会が減ったことで、精神的ストレスからの開放と自分への自信を回復することができる。補助犬が仲介役となって一般国民とのコミュニケーションの場も増えるだろう。それにより湧いてくる意欲で様々な活躍が期待でき、今まで自分の知らなかった能力を発揮できるかもしれない。まさに、社会に対して「福祉問題」を問いかけながら、補助犬は障害者の自己実現の可能にすることができる。
| あとがき |
この研究を進めている途中の2003年9月に、私は顔の半分の神経が動かなくなる「顔面神経麻痺」という病気を患いました。今まで身体障害者の方の気持ちについて、自分なりに考えてみたことはありましたが、朝起きたときに今まで何も意識することなく動いていた顔の筋肉がまったく言うことを利かなくなり、いざ自分自身の身体機能の一部が麻痺してしまった、そのときの言葉には表現できないほどの予想以上のショックは、涙も出ないほどのもので、今でもよく覚えています。
日常生活に大きな支障はありませんでしたが、神経麻痺という「障害」を自分自身で受け入れられない間は、「障害者の自立」についてが焦点となるこの研究を進める気持ちにはなれませんでした。「自分の顔」だとは認めたくないがために揺ぎ崩れる己の自信や、「不自然な自分の顔を他人はどう思うだろう」という自意識、「このままずっと自分は変われなのか」など様々な葛藤と戦う日々でした。
数多くのシンポジウムやイベントでは沢山の障害者の方のお話を聞かせていただきました。障害の程度で悲しみが変わったり、苦しみを図ることは間違っているのかもしれませんが、おそらく多くのユーザーは私以上に悩み、考えた経験をお持ちなのだと思います。それを乗り越えて、補助犬を持つことで「より一層自分を生かしたい」と強い意志を持ったユーザーの方々の勇気や強さを考えると、「知らないから」「一緒にいるのが犬だから」という理由で、まさに身体の一部である補助犬の同伴を拒まれたときの気持ちを考えると、自分自身を否定されてしまうような気持ちになったのではと思え、本当にいたたまれません。
人は、その当事者になってみなければ理解できないことが本当に沢山あります。人それぞれに千差万別の生き方や考え方があり、悩みもあります。2003年12月から横浜市営地下鉄が座席を全面優先席に始めましたが、JR埼京線や京王電鉄の女性専用車両など、このような半強制的な措置をとらなければ「相手の立場に立って物事を考える」きっかけを見つけられないことが、世の中の風潮なのかと考えると寂しいと感じます。
私が高校生のころ、聴覚障害をもった年上の女の子の友達がいました。インターネットで知り合ったせいもあり、実際に会ったことはありませんでしたが、彼女とメールなどをしたりするたびに「なぜ?」「どうして?」と不思議に思うことが沢山ありました。その一つに、「障害を理由に家が借りられない」という出来事がありました。彼女は非常に優秀で、日本でもトップクラスのある大学の受験に合格をしたそうです。通学するには自宅から距離が遠いため、上京するために準備を始めました。しかし志望学部に受かって喜んでいたのも束の間、どの不動産屋も聴覚障害を持つ彼女に部屋を貸すのは、万が一事故でも起こったら助けが呼べないではないか、などリスクが大きいから、と部屋を貸してくれないというのです。結局、入学手続きの締切日までに下宿先が見つからないという理由で、彼女は合格した第一志望の大学を諦めて自宅から通学できる別の大学に入学したそうです。
私は今春から不動産会社で勤務する予定になっています。彼女のように、障害を持っているが故に家を借りることが出来ず夢を諦めてしまう方が一人でもいなくなるように、最大限努力することも自分の一つの使命だと思っています。簡単に社会は変わりません。どんなに小さなことでも自分が出来ることからやってみる、それが席を譲ることでも、100円の募金でも、補助犬をそっと見守ることでも、まずはそれから始めれば、補助犬を利用する身体障害者の方たちだけでなく、小さな子からお年寄りまで誰もが安心して暮らせる社会が出来上がっていくのだと思います。自分以外の人々を理解して知ろうとする意識と心の余裕をもつこと、これこそが今の日本人にもっと必要なことではないでしょうか。補助犬法の見直しが行われる2005年、今よりも素敵な社会になっていることを願ってやみません。
最後に、この研究を進めるにあたり、多くの補助犬ユーザーや育成協会、マスコミ、訓練士希望の方など沢山の関係者の方々との出会いがありました。また上沼正明先生やゼミナールの仲間たちに協力をしてもらったり、励ましていただきました。皆様のお力なしには、この研究は成り立たなかったと思います。また研究を通じ、「物事のプロセス」を知る中で学んだことも数多くあり、これからの自分自身にとっても大きな勉強になりました。本当にありがとうございました。
| ●参考文献一覧 |
| ●参考ホームページ一覧 |
・・・毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/
・・・YOMIURI ONLINE http://www.yomiuri.co.jp/
・・・アシスタントドッグ育成普及委員会 http://www.assistant-dog.com
・・・dog data http://www.inter-highschool.ne.jp/~s0211003/dog_data/index.html
・・・(財)北海道盲導犬協会 http://www.h-guidedog.org/
・・・(財)日本盲導犬協会 http://www.jgda.or.jp/
・・・(財)アイメイト協会 http://www.eyemate.org/
・・・(財)中部盲導犬協会 http://www.tcp-ip.or.jp/~chubu/
・・・(財)関西盲導犬協会 http://web.kyoto-inet.or.jp/org/kgdba/
・・・(財)兵庫盲導犬協会 http://www.moudouken.org/
・・・(財)福岡盲導犬協会 http://www.fgda.or.jp/
・・・(社)日本ライトハウス http://www.h-guidedog.org/
・・・全日本盲導犬使用者の会 http://www.e-guidedog.net/
・・・特定非営利法人日本介助犬アカデミー http://www.jsdra.jp/
・・・NPO法人介助犬協会 http://www.s-dog.jp/index.php
・・・日本介助犬トレーニングセンター http://sdog.age.ne.jp/
・・・介助犬育成の会 http://www.kaijoken.info/index.htm
・・・介助犬シンシア日記 http://village.infoweb.ne.jp/~cynthia/
・・・mainitchi INTERACTIVE 介助犬シンシア http://www.mainichi.co.jp/osaka/cynthia/index.html
・・・介助犬「アトム日記」 http://chubu.yomiuri.co.jp/shiawase/conhp/atom_all.html
・・・日本ヒアリングドッグ協会 http://www.sun-inet.or.jp/~hearingd/0/
・・・(社)日本聴導犬協会 http://www.hearingdog.or.jp/
・・・特定非営利法人介助犬普及協会 http://www.hearingdogjp.org/
・・・エンゼル聴導犬協会 http://www4.ocn.ne.jp/~heardog/
・・・聴導犬育成の会 http://www.kamakuranet.ne.jp/~ikusei/
・・・全日本補助犬パートナーの会 http://members.at.infoseek.co.jp/assistancedog/
・・・はたらくわんこハウス http://www.sign-eg.com/wanko-top.htm
・・・DPI日本会議 http://www.dpi-japan.org/
・・・聴導犬美音(みお)とゆかいな家族 http://www.matsufamily.com/
・・・日本財団 図書館 http://nippon.zaidan.info/
・・・障害保健福祉研究情報システム:http://www.dinf.ne.jp/index.html
・・・内閣府 NPOホームページ http://www5.cao.go.jp/seikatsu/npo/
・・・NPOweb http://www.npoweb.jp/index.php3
・・・Assistance Dogs Internathional (US) http://www.adionline.org/
・・・hearing dogs for the deaf people (UK) http://www.hearing-dogs.co.uk/
・・・San Francisco society for the prevention of cluelty animals (US) http://www.sfspca.org/home.shtml
・・・Canine Companions (US)http://www.caninecompanions.org/
・・・Dog for the Deaf,INC (US) http://www.dogsforthedeaf.org/index.htm
・・・International Association of Assistance Dog Partners(US) http://www.iaadp.org/index.html
| ●参照ビデオ一覧 |
(提供=NHK厚生文化事業団 ビデオライブラリー)
「明日の福祉」 ~いいなあ私の町~
にんげんゆうゆう「ハイテク車いすが世界を広げた」
国際フォーラム「障害者差別をなくすために」
「アメリカ障害者法の衝撃」
社会福祉セミナー「これからの社会福祉」
「私の手足となってほしい」~障害者を支える介助犬~
「介助犬アトムと仲間たち」