[これからの日本人とスポーツの関係]
―新日鉄のクラブ化より―
text by Keitaro Toyoshima
□研究動機□
知将・故大西鐵之祐は著書「ラグビー 荒ぶる魂」の中でこのように語っている。
「スポーツの勝負におけるいろいろな情緒的行動ほど、コントロールのむずかしいものありません。ここにスポーツを通じてのもう一つの教育的価値があると思うので
す。激動する社会の闘争、あるいは競争の渦中にあって自らの情緒的行動をいかに平和にコントロールするか。
こうした修行の過程が、ゲームの中に存在すると考えるからです。」
しかし、せっかくの教育的価値も使われなければ意味はない。
かつてスポーツ少年・少女の受け皿であったはずの学校内部活動も、少子化による影響を免れない。入学した高
校にやりたい部活動がない。辛うじてあったとしても、教えるべき先生が素人だった、人数が足りずチームが組めない
、などの話は珍しくない。また、日本の企業アマチュアスポーツ界も不況のあおりを受け、廃部・撤退が相次ぐ始末。
これでは、底辺のスポーツ人口が減少するのも目に見える。
以下、勝手な予想。
今後、若者のスポーツばなれが進行。若者が大人へ成長。そして、情緒的行動をコントロールすることができない社会が誕生。
いささか大げさか?
このような不安を抱いている者が、新日鉄バレーボール部のクラブ化の話を聞いたとき、飛びつかずにはいられなかった。日本の将来
を左右する、今話題の”地域密着型スポーツクラブ作り”を考察したい。
▲ index ▲
□第1章 堺ブレイザーズの誕生□
①クラブ化の経緯
新日鐵バレーボール部。
全日本選抜リーグ(通称 日本リーグ)の初代チャンピオンに輝いてから今日まで、日本一になることなんと53回。
文字通り「常勝 新日鐵」であり、日本のバレーボール界をリードしてきた。
だが、「常勝 新日鐵」であっても、平成大不況に勝つことは出来なかった。一企業である新日鐵にとって、バレーボール部(以下、バレー部)だけで
2億数千万以上といわれる年間経費は重荷以外のなにものでもなかったのだ。そして、多くの企業がスポーツからの撤退を宣言する中、新日鐵が選んだ手段は・・・。
2000年11月、「企業スポーツの新たな方向を目指して」と題する発表を行った新日鐵は4カ所にある野球部(八幡、広畑、名古屋、君津)、男子バレーボール部(堺)、ラグビー部(釜石)、柔道部(本社と広畑)を、地元市民や複数企業、自治体から支援を得て運営する「広域チーム」にする決定を下した。
バレー部はその第1弾として「堺ブレイザーズ」と名前を変え、新しい形態に乗り出した。新日鉄の100%出資で運営会社を設立。選手は新日鐵の出向社員という形で生活を保障された。運営会社の「ブレイザーズスポーツクラブ」は、サッカーの横浜FCで有名になった「ソシオ(スペイン語で組合員などの意味)制度」を採用してサポーターの会員集めに着手。2月には堺市バレーボール協会と提携した市民大会を開催する。中学校のバレー部への指導者派遣も検討中。将来的には新日鐵所有の運動施設(体育館、軟式/硬式野球場、サッカー・ラグビー場、柔道場、弓道場、トレーニングジム、宿泊施設など)を市民に開放して総合型の地域スポーツクラブを創設する予定
[スポーツナビホームページより作成]
である。
この堺ブレイザーズの挑戦がどうして注目され、期待されているのか、企業スポーツ界の側面から次の項で見ていく。
◎ソシオ制度・・・会員を集め、試合のチケット優先販売などの特典と引き換えにチームの運営費となる会費を払ってもらう制度。つまり、会員はクラブのオーナーになるということ。
ちなみに、堺ブレイザーズのソシオ制度は以下のようになっている。
◆堺ブレイザーズの会員制度(ブレイザーズサポーターズクラブ)
- フレンズ会員・・・年会費 3,500円
- ソシオ会員
- 個人会員・・・年会費 1口・10,000円
- 法人会員・・・年会費 1口・50,000円(2口以上) ※全てに特典付き
「堺ブレイザーズホームページ」より
◆(参考)スペインFCバルセロナのソシオ制度
- ソシオ数・・・10万5千人以上(これだけの人が注目していると、当然、企業からの広告収入もすごくなる)
- 年会費・・・2万ペセタ(約13、000円)
同クラブはサッカー以外にもバスケットボールやハンドボール、野球、ラグビー、バレーなど10種目のチームを持つ。また、バルサのオーナーになるということで、市民にとってひとつのステイタスになっている。
「試合前に黙祷をした事があった。それは、1年間に亡くなったソシオに対して捧げたものだった。」
[産経新聞より]
20世紀の日本のスポーツは、プロ野球以外、企業アマスポーツで成り立ってきたと言える。
オリンピックが純粋なアマチュアの祭典だった頃、企業スポーツから数多くのメダリストを輩出
してきたことが、それを証明する。
先に述べたように、今では企業スポーツの廃部・休部が相次ぐが、かつて日本に根付いていた
企業アマチュアスポーツ。そもそもその意義とは何だったのか?見直していきたい。
企業スポーツは、社員の福利厚生に始まった。しかし、だんだんと競技力が上がっていくと、
試合の興行的側面も大きくなり、会社の求心力・広告塔・社員の士気高揚という存在価値が加えら
れていく。そのため、
ほとんど会社の仕事をせず練習だけをしてお給料をもらう、「プロもどき」が出現し、社員の一体感など
きれいごとに過ぎなくなるのだ。そして、「あんた仕事できるのかよ!」と言いたくなる外国人選手も、
勝つために名目上企業の社員になってもらった。また、練習環境も快適なものが求められ、遠征・合宿も強くなるには行かざるおえない。
なるほど、経費がかさむわけである。
それに加え、日本経済は平成不況真っ只中を走行中。
結果、この経費を払えなくなりスポーツから撤退する企業が続出し始めた・・・。
元リクルート陸上部監督、現ニッポンランナーズ理事長の金哲彦氏の証言は、企業スポーツの限界を如実に表している。
「実業団(企業スポーツ)の経費はその100%が福利厚生費です。(略)結局は税金対策です。実は儲かっているときにはすごく都合のいい仕組みだった。税金で払わなくてはいけないものを福利厚生費として運動部を運営することによって宣伝費の役割も果たして、社員の士気高揚にもつながっていた。」
だが。終身雇用制が崩れ始めた状況で、会社に誇りを持たせ帰属意識を高める士気高揚、ロイヤリティーは必要なくなる。さらに、社名のみで商品名をつけることができない陸上では、宣伝効果も薄くなった。
「2つの意義がなくなっているのにかかわらず、一つのチームを維持するのに陸上では年間2億円ぐらい経費がかかります。」
[『現代スポーツ評論6』より抜粋]
以下、経費を払うことを諦めた企業の一覧。
◆主な企業チームの休・廃部 (過去3年間)◆
| バレーボール |
ユニチカ・日立・朝日生命・小田急・東芝・象印・住友金属 |
| ラグビー |
伊勢丹 |
| 陸上 |
雪印・九州産交・横浜銀行・営団地下鉄・岩田屋・川崎製鉄千葉・三田工業・
ニコニコドー・ダイエー・王子製紙苫小牧 |
| ハンドボール |
三陽商会・大崎電気(女子)・中村荷役・三陽商会・デンソー |
| 野球 |
プリンスホテル・住友金属・大和銀行・東芝府中・ヨークベニマル・ニコニコドー |
| サッカー |
鈴与清水・松下電器・プリマハム・OKI(女子) |
| バドミントン |
三協アルミ |
| ホッケー |
ゴールドウイン |
| アイスホッケー |
雪印・日光バックス・ゴールドウイン(女子) |
| バスケットボール |
日立大阪・愛知機械・NKK・三井生命・ジャパンエナジー(男子)第一勧業銀行・
富士銀行・東京三菱銀行・三洋電機(女子) |
| アメリカンフットボール |
マイカル |
| スキー |
ニッカウヰスキー・地崎工業 |
| テニス |
豊田自動織機 |
| ソフトボール |
日通工(女子) |
*バレーボールでは1997年以降、V・V1リーグ合わせて9チームが休・廃部。ダイエーはオレンジアタッカーズ、東芝はシーガルズ、日立茂原は茂原アルカスとしてクラブ組織で存続。オレンジアタッカーズは昨年、久光製薬がオーナースポンサーとなった。2000年休部のユニチカは東レに全体移籍している。
[スポーツナビホームページより作成.2001時点]
◆年次別・企業スポーツ休廃部数一覧(1991~2003.11)◆
◆
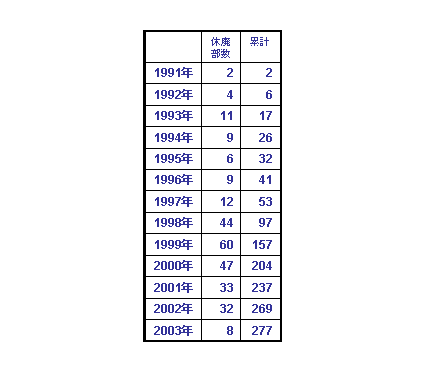
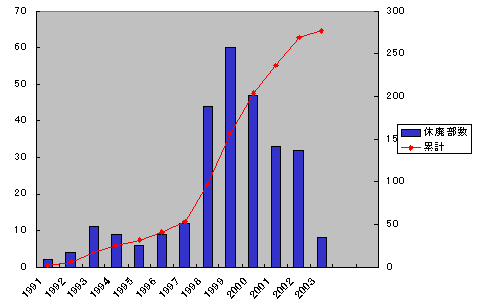 [スポーツデザイン研究所ホームページより作成]
[スポーツデザイン研究所ホームページより作成]
「利益にならないものは必要ない」
不景気の中、企業運動部が廃部・休部させられる理由はこれに尽きるだろう。企業が経営見直しをして、不況を乗り切ろうとする。そして多くの企業がリストラを選択する。アマチュアスポーツである以上、利益を生み出さない運動部は、リストラの対象でしかなかったのだ。
また、よく言われる「運動部への投資は社会貢献だ」とする考えも、企業の生き残りを前にするときれい事にすぎないのかもしれない。
もちろん、中には運動部を存続させた企業もある。
日産自動車もその1つだ。今や日産自動車の顔となったカルロス・ゴーンは、1999年6月に同社の最高執行責任者(COO)に就任して以来、工場の廃止などのリストラ策を講じてきたが、野球部をはじめとする運動部には手をつけなかった。なぜだったのか?
彼は毎日新聞のインタビューでこう語っている。
「スポーツは日産自動車のブランド・アイデンティティーであり、社員の帰属意識を向上させるからです。ただ、きちんとマネジメントされているか、競争力があるかが重要です。社員や一般の人が応援したくなるような強いチームでなければならないし、適切な量の資源を投入することが必要です。」
「企業がスポーツチームを持つ意味は、社員が支援することを誇りに思い、その成績によってやる気を出すといった成果を上げることです。」
(毎日インタラクティブより)
「スポーツのためのスポーツ」ではなく「企業利益のためのスポーツ」
つまり日産自動車の場合、先に述べた「スポーツ=社会貢献」ではなく、企業利益を最優先に考えたうえでの存続だったのだ。企業スポーツが崖っぷちの今、ひとつの在り方を示したといえる。ただ、この考えも驚異的な業績回復に向かっている日産だからこそ言えるのだろうが・・・ 。
しかし、何社かの業績優秀な企業が企業スポーツを存続させているからいい、という問題でもない。すでに数多くの企業が撤退していったことが、大問題を引き起こしているのだ。
「文化」 と 「競技力」
企業スポーツが減少することで、この2つが失われると理解している人は少なく、
失ってはいけないものだと理解している人はより少ない、のではないか。
文化。たとえば、ラグビーを知らない新入社員でも、会社が盛んなら自然とルールを覚えるし、応援もする。また、会社のある町の周辺住民は、大会があれば商店街に横断幕を掲げ、試合結果に一喜一憂する。これぞ文化。新入社員と近所の主婦の生活に不可欠になること間違いない。
競技力。企業スポーツには長い伝統がある。先の新日鉄バレー部は55年の歴史があり、この間に蓄えられたノウハウ、伝えられた技術はお金で買えるものではない。これがなくなってしまったら・・・。それだけで日本のバレーが55年古くなる!?さらには、企業スポーツに落とされるお金も減る。
また、各競技のトップクラスである企業スポーツが繁栄していなければ、その競技をやる若者が減少するのも否めない。次世代が育たなければ、その競技に未来はない。
したがって、この2つを失ってしまう前に、企業スポーツに変わる何かを早急に作る必要があるのだ。それが新日鉄が目指す「地域密着型スポーツクラブ」だ。パイオニアとしての堺ブレイザーズの挑戦が期待される理由がここにある。
以下の堺ブレイザーズ事業部長・小田勝美氏の言葉にもその決意と自覚が表れている。
「オーバーな言い方かもしれないが、ブレーザーズが成功したら、ほかの企業スポーツもみんなこれになるのではないか。逆に失敗したら、廃部のチームがもっと出るかも知れない。(略)」(「現代スポーツ評論」より)
現在、堺ブレイザーズ以外にも多くの地域密着型スポーツクラブ作りが行われているが、決して全く同じ形態ではない。第2章では、それらをタイプ別に見ていきたいと思う。
◆参考◆ ~企業スポーツが生き残るとしたら~
企業スポーツの危機・限界は見てきたとおりであり、欧州型の地域スポーツクラブを目指すべきではある。かといって、日本と欧州ではスポーツの生まれ方や歴史、文化がまるで違い(日本に厳密な意味でのスポーツは存在しないとも言われる。あるのは武道。)、欧州の完全なる模倣で成功するとも考えられない。
そこで、日本固有のスポーツ文化である「企業スポーツ」が存続できるよう見直すべきだ、と考えたのが、佐伯年詩雄氏(大崎企業スポーツ事業研究助成財団 情報交流委員)である。
以下、その考え方を紹介する。
現在の”企業スポーツ”は「企業→スポーツ離れ(不況)」、「スポーツ→企業離れ(地域クラブへの憧憬)」の影響で”企業”と”スポーツ”の間に、溝ができてしまっている。またバブル崩壊後、日本型経営手法の批判に伴い、同じく日本固有である”企業スポーツ”というシステムまでが、リストラ対象になってしまった。
だが、スポーツは「メディアバリュー」と「シンボリズム」を併せ持ち、手段によっては、企業にとって貴重な経営資源となるはずであるという。
企業にとってのスポーツの存在価値は、
[昔]・・・・企業求心力、福利厚生
↓
[現在]・・莫大な経費と利益なし、プロスポーツの台頭で求心力低下
↓
[未来]・・日本(企業)固有の経営資源として開発&活用
となるべき。
バブル崩壊後、日本企業の経営サイクルは短くなり、すぐに出る利益が求められた。だが、スポーツの場合は、長い目で育てていく必要があるのだ。例えばJリーグの「百年構想」[詳細は第2章「Jリーグの場合」へ] のように。
さらに、企業がスポーツに対する「特別扱い」をやめるべきだとも言っている。
- 特別なカネ・・・社長の趣味。だからお金が出る。
- 特別なヒト・・・強化のため、特別枠で新入社員が入ってくる。待遇も特別。
- 特別なモノ・・・グランド、設備などは正式なプロセスを踏まず作られること多い。自社工場なら何度も会議が重ねられるはず。
つまり、不況で会社のカネが無くなれば、趣味に費やすカネがなくなり、衰退するのは当たり前だと考えられる。
ではどうすべきか。
戦略的に考える。審議プロセスから、団結・宣伝・社会貢献・福利厚生・・・などの目的のうち、どれを狙って行うのか?という視点が必要となる。そして、狙った目的が達成されているならば、「負け・弱い=即廃部」にはならないのだ。「勝負以外に、価値がある」という考えを持たないとならない。
▲ index ▲
□第2章 地域密着型スポーツクラブの試み□
試行錯誤で行われてきた企業スポーツのクラブ化は、それぞれ異なったアプローチがなされている。そのアプローチの方法により幾つかのタイプに分類することができる。したがって、タイプ別にクラブ化の実態を考察していきたい。(なお分類は左近允輝一氏の「企業スポーツの新たな可能性」によるものに加え、企業スポーツ以外の地域型クラブとして”政府型”、”ワセダクラブ”、模範となるべき”ヨーロッパのスポーツクラブ”を加える)
①企業スポーツからの試み
◆生まれ変わった企業スポーツ分類例◆
| |
例(現チーム名) | 元の企業チーム | 種目 |
| 企業連携型 |
トップス広島 |
サンフレッチェ広島
JT
湧永製薬
イズミ
広島銀行
広島ガス |
サッカー
男子バレー
男子ハンドボール
女子ハンドボール
女子バスケット
バトミントン |
| 地域主導型 |
ヴィガしらおい
日光アイスバックス
ニッポンランナーズ
SCC
さいたまブロンコス |
大昭和製紙北海道
古河電工
リクルート
城山観光
マツダ |
社会人野球
アイスホッケー
陸上
陸上
男子バスケット |
| 企業主導地域支援型 |
堺ブレイザーズ |
新日鉄堺 | 男子バレー |
| 地域主導企業支援型 |
釜石シーウェイブス
広島メイプルレッズ |
新日鉄釜石
イズミ |
ラグビー
女子ハンドボール |
[「現代スポーツ評論6」中の表より作成]
■企業連携型■
同じ地域の企業スポーツが、競技の枠を越えて連携し行動することで、スポーツの発展・地域活性化を!
【トップス広島(正式名称:広島トップスポーツクラブネットワーク)】
(サンフレッチェ広島・JTサンダース・湧永製薬ハンドボール部メイプルレッズ・イズミ女子ハンドボール部・広島銀行ブルーフレイムズ・広島ガスバトミントン部)
「1本は折れても3本の矢は折れない。5本ならもっと折れない。」
2000年4月、全国で初めて企業チーム同士が互いに連携を取り合う形のトップス広島が立ち上げられた。地域とともに発展するJリーグの「百年構想」を共通理念とし、情報交換や観客動員での相互協力と、地域貢献を二本柱に据え、企業が休、廃部をしにくい環境づくりを狙う。
しかし、視野に入れてはいるものの、今のところ総合的地域密着型スポーツクラブにはなっていない。地域イベント、スポーツイベントの共同参加相互試合観戦や、学校への選手派遣による指導にとどまる。
また、企業スポーツという形態自体は変わっていないため、企業優先の考えでは活動資金に限界があり、それが活動内容までも限定してしまっている。
活動目標
- スポーツ情報の収集発信に関すること
- スポーツの普及に関すること
- スポーツの競技力向上に関すること
- スポーツの環境向上に関すること
- 県民市民及びクラブ相互の交流に関すること
- その他目的達成のために必要なこと
(クラブネッツホームページより)
■地域主導型■
チームのサポート・運営を地域に委ねることで存続させ、企業は完全にスポーツから手を引く。
【ニッポンランナーズ】
2002年4月1日にとして千葉県佐倉市にNPO法人「ニッポンランナーズ」発足。
前身はリクルートランニングクラブ(RRC)。RRCは1986年の創部以来、日本陸上界を牽引していた。小出義雄氏を監督として迎え、五輪メダリスト有森裕子や高橋尚子を輩出。全日本実業団女子駅伝で優勝2回、13年最多連続出場の実績がある。
しかし、RRCが世界レベルを追求するようになってから、競技の専門家集団へ変貌しはじめる必要が出てき、ごく普通の社員と選手を同じ「社員」として扱う矛盾や、個人の目標よりも企業の方針を優先しなければならない矛盾が生まれてきた。
さらに、バブル崩壊後の企業内構造改革にて、RRCが会社の投資に見合っているのか?再検証が行われた(第1章②参照)。結果、企業スポーツとしての限界から2001年1月休部となる。
同じ企業スポーツという仕組みのままでは、ほかの会社に移っても同じ結果になる。今儲かっている業種でもそう長くは続かない。と、考えた前出の金哲彦氏は、新しいスポーツの形態として総合型地域スポーツクラブに行き着いたのだった。
現在、年会費・月会費を集め、アスリート/ランニング部門/バレーボール部門/土曜スポーツ探検隊/ステイヤング/ノンプログラム会員、という子供からトップ選手、中高年までが参加できるプログラムを持つスポーツクラブとなっている。
●NPO法人
ニッポンランナーズは総合型地域スポーツクラブとして活動するために、NPO(Non-Profit Oganization:民間非営利組織)法人という形態をとった。NPOとは、株式会社などの営利企業と違い利益を関係者に分配せず、社会貢献や特定の目的に沿って活動する人々に持たせる法人格を指す。
「非営利」とは「NPOの活動はお金をもらってはいけない」という意味ではなく、お金をもらって収益活動(ビジネス)をしてもよいが、残った利益を(たとえば株式会社の「配当」のように)構成員が分けてはいけない、次の活動のために使わなければならない、という意味である。つまり、目的が「非営利」、手段として利益が出るわけである。
この場合の目的とは、『アスリート・市民・子どもたちに対し「スポーツの指導・養成」「スポーツ活動の支援」「スポーツ大会の企画・運営」等の事業を行い、スポーツ振興と人々の豊かな暮らしや地域の活性化に寄与すること』となる(ニッポンランナーズ定款より)。
特徴
・儲かっても税金はほとんど払わなくてすむ。
・社会的信用が高まるはず。→まだNPOの社会的認知度が低いのだが・・・。
・有限会社や株式会社と違い、最低資本金の規定がない。
・法定設立費用がかからない。
・事業委託・補助金が受けやすい。
今後の課題[ビジネスの視点から]
・資本金が無いことによる、資金難。
・1000/2000人単位の会員維持。
・そのための競技/種目数増加。
・人(スタッフ)。
・その彼らに払う給料と給料システム。
・ソフト充実。(たとえば、ランニング教室では20人に1人のコーチがいないと成立しない)
ライバル
民間のスポーツクラブ。
ニッポンランナーズと会員を奪い合うライバルである。敵方は、素人にはもったいないほどの施設があり、心地よい音楽が流れ、暖かいシャワーに、冬でも入れるプールもある。ただ、専門的なコーチはいない。いるのはインストラクター。カッコいいのは横文字なだけで、きっと体育の成績が悪くはなかった普通の人。
一方、期待のニッポンランナーズ。企業撤退のため、粗末な施設すら持っていない。公共の施設で充分、と。ハコモノよりも、俺らはソフトで勝負するぞ。だてに、有森・高橋を育ててはいない。営利を追求しないから、生徒による先生の取り合いだってなりはしない。地域に根づけば、コミュニティーにもなりうる。ちっちゃい子から、老いに反抗する中高年まで仲間だから。
なんだか、暖かいではないか。熱いシャワーなら家で浴びよう。
このためにも、安定した会員数と、多くなくていいが決して少なすぎてはいけない資金が最重要課題 なのだ。
■企業主導地域支援型■
企業はチームを手放す。その後、全額出資の子会社としてスポーツクラブを設立する。
【堺ブレイザーズ】
2000年末に発足した、大阪の元新日鉄堺の男子バレーボールチーム。
歴史、クラブ化の経緯は第1章①に書いた。
現状を詳しく。
堺ブレイザーズとなってからのチームは、Vリーグで8チーム中、6位、5位、3位、6位と新日鐵堺時代の栄光にはまだまだ遠い。2003年ワールドカップバレーボール日本代表にも、センター伊藤信博 1人のみの輩出である。
また、新たにつくられたジュニア(中学生)チームは、通う中学校にバレーボール部がない人のみを対象とし、奈良県から参加する選手もいる。それも、堺ブレイザーズのシニア選手から指導を受けられ、同じユニフォームを着、スタッフとしてVリーグのトップレベルの試合を間近で見られるという総合スポーツクラブの特徴が、魅力となっているからと思われる。
・運営
ブレイザーズ設立の資本金1000万円、年間運営資金2億6千万円は、ひとまず新日鉄の広告費となっている。その後クラブと新日鉄が1/2づつ、さらに理想としては企業(新日鐵含め)・自治体・地域住民が1/3づつ負担する「1/3セオリー」へと移行したい考えだ。今後の収入としては、大阪府内の中小企業を中心として法人会員93社と、ファンなどの個人会員約2700人の会費収入約3500万円が考えられる(会費については先に述べた)。
またブレイザーズは堺市へも積極的に支援を求めている。ただ、行政が運営費を直接支援することは難しいため、「堺市運動部活動活性化推進事業」(200万円)や「広域交流事業:ふれあいママさんバレーボール教室」(300万円)を委託することで支援としている。
今後の資金策としては、国際試合やオープン戦を有料にする、Vリーグの試合をホーム&アウェイ方式(ホーム試合の収益還元)にするなどが考えられる。しかし、現在Vリーグの試合が大阪府立体育会館で多く開催されるため、地元民の観客動員が望めにくい問題があるため、Vリーグを巻き込んだ改革が必要となっている。
地域密着例としてあげられるのが、「ブレイザーズカップスポーツ大会」である。これは堺市スポーツ少年団との共催であり、バレーに限らない地域スポーツの発展に協力している。
企業主導型のためかそれとも大都市のせい(地元意識の希薄化など)なのか、地域色が出てこず「新日鉄のバレーチーム」としての認識が強い。また、クラブとして自立できるまでは新日鉄が費用を負担するため、上手くいかなかった場合に他の企業スポーツが廃部になったのと同じ状況になりかねない。
一見、弱気にも取れる
「500万でも1000万でもいいから、一緒にやってくれる別の会社が出てくるといいのだが」
という新日鉄・羽矢常務のコメントが、その危機感を如実に表している。
・流れ
堺ブレイザーズの「地域密着型総合スポーツクラブ構想」に呼応する形で、
新日鉄堺柔道部⇒「ブレイザーズ柔道クラブ」
WEST JAPAN ウィルチェアーラグビーチーム⇒「ブレイザーズウィルチェアーラグビーチーム」
と名前を変えた。
「柔道クラブ」はシニアだけでなくジュニア(小、中、高)も含めた活動になり、「ウィルチェアーラグビーチーム」はバレーボールチームと同じデザインのユニフォームを使用する。
が、前者は運営・会計が別の組織であり、後者は他のチームにユニフォームを支援するに過ぎない。構想だけでなく、組織として一つにまとまることが地域密着型総合スポーツクラブへの課題である。
※ウィルチェアーラグビー・・・四肢麻痺者の人が参加するチームスポーツで、1977年にカナダで考案され、2000年シドニーパラリンピックで正式種目になった競技。
■地域主導企業支援型■
企業は撤退するが、クラブのスポンサーとして支援しながら運営は地域。
【釜石シーウェイブス】
2001年4月25日に設立。元新日鐵釜石ラグビー部。
「新日鐵釜石の日本選手権7連覇こそは、神戸製鋼のそれとは無関係に、いつまでもラグビー史のページを重くする偉大な業績である。
1978年度から7シーズン。ラグビーとはすなわち『釜石』だった。」
(藤島大「ラグビー特別便」より)
当時、国立競技場で揺れた、東北の小さな港町の大漁旗はラグビーに欠かせなかった。東北・北海道の無名高校生をスカウトし鍛え上げ、そこに、松尾雄治ら数名の有名学生ラガーの加入。今ではやったことのないラガーはいない「タッチフット」。日本にまだ普及していなかった頃、既に採用されていた。のちにオールブラックス(NZ代表)が用いた練習法「グリッド」も、名前は付いてなかったがあった。
しかし、鉄の時代は終わる。長引く不況と長い低迷(2001年度から国内トップレベルの東日本社会人リーグから2部に降格)。新日鐵の運動部クラブ化計画に伴い、地域密着型スポーツクラブへの道を選ぶ。
・企業と市との融合
「釜石大槌スポーツタウン構想」。
釜石市は、以前から隣町の大槌町と共同で、スポーツによる町づくりを計画していた。
この計画の柱が、
①効率的な施設整備と市・町相互利用のための環境整備
②余暇活動の充実、健康増進、競技スポーツの向上
③住民意識の高揚、地域イメージの向上、情報発信
の3つである。
②の具体的な取り組みとして考えられていたのが、文部科学省が推奨する総合型地域スポーツクラブの整備であった。[釜石市ホームページより]
そこに、地元新日鐵釜石ラグビー部クラブ化の話。必然的に、行政・企業が一体となったクラブ作りが行われることになった。
現在の計画では、釜石シーウェイブスを中心にした広域地域スポーツクラブをつくる。ここに、社会人チームだけでなく中学生・高校生チームも起こし、さらにサッカー野球と広げる。これを、「親クラブ」として、その下に、釜石市6ヶ所・大槌町4ヶ所に中学校単位の小さな地域スポーツクラブを置く。行政として、スポーツ競技力の向上や競技組織への支援、指導者育成など行い、スポーツ合宿地として潜在能力を高める。アテネ五輪の最終合宿地を目指し、名実ともに「スポーツタウン」を目指す。
また「競技」としてだけでなく、新日鐵釜石健康センターを中心に老若男女がスポーツを用いた「健康」作りをできる態勢も整備する。
・現状
釜石市が新日鐵の企業城下町であり、ラグビーV7時代から地域密着度は高い。クラブ化したために、ラグビー協会の規定問題(クラブチームは東日本社会人リーグに参加できない)が発覚した。だが、市民は3日間で14,861人分の署名を集め嘆願書を協会に提出したため、規定が改正された。ちなみに、釜石の人口は約47,000人。2000人分の署名が、出発の朝、北上駅のホームにギリギリ間に合ったとのエピソードも残る。
クラブ化しても選手の多くは新日鐵釜石主体だが、社外からも7名加わりチームを構成している。人件費は選手が所属する企業が負担し、運営費は法人会員200団体、個人会員3300人の会費、2350万円が主。だが赤字分の運営費は、新日鐵が負担している。
ブレイザーズと同じく「1/3セオリー」が理想であり、お金の自立が最優先課題だ。
釜石市の資金援助は、一法人サポーターとしての40000円/年のみ。だが、そのほかに、試合などで使用する釜石市陸上競技場は、新日鐵のものだが、市へ無償貸与され管理も市へ委託している。さらに、この競技場への固定資産税は減免されている。また、文部科学省推奨のモデル事業への申請が通れば、1300万円/年の補助を受けることができ、成功への大きなチャンスと考えられる。
ただ、堺の場合と違い、法人格の無い「官民共同運営(任意団体組織)」として活動しているのだが、経営を確立するためにも(社会的信用、資金借入、契約など)適切な法人格が必要と考えられている。それについては、第3章で詳しく書く。
・サポーター制度
- 個人ゴールドサポーター・・・・2000円/年
- 個人クリスタルサポーター・・・4000円以上/年
- 法人サポーター・・・・・・・・・・・40000円以上/年
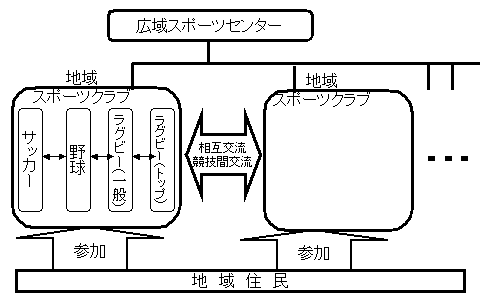
[釜石市ホームページより]
▲ index ▲
②「元企業」以外の試み
●政府主導型●
続いて、釜石シーウェイブスの説明でも出てきた文部科学省推奨のスポーツクラブについて見てみる。
文部科学省が2000年9月に発表した「スポーツ振興基本計画」内で「総合型地域スポーツクラブ」が触れられている。この計画の詳細は文部科学省ホームページに譲るが、これによると、
日本は
「年間労働時間の短縮や学校週5日制の実施などによる自由時間の増大、仕事中心から生活重視への国民意識の変化などにより、主体的に自由時間を活用し、精神的に豊かなライフスタイルを構築したいという要望が年々強まっている」らしい。
さらに、高齢化/日常生活での運動機会減少による体力低下/国民の期待が大の国際競技力の相対的低下/を、スポーツの振興をもって食い止め、「21世紀における明るく豊かで活力ある社会」を目指すねらいである。
3大方策として
①生涯スポーツ社会の実現に向けた、地域におけるスポーツ環境の整備充実方策
②我が国の国際競技力の総合的な向上方策
③生涯スポーツ及び競技スポーツと学校体育・スポーツとの連携を推進するための方策
を挙げている。
この①③の重要な政策として、「総合型地域スポーツクラブ」の全国展開を掲げているのだ。
・2010年までに、全国の各市町村においてすくなくとも1つは総合型地域スポーツクラブを育成する
・2010年までに、各都道府県においてすくなくとも1つは広域スポーツセンターを育成する
以上の目標を設定し、結果、誰でが、いつでも、どこでも、いつまでも、各自の興味目的に応じてスポーツに取り組める環境作りを目指す。
総合型地域スポーツクラブの特徴を次のように定めている。
①複数の種目。
②子供から高齢者まで、初心者からトップレベルまで、いつでも活動できる。
③スポーツ施設/クラブハウスがあり、定期的継続的活動ができる。
④質の高い指導者のもと、個々のニーズにあった指導が行われる。
⑤地域住民が主体的に運営する。
また、「広域スポーツセンター」とは、総合型地域スポーツクラブの、創設・育成に関する支援/クラブマネジャーや指導者の育成支援や、広域の市町村圏での、スポーツ情報の整備提供/交流大会の開催/トップレベル競技者育成支援や、スポーツ医学・科学面からの支援、の機能を持ったものをいう。
企業スポーツや大学(後で、大学の試みを紹介する)に対する施策を入っている。
「施設、人材等の面でスポーツに関する豊富な資源を有している大学等の高等教育機関においては、学生のスポーツ活動の充実はもとより、地域の一員として地域スポーツ振興に積極的に関わり、総合型地域スポーツクラブの育成に参画することが期待される。プロスポーツ組織や企業においては、大学等と同様に地域の一員として総合型地域スポーツクラブの育成に参画するなど、地域の実態に即した形での貢献を行うことが期待される。」
これより前、1995年には文部省(当時)の補助事業として、総合型地域スポーツクラブ育成モデル事業がスタートしている。これに通れば、毎年1300万円が3年間補助される。希望する地方自治体が事業計画を作り、各都道府県教委を通じて申請し、事業規模に応じて、国が三年間半額を補助する。2001年度までに全国115箇所がモデル事業となり設立されている。
この補助金の財源は、
『スポーツ振興くじtoto』があてられ、平成15年度は総合型地域スポーツクラブの活動助成として、385件 約6億3700万円の交付を行っている。( totoの収益は、地方公共団体又はスポーツ団体が行うスポーツ振興事業のための助成(2/3)と国庫納付(1/3)に充当することとなっている。)
さらに文部科学省以外にも、兵庫県では、2005年までに県内全ての小学校区に総合型地域スポーツクラブを作る方針である。1箇所につき1300万円の補助をする事としている。
●Jリーグの場合●
Jリーグはその設立当初より「百年構想」という理念を掲げてきた。
それは、30年50年100年後に向けた、ヨーロッパのようにスポーツが生活の一部となっている「スポーツ文化の確立」である。(サッカー文化の、では無いのだ!!)
そのため、欧州的「地域に根差した総合スポーツクラブ」を目標に、サッカーという競技を通じてさまざまな取り組みを行っているのだ。
参加チームには、下部組織の設置が必須事項となっている。ユース(16~18歳)、ジュニアユース(13~15歳)、ジュニア(8~12歳)のチームを保有し、それらの組織をホームタウンを中心に展開しているスクール・指導者派遣事業が支えている。この組織構造は選手育成・強化の側面だけでなく、地域へのサッカーの普及・振興という役割も持っているのだ。
Jリーグといえばサッカーであるが、先の理念を掲げた以上いつまでも単一種目クラブのままでもいけない。事実、Jリーグは各チームがサッカー以外の地域イベントや○○教室などに対しても、開催資金の援助を行っている。1997年に始まり2000年3月までの間で、17クラブ・57事業が援助を受けており、理念(地域に対するスポーツの振興)が着実に実行されている。
1999年の地域スポーツ振興支援対象イベントの一部
| 種目 |
主催クラブ | 内容 |
| 障害者サッカー |
ヴィッセル神戸
ベルマーレ平塚 | 障害者サッカー大会
電動車椅子サッカー大会 |
| ソフトテニス |
ベガルタ仙台 | ママさんソフトテニス教室 |
| テニス |
鹿島アントラーズ | テニスクリニック |
| バスケットボール |
ベガルタ仙台 | 高校バスケットボール教室 |
| ミニバスケ |
ジェフ市原
etc… | ミニバス ジェフカップ |
| バトミントン |
大宮アルディージャ
etc… | スポーツクリニックバトミントン教室 |
| フットサル |
京都パープルサンガ
他多数… | パープルサンガ杯 |
| マラソン |
ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田メモリアルマラソン |
| 駅伝 |
モンテディオ山形 | スポーツ山形21駅伝事業 |
| 柔道 |
鹿島アントラーズ | JODO FESTA |
| 野球 |
大宮アルディージャ | スポーツクリニック野球教室 |
[クラブネッツホームページ内「プロスポーツクラブによる地域スポーツクラブづくり」より作成]
また、「地域に根差した総合スポーツクラブ」への一歩と成りうる、こういう事例もあった。
2000年、「新潟アルビレックス」というバスケットボールチームが誕生した。大和證券男子バスケットボール部の廃部を機に、Jリーグ所属クラブ「アルビレックス新潟」とチーム名を共有し、バスケットボールの普及と地域スポーツ振興を目的とした地域のプロスポーツチームへの転身した。経営母体は別々であるが、新潟に「アルビレックス」の名を持つクラブがいくつも誕生し新潟のスポーツの普及と発展に協力して取り組む。それも一種の総合型地域スポーツクラブではないだろうか。
[「プロスポーツクラブによる地域スポーツクラブづくり」より]
●ワセダクラブ●
大学と地域が結びつくスポーツクラブ形態。
2003年9月、早稲田大学ラグビー部が主体となった地域密着のスポーツクラブが設立された。
2002年9月よりラグビー部が天然芝グランドを使い始めたことがきっかけとなった。せっかくの天然芝グランドを有効に使う可能性として”スポーツクラブ”が考えられ、結果スポーツ振興目的のNPO法人をつくり、青少年の育成・地域との交流を行っていく。大きくは、ラグビー人気の復活/日本スポーツの発展まで視野に入っている。
現在はラグビー部がモデルクラブとして一歩進んだ状況だが、アメフト部・サッカー部・ボート部もこのクラブに参加中。
「芝生のグラウンドでお兄ちゃんたちがいっしょにあそんで、教えてくれるというのがワセダクラブの基本」(ワセダクラブ専務理事 清宮克幸氏)
また、上記の理念とは別の重要意味も存在した。
大学スポーツの衰退は著しい。問題はスポーツ強化に欠かせない資金が集めにくくなっていること。早稲田大学佐藤英善教授は「体育会に43部があるが、運営予算の7割か8割は大学OBの寄付に頼っている」と話す。少子化で大学経営自体が苦しい。大学スポーツが自立できる運営の新しい手法が必要だ。
NPO法人のワセダクラブは、スポーツ指導者を雇用し、地域住民の指導に当たる傍ら、大学の運動部を教えるというもの。スポンサー企業などが資金を提供する。企業は宣伝に利用する。大学は当面の運営資金として2800万円を融資しているが、軌道に乗れば大学が人件費を負担することなく指導者に報酬を払うことができる。
(2003年11月23日付、日本経済新聞より)
つまり、スポーツ界・大学経営、二つの側面から必要とされたものである。スポンサー企業は、朝日新聞・アディダス・サントリー・三井住友VISAカード・日本公文教育研究会・三共など8社が集まった。運営資金は、上記の2800万円に加えスポンサーの年会費500万円×8とクラブ会員の会費が当てられる。
[クラブのチーム分け(ラグビーの場合)]
- 早稲田大学ラグビー蹴球部―関東大学ラグビー対抗戦1部所属
- ワセダクラブ シニアチーム―関東社会人連盟4部リーグ所属
- ラグビースクール―Category1~Category5 (幼児~中学生)。スクールはサッカー部も実施している。
[サポーターズクラブ]
早稲田大学のスポーツ振興事業をサポートするための組織となり、会費は、ワセダクラブが運営する各種スポーツのスクールや成人チームの運営に充てられるほか、大学スポーツの振興のために役立てられる。
| 区分 |
会費/年 | サービス内容 | 備考 |
| 一般 |
\5,000 |
会員限定オリジナルグッズの提供、
ワセダクラブホームページ有料コンテンツの無料閲覧、
定期会報の配布、
ワセダクラブ参画早大体育各部現役部員との交流イベントへの参加など。 |
個人 |
| スポンサー |
1口
\25,000
(1口以上) |
一般会員の特典プラス、
ワセダクラブホームページ上でのPR機会の提供、
その他ワセダクラブメンバーに対するマーケティング機会の創出 |
個人/団体 |
[ワセダクラブホームページより作成]
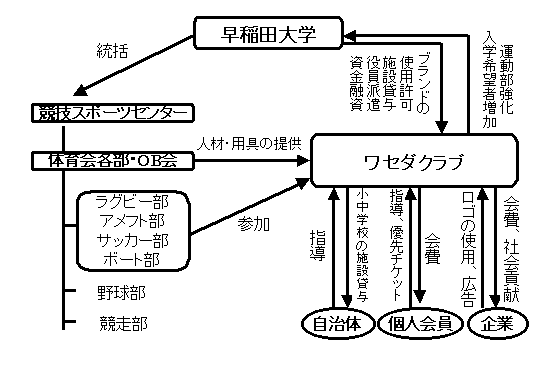
また、前出の日本経済新聞によると、ワセダクラブ以外にも「(国立)大学によるクラブ」の設立の動きがある。
・東京学芸大学―「学芸大クラブ(仮称)」
近くに練習場を持つFC東京(Jリーグ)と組みサッカースクールなどを運営する。
・筑波大学―「つくばユナイテッド」
各運動部が別々に開いていた地域向けのスポーツ教室などを一括管理する学内組織。
・鹿屋体育大学―総合地域スポーツクラブを計画中。
国内最高水準のスポーツ施設を持つ強みを生かす。
国立大学は地域貢献という側面が色濃い。法人化を控える国立大学は安定した資金を確保するために地域社会への貢献を迫られ、大学スポーツを生き残りの手段として活用しているのだ。(同新聞より)
●ヨーロッパのスポーツクラブ●
何度か書いてきたように、「企業スポーツ」というシステムは日本独自のものである(韓国、台湾にも存在する)。逆に「地域型スポーツクラブ」は欧州のものである。欧州で生まれたスポーツは当初、当り前だが市民の間で行われた。やがて、地域のスポーツ好きが自然に集まり、グループを形成した。これが、地域にあるスポーツクラブの原型である。
では、日本は。
そもそも日本にスポーツは存在しなかった(相撲と、柔道剣道などの武道のみ)。明治維新後、欧米文化流入とともにスポーツも伝えられた。それ以来、日本はスポーツを「富国強兵」「殖産興業」という目的のため利用し、「体育」という名称で国民に行わせたわけである。つまり、下(市民)から生まれたスポーツと上(国)がやらせた政策の一つと全く違うものなのだ。このように歴史・文化といった成長過程が全く違うため、欧州の完全模倣は難しいとも考えられる。
このような明治のスポ―ツ観は、
「(スポーツは、)練習万般一に武士的素養を持つ(練習のすべてに武士を育てるような要素がある)」
(玉木正之「スポーツ解体新書」)
に表れている。
欧米の”元祖”スポーツクラブのほとんどが地域社会に属し、誰もがスポーツを楽しむことができる。だが、稀なケースとして「企業城下町」にあるスポーツクラブが、その企業名を冠していることがある。ただ、表面上は日本と似ていても中身は全く違う。企業名が付いていようが、スポーツクラブは地域社会のものであり、その地域住民ならば誰でも参加、利用できるのである。
ここでは、日本の「企業スポーツ」とどう違うのか、どのように企業とスポーツと地域が結びついているのか、見ていきたいと思う。
【TSVバイエル04レバークーゼン】
ドイツ西部のレバークーゼン市(人口約16万人)にある、バイエル社が設立したスポーツクラブ(会員1万人)である。現在14の競技部門を運営しているが、中でもドイツプロサッカーリーグ(ブンデスリーガ)1部に所属している「バイエル04レバークーゼン」が有名である。また、これまでに金メダリストを9人も輩出し、パラリンピックでも多くのメダリストを生み出している。
(注):ブンデスリーガもJリーグと同じく、チーム名に企業名を入れることが禁止されているのだが、このクラブに限って市への貢献が認められ企業名を入れることが認められている。
◆TSVバイエル04レバークーゼンの14種目◆
| サッカー |
陸上競技 | バスケットボール |
| 障害者スポーツ |
ボクシング | ハンドボール |
| バレーボール |
氷上スポーツ | フェンシング |
| 体操競技 |
柔道 | 児童及び青少年スポーツ |
| レクリエーションスポーツと大衆スポーツ |
ファウスト・バル(ドイツ独自の球技) |
・歴史
1904年 バイエル社の前身の従業員の署名により従業員のための体操スポーツクラブが設立される。
1928年 サッカー、ハンドボールなど5競技からなるクラブが新たに誕生する。
1950年 後者のクラブに障害者部門が設立され、一般地域住民も受け入れはじめる。
1984年 二つのクラブが合併し、「社団法人 TSVバイエル04レバークーゼン」になる。
1999年 プロサッカー部門が独立、「バイエル04レバークーゼンサッカー有限会社」として独立する。
・クラブの現状
文字通り、老若男女はもちろん、障害者からトップアスリートが共存する総合型地域スポーツクラブである。同じくドイツにある、巨大クラブ「バイエルンミュンヘン」が、トップチームのチケット優先権目当ての会員が多いのに比べ、自らスポーツを楽しむ会員が多いのが特徴とされている。
クラブは社団法人となっているが、約200名のプロ契約選手がいるため(最高給はプロバスケの数億円)、経営者もプロとしてバイエル社から出向している。会員は、約3600円の入会金プラス、会費約1300円/月(子供は780円)を払う。3000円の家族会員制度も存在する。また、会員はクラブ運営などに関わる議決権1票を持っている。会員を教えるコーチ陣として、プロ20名、アマチュア400名が在籍し、彼らはすべてライセンス保持者であるためサービスは悪くない。また各スポーツ協会からライセンス者数に応じて、クラブへ助成金がでることになっている。
バイエル社は、イベントの企画支援やクラブ広報、プロ契約スカウティングなどのマネジメント支援を行っている。さらに、クラブ内14競技の各会長はバイエル社社員である必要があり、自社の政策にあったクラブ運営をコントロールできるようになっている。
レバークーゼン市との関係。市の人口1/4がバイエル従業員であり、クラブ・バイエル社と市の依存度はきわめて高い。不景気のため、市が得る法人税が激減。そのため、スポーツセクションを民間団体へ移したり、市所有のスポーツ施設をクラブへ無償で貸し出す代わりに、管理費をクラブに持ってもらっている。その結果、管理経費は6000万円→1800万円へ減らすことに成功している。
・方向性/課題
まず第一に、市民のスポーツニーズの把握と、それに呼応した部門統廃合だ。特に最近の傾向は、健康志向のニーズである。また、バイエル社のスポーツ支援は、プロフェッショナルスポーツ支援への比重が大きくなってきている。そのために、ドイツ全国から優秀な選手を集めなければならず、地元レバークーゼン出身選手のプロ契約を奪ってしまうなど、地域との関係が弱まってしまう可能性が考えられている。
[スポーツシューレを考える会「ドイツ視察報告書」より]
▲ index ▲
□第3章 これからのクラブスポーツはこれだ!□
この章では、これまで見てきた例を参考に「企業スポーツのクラブ化」「脱企業スポーツ」が成功する条件を考察する。
◆
まず、クラブの継続的安定には、企業の場合に言われるのと同様に「ヒト」「モノ」「カネ」の充実は欠かせない。
「モノ」。
スポーツを行うにあたって、「モノ」が無いと始まらない。グラウンド、体育館、施設やクラブハウスなどである。自クラブで保有していなくとも、ドイツの例のように公共施設を借りられるの場合もある。ただ、日本に公共スポーツ施設が多くない。文部科学省曰く、「2010年までに、全国の各市町村においてすくなくとも1つは総合型地域スポーツクラブを育成する」である。そんなに沢山も公共施設はない。また前出の金氏が言うように、これから「ビジネスとして成り立た」せなければならない時、公共施設では客(地域住民)に対して弱い。
だから、企業スポーツ時代の「モノ」を使わない手はない。かつては、日本トップレベルの選手が使用していた施設である。ワセダクラブのように、せっかくの芝クランドを有効活用したいという目的でもいい。むしろ、それらを使わないことは「社会的損失」であるとも考えられるのだ。
結果、「脱企業スポーツ」と言っても、企業が完全に手を引く・企業から完全独立するということは難しい。クラブの母体として、所属すべきである。
また公共施設以外に使うモノがない場合。ドイツの例のように、地域に対する貢献事業と引き換えにして、施設の優先利用を認めることが望ましい。
次に「カネ」。
「企業スポーツのクラブ化」した例では、どこもお金には困っている。「トップレベルの競技力を維持するために、人件費含め3~5億円かかるといわれている」(現代スポーツ評論より)。地域(県、市、住民)だけでは到底無理だし、一企業だけでも同じことである。だが、それそれ負担を軽くしながら地域みんなでクラブを持つことならできるのではないか。
つまり、地域企業(もちろん1社ではなく)に、会員となる地域住民、行政(国・県・市区町村)の助成、競技団体の支援(資金不足の団体が多いのだが、Jリーグのようにイベント開催ごとの支援でもよい)である。もちろん、お金を出してくれる企業に対しては「メリット」を明確に示す必要があるのも事実だ。これが最も重要かも知れぬが。株主に説明できるメリットはクラブ側の運営・マネージメント能力にかかっているとも言える。
JOC(日本オリンピック委員会)の竹田恒和会長はこう言っている。
「企業には社会貢献の一環として支援してもらう形が必要だ。また、企業からの資金については、政府に免税措置を働きかけて、支援しやすい方法を考えていきたい」
(2003年12月6日付、読売新聞より)
しかし、「社会貢献」だけで出してくれるのなら、ここまで企業スポーツは潰れていない。自分たちの努力があって初めて資金援助をお願いするべきであって、フワフワの椅子の上でふんぞり返っていてはいけないのだ。
そして「ヒト」。
指導者の質は言うまでも無い。トップレベルの企業スポーツを指導していたコーチ陣にとって、子供お年寄り相手に技術不足は心配ない。ここで重要となるのは、コーチではないのだ。
「カネ」で述べたように、資金集め等ビジネスとしての“クラブ運営”をしなければならず、企業に訴えるようなソフト/地域住民を惹きつけるソフトを作ることのできる人材・ゼネラルマネージャーが必要だ。最近、この人材を育てるための試みが、行われた。「スポーツ・ゼネラルマネジャー講座~スポーツの経営・運営人材養成~」が、(財)大崎企業スポーツ事業研究助成財団・(財)日本オリンピック委員会の共催、文部科学省・(財)日本体育協会の後援で行われたのだ(03・9~04・1)。今後への危機感が、形になりはじめたといえる。
これら3つの条件に加えて、重要になるのが「組織形態」である。
今後、クラブが自立していくためには、社会的信用力、資金の借入、契約などの問題から、適当な法人格が必要であるのは間違いない。実際は、有料試合やグッズ販売の利益が欲しいから株式会社、短期間で設立したいから有限会社、資本金がないからNPO法人、などの理由で、その組織形態はバラバラである。「官民共同運営(任意団体組織)」の釜石シーウェイブス、「株式会社」の堺ブレーブス、「有限会社」の日光アイスバックス、「NPO法人」のニッポンランナーズ・ワセダクラブ、etc.
だが、最善の形態を考えるならばこうである。
①運営組織を株式会社にし、地域住民や青少年を対象とするなど公益的な部門を分離しNPO法人にする。
もしくは、
②運営組織をNPO法人にし、グッズ販売など収益を見込む部門を分離し会社形態にする。
である。(文部科学省HPより)
こうすることで、NPOと会社と、良いところを利用することができるのだ。資金不足の問題など、多少緩和するはずである。
そして、「地域との密着」である。上記の「ヒト」「モノ」「カネ」は地域との関係があってこそ成り立つからだ。
クラブは地域に受け入れられ、知名度が高い必要がある。そのためには地域貢献事業が欠かせない。スポーツ教室、コーチの派遣、施設開放など、地域に貢献することで地域の理解を得ることができる。また、そうすることで、スポンサー・ファンクラブ会員・自治体からの支援が得やすくなるのだ。
自治体の姿勢も大切だ。釜石の例のように、自治体がクラブへの支持を明確にすることで「地域のシンボル」として受け入れられるのだ。
忘れられがちだが重要なのは、各競技団体の協力である。
ブレイザーズで書いた、オープン戦の有料化やリーグ戦のホーム&アウェイ化は、クラブを潤わせる。シーウェイブスは協会の規定が改正されなければ、社会人大会に参加できなくなっていた。レバークゼンでは、在籍しているコーチのライセンス取得者数に応じて、各協会からクラブへ助成金が出る。
クラブを支援することが、後々の競技人口の安定につながるはずなのだ。
▲ index ▲
□第4章 まとめ□
明治時代、文明開化によって欧米のスポーツに出遭った。その後「富国強兵・殖産興業」や武術の影響から、本来の「スポーツ=遊び」ではなく、身体鍛錬・精神修養に利用された。それは全国の学校を通じて「体育」として広められた(上から下へ与えられた)。体育は教育の一環であるため、「強制」を伴った。スポーツ=学校で行うものだった。学校卒業後もスポーツしたい人は、企業の下でやらせてもらった。これが「企業スポーツ」になった。そして、競技力が上がり、スポーツに力を入れることは企業のイメージ戦略になった。その後、世間はバブルになり、崩壊した。
確かに、明治的思想によって、世界における日本の競技力が上がったことも事実である。だが、明治という時代にスポーツが伝えられた時点で、「スポーツ」が「スポーツ」として伝わらなかった時点で、企業スポーツ崩壊は運命付けられていたのだ。市民の自発的行動から生まれたものを、市民はやらされた。
無意識に「自然ではないもの」に作り変えられ、それは自然社会に適応せず、とうとう崩れはじめた。それと同時に、少しずつ本来の「スポーツを楽しむ」意識が生まれてきたのである。それを可能にするのが、このクラブ化だった。
すでに、クラブスポーツへの流れは始まった。いまさら、古き良き企業スポーツへ、と過去には戻らない。戻れない。完全に欧州と同じ形、は無理かもしれない。スポーツを企業が利用する、スポーツが企業を利用する、ことに異論はない。だが、スポーツを独立したモノとして見ることは譲れない。企業の下にあるスポーツは絶対おかしいのだ。
ただ、現状は厳しい。
スポーツプロデューサーの杉山茂氏は言う。
「文部科学省の推進する『総合型地域スポーツクラブ』が、2003年も、たくましい姿を見せないで過ぎた。図面のまま立たないビルのようだ。特に、競技団体が、どこまで関心を抱いているのかとなると、私の見聞する限り、かなり低いレベルだ。」
[スポーツデザイン研究所HPより]
そう、「図面」はあるのだ。
では何故、ビルは立たないのか?第3章で書いたように、図面において競技団体の協力は不可欠である。が、それにも増して大切なのが、「情熱」であり「思い」なのだ。古今東西、それがひとの行動を誘ってきた。藤島大氏の著書「知と熱」(文藝春秋)によれば、物事を成し遂げる際、「知」と「熱」の融合は欠かせない。知と熱とは、科学と非科学、合理と非合理とも書きかえられた。もちろん、知は図面を指す。あとは熱。ブレイザーズの小田氏然り、ニッポンランナーズの金氏然り、ワセダクラブの清宮氏然り、Jリーグの川渕氏然り。これら全て、彼らの(情)熱が日本にクラブ化をもたらした、のは間違いない。
それに続く、市民発の「スポーツしたい」という熱が必要なのである。
市民発の熱がないままでは、明治時代と変わらない。上から提供されるだけの「スポーツ」でしかないからだ。
研究冒頭、故・大西鐵之祐氏の言葉は、もしかしたら明治の思想を含んでいるかもしれない。だが、スポーツをプレーする最中においては今も昔も変わらないはずである。
▲ index ▲
|