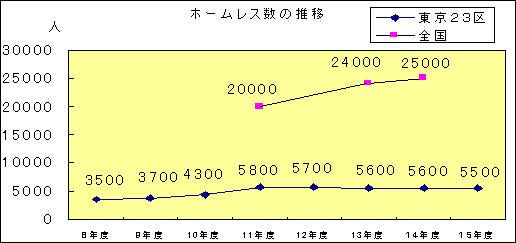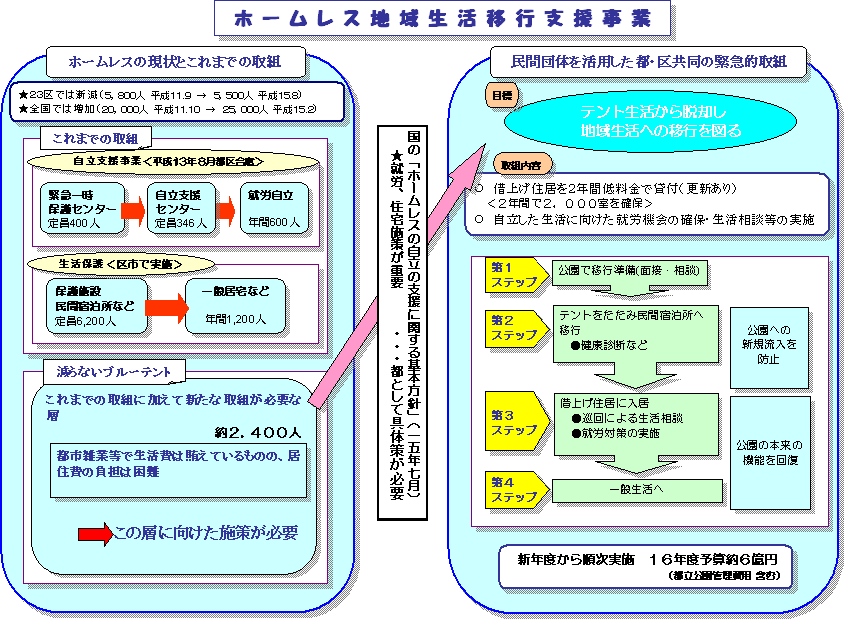|
|
|
 |
|
|
|
|
上沼ゼミ個人研究
早稲田大学社会科学部5年 熊沢 理
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
研究テーマ:ホームレス自立支援政策
ケース:行政サポートとNPOサポート、その有効性と問題点
研究動機:
私がアルバイトをしている原宿では多くのホームレスの人々が生活をしている。その光景は街の景観の一部分のように思えるほど当たり前の存在となっている。
当然、彼らも生きるための生活をしていかねばならず、私の働くコンビニエンスストアも利用する。私の勤務時間は主に早朝から昼の時間帯なので、客の殆どは通勤客なのだが、時間に追われるサラリーマンとホームレスがレジの前に一緒に並んでいるのはなんとも不思議な光景だ。彼らが主に買っていくものは、酒とタバコである。殆どそれのみといってもいいくらいだ。私がホームレスに興味を持った始まりは、朝から酒とタバコを買うことに違和感を覚えたことからだった。
私の興味は朝から酒を飲む彼らはどのようにしてそのような生活になっていったのか?どうやって生活しているのか?今後はどうするつもりなのか?といった疑問に発展し研究対象とすることにしたのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
|
|
| |
ホームレスの定義・概要
行政の自立支援政策
NPOを中心とした自立支援策
行政・NPO支援の総合比較
諸外国のホームレス事情と対策
政策提言
|
|
| |
|
|
第一章 ホームレスの定義・概要
ホームレスの定義
現在、我が国に明確に定義されているところのホームレスとは、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(平成14年施行)の第2条に記されている「ホームレスとは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいるものをいう。」とされている。
この定義は、国が「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(以下ホームレス自立支援法とする)を作成し、施行する為の定義である。
まず、ここで使われている「ホームレス」という言葉に着目してみたい。
この「ホームレス」という言葉はもちろん英語であり、正確には"the homeless"となる。日本ではこの言葉をかつて「野宿生活者」もしくは「浮浪者」と呼ばれていた人々に新しい統一名称としてあてがったのである。欧米でhomeless peopleといえば、屋外で寝ている人のほかに、シェルターや福祉ホテルに泊まっていて、自分固有の住居を持たない人も含む概念である。
しかし、日本ではホームレスといえば、野宿生活者のみを指し、簡易宿泊所やサウナ、ビジネスホテルに泊まっていたり、会社の寮や建設現場の飯場に入っている自分固有の住居を持たず、たやすくホームレスになりそうな人々は含んでいない。
政府がこの言葉を採用するに至ったいきさつを追ってみると、1990年代のバブル崩壊からの長期不況により野宿生活者が顕著に増加し、大都市のみならずあらゆる自治体で野宿生活者が現れ増加するという事態を受けて、1999年、政府がこの問題に取り組む為に「ホームレス問題連絡会議」という名称の機関を設置し、この時点で初めて国レベルでホームレスという言葉が採用されることとなった。
このことにより、マスコミなどでも「ホームレス」は使用され、世間でも多用されることとなった。
当初、「ホームレス」という語を使うことに抵抗を感じる意見も多数表明された。「ホームレス」は、街頭で恒常的に野宿生活をしている人を差別的に呼ぶ時の呼称である「浮浪者」を英語に言い換えただけである、というものである。
野宿生活者がこれだけ急増するのは、社会・経済的構造上の問題が背景にあって起こってきているからであるのに、「ホームレス」という語を使うことにより、そのことが隠されてしまい、「怠けているから野宿になるのだ」という偏見が蔓延してしまうことを危惧したからだ。
「ホームレス」という言葉に問題があるのではなく、この問題が背景を含めて社会に正しく理解されていくかが「ホームレス」を定義する上で忘れてはならない重要な要素である。
次に、現在のホームレスの概要を示したい。
ホームレスの概要
ここでは、厚生労働省がホームレス自立支援法のもとに行った全国調査の結果から現在のホームレスの概数・状況を見ていただきたい。
平成15年1月から2月にかけて、すべての市町村を対象に統一した調査方法による全国調査(以下「ホームレス実態調査」という)を初めて実施したところ、以下のような結果であった。
都道府県別のホームレスの数(平成15年)
|
都道府県名 |
男 |
女 |
不明 |
合計 |
|
北海道 |
112 |
7 |
23 |
142 |
|
青森県 |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
岩手県 |
16 |
2 |
0 |
18 |
|
宮城県 |
208 |
11 |
3 |
222 |
|
秋田県 |
13 |
0 |
0 |
13 |
|
山形県 |
20 |
3 |
1 |
24 |
|
福島県 |
39 |
0 |
4 |
43 |
|
茨城県 |
115 |
12 |
3 |
130 |
|
栃木県 |
126 |
5 |
3 |
134 |
|
群馬県 |
81 |
3 |
3 |
87 |
|
埼玉県 |
735 |
25 |
69 |
829 |
|
千葉県 |
610 |
25 |
33 |
668 |
|
東京都 |
6,174 |
187 |
0 |
6,361 |
|
神奈川県 |
1,782 |
37 |
109 |
1,928 |
|
新潟県 |
70 |
4 |
0 |
74 |
|
富山県 |
22 |
1 |
1 |
24 |
|
石川県 |
22 |
0 |
0 |
22 |
|
福井県 |
24 |
0 |
0 |
24 |
|
山梨県 |
46 |
0 |
5 |
51 |
|
長野県 |
35 |
1 |
1 |
37 |
|
岐阜県 |
59 |
5 |
22 |
86 |
|
静岡県 |
393 |
33 |
39 |
465 |
|
愛知県 |
1,984 |
78 |
59 |
2,121 |
|
三重県 |
39 |
7 |
0 |
46 |
|
滋賀県 |
57 |
0 |
0 |
57 |
|
京都府 |
580 |
20 |
60 |
660 |
|
大阪府 |
4,565 |
104 |
3,088 |
7,757 |
|
兵庫県 |
716 |
34 |
197 |
947 |
|
奈良県 |
14 |
0 |
0 |
14 |
|
和歌山県 |
80 |
9 |
1 |
90 |
|
鳥取県 |
12 |
1 |
0 |
13 |
|
島根県 |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
岡山県 |
58 |
3 |
4 |
65 |
|
広島県 |
221 |
10 |
0 |
231 |
|
山口県 |
30 |
2 |
1 |
33 |
|
徳島県 |
14 |
0 |
0 |
14 |
|
香川県 |
42 |
4 |
0 |
46 |
|
愛媛県 |
36 |
5 |
44 |
85 |
|
高知県 |
22 |
1 |
0 |
23 |
|
福岡県 |
1,024 |
81 |
82 |
1,187 |
|
佐賀県 |
38 |
3 |
0 |
41 |
|
長崎県 |
41 |
0 |
0 |
41 |
|
熊本県 |
115 |
9 |
0 |
124 |
|
大分県 |
34 |
5 |
0 |
39 |
|
宮崎県 |
16 |
2 |
4 |
22 |
|
鹿児島県 |
71 |
3 |
6 |
80 |
|
沖縄県 |
130 |
7 |
21 |
158 |
|
合計 |
20,661 |
749 |
3,886 |
25,296 |
|
割合 |
81.7% |
3.0% |
15.4% |
100.0% |
(1)ホームレスの数
ホームレスの数については巡回による目視により確認したところ、ホームレスが確認された都道府県は581市町村で、その数は25,296人となっている。
また、都道府県別に見ると、大阪府(7,757人)や東京都(6,361人)が多く、数のばらつきはあるものの全ての都道府県でホームレスが確認された。
さらに、市町村別では、ホームレスが確認された581市町村のうち、500人以上の市町村が9ヶ所、100人以上の市町村が41ヶ所であるのに対し、10人未満の市町村が391ヶ所と7割弱を占めている。
(2)ホームレスの生活実態
ホームレスの生活実態については、ホームレスの数が比較的多いと考えられる地方公共団体において、全体で約2,000名を対象に個別面接調査が行われた。
①年齢
ホームレスの年齢分布については、50歳から64歳までが全体の65,7%を占め、全体の平均年齢は55,9歳となっており、中高年層が大半を占めている。
②野宿生活の状況
野宿生活の実態としては、生活の場所が定まっている者が84,1%であり、このうち生活場所としては「公園」が48,9%、「河川敷」が17,5%となっている。
また、ホームレスとなってからの期間は「1年未満」が30,7%となっている。
さらに、仕事と収入の状況としては、ホームレスの64,7%が仕事をし、その仕事内容の内訳は、「廃品回収」が73,3%を占めており、平均的な収入月額は「1万円以上3万円未満」が35,2%と最も多い。
③野宿生活までのいきさつ
野宿生活までの直前の職業としては、建設業関係の仕事が55,2%、製造業関係の仕事が10,5%を占めており、雇用形態は、「常勤職員・従業員(正社員)」が38,9%と大きな割合を占め、「日雇」はほぼ同程度の36,1%となっている。
また、野宿生活に至った理由としては、「仕事が減った」が35,6%、「倒産・失業」が32,9%、「病気・怪我・高齢のため仕事が出来なくなった」が18,8%となっている。
④健康状態と福祉制度等の利用状況
現在の健康状態については、身体の不調を訴えている者が47,4%であり、このうち治療を受けていない者が68,4%となっている。
また、福祉制度等の利用状況としては、これまでに福祉事務所へ相談に行ったことのある者が33,1%、緊急的な一時宿泊所であるホームレス緊急一時宿泊施設(以下「シェルター」という)の利用を希望する者が38,7%、ホームレス自立支援施設(以下「自立支援センター」という)の利用を希望する者が38,9%、これまでに生活保護を受給したことのある者が24,5%となっている。
⑤自立について
自立に向けた今後の希望としては、きちんと就職をして働きたいという者が49,7%であるのに対し、「今のままでいい」という者も13,1%となっている。
⑥生活歴
家族との連絡状況については、「結婚していた者」が53,4%を占めているが、一方で、「この一年間に家族・親族との連絡が途絶えている者」が77,1%となっている。
⑦行政への要望・意見
行政への要望と意見としては、仕事関連のものが27,1%と多くを占めており、以下、住居関連が7,8%、健康関連が3,8%となっている。
以上の厚生労働省が行った調査の概要をまとめると、ホームレス問題は、その時代における社会問題が複合的に絡み合って生じてきている問題であり、主に①仕事の問題(会社の倒産等による失業や日雇・住み込みなどにかかる仕事の減少等)、②家族の問題(離婚、実家とのトラブル、家出等)、③住居の問題(家賃の滞納による立ち退き、住み込み先の喪失等)が複合的に絡み合って生じており、さらにその中に、アルコール依存症、病気やけが、借金などの問題が含まれることもある。
また、ホームレスの多くは50歳代の中高年齢層の男性が中心で、結婚歴が無いかあるいは結婚歴があっても離婚等をしている者が多いため家族の支援が得られにくく、さらに仕事を失うことによって一般社会から孤立してしまう傾向にある。最近では、何らかの理由により家を失ったり、家賃の滞納による立ち退きや夫の暴力からの逃避などにより、女性や家族のホームレスが一部にみられるようになってきている。
生活実態については、ホームレスの平均年齢は50歳代の半ばで高齢者も相当数含まれている。
また、野宿生活が長期化していることに伴い、衛生状態の悪化や栄養状態が十分でないことなどにより、健康状態の不調を訴える者も多くなっている。この中には、アルコール依存症、精神に障害を有する者なども含まれている。
また、ホームレスの多くは、都市の公園、河川、道路、駅舎等を起居の場所として日常生活を送っており、地域社会との軋轢も生じている。
第二章 行政の自立支援政策
第2章では政府・行政のホームレス問題への方針・政策を検証していきたい。
まず、平成14年に施行された「ホームレスの自立の支援に関する特別措置法」の全体を以下に提示する。
 |
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
|
 |
|
公布:平成14年8月7日法律第105号
施行:平成14年8月7日 |
目次
第一章 総則(第一条−第七条)
第二章 基本方針及び実施計画(第八条・第九条)
第三章 財政上の措置等(第十条・第十一条)
第四章 民間団体の能力の活用等(第十二条−第十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在し、健康で文化的な生活を送ることができないでいるとともに、地域社会とのあつれきが生じつつある現状にかんがみ、ホームレスの自立の支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講ずることにより、ホームレスに関する問題の解決に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。
(ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等)
第三条 ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とする。
一 自立の意思があるホームレスに対し、安定した雇用の場の確保、職業能力の開発等による就業の機会の確保、住宅への入居の支援等による安定した居住の場所の確保並びに健康診断、医療の提供等による保健及び医療の確保に関する施策並びに生活に関する相談及び指導を実施することにより、これらの者を自立させること。
二 ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心として行われる、これらの者に対する就業の機会の確保、生活に関する相談及び指導の実施その他の生活上の支援により、これらの者がホームレスとなることを防止すること。
三 前二号に掲げるもののほか、宿泊場所の一時的な提供、日常生活の需要を満たすために必要な物品の支給その他の緊急に行うべき援助、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施、国民への啓発活動等によるホームレスの人権の擁護、地域における生活環境の改善及び安全の確保等により、ホームレスに関する問題の解決を図ること。
2 ホームレスの自立の支援等に関する施策については、ホームレスの自立のためには就業の機会が確保されることが最も重要であることに留意しつつ、前項の目標に従って総合的に推進されなければならない。
(ホームレスの自立への努力)
第四条 ホームレスは、その自立を支援するための国及び地方公共団体の施策を活用すること等により、自らの自立に努めるものとする。
(国の責務)
第五条 国は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、当該地方公共団体におけるホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(国民の協力)
第七条 国民は、ホームレスに関する問題について理解を深めるとともに、地域社会において、国及び地方公共団体が実施する施策に協力すること等により、ホームレスの自立の支援等に努めるものとする。
第二章 基本方針及び実施計画
(基本方針)
第八条 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、第十四条の規定による全国調査を踏まえ、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定しなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について策定するものとする。
一 ホームレスの就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保健及び医療の確保並びに生活に関する相談及び指導に関する事項
二 ホームレス自立支援事業(ホームレスに対し、一定期間宿泊場所を提供した上、健康診断、身元の確認並びに生活に関する相談及び指導を行うとともに、就業の相談及びあっせん等を行うことにより、その自立を支援する事業をいう。)その他のホームレスの個々の事情に対応したその自立を総合的に支援する事業の実施に関する事項
三 ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心として行われるこれらの者に対する生活上の支援に関する事項
四 ホームレスに対し緊急に行うべき援助に関する事項、生活保護法による保護の実施に関する事項、ホームレスの人権の擁護に関する事項並びに地域における生活環境の改善及び安全の確保に関する事項
五 ホームレスの自立の支援等を行う民間団体との連携に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、ホームレスの自立の支援等に関する基本的な事項
3 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、基本方針を策定しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長と協議しなければならない。
(実施計画)
第九条 都道府県は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認められるときは、基本方針に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければならない。
2 前項の計画を策定した都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認めるときは、基本方針及び同項の計画に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければならない。
3 都道府県又は市町村は、第一項又は前項の計画を策定するに当たっては、地域住民及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体の意見を聴くように努めるものとする。
第三章 財政上の措置等
(財政上の措置等)
第十条 国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を推進するため、その区域内にホームレスが多数存在する地方公共団体及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(公共の用に供する施設の適正な利用の確保)
第十一条 都市公園その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。
第四章 民間団体の能力の活用等
(民間団体の能力の活用等)
第十二条 国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に留意し、これらの団体との緊密な連携の確保に努めるとともに、その能力の積極的な活用を図るものとする。
(国及び地方公共団体の連携)
第十三条 国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
(ホームレスの実態に関する全国調査)
第十四条 国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
第二条 この法律は、この法律の施行の日から起算して十年を経過した日に、その効力を失う。
(検討)
第三条 この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
以上
|
|
 |
国のホームレス問題への基本的な考え方
ホームレス自立支援法の根本にあるホームレス問題に対する国の認識や考え方をまとめると、まずホームレスになるに至った原因としては、主として就労する意欲はあるが仕事がなく失業状態にあること、医療や福祉等の援護が必要なこと、社会生活を拒否していることの三つがあげられる。
これらが複雑に重なり合ってホームレス問題が発生しているとしている。
こうした中、経済状況の悪化、家族や地域の住民相互のつながりの希薄化、ホームレスに対する社会的な排除等が背景となって、ホームレス問題が顕在化してきたと指摘しており、こうした要因や背景を踏まえた総合的かつきめ細やかなホームレス対策を講ずる必要があるとしている。
特に、ホームレス対策は、ホームレスが自らの意思で安定した生活を営めるように支援することが基本であるとし、このための就業機会の確保を最重要課題として挙げている。
それに伴った住居の確保もやはり必要であり、その他保健及び医療の確保、生活に関する相談及び指導等の総合的な自立支援施策を講ずる必要があるとしている。
なお、野宿生活を前提とした支援については、恒常的に実施するものではなく、あくまで緊急的かつ過渡的な施策として位置付ける必要があるとしている。
また、ホームレスの数の違い等ホームレス問題の状況は地方公共団体ごとに大きく異なっており、こうした地域の状況を踏まえた施策の推進が必要であるとし、具体的には、ホームレスの数が多い市町村においては、実情に応じて必要なものを積極的かつ総合的に実施し、また、ホームレスの数が少ない市町村においては広域的な施策の実施や既存施策の活用等を講ずるとしている。
一方、国は地域の実情を踏まえ、ホームレス数が少ない地方公共団体が取り組みやすいような、事業の要件緩和や既存事業への配慮等を検討するとしている。
行政のホームレス支援策
以下に示すのは東京都が示したホームレス自立支援の具体策である。
ホームレス対策の現状について
1 ホームレス(路上生活者)数の推移
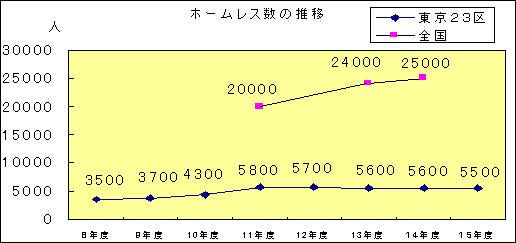
(東京都福祉保健局ホームページより)
東京23区内のホームレス数は、平成15年8月現在、約5,500人。
○依然として、高水準ではあるが、平成11年度の5,800人をピークに漸減傾向にある。
→ 自立支援システムの効果、生活保護の適用など
2 一貫した自立支援システムの構築
○ 東京都と特別区は、ホームレス問題の抜本的解決に向け、全国に先駆けて、緊急一時保護センター、自立支援センター、グループホームの3つのステップからなる一貫した自立支援システムの構築に取り組んでいる。(平成13年8月1日「路上生活者対策事業に係る都区協定書」締結)
【第1ステップ】 緊急一時保護センター
・心身の健康回復と以後の処遇方針の確定(アセスメント)
【第2ステップ】 自立支援センター
・就労による自立に向けた生活指導、就労指導、住宅相談等
【第3ステップ】 自立訓練ホーム(グループホーム)
・地域での安定した生活を営むための援助、訓練等
○ 緊急一時保護センター利用実績(平成15年12月末現在)
入所者累計5,808名 退所者累計 5,446名(うち自立支援センター入所2,523名)
平成15年12月末現在
○ 自立支援センター利用実績
入所者累計
A |
退所者累計
B |
就職者実人員 C
(就職率C/A) |
就労自立者数 D
(自立率D/B) |
就労自立実績
既設4ヵ所合計
(台東、新宿、豊島、墨田) |
| 住宅確保 |
住込み等 |
| 3,509名 |
3,203名 |
2,779名
(79%) |
1,002名
(31%) |
632名
(20%) |
1,634名
(51%) |
就労自立率の推移
(13年4月末)34% → (14年3月末)47% →(15年12月末)51%
3 各施設の設置状況
| 施設 |
設置箇所・定員等 |
全体計画 |
| 緊急一時保護センター |
13年度 大田寮(300人)
14年度 板橋寮(100人)
15年度 江戸川区に開設予定
16年度 荒川区・千代田区に開設予定 |
計5ヵ所
700人程度 |
| 自立支援センター |
12年度 台東寮(104人) 新宿寮(52人)
13年度 豊島寮(80人) 墨田寮(110人)
15年度 渋谷区に開設予定 |
計5ヵ所
400人程度 |
| 自立訓練ホーム |
16年度中に事業開始の予定 |
|
①雇用促進住宅の活用
平成15年、厚生労働省は、特殊法人の雇用・能力開発機構が運営する「雇用促進住宅」の一部を、社会復帰を目指すホームレスが入居できる住宅として地方公共団体に売却する検討を始めた。これが実現されれば定住先なかったことで就職が困難である人々を側面支援することが可能となる。これは経済的自立を促すホームレス自立支援法に沿った対応といえる。
雇用促進住宅は炭鉱離職者の増加などをきっかけに61年度から建設され、99年度まで整備された。入居率は83.1%で、全国14万3千戸に約35万人が暮らしている(02年3月末)。特殊法人の整理合理化計画により、同住宅についての早期廃止が打ち出され、今後30年をめどに全戸を自治体に売却することが決まっている。
買い取った自治体が引き続き貸すことになるが、老朽化が激しく、交渉の難航が懸念される物件もある。ホームレス住宅への転用は、こうした問題の対応策の1つでもある。
全国で最もホームレスの多い大阪府には、建物を格安で売却する方向だ。大阪府堺市の単身者向け住宅「泉北丘陵」(約千室)が対象で、古くて狭いこともあって利用者が減り、平成15年3月には全室が空室となっている。大阪市内の別の3ヵ所もホームレス住宅に活用することを申し入れている。ほかの入居者もいるためいったん緊急一時宿泊所などにはいって仕事を見つけてから入居してもらい家賃を徴収する方法も提案する。
②ホームレス地域生活移行事業
東京都は特別区と共同して平成16年度から公園でテント生活をするホームレスが地域生活に移行することを支援するための新しい取り組みを始めた。事業の目的から内容までを以下のようにまとめてみる。
Ⅰ 事業の目的
ホームレスに低家賃(一ヶ月3000円)の借り上げ住居(都営住宅、民間アパート)を貸し付け、自立した生活に向かわせると同時に公園本来の機能を回復させる。対象は新宿中央と戸山の新宿地区、隅田、代々木、上野の五公園で、二カ年事業。
Ⅱ 事業の内容
借り上げ住居を2年間(更新あり)低家賃での貸付をおこなう。その後、自立した生活に向けた、就労機会の確保や生活相談等を行う。事業の活動そのものはノウハウのある民間団体(社会福祉法人、NPO法人)に委託をしている。
Ⅲ 事業の経過
〜新宿2公園での地域生活移行支援事業の状況〜
平成17年3月10日
福祉保健局
平成16年6月から開始した都立戸山公園及び新宿区立新宿中央公園においては、平成17年2月末で参加希望者の借上げ住居への入居が終了し、計421人が地域生活へ移行した。
新宿2公園の状況
| 公園名 |
移行人数 |
| 都立戸山公園 |
228人 |
| 新宿区立新宿中央公園 |
193人 |
| 合計 |
421人 |
〜代々木公園での地域生活移行支援事業の状況〜
代々木公園の地域生活移行支援事業は、5月1日に開始され、同日から30日まで、約20
名体勢で聞き取り調査を行った。テント生活者や移動層(テントを持たない人)に地域生活移行支援事業が始まったことを伝えていった。
調査結果および、現状は以下のようになった。
<ホームレスの人数>
テント数:約300戸(ただし、荷物だけしか置いていないもの約30を含める)
移動層:150名
<参加者数>
テント層:居住用270テントのうち、約160名がアパート入居を希望、約30名が希望せず(話すら聞いてもらえない人も含め)、80名が検討中(入居を前向きに検討している人が多い)
移動層:ほぼ全員がアパート入居希望
<入居>
入居者の希望をもとにアパート探しに費やすのは約1ヶ月。あまり厳しい条件を出すと、ほとんど見つからないため第2、第3希望まで出してもらうことになる。
※ 2週間ごとに20名の入居が決定される。
<都から提供される仕事>
仕事内容:主に公園などの清掃 ※特別清掃
日当:8,000円/1日
提供期間:6ヶ月
提供回数:2〜15日/1ヶ月 ※かなりバラつきがあるため、入居者には不安もある
<電化製品>
入居準備として、28,000円分の家電が提供される
※都が用意している家電リストから希望の物を選ぶ
このほかに平成17年の11月まで上記を含む都内5公園から合計800人がアパートに移り住んだ。さらに、平成18年の2月までにさらに400人のアパートへの入居が見込まれている。
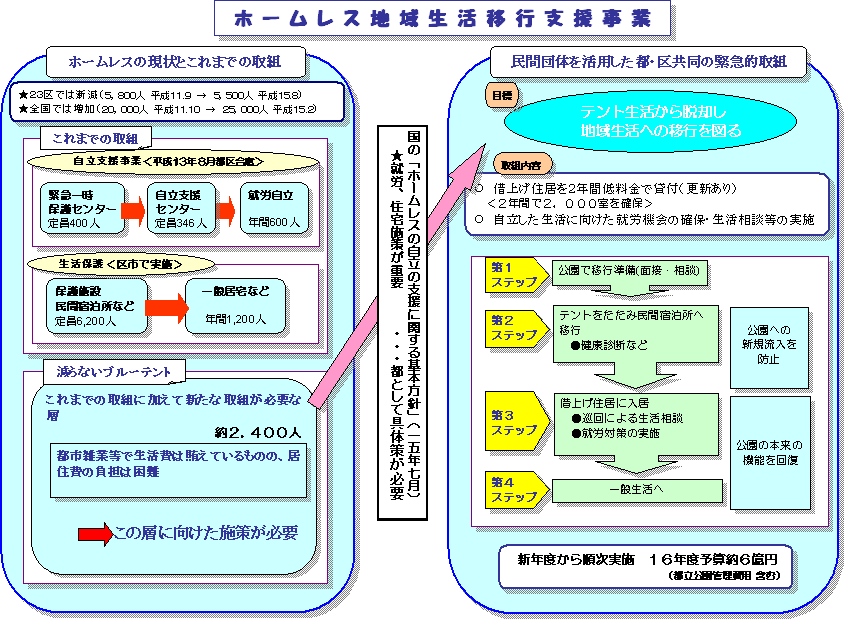
(東京都福祉保健局ホームページより)
生活保護制度
生活保護の理念とその目的
戦前の救貧行政(1874年じゅつ救規則、1929年救護法)から脱皮し、生存権保障の具体化としての生活保護法(1946年制定、1950年全面改正)
の第一条では、「日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障すると共に
その自立を助長することを目的とする」と定められている。
生活保護法の定める保護は、生活、住宅、教育、医療、介護、出産、生業及び葬祭の八種の扶助あり、生活扶助(衣、食など日常生活のニーズに対応)と住宅扶助(家賃、間代、自宅の補修費など)
は、いずれも金銭給付が原則である(医療扶助と介護扶助のみは、現物給付)。
実施機関は知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長であり、実務の実際は福祉事務所のケースワーカーが担当している。
保護の開始にあたって、実施機関は本人またはその扶養義務者の資産・収入等について調査することができる。
「生活に困窮する全ての国民」を対象としたこの法律が十分に機能しているならば、失業により野宿生活者となっている大部分の人々は、生活扶助、住宅扶助などにより救済されるはずである。
しかし、実際の運用は、「働く能力がある」、「住所がない」という理由で生活保護制度の趣旨に反する適用制限がなされている。
第三章 NPOを中心とした自立支援策
この章では、ホームレスの自立を支援する各種団体やNPOの取り組みに焦点を当てたい。現在ホームレス支援のため活動している団体は北は北海道から南は沖縄まで、日本全国各地に40近くの支援グループがあるといわれている。活動の態様は、各地の事情により、また、そのグループの歴史により様々である。支援団体はその団体を分類してみると以下のように分けられる。
①ホームレスを主体としそれを活動家が支援する団体
ホームレスを主体とし、ホームレス同士の連携を図り、支援者が共に方針を決めていく組織である。ホームレス問題を社会問題と捉え、その根本的解決のため行政、立法に働きかけ法整備などの問題を提起している。
②ホームレスが路上から地域社会へ復帰することを目指し福祉活動に取り組む団体
ホームレス問題の是非については言及せず、路上で苦しんでいる人々を法律による救済手段でサポートしている団体である。定期的に路上訪問を行い、信頼を築きながら各種の相談に乗っている。
③慈善事業としての給食活動団体
宗教的理念に基づき、各地で炊き出し、衣料品、日常品の配給を行う団体。キリスト教会関係の団体が多い。
以上のように大きく3分類することができる。現在活動している多くの団体は、夜回りを中心に定期的な炊き出し、医療相談・病院訪問、生活相談、行政窓口との折衝を行っている。そのほかに、就職探しの援助やアパート探しの援助、保証人になったり、少しでも現金収入になるようにと内職やアルバイトを探したりするNPOもある。
ここからは、支援策について具体的にどんなことが行われているのかについて紹介していくこととする。
民間諸団体の取り組み状況
(1)民間諸団体の取り組みの位置づけと役割
野宿生活者が増大し社会問題化していくこれまでの過程には、民間諸団体の積極的な取り組みがあり、そうした動きに地元自治体や国の具体的な動きが新たに加わった状況にあるといえる。
しかし、野宿生活者の問題は、いかに先進的、積極的な民間諸団体の取り組みがあったとしても、それらの力のみで解決できる領域を超えており、国をはじめ関係自治体、民間企業は言うに及ばず多様な諸団体、市民との協力連携なしには解決できないとの認識が必要である。
そうした認識のもとに、関係諸団体がそれぞれの役割、機能を発揮していくことが求められる。
①野宿生活者の問題は一つの今日的貧困問題
「ホームレス問題に対する当面の対応策について」は、ホームレスに至る要因について、「ホームレスに至る大きな要因は失業であるが、社会生活への不適応、借金による生活破綻、アルコール依存症等の個人的要因によるものも増加し、これら社会的背景や個人的要因が複雑に絡み合っているものと考えられる」と述べている。
また、「ホームレスの自立支援方策に関する研究会」は、ホームレス問題の背景及び要因について、「ホームレス問題は、その時代における社会問題が複合的に絡みあって生じているものであるが、これは過去にも繰り返し現れた一つの貧困問題であり、近年の経済・雇用情勢等を背景として、今日また新たな形で出現している。」と述べている。
社会的貧困問題の解決に民間諸団体の力だけでは限界があり、国自らが貧困をなくしていくための一つの社会システムを率先して構築していくことが必要であり、そのシステムの中に民間活力、善意や相互扶助(ボランティア等)を組み込んでいくことが求められる。
今日、我が国の旧来の社会制度にさまざまな齟齬が生じている、いわば社会構造的転換を迎えているともいえ、野宿生活者問題に限らず現代的貧困への対応のために、社会的援護の新たなシステム構築が求められよう。
②民間諸団体の取り組みの支援と連携
野宿生活者問題における民間諸団体の取り組みは多様である。宗教的、人道主義的な観点からの取り組みや博愛主義的な発意からの取り組みもある。あるいは街づくりや主義主張による野宿生活者問題へのアクセスの仕方もあろう。
しかし、大事なことはこうした多様な取り組みが大きなうねりとなって、野宿生活者問題が解決の方向に向かうことが望まれる。そうした中で、民間諸団体のそれぞれの役割、国や関係自治体の役割が存在するはずであり、そのためには協力・共同、連携関係の構築が必要となる。
現在、野宿生活者問題への対応はスタートしたばかりの状態ともいえ、必要なことは先進的、あるいは熱心に野宿生活者問題に取り組んでいる諸団体、人々への国や自治体による早期の連携関係の構築、支援であろう。
(2)民間諸団体の取り組み事例
①「食」から「職」へ取り組む「お米の勉強会」
【お米の問題からテーマの広がり】
お米の勉強会は、1986年10月8日に始まり、毎月1回の例会を開催し、現在まで続いている。勉強会の始まりは、食管法やお米の輸入問題などから始まったが、その後、農業・食べ物から環境問題に至るまでテーマは広がってきている。
いろいろな立場の人たちが一緒になって、広い角度から問題の本質を勉強し、検討し、今後も現在以上にいい状態で農業が続けられ、質のいい食べ物が得られるよう、根本的な改革の方向を見いだすために勉強する。そして、会員の意見が一致したところについては、改革のための運動もする。そのためには、いろいろな立場の人たちから幅広く意見を聞くことに努め、また、意見の違う人たちが同じテーブルについて、自由に意見を出し合い、討論できる場として、この会が存在する。
会員は、消費者、生産者、流通関係者、マスコミ関係者など個人会員制で、現在約350名、各方面から多くの人々の協力も得て会は運営されている。会費は年間4,000円である。
【「食」から始まり「職」にも取り組む】
お米の勉強会と野宿生活者−釜ヶ崎との関わりは、ビールメーカーに売っていた「くず米」を、「食べるのに困っている人がいるのであれば、送ってあげよう」との生産者会員の発案で始まった。そうしているうち、阪神・淡路大震災が起こり、被災した神戸市民への炊き出しも教会関係者との協力で始まった。
釜ヶ崎との縁は、能勢の棚田づくりで大淀寮の施設長にお世話になった関係で始まった。震災以降に、「食」だけでなく働く場−「職」も確保しようと支援の方向が生まれてきた。施設長が能勢農場に野宿生活者を連れて行ったことで、就農のきっかけができ、兵庫県氷上町の農家(M氏)でも受け入れをしていただいた。農村のような田舎で、普段見かけぬ人がいると目立つところで、身分保証のない人を受け入れることがどんなに難しいことか、察するに余りある。M氏はそれだけに留まらず、県にも野宿生活者の受け入れについて相談に行かれたが、県の農業担当者からは前向きな対応はしてもらえなかったとのことであった。
【篤志家と熱心な仲介者】
野宿生活者が就農の機会を得られたというのは、篤志家である施設長のような熱心な仲介者があってうまくいったように思われる。本来は、役所や農協がそうしたことに熱心に取り組むべきことかと思われると同時に、不況業種指定のようなものに「農業」は入っていない関係で、雇用に関わる助成金のようなインセンティブを期待するわけにはいかない。
今日、農業においては人手不足であるにもかかわらず、パートでも料金が安いということでなかなか来てくれないという。
兵庫県下のある町の農家を対象にアンケート調査を行った時、専業農家は100人に1人の割合で、専業農家以外の多くの農家は、農業は自分の代で「終わり」と思っており、そういう人は、農地を貸してもよい、住まう家もあると考えている。また、農家の人は、都市生活者より外国人の方が農業で働いてくれるのではないかと思っている。というのは、農家の人たちは工場で働く外国人を見ているから、そう考えるのであろう。
【日本農業再生に農村と都市生活者が手を結ぶ】
耕作されず荒れた農地も広がっており、日本の農業を再生していくためには、農村と都市生活者が手を結ぶ必要があると思う。現実に、野宿生活者のみならず都市には失業している人がたくさんいる。
農村への“入りにくさ”は厳然と存在するし、門戸を広げていく必要がある。ある町では、空き家農家の登録をして、受け入れを行っており、そうしたことに対する行政の役割は大きい。新しい住宅を造ることや新しく道路を造ったり、広げたりすることだけが、行政の仕事ではないはずである。
また、たとえ野宿生活者が就農・帰農しても、数が少ないと寂しくて帰ってしまうことになりかねず、初めは農業生産法人でアルバイト的にでも数人が一緒に住まい、農業に従事することも考えられる。せっかく就農・帰農した野宿生活者も、農業のことがよくわからず、何をしていいか戸惑っているとの話も聞く。就農・帰農する過程で、行政による事前研修を行うことができれば、抵抗なく農業に就いてゆけるのではないか。
野宿生活者を受け入れた側の思いは、お米づくりだけの農業から野菜づくりなどの展開も考えておられ、人を中心にした通年の農業のあり方を考えてのことである。
農村と都市生活者が手を結び、「“食”と“職”を確かなものにする」ことが「お米の勉強会」のテーマの一つとなっている。
②生ゴミリサイクルと就農・帰農のリンケージ
【運動を“したたか”に続ける】
生ゴミリサイクルに取り組むNGOシティズンホームライフ協会は「野宿生活者の問題は、我々の生活と地続きの問題である」と考えている。運動をしたたかに展開することが必要で、きれいごとでは片付かない。店舗や工場が倒産したところの倒産品を扱う老舗のリサイクルショップがある。そこは、回収に6〜7人が従事するまでになっているが、“したたか” に仕事を続けることの意味をうかがい知ることができる。
生ゴミリサイクルも答を出していきたいと考えている。利用価値があれば、公的な補助が付いたりするはずで、近畿農政局に足を運んだりしているが、まだまだPRが足りない。実験農場を作って、生産物の出来具合も見ている。
【生ゴミの循環で新たな就労が生まれる】
生ゴミ処理だけでは就労は生まれない。機械をみる人間が1人いれば済むことである。しかし、「生ゴミ」を循環させることで、新たな就労の機会が生まれる。生ゴミ排出→処理再生事業者→流通事業者→農業利用→生産物販売→消費者→生ゴミ排出…の循環過程、生ゴミ処理再生事業以外のところでは多くのマンパワーを必要とするところがあり、新たな就労の場となり得る可能性がある。
生ゴミは一般家庭からの回収は行っていない。品質にバラツキがあり、何が混入しているかわからない。家庭からの生ゴミ回収は、運動に関わっている市民のところのみで、学校給食や量販店等の大規模事業所が中心であり、その割合は、100tのうち、前者10t、後者が90tくらいである。
回収には、1人が、1件の回収先につき1㎏/日、1週間で7㎏の生ゴミを100件回収する形でローテーションしている。2人で1台のパッカー車を稼働させている。
【生ゴミ肥料に農家の関心は薄い】
生ゴミを肥料化したものに一般の農家は興味を持っていないのが現状である。このため、兵庫県篠山市に空いている土地があって、EM菌栽培で中心になりたいという人がいて、そこで生ゴミからできた肥料を使って有機野菜の栽培を行っている。それも、半年間の交渉の末にようやく実現した。
生ゴミ処理事業の循環の中で野宿生活者の就労を考える場合、農業生産の場で就労を実現していかなければならない。しかし、既存の農家ではそのことは困難であり、農業生産法人等受け入れ先としては望ましい。
また、野宿生活者は農業には素人である。この素人に農業を“教える”ことが必要になる。まずは、「実験農場」をつくることが必要だと考えられている。農業に素人の野宿生活者が、農業の基本をそこで身につける。そのために、大阪府・大阪市等の行政による支援も必要である。農業生産を基本において自給自足生活に取り組んでいる団体が存在するが、そうしたイメージを、実験農場に抱いている。
現在、研修機関としてある「○○協議会」とかは、技術の話ばかりであったり、生産物への補助をどうするとかが中心で、野宿生活者の就農に向けた研修・訓練という意味では役立たない。
生産物の販売においては、市民を巻き込んだ「援農クラブ委員会」の設立を考えている。露店での販売や、自転車による宅配、商店街の中での有機野菜の販売等が考えられる。自転車による宅配は、その範囲は限られており、まちづくりの中で十分機能していくと思われ、すでに市民運動として活発に取り組んでいるTまちづくり協議会へも提言しているところである。
自立支援センターも整備され始めて、野宿生活者が就労するうえで困難となっていた「身元」の問題も一定解決されつつあり、そうしたまちづくりへの参加も可能となる。生ゴミ再生利用の肥料を使った有機野菜栽培については、農水省や近畿農政局へも積極的に働きかけ、有機物協議会の組織化を考えている。今、1人でも、あるいは何人かでも有機野菜に目を向けてくれることが必要であるが、生ゴミは「タダ」の感覚があって、その価値を認めるに至っていない。大阪府にもリサイクル協議会はあるが、生ゴミをどうしたらいいのか方向性が出ていない。問題点をあげて、消去法で取り組んでゆけば、答はおのずと明らかになるはずである。
このような状況の中で、生ゴミリサイクルに“したたか”に取り組みを続けることが必要であると考えている。
③営繕事業について
【営繕事業の経験】
かつて、NGOシティズンホームライフ協会のO氏が取り組んでいた営繕事業は、阪神・淡路大震災があって、ブルーシートを大量に配布するなどした結果、経営(運営)がおかしくなってしまった。しかし、プロが明確な責任体制のもとで、設計から営業まで手掛けていけば、(腕に覚えのある野宿生活者を集め)雇用を創り出すことは可能と考えている。
【ニーズは必ず存在し、体制づくりが鍵】
網戸を修理して欲しい人やフスマの貼り替えを頼みたいと考えている人は必ずいるはずで、そうしたニーズに応えた営繕事業は十分成り立っていく。体制づくりが必要であるが、O氏自身は生ゴミ処理事業に取り組んでおり、核となる人材がいない。
かつて、営繕事業を立ち上げた時は、全国営繕事業協同組合とも連携を取りながら、30人くらいでスタートした。欠陥住宅問題も話題になっている頃で、A建築事業協同組合と消費者の窓口的機能を受け持つNGOシティズンホームライフ協会がタイアップする形であった。
営業としてはチラシをまき、プレハブメーカーの下働きのようなことから始め、徐々に事務所や作業場を確保し、受け皿を作っていった。スタッフの指導には、事業に加わるメンバーは、少なくとも、「自分はできる」と考えていることは確かであり、彼らのリーダーとして頭に立つ人間は、彼らに「腕」においても一目置くような実力とパフォーマンスができる人でなければならない。また、顧客の電話の受け応えは素人ではダメで、仕事内容等のモノごとが判った人間が応対しなければ、顧客は仕事を出してくれない。
【行政やマスコミ等の支持・支援の獲得】
組織としては、(責任の所在の問題があり)NPOでは限界があるのではないか。“リフォームはお金になる”ということで、いろいろなところの参入もある。地域の工務店とうまくタイアップしてやっていくことを考えるべきであろう。もっとも、3ヶ月間は仕事が来ないことを覚悟しなければならないし、リフォームだけでなく、介護もやるような「何でもやります」ということをチラシにも書いて、大量に宣伝していく必要がある。
それと、社会的公共性ということが大事であり、消費者の味方であるとのスタンスが必要になる。そのためには、行政の支持・支援や新聞等マスコミの支援を取り付けていくことが必要である。
④他地域等での就労・自立の取り組み
東京では野宿生活者とともに、野宿生活者の就労機会を開拓すべく活動を続けている団体、正式名称を「渋谷・野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合」(略称「のじれん」)があり、1998年4月に正式発足以来、野宿生活者の生活改善と居住権の確立を求めて活動を続けている。
「のじれん」の野宿生活者の就労機会づくり、就労機会確保の状況について紹介する。
○NGOによる海外への救援物資積み込み作業手伝い
ベイルートの難民キャンプに送るという救援物資(コンテナ一台分)の積み込み作業に他のボランティアの人たちと一緒に従事。約3時間で賃金は5人で22,000円(交通費込)。
○市民団体事務所における軽作業手伝い
リサイクル活動などを行っている事務所で、回収した割り箸の箱詰め、物資の運搬、清掃などの軽作業に従事。1月から毎週、毎回2人が約3時間就労する。時給800円(交通費込)。
○社会福祉法人での作業手伝い
社会福祉法人が行っている事業で、トイレットペーパーの出荷用箱詰め、トラックへの積み込みの他、木材の運搬等の作業に従事。夜は、作業所の空室に宿泊し、5 名が4日間就業する。
○山梨の農家で農作業の手伝い
農家の方の指示にしたがい農作業の手伝いに従事し、夜は離れで宿泊。2ヶ月間で延べ6日間、2名が従事する。
○手作り弁当の販売
調理師免許を持っている仲間などを中心に、普段、共同炊事や炊き出しで鍛えた腕前を発揮して市民団体の集会などで自作の手作り弁当の販売を開始。半月に一回程度のペースでおにぎり、炊き込み御飯、パンケーキ、それにジュースなどを販売、売れ行きはなかなか好調である。
Ⅰ ビッグイシュージャパンの取り組み
ビッグイシュージャパン
ビッグイシューとは、ホームレスのみが販売できる雑誌である。ロンドンで始まったこの仕組みは、またたくまに世界に広まり、現在では24ヶ国で、約50雑誌が発行され世界中のホームレスの仕事をつくっている。ビッグイシューは、1991年9月に英国ロンドンでボディ・ショップ・インターナショナルのゴードン・ロディックとジョン・バードにより設立された。設立の目的はホームレスに収入を得る手段を提供するというものであった。
現在日本では、東京、大阪の大都市を中心に北から青森、宮城、千葉、神奈川、京都、神戸で販売が始まっている。読者層のターゲットは20〜30代の若者であり、このため誌面の構成は国際記事、特集記事、エンタテイメント記事である。表紙は若者に支持を受ける有名ミュージシャンや著名人が飾り、そのデザインも若者を意識したものとなっている。
Ⅱ ビッグイシューの仕組みとは?
ビックイシューとは前述した通りホームレスのみが販売できる雑誌であるのだが、ここではホームレスに収入をもたらすその仕組みについて説明する。まず、ホームレスはビックイシューを販売するための登録をする必要がある。ビックイシュージャパンでは、販売員に対するいくつかの規約を設けておりこれを守れない者には販売を許可しないという姿勢をとっている。続いて、登録をした者は最初に一冊200円の雑誌を10冊無料で受け取り、この売り上げ2000円を元手に、以後は定価の45%(90円)で仕入れた雑誌を販売、55%(110円)を販売員の利益とする。
Ⅲ ビッグイシューの考える自立への三つのステップ
ビックイシューではホームレスに対してどのように路上生活から自立生活に移行するかを三段階に分けて明示している。
①簡易宿泊所(一泊1000円前後)などに泊まり路上生活から脱出する。これは、1日に25冊〜30冊売れば可能となる。
②ある程度資金が貯まれば次のステップは自力でアパートを借り、住所を持つこととなる。月2回刊行で、1日35〜40冊を売り、毎日1000円程度を貯めていけば7〜8ヶ月で敷金を作ることが可能となる。
③住所をベースに新たな就職活動をするというようなプランである。
Ⅳ ビックイシュージャパンの現状
<販売収入>初刊が発売された2003年9月から2005年4月末の段階で実売数は1,022,025冊と、百万冊を突破している。その結果、計算によると販売員(ホームレス)に1億1,242万円の収入をもたらしたこととなる。
<販売員の現状>外での長時間の立ち仕事であることから健康面に不安を抱えるホームレスにはかなり厳しい仕事だといえる。さらに、ビックイシューの掲げる自立へのステップを可能にするためには、真夏の猛暑の中や真冬の極寒の中でも毎月一定の売り上げをこなさなければいけなくなる。これはかなりの至難業である。
また、一日に100冊も売るカリスマ販売員もいるが、平均的な売り上げを実地で調べた結果は20〜30冊といったところである。ホームレスの中には人付き合いの苦手な者も多くまして商売をするのであれば、そういった性格上の理由で売り上げもかなり差が生じてくる。しかし、これに対しては、販売者同士のミーティングにより販売力の向上につなげていこうとしている。私に情報提供してくれた方も、まだ路上生活とのことだがビックイシューは安定した収入が手に入ることが嬉しいといっていた。
<販売員の一ヶ月の収支>ここで販売員の一ヶ月の収支を何名かの例を挙げながら検討してみたい。
|
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
|
○Aさんの一ヶ月の収支
[収入]
ビックイシューの一日の売り上げ 26冊×200円→5200円
ビックイシューの一日の仕入れ 26冊×90円→2340円
収入合計 ビックイシューで得る利益 (5200円−2340円)×30日=85800円
[支出]
朝食 300円×30食=9000円(立ち食いそば、牛丼など)
昼食 300円×30食=9000円(立ち食いそば、牛丼など)
夕食(飲み物含む) 1000円×30食=30000円(コンビニ弁当、飲み物)
飲み物(日中) 300円×30日=9000円
タバコ 300円×30箱=9000円
電車代 320円×30日=9600円
風呂代 400円×13回=(平均)=5200円(銭湯)
洗濯代 300円×5回=1500円(コインランドリー)
靴下・下着等 300円(100円ショップにて)
支出合計 82600円
★収支 85800円−82600円=3200円
○Bさんの一ヶ月の収支
[収入]
ビックイシューの一日の売り上げ 7冊×200円→1400円
ビックイシューの一日の仕入れ 7冊×90円→630円
収入合計 ビックイシューで得る利益 (1400円−630円)×30日=23100円
[支出]
米(5キロ) 1800円×3袋=5400円
おかず、調味料 300円×30食=9000円(立ち食いそば、牛丼など)
夕食(飲み物含む) 150円×30日=4500円
タバコ 280円×30箱=8400円
ガスボンベ 100円×10本=1000円
ろうそく 100円(6本入り)×5箱=500円
洗濯代 200円×4回=800円
※冬以外は公園の水道で体を洗うため風呂代はなし
支出合計 20600円
★収支 23100円−20600円=2500円
○Cさんの一ヶ月の収支
[収入]
ビックイシューの一日の売り上げ 17冊×200円→3400円
ビックイシューの一日の仕入れ 17冊×90円→1530円
収入合計 ビックイシューで得る利益 (3400円−1530円)×30日=56100円
[支出]
朝食 230円×30食=6900円(パンと牛乳)
昼食 200円×30食=6000円(パン、カップラーメンなど)
夕食 450円×30食=13500円(カツ丼、カレーライスなど)
飲み物(日中) 300円(氷と水)×30日=9000円
タバコ 300円×17箱=5100円
風呂代 400円×4回=1600円(銭湯)
洗濯代 300円×4回=1200円(コインランドリー)
靴下・下着等 500円(100円ショップにて)
支出合計 43800円
★収支 56100円−43800円=12300円
|
|
以上の結果から、ビックイシューはホームレスの生活状況の改善には、大いに貢献しているといえる。
まず、販売員はノルマなどによってではなく自分の責任においてビックイシューを仕入れ、自分の生活状況を考慮しながら
販売をしている。社会復帰をしていく上で自分の意思によって行動し自立していくことは一番大切なことである。
そういった姿勢を維持していくためには、ホームレスの人自身がある程度の責任を持つことが必要ではないか。
ただ、上記の収支の内訳を検討すると自己資金によって部屋を借り自立をしていくには、少し無計画ではなかろうか。
ビックイシューの売り上げでいくら路上生活の質を向上させても最終的に路上からの脱却に向けた生活をしていなければ
自立への道は遠のく一方である。一人一人に収支管理のアドバイスをすることや、自立に向けた具体的な金額の目標設定を
していかなければならないのではないか。
例えば、理解のある不動産賃貸業者と連携して、ホームレスに具体的な物件を
提示しそこに住むための具体的な金額を設定し明確な目標を持ってもらうというのも一つの手ではないだろうか。
第四章 行政・NPO支援の総合比較
ここでは、行政のホームレスサポートとNPOのホームレスサポートを、様々な点から比較、検討していきたい。
1 支援行動への動機
まず、なぜホームレスを路上生活から脱却させようとするのか、その行動の動機となる部分を比較してみたい。
行政がホームレス支援を行う最大の理由は、憲法11条と25条を実現させるためである。
憲法11条とは基本的人権の普遍性、永久不可侵性、固有性を規定した条項であり、憲法25条は国民の生存権、国の社会保障的義務を規定した条項である。
行政の場合、その行動は法によって制約されているという側面から、ただ単にホームレスに対する慈悲からの行動ではなく公共福祉という概念からの支援行動である。
この公共福祉という概念も複雑であり、例えば公園をブルーテントで占拠しているホームレスを福祉という観点から自立に向けて支援していくのか、それとも市民のための公共という観点から公園をブルーテントのない元の姿に戻すことを優先するのか、行政は板ばさみの立場にある。
公園の事例に関しては、誰もがいつでも快適に利用できる本来の公園の姿に戻すという理想の状態を実現することが最終目標となる。その実現にホームレスの社会復帰が欠かせないことはいうまでもない。
このことからも言えるように行政のホームレス支援の動機は、憲法の精神によるホームレス個人の救済という側面と社会の公共性すなわち一般市民の利害といった側面を併せ持ったものだといえる。
それではNPOならびにその他の支援団体はどんな動機のもとにホームレスに対する支援を始めたのだろうか。
ホームレス支援を行っている団体は数多くあるが、その動機については様々である。歴史的に古くからキリスト教や仏教の立場から生活困窮者の援助を続けてきた人々や、社会活動家がホームレスという社会問題を解決するために国家と闘うことで支援しているケース、本当に一人の市民が路上生活者の姿に見て見ぬふりをできずに始めたケースまでその動機は、活動している人々の数だけあるとも言える。
NPO及び各種団体の理念を見るにホームレス支援者にとってホームレスは資本主義経済の犠牲者といった見方が強い。要するに、ホームレスの支援者となる者はもともと社会構造に対してなんらかの疑問を持っている。
これらの人々に総じて言えるのは、自らの意志のもとに支援活動をしているということである。そこには、慈愛ともいうべき精神がある。そんな他人をほっとけない思いが彼らの動機なのだ。そんな彼らは国や行政が手を付けたがらない問題に対して市民の力で改善、解決をしていこうとする a philanthropist〈奉仕活動家〉なのである。
2 ホームレス支援に対する考え、姿勢
行政の場合、ホームレスに対する支援は前述した通り法律に則って行われている。そのため、生活保護法やホームレス自立支援法などの法に規定された範囲で支援はなされる。
基本的に行政にとってホームレスを抱えるというのは、公共性の点でも予算の点でもマイナス要因でしかない。法律上の支援に対する考え方とは別に、現場職員のレベルで考えれば自分の属している区なり市などにホームレスがいなければ支援する必要もない。それにより、ホームレスの数の少ない自治体ではホームレスに居住所がないことを理由に少しの金をホームレスに渡し隣の市なり町に移動してもらうというケースも起こっている。
生活保護や支援施設の利用申請についてもホームレス自らが自分で役所に行かなければまず支援を受けられない。行政はホームレスの支援についてはかなりの部分でホームレス自身の自主性を尊重している。これが良いのか悪いのかは現状から判断するほかないが、一方で路上から脱却するにはホームレス自身が強い意志を持って社会復帰への道を歩んでいくほか無い。しかし、行政が果たすべき役割はナショナルミニマムとしての最終的なセーフティーネットを用意し必要とされる者には適用していく責務がある。
最近では一部の支援策においては、NPOとの支援の協力体制も次第に進んできており、行政の姿勢にも変化が見られるようになった。このようなNPOとのミッションの共有できる分野での協調が今後も求められる。
NPO及びその他の支援団体では、支援に対する考え方や姿勢も様々でありそれは実際の支援活動にも現れている。
まず、その団体が掲げる理念、つまり最終的にホームレスにどうなってもらいたいのかということに団体間の差がある。
実際、ホームレスのサポートはかなり多岐にわたっているともいえる。では、どのような考え方のもとそのサポートは実行されているのだろうか。
先にも書いたが、NPO及び各種団体の理念を見るにホームレス支援者にとってホームレスは資本主義経済の犠牲者といった見方が強くホームレスの支援者となる者はもともと社会構造に対してなんらかの疑問を持っている場合が多い。
実際のサポート内容についてもサポートする側個人の社会に対する主義や主張が色濃くでている。
あえて、その考え方と姿勢を分類するならば以下のようになる。
《社会問題提起型》
ホームレス問題を通じて社会構造の変革を国家に要求していく団体。ホームレスのサポートに関しては物資や食料のみならず、公園での居住権の獲得そこから発生する立ち退きに際しての行政、警察との闘争までを支援している。また、ホームレス同士での仲間としての生活を提案している。
《自立支援援助型》
ホームレス自身が独力で生活していけるように援助をしている団体。これらの団体は行政の支援に対して限界を感じており、民間だからこそ出来るサポートを探し取り組んでいる。
衣食住を総合的にやっている場合もあれば1つに特化したサポートをしている場合もある。
一人でも多くのホームレスの社会復帰を望んでおり、毎週の夜回りパトロールなど日々地道な活動を行っている。
《食料・物資供給型》
ホームレスが生きていくために一番必要な食料や冬を越すための毛布や衣類の供給を行う団体。ホームレスを助けたいという思いから日々の生活に困窮しているホームレスへの身近な援助として取り組んでいる。ホームレス自身に炊き出しの準備を任せるなど自立への促しにも取り組んでいる。
3 支援の具体例とその効果
大都市だけでなく地方の市町村にまでホームレスという現象が起こっている現在、行政のホームレス支援策は国の定めた「ホームレス自立支援法」に基づき各自治体がそれぞれ抱えているホームレス問題の現状に即して取り組んでいる状況だ。
前述されたものを含む都市部におけるホームレスの支援策を提示しその支援策が現実ではどのように機能しているのか、そして現場の人々はどんな思いを抱いているのかを検証していきたい。
☆地域生活移行支援事業
東京都が特別区と共同し平成16年から始めた事業である。事業の目的や内容、経過については第三章で述べたが、ここでは出来るだけ総合的にこの事業の効果について考えてみたい。
この地域生活移行支援事業には大きく分けて二つの見方が出来る。
一つには今までの支援の流れであった仕事を見つけ資金を貯め部屋を借りるといった二段階の自立へのステップを、期間限定ではあるが住居と仕事を同時にホームレスに提供することにより短い期間で自立生活に入ることができる。
この点では、ホームレスにとっては自立への選択肢が増えることになる。
もう一方では、これを機にホームレスを公園に戻ってこさせないという行政の公園適正化を目的とする見方も出来る。この見方を裏付ける部分としては、ホームレスはこの支援を受け入れる代わりに二度と公園には戻ってこないことを誓う誓約書を書かされることになる。
加えて事業の計画そのものが二年間の定めがありその後のサポートに対しての具体的な取り決めがないことからも公園の機能回復優先なのではないかと考えられる点もある。
支援を受ける当事者のホームレスはどう考えているのか。支援を受けるまたは受ける予定のホームレスの数を合計すると千人を超えていることや、各公園のテントの8割近くが片付いていることから考えると大部分は積極的にではないにしてもこの事業を受け入れているといえる。しかし、移行に際してホームレス個人が抱える不安も様々である。公園で暮らすホームレスのなかにはテント生活者同士でコミュニティを形成している場合もあり、移行事業によりその仲間と離れ離れになることを恐れている人や、今までテントから通っていた仕事場へ新しい住居から通えるのかどうかなどが不安なようである。
この事業自体がホームレスの自立支援にどの程度有効だったかの結果が出るのはまだ先だと思われるが、17年8月の時点でホームレスの数が4200人あまりであるという調査をもとに考えると23区内ではホームレスが2割減ったということになる。この数の減少は一時的かもしれないが評価できるといえる。このように事業がスムーズに進んでいるのも今までホームレスとの関係を長期にわたって持ち続けたNPOなどが実際の業務を行っているからであろう。
ではこの事業の問題点はどこにあるのだろうか。
一つには、事業計画が終わる2年後に新たな予算が組めるかどうかがあげられる。都はこの2年間に合わせて18億の予算をかけており、この負担を都が続けていくのかということがあげられる。
二つめには臨時の仕事ではなく固定の仕事を見つけてからでなければ結局住居を維持できなくなることである。そもそもこれまでと同じように簡単に仕事が見つかる可能性は低い。加えて都が用意している仕事は臨時のものでありその勤務日数も定まっていない。これでは収入も不安定になってしまう。
このほかにもこの事業そのものを信用していないホームレスは公園という居場所を失い、その周辺に新たに生活場所を求めてさまよっている。
確かにこういった事業は期間を限定しなければ効果を発揮できない。しかしこれまでの応急処置的な対応から、継続的、長期的な対応への変化にシフトしていかなければ不定期なホームレスの発生には対応しきれないといえる。
事業後の新宿中央公園の様子

事業後の新宿中央公園周辺の様子(都庁第一庁舎前)

★NPOによるグループホームでの自立支援
前述の地域生活移行事業との比較として、民間団体が取り組んでいるグループホームでの自立支援を取り上げたいと思う。なかでもここでは「ふるさとの会」が取り組んでいる事業について触れたい。ふるさとの会は東日本最大の寄せ場『山谷』を活動拠点に、ホームレスが地域社会の中で安定した住居と生活を確保することを通して、社会の中で再び「役割」や「人としての尊厳」「居場所」を回復することを支援しているNPO法人である。
家の無い一人暮らしで、疾病や高齢などの理由で病院や施設にいた人たちが、再び地域社会で自立するための第一歩としての中間・通過施設を運営している。
平成14年3月までで延べ140名の入所者があり、123名が退所。ふるさとの会のアパート保証人によって自立生活を始めた方は26名(自立支援センターの利用者登録)である。
ふるさとの会は「再びホームレスとなることを防止し居宅生活を継続するための支援」アフターケアが何よりも重要と考えている。
路上生活を経験した人が、再び路上に戻ることなく地域の中で安心、安定して生活するためのアフターケア事業として「共同リビング事業」を行ってきた。
「共同リビング事業」は財団からの助成をうけ1995年に開始。
マンションの一室を開放し、簡易旅館、アパート等で地域生活を始めた路上生活経験者等を対象に日中のリビング提供、食事提供、家事援助、金銭管理、欠席時の安否確認などを週4日行っている。
また、リビング事業への定期的な参加を前提に、アパートの保証人活動も行い、生活基盤確保を支援し、現在までに約50名の方の保証人を引き受けている。
現在では、運営宿泊所からの退所者へのアフターケアとして、リビング事業へ繋ぎアパート保障を実施するとともに、更生施設、病院の医療相談室からもアフターケア依頼をうける広域的な事業に発展していっている。
リビング事業では日常的に利用者と顔を突き合わせ、欠席時には安否確認に訪問することにより、トラブルを未然に防ぐことができ、地域生活を安定して継続することができるといえる。
ふるさとの会では第2種社会福祉事業宿泊所を5館運営しており、全体で100名の宿泊規模がある。定員は20名前後の小規模なグループホームである。
入所者の多くは高齢で、身寄りの無いために帰来先を確保できず、長期にわたって入院を余儀なくされてきたいわゆる「社会的入院層」である。要介護高齢者のため、単身で地域性を継続することは難しく、生活の場において日常的な支援を必要としている。
宿泊所は、中間通過施設を基本性格とし、今後の処遇を決めて行くにあたってのアセスメント、生活訓練、アフターケアプログラムに繋がって地域生活を円滑に開始するための退所援助が業務の中心となっている。
宿泊所は、路上生活者がそこを通過してアフターケアを受けながら地域生活を始める、それまでに生活訓練をしながら準備を整え、やはり最終的には再び地域の中で暮らす、そのための有力な手段と位置づけている。
職員配置は、日中は1〜2名、夜間は宿直員を常駐させ、24時間365日の支援体制を敷いている。高齢者を抱えていることもあり、救急車を呼ぶ、痴呆で徘徊する利用者を職員が探しまわることも稀ではない。警察に捜索手配をかけ、迷子老人としての届出も日常化しつつあるようだ。
このような高齢、疾病、障害等を持つ利用者が地域の中で生活して行くために、ふるさとの会宿泊所では多数の社会サービスを導入してきている。ホームドクター制による毎週の往診(地域の開業医に依頼)、服薬管理、金銭管理、在宅サービスの導入(介護保険によるヘルパー、訪問看護)、自助グループ(アルコール、薬物など)の紹介などを実施。
第2種社会福祉事業宿泊所ではあるが、そこで提供されるサービスの中身は生活保護関連施設(更生施設、救護施設)とほぼ同等のものである。日常生活支援と適切な社会サービスの提供を行うことによって、より多くのホームレスが再び地域で生活することが可能となると考えている。
ではこのような民間のグループホームによる支援の問題点はどこにあるのであろうか。
民間のグループホームには、きめ細かなケアをしているところもあるが、食事の提供のみにとどまるところもあり、施設によって処遇内容に大きな差がある。
その他、食料支援、生活相談など、さまざまな活動を展開しているが、団体数の少なさ、地域的な偏在、財政基盤の弱さなどが挙げられる。
これについてその原因をもう少し詳しく述べると、痴呆・精神・知的障害者等のグループホームは制度化されているのに対し路上生活者はその限りでない。したがって路上生活者が既存のグループホーム事業を活用し、地域生活へと移行してゆくのは困難な状況である。その理由として、ひとつには各種グループホームの絶対数が足らない、供給不足の側面。ふたつめに、各グループホームは基礎自治体の補助事業であり、利用者は各障害を持つ区民一般を対象としており、利用を路上生活者に拡大できないこと。三つめに路上生活者は住所不定が多く、グループホームの設置区に財政負担が発生する場合、どうしても行政は実施に消極的になってしまうことが挙げられる。
ホームレス問題は広域的な問題であり、その財源確保を広域行政である都や国が率先して負担してゆかなければ、各種グループホームの展開は困難といえる。
単純に両者の比較をすることは難しいが、ここで一つの観点として一人での自立と複数での自立という点で比べてみると、やはりグループホームによる自立が好ましいといえる。
その理由として、地域移行支援事業では一人での自立を強いられることとなる。NPOがアフターケアをするといってもその負担は大きい。ホームレス側からしても公園などの生活を通じてできた仲間と離れてはそれこそ一人になってしまう。また、ホームレスにしてみれば自分がホームレスであったことを必要以上に意識してしまうこともあり、一般市民との間に自ら壁をつくってしまいがちである。
このことからも、グループホームといういわば経験を同じくした者同士が集まって社会生活の感覚を取り戻す場がホームレスの社会復帰には必要といえる。
つまり、グループホームを社会復帰へのワンクッションとして利用することでホームレス自身の不安や心配を徐々に取り除いていくことが出来るといえる。
次の観点として自立までの期限の有無で比較してみると、地域生活移行事業では2年間という一応の期限がありこの期限があるからこそホームレスの自立を促せるともいえる。
反対にグループホームでは期限の設定がなく個人の能力に応じた自立という姿勢から期限を設定すること自体がなじまないといえる。これにより利用者の増加には施設を増やしていくことでしか対応できない。グループホームを増やすにしても資金準備や場所選び、地域住民との話し合いなどNPOの負担は計り知れない。
以上のことから民間でできることと行政にできることには限界があるといえる。しかし、ホームレスへの支援事業はまだ動き出したばかりであり行政と民間の結束があればさらに発展した支援が可能になる。しばらく両者の関係を見守りたい。
欧米諸国におけるホームレス事情
まず、欧州でのホームレスの定義は、日本で言う野宿生活者だけを指すものではない。簡易ホテルや一時的滞在施設に入所している人等も含む広い概念である。その数は、イングランドで10万人(1999年),フランス73万人(1998年)、ドイツ55万人(1999年)となっている。純然たる路上生活者数は、イングランド703人・ロンドン357人(2001年)、ドイツ26,000人(1999年)(フランスについては不明)とされている。
ホームレス対策の法的根拠としては、イギリスでは住宅法、ドイツでは社会扶助法があり、フランスでは複数の法で対応している。
野宿者に対する支援については、いずれの国も、シェルター等の滞在施設、食事提供、医療面の支援を行っている。
イギリスでは恒久的住宅を確保したり、精神障害、アルコール、薬物問題を重視し、これらの専門家チームを作ってアプローチしている。
元野宿者の生活を再構築して、野宿に戻らないようにする施策として、イギリスでは、賃借権維持チームの設立や、家具の修繕等のプログラムによる、給付に依存する生活から雇用への移行を図る支援がなされている。
フランスでは、社会参入宿泊施設から社会住宅への移行の道筋が作られており、そのために必要なケアを併せて受けることができる。また就労支援として、企業での職業養成実習、雇用契約等が国の補助を受けて行われており、職業訓練として、民間団体が精神的身体的に問題を抱えた人(野宿者も含まれる)を非営利組織等に派遣、そして技能水準が上がれば企業に派遣する、といった取り組みをしている。
さらに、新たな野宿者の発生を予防するために、ドイツでは自治体が滞納家賃を肩代わりする措置を行っている。
日本では「自立支援法」が出来て間もなく、その運用の仕方を含めた今後の施策が問われている段階である。
これらの欧州諸国に比べると予防目的の施策や社会再参入に必要な就労面や住宅面でのバックアップがまだまだ薄く、これらの事例から学ぶことは多い。
○ イギリスにおけるホームレス問題は、複合原因説が大体合意を得ており、住宅法の中でホームレスの定義やその対策の法的根拠を示している。
ホームレスの現状としては、1991年のピーク時で約145,000人(イングランドのみ)、1995年で約121,000人と減少傾向にあるが、ティーンエイジャーのホームレスについては増加傾向にあり、雇用、家族問題、ドラッグ等の問題がクローズアップされている。
(注)イギリスにおけるホームレスの定義
1)占有できる住居を持っていない状態にある世帯の一員
2)家があってもそこに立ち入れない場合、住むことが許されていない車両や船で生活している場合、家があってもそこに継続的に住む理由を持っていない場合
3)28日以内にホームレスになる可能性のある場合
○ イギリスの地方政府においては、ホームレスに対し、1)助言と情報を無料で提供する、2)優先的なニーズを持つホームレスに対して、住宅手当と実際に住居を得るための援助を行う義務を負っており、この期間は2年で更に継続が可能である
しかし、住宅が不足しているために恒久的な住宅に移れず、ホステル等の臨時施設に住んだり、路上に出るなどの問題があり、住宅の確保と保健・福祉サービス、就労援助など総合的な支援が必要となっている。
○ 近年では、首都ロンドンを中心とした野宿者対策が重点課題として取り上げられ、1)「社会的排除」を防止するため、住宅、保健、雇用などを含めたサービスが受けられるよう戦略全体を調整する責任を持つ省を定め、2)これを監督するための内閣委員会を設立し、年1度の報告義務を設ける、3)全体目標として2002年までに野宿者の数を3分の2まで減らす、4)予防のために、刑務所・保護観察サービスの改善、退役軍人へのサービスの改善等を行う、5)雇用への援助を集中的に行う等が強調されている。
○ フランスでは、住宅問題を抱えた者を施策の対象とし、その数は、ホームレスが20〜40万人(個人の自治的住居に居住していない者、施設入所者を含む)、住宅最低限基準に満たない住宅の居住者が200万人で計220〜240万人と言われている。
しかし、宿泊所や一般的住居入居を待機する「一時的住宅」が普及しており、長期の野宿生活者はほとんどいない。
○ ホームレスだけの制度は隔離につながることを理由に、ホームレス対策についての単独法はなく、住宅対策、失業対策、生活扶助等の一般対策において取り組む形で進められている。生活扶助(RMI)は25歳以上であれば、民間認可団体、福祉事務所に住所登録さえすれば、支給が行われている。
さらに、民間アソシエーション(貧困援助団体)が早くから地道に活動しており、それがホームレス対策の改善につながっている。
○ 1998年7月に「反排除基本法」が制定され、その中で各省庁に横断的に施策の責任を担う部局を設置し、目標を立てることによってどれだけの問題を解決するか、そして目標未達成の責任はその部局が負うことを明確に示した。
また、トラス(TRACE)という国庫補助雇用を新しく設置し、ソーシャルワーカーが福祉領域に限らず、雇用政策、住宅政策においても援助を行っていくこととしている。
さらに、課題としては、宿泊施設からノーマルな住居への入居と、補助雇用から一般的雇用の確保が挙げられる。
○ 日本では失業保険の受給期間が終われば生活保護までの支援制度はないが、ドイツでは失業手当(失業保険)が2年8ヶ月支給され、その後も失業していれば無拠出の失業扶助が受けられる。
これは生活保護ではなく労働行政の分野で、失業手当より支給額は減るが、無期限で受けられる。
○ ドイツでは困窮者がホームレスになる前に、予防措置を取るように法律で定められている。例えば家賃が払えずに強制退去を命じられそうな場合にはまず福祉事務所が家賃を立替えて、とりあえずその人が家を出なくて良い状況を作り、それからケースワークを始めるという予防的なやり方が全国的に取り組まれている。
○ またすでにホームレスになってしまっている人に対しては、NPO等がいつでも利用できる場を提供し、そこで決して強制ではなく自発的に様々な援助が受けられる。そして自立したいという気になれば、今度は生活扶助(生活保護)法72条による手厚い援助を受けながら、普通の住宅で暮らせるように自立していくこととなる。
○オランダではホームレス、ルーフレス、社会の落ちこぼれになるマージナルな人が約3万人とも言われている。多くはアルコール依存症、薬物中毒などから社会とのつながりを保つことが困難になってしまった者である
○「生存権の保障」という概念の下、オランダでは生存権を保障するためオランダに合法的に住んでいる者には、各自治体が月額720ユーロ(約9万円)の生存金を無条件で支給している。オランダのホームレスはこの中から施設利用費用、食事代として550ユーロ程度を天引きされ、残りの170ユーロほどを小遣いとして受け取ることができる。
○全国に何千という規模のNPO福祉施設をホームレスは住所として使用することが可能である。
○ アメリカでは、1987年に作られたスチュワート・マッキーニ法により、連邦政府が法的根拠とホームレスの定義を示している。
マッキーニ法では、ホームレスに対するプログラムを策定し、それに補助金を出す仕組みとなっており、社会とホームレスの相互責任の原則を強く打ち出している。
(注)アメリカにおけるホームレスの定義
1)夜間において定まった住居がない者
2)一時的宿所(シェルター、福祉ホテルなど)に泊まっている者
○ ニューヨークでは1994年にホームレス支援計画を策定し、具体的な改革の内容、目標、実施計画をつくり、その方向で施策を行っている。
その内容は、1)路上や公共の場所にいるホームレスに対する相談支援(アウトリーチ)、2)アセスメントシェルターで家族は10日以内、単身者は90日以内に行うアセスメント、3)特別な援助を必要とするホームレスに対するサービスの強化、4)雇用と職業訓練を関連させた経済的自立への援助、5)援助を受けると同時に責任も果たすという相互責任の原則、6)恒久的な支援ができるよう住宅供給の機会を増加させる等が挙げられている。
また、実施計画には、アウトリーチ、サービスプログラムの策定、住宅取得の援助等が盛り込まれている。
○ 各種施策においては、民間団体や非営利団体の果たす役割が大きい。
| 付表 イギリス、フランス、ドイツのホームレス支援策等の概要 |
|
|
|
|
|
|
|
|
イギリス |
フランス |
ドイツ |
|
ホームレスの 定義 |
①占有することができる住居を持っていない状態にある世帯の一員、 ②家があってもそこに立ち入れない場合、そこが住むことが許されない車両、船である場合、③そこが継続的に占有する理由をもっていない場合、④28日以内にホームレスになる可能性がある場合 |
短期間で自治的な住居にアクセスできる展望のない人々:①宿泊センター・受け入れセンター入所者、 ②ホテル・家具つき部屋等の居住者、③第三者宅での居候のうちで住居アクセス手段のない・余儀なくされた宿泊者、④ロマ人等キャンピングカーや一時しのぎ住宅居住者、SDF(=住所不定者) |
賃貸借契約上、保障された居住空間を持たない人。路上生活者だけではなく、一時的に知人の家に宿泊している人、安い簡易ホテル、一時的滞在施設に入所している人等も含む広い概念 |
|
ホームレス数 |
104,770人(イングランド・1999年) |
約730,000人(1998年) |
550,000人(1999年) |
|
野宿者数 |
703人(イングランド・2001年), 357人(ロンドン・2001年) |
不明 |
26,000人(1999年) |
|
ホームレス対策の法的根拠 |
住宅法(1977年) |
ホームレスのみを対象とした法律はない。参入最低限所得手当、住宅扶助、普遍的医療保障法、「社会的排除と闘うための法律」等で対応。 |
社会扶助法(1961年) |
|
野宿者対策 |
①野宿者に 対する施策 |
シェルターの設置、医療サービス、恒久的住宅の確保、精神障害・アルコール・薬物の専門家チームによるアプローチ等 |
豗)無料電話による緊急対応、 豩)緊急援助(医療、食事、寝具等) |
「敷居の低い扶助」(日中滞在する施設、食事提供、移動医師、臨時宿泊所、社会扶助の基準額支給) |
|
②元野宿者の生活を再構築し、再び野宿に戻らないようにしていく施策 |
豗)芸術活動やワークショップの実施(野宿者に自信を持たせる施策)、豩)賃借権維持チーム設立(仕事や訓練機会提供を通して住宅の賃貸契約が維持されるよう支援)
豭)給付に依存する生活から雇用への移行(路上新聞、家具の修繕、ガーデニング、運転免許取得等のプログラム) |
社会参入宿泊施設→社会的レジデンス("住宅")→社会住宅へと移行。この間、医療保障、メンタルケア、ソーシャルワーカーの相談、家賃補助等が受けられる。就労支援として、企業における職業養成実習、企業の雇用契約(国の補助を受けての公的就労)、派遣による就労困難層の職業訓練 |
住宅獲得後のソーシャルワーク援助 |
|
③新たな野宿者の発生を防ぐための施策 |
犯罪歴のある者や軍隊経験のある者に対して、住宅、各種給付に関する相談の実施 |
|
「特別な場合の生活扶助」(自治体による滞納家賃の肩代わり措置) |
○引用・参考文献:(1)福原宏幸編(2002):小特集:ヨーロッパにおけるホームレス問題への挑戦.経済学雑誌,102巻
3・4号,1-55.
(2)嵯峨嘉子(2002):ホームレスと社会扶助.雇用政策と公的扶助の交錯,御茶の水書房,東京,pp.203-219.
今後のホームレス支援のあり方
ホームレスがいない、もしくは新たなホームレスが出ない社会こそが本来望まれるべきだと私は考えているのだが、現在の社会的風潮などから察するにそのような社会を望むこと自体が非常に困難な時代だと痛感する。
この章では総括として、今後のホームレス支援のあり方について考えていきたい。
最も重要になってくることとして、行政とNPOの連携があげられる。私が研究を始めた当初は、両者はあえていうならば対立関係にあった。このような関係になってしまった大きな要因として、行政とNPOでのホームレス自立に対する考え方の相違や共通のミッションを持たなかったことが考えられる。
そこにホームレス自立支援法という一つの共通点を作り出したことから行政とNPO の連携が成り立つようになった。この共通点にはまだまだ意見の争いはある。しかし、それまでのようにNPOないしボランティア団体が路上から自立への全てのプロセスを背おわなければならなかった状況からかんがみれば、行政とNPOが得意な分野、またはそれぞれでしか担当できない分野を役割として分け合うことでより効果的な支援体制が構築できるという可能性は現在の活動からも十分にある。
また、ホームレス問題が解消されない原因として日本の行政・企業・社会は、リストラされた人間を受け入れる体制を十分には整えていない。にも関わらず、企業はリストラを基本とする欧米式経営手法を積極的に導入、行政もそれを許容している。この不一致が、リストラに伴う生活破綻に備える消費行動の自発的自粛や日本経済の悪循環を引き起こしている。日本経済を好循環にのせるためにも、政策の見直し、または、行政による失業者のソフトランディングの充実が切望されている。
政策の見直しについては、かつてルックイースト政策を提唱したマレーシアのマハティール元首相のように、日本は米国式を脱却する必要があるという意見がある。その根拠として、欧米流のリストラ→再就職の循環による産業構造は、終身雇用制を基準とする日本文化と日本の社会制度に適合しないことがあげられる。欧米式政策を導入したこの10年が日本経済の低迷時期と一致することが、その事実を示している。
ソフトランディング策については、フランス・カナダの例が参考になる。フランスでは、失業者は社会への貢献活動を行っている間は、手当を受けることができる。 カナダでは、失業者も家・医療の保証がある。このように、路上からの社会復帰のプロセスの見直しと同時に不況下における失業者を路上に出さないような政策なりを考える必要がある。
ホームレス問題は、さまざまな要因が絡んで発生しているといえる。社会構造から個人の心の問題まで実に複雑である。ホームレス問題が新たなステージに入ったといえる現在、柔軟な考え方での解決が求められている。
付記
研究を通じてホームレスに対して多くの人が持っている様々な意見に触れる機会を得た。ネット上ではホームレス自身が意見を述べているブログも出てきている。情報を提供して下さった全ての人に感謝してこの論文の結びとしたい。
・松繁逸夫・安江鈴子著 「知っていますか?ホームレスの人権」解放出版社
・小玉徹著 「ホームレス問題 何が問われているのか」岩波書店
・櫛田佳代 「ビックイシューと陽気なホームレスの復活戦」株式会社ビーケーシー
・岩田正美『ホームレス/現代社会/福祉国家「生きていく場所」をめぐって』明石書店
・朝日新聞
・東京都福祉保健局 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
・特定非営利法人 釜ヶ崎支援機構 http://www.npokama.org/
・ふるさとの会 http://www.d5.dion.ne.jp/‾hurusato/
・ミッドナイトホームレスブルー http://blog.livedoor.jp/kenjiro45/