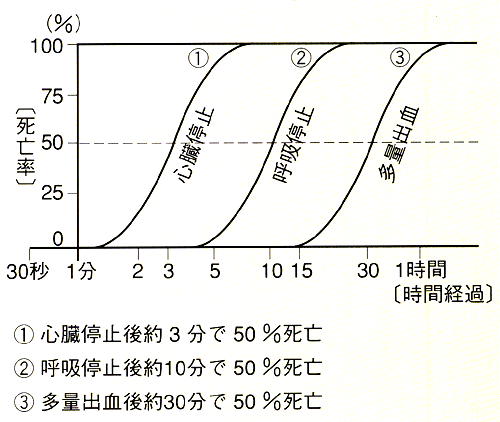早稲田大学社会科学部上沼ゼミⅡ
平塚直大 ホームページ
上沼ゼミは政策科学という学問分野を専攻するゼミです。
このホームページは上沼ゼミ生、平塚直大の研究発表ページです
今年度の研究テーマ
ドクターヘリ導入の過程と災害時の航空機利用
目次
- 序章 研究動機
- 第1章 ドクターヘリとは
- 第2章 80年代からの研究
- 第3章 阪神大震災前後の政策、運用の変化
- 第4章 阪神大震災から現在までの制度と新制度の比較
- 第5章 新制度と実際の運用の比較
- 第6章 政策提言
序章 研究動機
私の研究テーマは「安全な日本の再生」です。ここで、「安全な日本の再生」という言葉を使いましたが、何を以って安全といえるのでしょうか。もちろんこれは多様な意味を持ちます。ある面では、国家の安全保障、治安維持やテロ対策といった伝統的な(または夜警国家的)ものがあるでしょう。また、別の面では雇用や社会保険といった面があるでしょう。これらは、それ単体でも、非常に重要なテーマです。
では、何故このテーマを、そしてドクターヘリとおいうテーマを選らんだのか。これには二つの理由があります。一つは自分の経験によるもの。もう一つはドクターヘリが上記の夜警国家的な「安全」と福祉国家的な「安全」と言うものの隙間を埋める、両者の性格を併せ持つものであると言うことです。
前者の理由では、私が小学生だった95年当時、社会は阪神大震災とオウム真理教によって引き起こされた、テロ事件で動揺していました。そして、私自身も直接的には巻き込まれなかったものの、テロの方に関わりを持つことになりました。この二つの出来事、特に後者は非常に大きな出来事として記憶に残っています。それまではどこか遠いことと思っていたようなことが自分の身の周りで起きたことが非常にショックな出来事でした。そして本当に自分が死んでいたかもしれないとも思いました。これが、危機管理や安全といったものに興味を抱く、最初で最大のきっかけとなりました。
また、阪神大震災時に各方面で議論されれいた、日本の危機管理体制の欠如というも問題もこの時期にあわせて、私の記憶に強く残りました。
そして、後者の理由について述べると、この夜警国家的な安全観と福祉国家的な安全観を別個のものではなく、「安全・安心」のためにひとつのものとして考える必要があるからです。
夜警国家的な安全観と福祉国家的な安全観という表現を使いましたが、概念としては往々にして対立的に捉えられるます。片や、警察力や軍事力に注力し福祉を削減するもの、
片や、それとは正反対のものとして。しかし、以下本論にて述べるように「安全や安心」というものには両方の考え方必要であり、ドクターヘリはそれに対応するものと言えます。
つまり、医療問題への解決策の一つとして(福祉国家的側面)と大規模災害やそれに類似する事態への対応(夜警国家的側面)という具合です。
こうしたテーマを掘り下げることにより、現在、少なくない人間が安全ではないと感じている状況に対して何らかの結論が出せればと思い、このテーマを選びました。
第1章 ドクターヘリとは
1.ドクターヘリの歴史
1-1 航空機の黎明期
ドクターヘリの歴史、航空機を医療分野に使用するという考え方の起源を見てみると、意外にも古いところにあることがわかった。病院等の
患者が集中する拠点から他方の拠点へと移動するために長距離・大量輸送手段としての使い方はもちろん、後に詳述するようなドクターヘリ的な運用も早くから考えられたいた。
これらの例を挙げていくと、二つの面白い例にあたる。一つは近年、「日本の航空機開発の父」として注目を浴びるようになった二宮忠八(1866~1936)。彼が航空機開発を志した理由の一つが、彼が衛生兵として参戦した日露戦争の経験にあると言われる。彼は、前線で傷病者の治療に携わるなか、前線から施設の整った場所に傷病者を迅速に送るために「空を飛んだほうがいいのでは」と考え、飛行機の開発を志したともいわれている。もう一つは戦間期~第二次世界大戦前半のドイツの例。当時の最先端技術であった水上機にこれも当時の最先端技術であった心電図と電気毛布を搭載して、衛生兵(これは軍が運用していたため)や医師を搭乗させたもので、漂流者の救助にあたっていたという例がある。ドクターヘリの特徴の一つは、現場に医師を派遣し専門の機器・薬品で迅速に治療を開始する、というものがある。こうして見てみるとこの戦前のドイツの例は、この特徴を備えているといえる。また、ドクターヘリというものがドイツで最初に誕生したことと併せて考えると興味深いものがある。
もちろん、こうした例は明確にドクターヘリというものが概念として確立されていた時代のものではないし、この時代にドクターヘリ
というものが考えらていたとは、(少なくとも私は)確認できなかった。しかしこうした事実は、特に重症の患者の治療に当たっては迅速な
治療の開始と搬送が必要であり、そのために航空機は有効な道具であると認識されていたことを物語っている。
1-2 1960年代からの発展
本格的にドクターヘリという概念が成立し、実際に使われるようになるのには1960年代になるのを待たなければいけなかった。これには二つの要素がある。一つは技術的なもの。もう一つはベトナム戦争である。前者に関してはある意味簡単な話であり、ヘリコプターというものが技術的に確立したものとなり、一般的に使われるようになったのが1960年代であるということである。次に後者についてであるが、これがドクターヘリの直接の起源となったものである。ベトナム戦争においてアメリカ軍は初めてヘリコプターを大々的に使用したが、その利用方法の中には負傷者の救難・搬送(コンバットレスキュー)というものがあった。これが、ベトナム戦争における米軍の死者を大きく減らすことが出来た要因となった。これが可能となった背景にはやはり、ヘリコプターの普及によるところが大きい。つまり、固定翼機とは違い着陸場所を選ばず且つ航空機としての速度を持つヘリコプターを導入したことで、負傷者の居るところに直接着陸し迅速に搬送することによって成し遂げられたことといえる。これが、ドクターヘリの直接のヒントになった。
このベトナム戦争の戦訓に目をつけたのが、交通事故死者の増加(年間二万六千人)に悩んでいた1960年代後半のドイツであった。ドイツでは、特に重篤な事例に陥る事例が多かった高速道路での事故対策にADAC(ドイツ自動車連盟、日本のJAFに相当)が医師をヘリコプターに搭乗させ現場に搬送し、治療を開始するドクターヘリのシステムを開始した。これがドクターヘリの始まりである。このシステムは、ドイツにおいて交通事故死者の削減に大きく貢献し、運用が開始された1968年には年間二万人を超えていた死者数を現在では七千人台にまで低下させる効果を見せている。これが一つの先行事例として、欧米にこのシステムが広がっていくことになった。
2 ドクターヘリの特徴
ここまで、ドクターヘリの歴史を見てきたがここではドクターヘリの特徴、利点を見ていきたいと思う。これについては、歴史の項で、
少々触れたが、そこから利点を抜き出すと以下のようになる。
①医師の現場到着までの時間を短縮できる。
②治療開始までの時間を短縮できる
③搬送中も治療を継続することができる。
④広範囲の事態にも対応できる。
以上が特徴のなかでも利点といえる。これらの特徴について言えば、着陸場所を選ばないヘリコプターだからこそ可能であると言える。
特に①~③について言えば、歴史の項でも触れたように、重傷者の治療においては負傷から治療開始までの時間を短縮することが重要であるということである。この治療開始までの時間短縮の重要性を示したものとして、「カーラーの救命曲線」というものがある。
これは、1981年にフランスの麻酔科医のカーラー博士が発表したものである。以下にこれを示す。
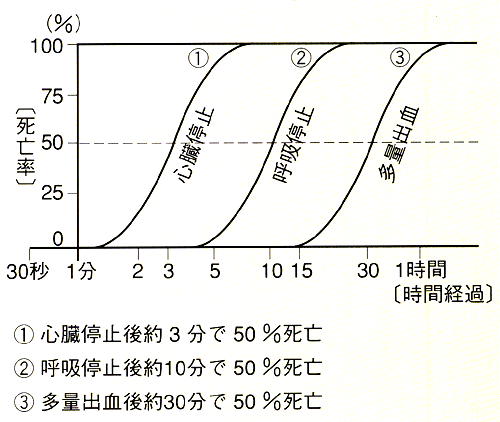
国立大学法人大阪教育大学HPから転載
この図は心臓停止、呼吸停止、大量出血という致命傷に至る症状について縦軸が死亡率、横軸が治療開始までの時間を表している。
みて分るとおり、こうした症状に対してはとにかく迅速な治療の開始が生死を分けるということが分る。この三症状の中では一番余裕
がある、大量出血でも30分経つと、救命率が50%に下がるということが分る。
次に弱点、不利な点を挙げていく。
①着陸場所の確保。
②コストの問題。
③ヘリポートの設置問題。
経過報告(7/31)
今年度に入ってから、ドクターヘリ及び航空医療に関しての大きな動きがあった。ここで主なものを報告する。
4/1 日本医大北総病院所属のドクターヘリが高速道路上での運用開始
4/1 和歌山県でヘリからの医師のホイスト降下開始
埼玉、福島、新潟、大阪の各府県で、07年度~08年度の導入を目指して検討開始。
5/9航空自衛隊小牧基地に航空機動衛生ユニット配備(小牧基地HP)
6/19ドクターヘリ特措法が成立(公明党新聞)
骨太の方針2007にも取り入れられる(pp.46~47)
今後の研究方針
上記のように、現在の動きを見るとドクターヘリや航空機を救急医療(災害時を含む)の社会的な認知や必要性の認識は、一定の範囲で獲得されたといえる。
そこで、これからの研究は導入の促進という観点からだけでなく、このたび成立した特措法を中心にこのテーマにまつわる法制度や政府の政策といった面からアプローチしていきたい。
特措法の概要と政策の流れとしてのドクターヘリ
前回予告したとおり、成立した特措法の概要をここでかいつまんで見てみる。
まず、多くの方が疑問に思われるのが、ドクターヘリと他の防災ヘリとの違いだろう。この法律では
ドクターヘリを「医療器具や薬品を搭載。同時に医師が搭乗し、速やかに傷病者のいる場所に赴き、
治療を開始することに供されるヘリコプター」と定義している。
対して、防災ヘリに関しては、「災害時に、消火、救助、情報収集といった多様な任務が与えられているヘリコプター」
という定義が、政府の見解としてなされている。
つまり、ここでは防災ヘリよりドクターヘリのほうがより救命に特化している。だからこそ、導入すべき
という政府、法案提出者の考え方も読み取れる。
次に、この法律で想定されている最策実行の流れと伝統的な政策の流れを比較してみる。
伝統的な政策形成・実行のプロセスは、国(中央省庁)を頂点に据え、さまざまな圧力集団がその国に要望を出す。
次に、国の側はそれを他の利害関係者との協議や調整を経て、法もしくは政省令として成立可能かどうかを審議する。
可能であるとされれば、与党の事前審査を経て国会で成立して政策として実行に移される。そして国からその政策を実行
する側に人、モノ、金が流れていくという、典型的なヒエラルキー構造となっていた。
対して、今度示されたドクターヘリ特措法の方は、まず政策としての出発点が国や圧力団体ではなく大学と社団法人が出発点にある、
というのが大きな特色であると言える。ドクターヘリは日本においては、80年代に交通事故死対策として大学の自主的な研究として
開始された歴史がある。その成果が社会に公開されて、政治(政党)が目を向け国会で取り上げられる。というプロセスを辿り、
昨年成立した。
ただ、政策の流れとしてみると、決して平坦な道のりとは言えなかった。それは、実験が開始されてから法制化されるまでに20年以上の
時間がかかっていることからもわかる。ここには、一つの政策(ドクターヘリ)が採用されるまでには問題点の変更があった。
前述したように、ドクターヘリは交通事故対策として日本でも研究が始まった。しかし現在は医療崩壊、医療過疎対策としての視点が重視されるている。
当初の目的である、交通事故対策が、道路や信号の整備、救急救命士制度の導入によって一定の落ち着きを見せるとよりコストや法律の改正が煩瑣になる
ドクターヘリは政策の場からはフェードアウトしていった。しかし、近年の救急医療、特に搬送に時間がかかることが問題視され始めて再び注目を集めるようになった。