| ○1章 日本の現状(国債依存) |
平成22年の予算は92億円にのぼり、過去最大の支出となりました。なかでも特出すべきは国債の返済に予算の2割以上を当てていることです。
20兆円以上ものお金を国債の返済にあてているものの、国債残高は拡大するいっぽうです。
というのも、所得税などを始めとする租税収入は全体の40%弱に過ぎず、公債を発行することによって、その不足分を補っているからです。
つまり国の歳入の半分はわたしたちを含む将来世代から借金をしているということです。
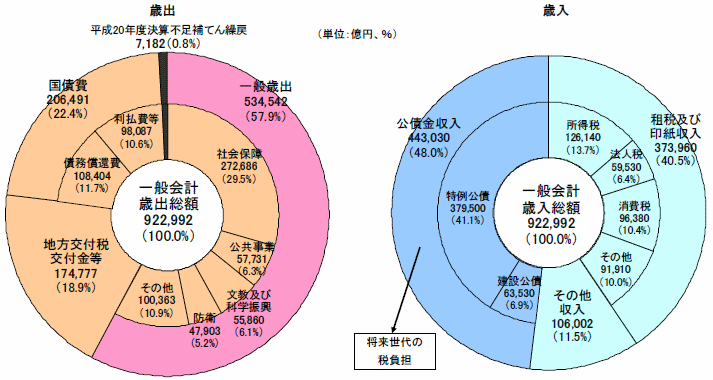
[出典:財務省]
歳出における国債より歳入に対する国債のほうがはるかに大きいため、公債残高は増える一方です。
その額は今や600兆円を超えています。この額は国民一人当たり約500万円負担していることになります。
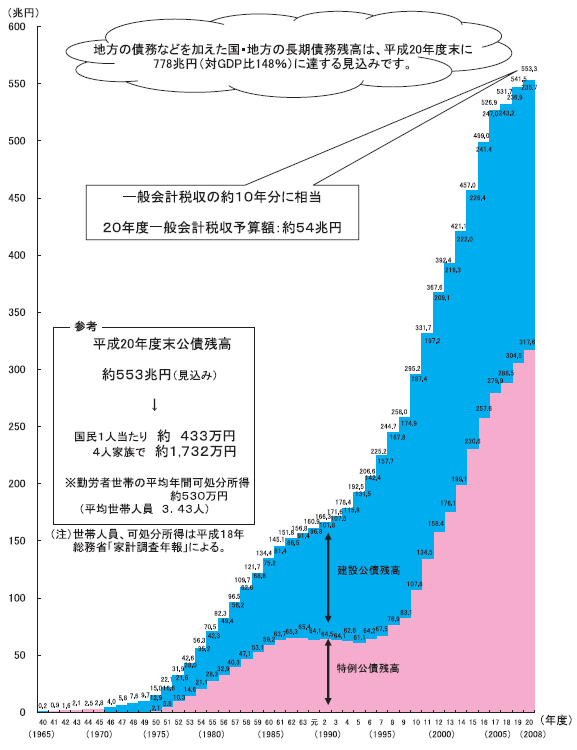
[出典:財務省]
では、日本は安全なのでしょうか。これから検討していきたいと思います。
日本の総貯蓄率は外国に比べて高いので、その貯蓄を使って銀行などが国債の購入をしています。
その貯蓄の額は1400兆円。どのように購入するのか具体的にいうと、まずわたしたちはお金を銀行に預けます。銀行はその預金を使って企業に融資したりします。
その一例が国債の購入です。国債は一般的な債券に比べ、金利も高く、さらには国が返済債務を負っているという非常に魅力てきなものであるため、銀行も購入するのです。
そして国債の買い手のほとんどは国内企業で、海外の買い手は5%くらいです。
ここで、破綻の危機に瀕しているギリシャを日本の比較としてあげたいと思います。 ギリシャの国債は買い手の70%を海外に依存しています。ここが日本との決定的な違いです。つまり、国債による資金調達を国内でするか海外でするかです。 ではこの海外への依存が破綻危機を生んだのか分析したいと思います。 EUでは対GDP比の赤字額が3%以下に義務付けられていました。2008年ギリシャは対GDP比での財政赤字額は3~6%と、3%の基準は守れていませんが、 ひどい状態とは判断されませんでした。ところが、その後政権が変わると12%と発表されました。これにより、ギリシャに対する信用が低下し、国債は利子を 高くしても売れなくなりました。そのため返済期限が迫った国債の借金も返済できない状態に陥りました。これによりギリシャは破綻の危機に陥りました。 ここでは例としてギリシャをあげたため詳しく触れませんが、デフォルトが起きたら、国債の買い手である諸外国にも多大な損害を与え、とくに財政が苦しい スペインなども連鎖的に破綻する恐れがあるので、EUは13兆円の融資、IMFは3.5兆円の融資を決定しました。 結論はギリシャは国債を海外に依存し、国内で資金調達をできないため破綻の危機にあります。 財政赤字が拡大しても、通貨をどんどん発行してインフレにすれば、赤字額の相対的価値が下がり、借金が返済できる可能性もあります。 しかし、ギリシャは自国で通貨を発行していないので、それができません。日本は国債を国内の貯蓄を依存しており、破綻危機に直面してもすぐには破綻しません。
| ○2章 資金調達方法 |
1.消費税増税について
以前増税した時、どうだったか検証したいと思います。

[出典:財務省]
この図はここ数10年の税収の動きを示したグラフですが、注目してほしいのは消費税を5%に増税した平成9年です。
この年、税収は増えていますが、それ以降は同水準まで税収は回復していません。ここからは増税の効果は短期的で、長期的にはないと読み取れます。
ですが、増税は本当に効果がないのかを次に検証したいと思います。

[出典:財務省]
平成9年以降をみてもらうとわかるとおり、消費税による税収はほぼ一定の数値をとっていることから、消費税増税による効果はあることがわかります。
よって増税によって、一定の安定した税収は見込むことができます。
ですが、この図からはさらなる問題が見て取れます。まずは法人税です。この2年間は世界的大不況の影響を受けて、企業の売り上げが激減し、税収が減っています。
今日日本の法人税は高すぎるので、国際競争力をつけるためにも減税しろと要求されていますが、それは事実でしょうか?
次に所得税です。所得税による税収は平成2から3年にかけて最大でたが、このときの最高税率は60%でした。法人税にも言えることですが、
さらにこの時期はバブルと重なったこともその要因でした。ですが、その後、所得税は下がり続け、現在最高税率は40%です。
消費税増税は一定の効果があるが、現在の日本は超過供給のため消費や設備投資を低下させる。
よって、税収増加を消費税だけに頼るべきではなく、増税は最小限にするべきです。
2.法人税は高いか
実際日本の法人税は高いのか、諸外国と比較してみたいと思います。

[出典:財務省]
この図をみると、日本の税率はアメリカと並んで、高水準にあることがわかります。これだけみるとやはり日本の法人税は高いから、
引き下げなければ国際競争においていかれると主張するのは当然のことと思います。ですが、次の図からは違うことが読み取れます。

[出典:しんぶん赤旗]
図の下のほうを見てもらうと先ほどの図では法人税は40%だったのに、実際に大手企業の負担している税率は33%です。なかでもソニーに至ってはわずか13%です。
以上の図をとおして法人税は高いのかという問題について掘り下げたいと思います。
まず始めに日本の法人税は高くありません。その理由は2つあります。
1つは優遇措置が認められている(減税、税額控除など)ことです。例:海外進出している企業は外国税控除
問題は2つ目です。社会保険料を無視して法人税を考えてはいけません。なぜなら企業は社会保険料も負担しなければいけないからです。
これは他の先進国より負担が低いです。フランスやドイツの7~8割ほどです。
3.所得税の意義
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 330万円以下 | 10% | 0円 |
| 330万を超え900万円以下 | 20% | 330,000円 |
| 900万円を超え1800万円以下 | 30% | 1,230,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,490,000円 |
以上から見える改善点は?
330万以下の低所得者に対し低い税率を設けた一方で、695万以上の所得者に対し高い税率を設けるようになった。
低所得者に対し高い控除額を設けた。一見、所得格差の是正を図る政策のように見える。しかし、本音は社会保障費などの財源確保のためである。
所得税増税の意味
建前:所得格差を是正し、公平な社会の実現
本音:社会保障費などの財源確保
+面:確かに垂直的税であるので、格差是正につながるというメリットがある。
-面:所得税は現役世代だけに課される負担、高齢者の負担を現役世代だけに求めている。
以上から所得税増税はすべきでなかった。
ではなぜ、増税に至ったのか、実際のところは反対の声は大きかった。しかし、政府にとってそれはどうでもいいこと。
なぜなら、反対する若者は自分たちに興味がないからです。逆に高齢者に負担を強いることは不都合になります。
なぜなら、高齢者は自分たちに関心があるからです。政府(政権)にとって高齢者を手厚く保護することが現体制の維持につながるのです。

[出典:]
| ○3章 これからの課題 |
| ○参考文献 |