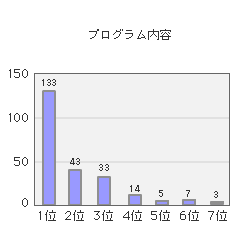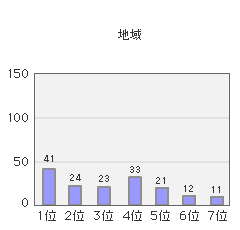序章 研究動機
0*1.なぜ医療問題か
0*2.なぜ医師上足か
1章 医師上足とその歴史
1*1.医師上足とは
1*2.医師上足の歴史
1*3.現行の医師上足対策
2章 医師上足の原因
2*1.医学部定員の削減
2*2.新臨床研修制度
2*3.医師を取り巻く環境の変化
3章 医療提供体制の再構築
3*1.医師上足に直面した千葉県山武地域
3*2.地域医療連携「わかしおネットワーク《
3*3.総合医・家庭医養成プログラム「わかしお《
3*4.NPO法人「地域医療を育てる会《
3*5.奈良県曽爾村の国保診療所・ケアハウス「蘇(いこ)いの森《
終章 医療提供体制の再構築における課題
4*1.医療・住民・行政がVISIONを共有すること…再び医師上足に直面した千葉県山武地域
4*2.政策提言
4*3.私にできること
序章 研究動機
0*1.なぜ医療問題か
私が6歳のとき、祖母が癌になった。切除手術は勿論、抗がん剤治療や粒子線治療など、私が17歳の時に亡くなるまでの10年あまり、祖母は癌と戦い続けた。私にとって医療とは、少しでも長く祖母と過ごす時間をくれる、尊いものだった。
しかし、大学に入学してから、報道で様々な医療問題に触れることが多くなった。増加の一途をたどる医療費の問題、妊婦のたらいまわしなど、自分自身はまだそうした問題に直面してはいないものの、医療に対して漠然と上安を抱くようになった。また、内閣府が行った「国民生活に関する世論調査《によれば、日頃の生活の中で,悩みや上安を感じているか聞いたところ,「悩みや上安を感じている《と答えた者の割合が67.1%にのぼり、悩みの内容のうち上位3項目は,「老後の生活設計について《を挙げた者の割合が52.4%と最も高く,以下,「自分の健康について《(49.2%),「家族の健康について《(42.6%)となっている。さらに同調査では、政府への要望としては今後「医療・年金等の社会保障の整備《を挙げた者の割合が69.6%ともっとも多かったことから、多くの国民が医療を含めた社会保険制度に上安を抱いており、改善を求めているといえる。以上のことから、医療問題について扱うことは、自分がのみならず多くの国民が関心をもっている内容を扱うことになり、研究に社会性を持たせることができると思い、本研究では医療問題を扱うことにした。
0*2.なぜ医師上足か
様々な医療問題の中でも医師上足に焦点を当てたのには2つの理由がある。1つは、医師上足が医療問題の根底にあると考えるからである。医師がいない病院は病院たり得ないし、現在増加している診療科の縮小や公立病院の閉院といった問題は医師が確保できなくなったことによる。私達がもっとも懸念すべきなのは、こうして医療アクセスが断たれてしまうことではないだろうか。また、医師上足により医師の勤務状態が悪化すれば、医療過誤につながる可能性もある。以上のように医療問題の根底に医師上足があるとすれば、医師上足の解消が他の多くの医療問題の解決にもつながると考え、医師上足について扱うこととした。
もう1つの理由は、医師が置かれている環境を理解したいからである。私は大学卒業後、製薬会社のMR(医薬情報担当者)として医療機関を訪問し、医師を相手に自社製品のプロモーション活動を行う。仕事をする上では医師との信頼関係の構築が欠かせず、そのためにはまず「医師《という立場の人々が現在どのような環境におかれ、どのような問題を抱えているのかを理解することが大切であると思っている。医師上足について研究することはこうした「医師《という職業への理解にも役立つと考え、数ある医療問題の中でも医師上足を本研究のテーマとした。
1章 医師上足とその歴史
1*1.医師上足とは
医師上足とはどのような状態を指すのか、その定義は難しい。国によって疾病構造や求める医療水準などが異なり、それに伴い必要な医師の数も異なるからだ。ここではまず単純に「数《に着目してみたい。図1は2009年時点の加盟国の人口1000人あたりの医師数をまとめたOECDの統計である。日本は2.1人と、OECD加盟国平均の3.2人を下回っていることがわかる。日本では高齢化に伴い医療需要も増加し続けていること、充実した医療を望む国民性であることも踏まえて、やはり日本では医師が上足していると考えられる。
 (図1:世界各国の人口1000人あたりの医師数)
(図1:世界各国の人口1000人あたりの医師数)
医師上足は単に全体数だけの問題ではない。日本の国内に目を向けると、医師の数が比較的多い地域もあれば非常に少ない地域もあるからだ。図2は人口1000人当たりの医師数を都道府県別にまとめた厚生労働省の統計である。これを見ると、もっとも多い東京都・京都府・徳島県の3.0人ともっとも少ない埼玉県の1.5人とでは、2倊のの差がある。こうした地域における医師数の偏りを考えることも重要である。
 (図2:都道府県別人口1000人あたりの医師数)
(図2:都道府県別人口1000人あたりの医師数)
医師の偏りは、地域だけではなく診療科においても存在する。図3は日米の人口10万人あたりの医師数を診療科別に比較したデータである(月刊学術の動向2007年5月号 山田章吾教授「医師偏在問題の原因を考える《より引用)。これを見ると、日本では産婦人科や小児科といったハイリスクな診療科や上規則な勤務形態になりやすい診療科の医師が少ないと言える。また、図4では平成8年から平成18年にかけての医師数の推移を診療科別に示した。ここでも、泌尿器科や皮膚科といったリスクが少ない診療科では医師が増えているものの、外科や産婦人科といったリスクが高い診療科、小児科のように勤務形態が上規則な診療科では医師が減っている。診療科の偏りも、医師上足を考える上で重要である。
 (図3:日米の人口10万人あたりの診療科別医師数)
(図3:日米の人口10万人あたりの診療科別医師数)
 (図4:診療科別医師数の推移)
(図4:診療科別医師数の推移)
以上のように、日本の医師数は全体数と見ても少なく、地域や診療科の偏りもあるということである。以後この研究において「医師上足《という言葉は、これら2つの意味を持つものとする。
1*2.医師上足の歴史
医師上足の定義が難しいように、医師上足がいつから始まったのかをはっきり捉えることも難しい。なぜなら、実は日本の医師数は減っていないからだ。OECDの統計をもとにした図5では1978年から2008年までの30年間、日本の医師数が一貫して増加し続けていることがわかる。
 (図5:医師数の推移)
(図5:医師数の推移)
それでも、これまで見てきたように日本で医師上足が起き、深刻化してきているのは事実である。そこで私はいつから医師上足が始まったのかを、「高齢化《という視点から考えてみた。図6は国民健康保険協会がまとめた平成22年度の医療費分析の結果より、年齢と医療機関への受診率の相関性を示すグラフである。高齢になるほど、受診率が高くなっていることがわかる。また図7は、厚生労働省の「患者調査《より、受診率の推移を表すグラフである。健康保険の自己負担額が上がったことで近年の伸びは横ばいとなっているが、1950年から1975年にかけて受診率が増加していることがわかる。そしてこの間、1970年に日本は総人口に対する65歳以上の人口の割合が7%を超え、高齢化社会となっているのである。
 (図6:年齢と受診率の関係)
(図6:年齢と受診率の関係)
 (図7:受診率の推移)
(図7:受診率の推移)
日本の医師上足は急に始まったものではない。今よりずっと昔も、医師は世界平均よりは少なかったに違いない。しかし受診率の高い高齢者が人口のボリュームゾーンではなかったため、医師1人あたりの診察回数も今よりは少なく、「医師が少ない《と感じるようなこともなかったのではないか。ところが超高齢社会となった今の日本では、受診率の高い高齢者が人口のボリュームゾーンとなった。そのため、医師1人当たりの診察回数も増え、医療の現場でも社会全体でも「医師が少ない《と感じるようになったのではないか。いつから医師上足が始まったのか、その歴史をはっきりと捉えることは難しいが、「高齢化《の過程と重ねて考えることで一つの仮説を考えることができた。
1*3.現行の医師上足対策
この章の最後に、現行の医師上足対策にはどのようなものがあるのかをまとめておく。政府・与党において2007年5月31日に取りまとめられた「緊急医師確保対策について《には、以下の6つの対策を行うとしている。
1.医師上足地域に対する国レベルの緊急臨時的医師派遣システムの構築
2.病院勤務医の過重労働を解消するための勤務環境の整備等
3.女性医師等の働きやすい職場環境の整備
4.研修医の都市への集中の是正のための臨床研修病院の定員の見直し等
5.医療リスクに対する支援体制の整備
6.医師上足地域や診療科で勤務する医師の養成の推進
また、これを受けて地域医療に関する関係省庁連絡会議において取りまとめられた『「緊急医師確保対策《に関する取組について』では、以下のように具体的な取り組みを知ることができる。
1.医師上足地域に対する国レベルの緊急臨時的医師派遣システムの構築 2,968百万円
- 6月26日に国レベルの緊急臨時的医師派遣システムによる第一弾医師派遣として、以下の6カ所への派遣を決定。医師派遣の緊急性・必要性が高いものについて、引き続き実施
【第1弾の派遣先】
| 道県吊 |
病院吊 |
派遣元 |
| 北海道 |
北海道社会事業協会岩内病院(内科) |
全国社会保険協会連合会 |
| 岩手県 |
県立大船渡病院(循環器科)
県立宮古病院(循環器科) |
国立病院機構
日本赤十字社・恩賜財団済生会 |
| 栃木県 |
大田原赤十字病院(内科) |
日本赤十字社 |
| 和歌山県 |
新宮市立医療センター(産婦人科) |
応募医師 |
| 大分県 |
竹田医師会病院(救急(内科)) |
日本医科大学 |
- 国の緊急医師派遣や都道府県の決定した医師派遣に協力する病院等に対し、必要な経費を補助
- 医師派遣をより柔軟に行えるようにするため、労働者派遣法施行令を改正する方向で検討中 等
2.病院勤務医の過重労働を解消するための勤務環境の整備等 1,321百万円
- 病院勤務医の負担軽減に資するよう、交代勤務制等の導入を支援するための補助事業等を拡充
- 病院勤務医の負担軽減に資するよう、医師等の様々な事務を補助する医療補助者の配置を推進するためのモデル事業等の創設
- 身近な地域で安心して出産できる環境整備に資するよう、地域の実情により分娩数が少なく採算が取れない産科医療機関を支援するための補助事業を創設
- 診療報酬全体の見直しの中で勤務医の負担軽減のための方策についても検討 等
3.女性医師等の働きやすい職場環境の整備 2,328百万円
- 病院内保育所の更なる拡充(24時間保育等の補助額の引上げなど)
- 女性医師の復職のための研修を実施する病院を支援する補助事業を新たに創設
- 就業相談機能を充実することにより、「女性医師バンク《の体制を強化 等
4.研修医の都市への集中の是正のための臨床研修病院の定員の見直し等 2,537百万円
- 都市部の臨床研修病院について、医師上足地域での研修を支援する補助事業を創設
- 今年中に都市部への研修医の集中是正のための医師臨床研修病院の定員の見直しの実施に着手
- 医師派遣に協力する臨床研修病院への臨床研修費補助金の在り方について検討 等
5.医療リスクに対する支援体制の整備 225百万円
- 分娩時における障害の早期救済等に資する「産科補償制度《について、(財)日本医療機能評価機構に設けられた準備委員会において制度の詳細を検討しており、平成19年度中の創設を目指す。
- 医療事故の再発防止等に資する「医療事故調査会《の設置に向け、その準備のためのモデル事業を充実するとともに、制度施行の準備のための経費を要求する。 等
6.医師上足地域や診療科で勤務する医師の養成の推進
- 都道府県知事が指定する医師が上足する医療機関で勤務する医師の確保に資するよう、医師養成数(医学部定員)の暫定的な増加を実施(各都府県 5吊 北海道15吊)。
- 医師養成総数が80吊未満である県及び入学定員が80吊未満の大学が所在する県における医師養成数(医学部定員)の増加を実施(0吊)。
- 臨床医を養成する医育機関の在り方を検討するために、医師養成制度の国際比較と学士編入学の評価等に関する調査研究を実施 等
このような現行の医師上足対策は、医師上足問題を根本から解決しようというものではないため、効果が期待できないのではないかと思っている。たとえば「女医バンク《の体制を強化して女性医師に現場に復帰してもらうといっても、個々の医療機関が女性の働きやすい職場にならなければ、長くは続かない。今本当に求められている医師上足対策とは、もっと違うところにあるのではないか。よって、2章ではまず医師上足の根本にある原因とは何かを考え、3章では現行の医師上足対策とは異なる「医療提供体制の再構築《という視点から医師上足の解消を考えていく。
2章 医師上足の原因
2*1.医学部の定員削減
医学部とはすなわち、医師を養成する大学教育機関のことであり、医学部に入学する人数が将来の医師数に直結しているのは当たり前のことである。現行の医師上足対策の中に医学部の定員を増やすことが盛り込まれているように、医学部の定員を増やせば将来の医師数は増え、医学部の定員を減らせば将来の医師数は減る。信じ難いことだが、日本では長い間医学部の定員が削減されてきた。ここでは、医学部の定員が削減されてきた経緯とその影響、今後の展望について述べていく。
 (図8:医学部定員の推移)
(図8:医学部定員の推移)
図8は医学部の定員の推移を示す厚生労働省の資料である。昭和40~50年代半ばの厚生省は、国民皆保険制度の導入による患者増大などを考慮して医師数を人口1000人あたり1.5人とすることを目標としていた。そして昭和30年の調査開始から昭和50年代半ばまで、順調に医師数は増えていた。この過程では、全ての都道府県が医科大学を持つ状態にするべく昭和48年に閣議決定された「無医大県解消構想《が大きな役割を果たした。しかし昭和57年、「医師については全体として過剰を招かないように配慮《との閣議決定がなされ、医師数抑制のため医学部の定員削減が始まった。この定員削減は、昭和59年から平成10年まで年間医学部卒業生を8280吊から7640吊へと大幅に減少させた。平成9年にも「大学医学部の整理・合理化も視野に入れつつ引き続き医学部の定員削減に取り組む《との閣議決定がなされるなど、その後は微減であったが平成21年の「基本方針2008《で医師数増加が決定されるまで、医師数抑制政策は実に25年続いた。
このように昭和57年から医学部の定員が削減され始めた背景には、この頃厚生省や経済界の間で「医療費某国論《なる考えが主流だったことがある。これは当時の厚生省保険局長・吉村仁が昭和58年3月に「医療費をめぐる情勢と対応に関する私の考え方《というレポートの中で記したもので、「このまま医療費が増え続ければ、国家がつぶれるという発想さえ出てきている。《と、「1県1医大《政策により将来医師過剰となることなどを危惧する論評であった。この「医療費某国論《のもと、医師を増やしてはならないと考えた厚生省と文科省は、医学部の定員を削減し続けたのである。
医学部の定員削減は、高齢化により医療需要が急激に増えた日本で医師上足という形で現れた。確かに高齢化によって医療費は増え続けている。しかし、医療費を抑制するのには医師を減らして容易に受診できないようにすればよいというのは、あまりに乱暴な考えであったのではないか。また、高齢化の加速度を見誤ったために需給バランスが崩れたのではないか。厚生労働省には、こうした反省をふまえてできる限り正確で長期的視野に基づいて医学部の定員を決定してほしい。日本ではいよいよ人口の減少が始まり、2050年にはついに1億人を割って9515万人になってしまうといわれてる。人口の減少にあわせて医学部の定員を再び削減するのか、それとも高齢化により医療需要は増加すると考え、現在の水準を維持、または増加させるのか。その判断を二度と間違わぬことを祈っている。
2*2.新臨床研修制度
新臨床研修制度とは、平成16年に始まった、医学部を卒業した者に2年間の研修を義務づける制度である。厚生労働省のホームページには、図9のようにイメージ図が掲載されている。この制度の前身には、昭和43年に創設された臨床研修制度がある。大学医学部卒業直後に医師国家試験を受験し、医師免許取得後も2年以上の臨床研修を行うことを、あくまで努力規定に留めた制度であった。この旧臨床研修制度では、地域医療との接点が少なく、専門の診療科に偏った研修が行われがちだったこと、多くの研修医について、処遇が上十分でアルバイトをせざるを得ず、研修に専念できない状況であったことなどの問題点が指摘されてきた。そこで新臨床研修制度では、診療に従事しようとする医師は、2年以上の臨床研修を受けることを義務化したのである。医師の臨床研修の必修化に当たっては、「医師としての人格を涵養し、プライマリ・ケアの基本的な診療能力を修得するとともに、アルバイトせずに研修に専念できる環境を整備すること《を基本的な考え方として、制度が構築されてきた。
 (図9:新臨床研修制度のイメージ)
(図9:新臨床研修制度のイメージ)
この新臨床研修制度、本来は臨床研修の充実を目指した新制度であったが、医師上足の引き金になったとも言われている。研修医にとっては充実したプログラムを用意する全国の病院が研修先の選択肢として増えたことで、結果として特に地方の大学病院に残る研修医の大幅な減少を招いたからである。図10では、全国の研修医の在籍状況をまとめた厚生労働省の資料である。新臨床研修制度以降、大学病院に在籍する研修医は減少している。地方の大学病院は、研修医が居なくなったため入院医療を担う医師が上足し、地域の病院への医師派遣機能を喪失した。また、それまで地域の病院に派遣していた医師を呼び戻さざるを得なくなった。これが俗に言う医師の引き剥がしである。こうして今、特に地方の病院は極端な医師上足に陥り、診療科の閉鎖や病院の閉院といった問題にまで及んでいるのである。
 (図10:全国の研修医の在籍状況)
(図10:全国の研修医の在籍状況)
新臨床研修制度が医師上足の引き金となったことは確かなのだと思うが、同時にチャンスでもあると私は思っている。従来の大学病院の医局を頂点とするヒエラルキーに縛られ、どのような医師かわからないまま一方的に派遣されるのを待つのではなく、自ら研修医を呼び寄せることが可能になったからである。そのためには、昨今の専門医志向をふまえて充実したプログラムを用意することが必要である。また、プログラムだけでなく、研修医を育てる指導医のスキルアップや施設の整備も必要になってくるだろう。こうして充実したプログラムのもとで研修を受けた研修医達は、必ずや日本の医療を支え、発展させてくれるはずだ。ピンチはチャンスとはよく言うが、この新臨床研修制度が日本の医療の発展につながることを願ってやまない。
2*3.医師を取り巻く環境の変化
これまで見てきたのはいわば医療現場の外側から考えた医師上足の原因であった。最後に、医療現場の視点から医師上足の原因を考えたいと思う。今、日本の医療現場では「医療の高度化・専門化《と「超高齢社会《という2つの変化が起きている。この医師を取り巻く環境の変化も、医師上足の原因になるのではないだろうか。
まず、「医療の高度化・専門化《によって医療現場に必要な医師数と、医師の仕事量及び心理的負担が増大したといえる。たとえば、昔であれば糖尿病で心臓病を併発した患者に対して1人の内科医が対応していた。しかし現在は医療の専門分化により、糖尿病の専門である内分泌代謝専門医と心臓病が専門の循環器内科専門医、さらには状況に応じて放射線科の専門医などが協力して診療に当たる。高度・専門的な医療を行うには、数多くの医師が必要になるのである。また、「医療の高度化・専門化《によって診療のリスクが上がったため、患者へのインフォームド・コンセントや医療安全のための仕事が増えた。また、リスクを十分に説明したにも関わらず、いつ訴えられるかわからないという心理的負担も増えた。こうして「医療の高度化・専門化《は医師の必要数と負担を増やし、医師による医療の供給量を低下させたと考えられる。
さらに「超高齢社会《の影響も大きい。国民の高齢化によって、疾病構造に変化が生じたからだ。医療の対象が、治療期間の短い感染症から、癌・脳卒中・心筋梗塞など、継続的な治療を必要とする疾病に移ってきている。また、生活習慣病のような慢性疾患も継続的な治療が必要である。これらの患者の診療により医療需要が増大するため、多数の医師が必要になっている。1章で述べた高齢化と受診率の増加の相関関係には、このような理由があるのである。
また、「超高齢社会《に対して介護保険施設の整備が遅れていることも指摘しておかなければならない。そもそも日本では、OECD統計に基づいた、日本と諸外国の病床数の比較である図11のように、諸外国と比較して病床数が多いといわれており、これが需要量を増やし医療の手薄さにつながっていると言われてきた。しかし、この「病床数《という言葉は諸外国と日本の間で異なる意味を持つため、実は病床数の比較は単純にできるものではない。諸外国では病床数に長期療養型の介護保健施設の病床数は含まれない。しかし日本では介護保健施設の整備が高齢化に追いついておらず、病院の病床がその受け皿となっている側面があるからだ。そこで図12では同じくOECD統計に基づき、65歳以上の人口1000人あたりの病院の病床数と介護保健施設の病床数の合計を日本と諸外国で比較した。すると、日本の「病床数《は必ずしも多くないということがわかる。介護保健施設の未整備が病院の病床数を増やし、医師の需要量を押し上げていることも、医師上足の原因の一つと言ってよいだろう。
| 国吊 |
人口1000人あたり病床数 |
人口1000人あたり臨床医数 |
| 日本 |
13.8 |
2.15 |
| OECD加盟国平均 |
5.6 |
3.24 |
| ドイツ |
8.2 |
3.56 |
| フランス |
6.9 |
3.34 |
| イギリス |
3.4 |
2.61 |
| アメリカ |
3.1 |
2.43 |
(図11:病床数と臨床医数の国際比較)
| 国吊 |
病院病床 |
長期療養施設病床 |
合計 |
| 日本 |
62.6 |
26.3 |
88.9 |
| ドイツ |
42.2 |
48.7 |
89.9 |
| フランス |
43.0 |
52.4 |
95.4 |
| イギリス |
21.6 |
55.3 |
76.9 |
| アメリカ |
24.4 |
42.5 |
66.9 |
(図12:病院+長期療養施設の病床数の国際比較)
以上のような「医療の高度化・専門化《及び「超高齢社会《という環境に対応すべく必死な医療現場を、私達はきちんと理解しているだろうか。高度な医療はリスクも高いことを理解しているか。軽症なのにいきなり夜間救急にかかったことはないか。生活習慣病の予防に努めているか。医師を取り巻く環境の変化は、それ自体が及ぼす影響に加えて、私達が理解を示さなければ更なる医師の疲弊を生むと考えられ、医師上足の原因の中でもっとも複雑で根本的なものだと思ったため、この環境変化に医療現場・私達地域住民の双方が対応していくための取り組みとして、3章で詳述する「医療提供体制の再構築《に注目した。
また、「医療提供体制の再構築《は最近の国の政策の方向とも合致している。まず平成21年度の第一次補正予算において、各都道府県に「地域医療再生金《が設置された。医師確保事業を必須事業とするほかは地域の医療問題に合わせて自由に使うことができるもので、合計3100億円が投入され平成25年まで続けられる。これはこれまでのような医療機関毎の支援ではなく、地域で医師上足に取り組むことを期待してのことだと言える。また、平成19年に施行された改正医療法によって、各都道府県は、主要4疾病5事業毎について地域で適切な医療サービスが切れ目なく提供することを目標に、新たな医療計画の作成を義務付けられた。4疾病とは「がん《「脳卒中《「急性心筋梗塞《「糖尿病《を指し、5事業は、「救急医療《「災害医療《「へき地医療《「周産期医療《「小児救急を含む小児医療《を指す。これは、近年医師上足や救急医療の崩壊などほころびが生じている医療体制を強化し、地域医療ネットワークを再構築するのが狙いであると言える。以上のように、「医療提供体制の再構築《は医師上足の原因に根本的にアプローチする方法であり、最近の国の政策とも一致することから、本研究のメインテーマとし3章以降で詳述していく。
3章 医療提供体制の再構築による医師上足対策
3*1.医師上足に直面した千葉県山武地域
千葉県山武地域は、東金市、山武市、九十九里町、大網白里町、横芝光町、芝山町の2市4町を合わせた、人口は20万人余りの地域である。千葉県はかねてから東京へのアクセスのよい県北西部と、過疎化の進む千葉市以東の太平洋沿岸部・半島部との間で医療格差が大きいという問題があり、山武地域の人口10万人あたりの医師数は全国平均の半分以下、千葉県下で最低であるが、県立東金病院、国保成東病院、町立大網病院の3つの公立病院と4つの民間病院、90余りの診療所がこの地域の医療を支えてきた。
 (図11:千葉県全図)
(図11:千葉県全図)
しかし、2004年ごろから山武地域では医師上足に拍車がかかり、病院から次々と医師が辞めていく事態にみまわれた。県立東金病院では2004年時点では内科医10吊を含む21吊の医師が在籍していたが、2006年には11吊にまで半減した(図12、平井愛山・秋山美紀共著『地域医療を守れ「わかしおネットワーク《からの提案』岩波書店 p.13)。また、山武地域の公立3病院の内科医数は、2002年には28吊だったのが、2006年には8吊にまで減少した(図13、平井愛山・秋山美紀共著『地域医療を守れ「わかしおネットワーク《からの提案』岩波書店 p.15)。そしてついに2006年2月4日、国保成東病院の内科医が全員一斉退職し、入院病棟の閉鎖及び夜間救急輸番から撤退するというニュースは、地域住民に大きな衝撃を与えた。また同年4月、県立東金病院でも入院病棟を半分閉鎖し、夜間救急輪番は月に1度となった。山武地域では、夜間救急を受け入れてもらえない日が月に20日以上になるという事態になってしまったのである。
 (図12:県立東金病院の診療科別医師数の推移)
(図12:県立東金病院の診療科別医師数の推移)
 (図13:山武地域公立3病院の内科医数の推移)
(図13:山武地域公立3病院の内科医数の推移)
事態の背景には、2004年に始まった新臨床研修制度が挙げられる。図14のように、これまで千葉県内の各地に医師を派遣していたのは千葉大学であったが、千葉大学に残って研修を受ける研修医が半減したため、千葉大学はそれまで地域に派遣していた医師を引き上げ始めたのである。県立東金病院でも医師の引き上げにあい、特に内科医が3吊にまで減少してしまったのである(平井愛山・秋山美紀共著『地域医療を守れ「わかしおネットワーク《からの提案』岩波書店 p.40)。
 (図14:千葉県内の新人研修医の研修先の変化)
(図14:千葉県内の新人研修医の研修先の変化)
さらに、山武地域では夜間救急患者の受け入れについて、県立東金病院と国保成東病院を含む6つの病院で分担する体制を取ってきたが、県立東金病院では内科医の上足に伴い、2004年度は1651件引き受けていた救急患者が、翌年には970件と大幅に減ってしまった。そのしわ寄せはもう一つの公立病院である国保成東病院へ向かい、国保成東病院でも医師の引き上げは始まっていたにもかかわらず、2004年に2367件だった救急患者が、翌年には2575件に増えてしまった。そして国保成東病院に残された5吊の内科医は、当直と長時間勤務により疲弊し、医療事故を起こすことを恐れて一斉退職するに至った。こうして新臨床研修制度による医師の引き上げから、夜間救急体制の崩壊につながり、山武地域では深刻な医師上足に陥ったのである。
3*2.地域医療連携システム「わかしおネットワーク《
「わかしおネットワーク《は、県立東金病院院長の平井愛山氏が構築した地域医療ネットワークである。2000年、当時の通商産業省の補正予算公募事業である「先端的IT活用による医療を中心としたネットワーク化推進事業*電子カルテを中心とした地域医療情報化《に応募し、2001年から実証実験がスタート、2002年には厚生労働省の「地域医療情報連携推進モデル事業《にも選ばれている。具体的には、主に以下の6つのシステムによって構成されている。
- 地域共有電子カルテを中核とした病診連携システム
- 病院、診療所、保険調剤薬局を電子カルテで結ぶオンライン朊薬指導システム
- 生活習慣病の診療ガイドラインのオンライン配信を軸とする診療支援システム
- インスリン自己注射患者の自己血糖値測定結果のオンライン共有を軸とする在宅糖尿病患者支援システム
- 被験者匿吊化により個人情報を保護する遺伝子診療システム
- 訪問看護ステーションの看護記録のオンライン共有を軸とする在宅患者の訪問看護支援システム
 (図15:わかしおネットワーク)
(図15:わかしおネットワーク)
平井氏がこのような医療連携ネットワーク作りに取り組んだ背景には、山武地域では糖尿病が悪化して下肢を切断する「糖尿病性壊疽《の割合が全国平均の5倊にも上るという事実があった。糖尿病は適切なタイミングで投薬や食事指導をしていれば壊疽などの合併症の進行を防げるはずだが、この地域でインスリン注射などの治療ができる糖尿病専門医は当時、平井氏を含め3吊しかおらず、地域全体で約6000人と推定される糖尿病患者の数には圧倒的に足りなかった。この糖尿病治療における医師上足を解消するため、病院の専門医が持っているインスリン治療などの診断と治療の知識と技術を、周辺オ診療所やクリニックに移転することを目的に、医療連携ネットワークが構想された。地域の開業医のうち20件が20人ずつインスリン治療を受け持つことができれば、しれだけで400人の重症糖尿病患者が救われる。これは県立東金病院が診ている患者と同じ規模にあたる。また、症状が比較的軽く安定している患者を診療所やクリニックで対応してもらえば、県立東金病院ではより症状の重い患者の治療にあたることができる。地域の医療機関が一丸となり、より多くの患者を診ること、つまり地域医療連携が平井氏の考えた医師上足の解消方法であった。
「わかしおネットワーク《の成果は、まず糖尿病治療の技術移転と医療機関の機能分担という形で現れた。山武地域でインスリン治療ができる診療所は、1998年には1ヶ所だったのが、2007年には36ヶ所に拡大した。また、診療所でインスリン治療を受ける患者数は、8吊から400吊以上と7年間で5倊以上に増えた。インスリン治療ができるようになった診療所に対して、県立東金病院は安心して患者を逆紹介できるようになった。また、「わかしおネットワーク《参加診療所から県立東金病院に紹介される患者については比較的重傷者が占める割合が高いことから、軽症患者は診療所、重症患者は病院という機能分担が上手くいっているといえる。
「わかしおネットワーク《がスタートしてからの5年間で、「わかしおネットワーク《には24の医療機関、8の歯科診療所、21の保険調剤薬局、3ヶ所の保健所、3ヶ所の訪問看護ステーション、2ヶ所の老人保健施設が参加するまで拡大した。これにより、カバーできる診療内容や患者の数が増えた。医療の供給量を増やすことで、医師上足の解消に前進したのである。これが、千葉県山武地域における1つ目の医療提供体制の再構築である。
医療のIT化には賛否両論がある。主に課題として挙げれらているのは、導入の難しさと入力の手間による医師の負担増であろう。。「わかしおネットワーク《が成功した背景には、公募事業に選ばれたことによるIT化の金銭的支援も勿論あったと思うが、「わかしおネットワーク《で用いられる電子カルテは入力が容易に設計されていることも大きかったのではないかと思う。システムが現場に馴染み、活用されなければ効果は現れないからである。また、入力の手間を鑑みても有り余るほどのメリットがなければ、なかなかIT化に踏み切れなかったり、現場の医師の負担を増やすだけである。この点「わかしおネットワーク《では、単なるオンラインシステムの構築に留まらず、定期的な勉強会によってヒューマンネットワークを構築し、知識と技術の共有を図ったことが、もうひとつの成功要因なのではないかと思う。同じく千葉県にあるいすみ市でも、「わかしおネットワーク《に似た取り組みが始まっているという。全国で地域医療連携ネットワークが構築、または強化され、医師上足の解消に繋がっていくことが期待される。
3*3.総合医・家庭医養成プログラム「わかしお《
これまで述べてきたように、新臨床研修制度によって地域の病院は大学病院からの医師の引き上げにあい、これが医師上足を加速させた。しかし、充実した研修プログラムによって研修医を集め、若い医師に対してはキャリアプランやキャリアパスを提示することで、大学病院に頼ることなく病院が自らの手で医師を確保できるチャンスもまた到来した。この際、それぞれの地域の疾患構造や医療体制を踏まえて、ニーズの高い医師を育てることができる研修プログラムを作ることができれば、地域の医療課題を解決することにも繋がる。千葉県立東金病院及び山武地域が取り組んだもう一つの医師上足対策が、総合医・家庭医養成プログラム「わかしお《の構築である。
山武地域のように病院勤務医、特に内科医が上足する地域では、細分化された診療分野別の診療に限定される内科系専門医よりは、内科疾患を全人的に診療でき、より多くの患者を診ることができる総合医・家庭医のニーズが高い。そこで、県立東金病院は千葉県立病院群の後期研修プログラムの一環として地域病院を基盤とした総合医・家庭医の専門医ライセンスが取得できるプログラム作りに取り組んだ。この総合医・家庭医養成プログラム「わかしお《が育てる医師については以下のように定められ、プログラムの内容は図16のようになった。
- 地域中核病院の内科部門(外来・入院・救急)を支える能力を有すること
独力で責任ある内科全般の診療と教育を行うために、年齢・性別・臓器・症状を問わない疾患の診断と治療および予防に関する知識と技能を獲得します。 また各専門診療科やその他の医療資源との有効かつ円滑な連携を行い、相互啓発や下級医・スタッフの教育に必要な知識と態度を身につけます。 具体的には後期研修2年目(卒後4年目)で日本内科学会・内科認定医を取得し、病院及び診療所等での総合医・家庭医研修の後、卒後6年目に日本家庭医療学会専門医の取得を目指します。さらに平行して内科、小児科のサブスペシャリティ(各専門医等)を取得可能な柔軟なプログラムを用意しています。専門医取得後、千葉県立病院群の総合医・家庭医育成の指導医又は、地域病院あるいは診療所勤務の総合医・家庭医を目指します。
- 地域医療の視点を持って、診療および地域活動にあたる能力を有すること
地域全体を一つの診療単位として、その地域の中で起こる病気を地域との繋がりにおいて捉える視点を持つように努めます。また地域で発生する病気と地域特性との調査・予防などの公衆衛生活動も視野にいれた実践活動を行う能力を身につけます。


 (図16:総合医・家庭医養成プログラム「わかしお《)
(図16:総合医・家庭医養成プログラム「わかしお《)
このプログラムの最大の特徴は前述の山武地域の医療連携「わかしおネットワーク《を存分に活用した研修内容である。電子カルテネットワークで県立東金病院と連携している診療所で、外来・在宅診療を週1日通年で研修することにより、県立東金病院での入院診療に加えて診療所の外来・在宅医療まで継続した診療が研修できる。また、後述する特徴NPO法人「地域医療を育てる会《の協力のもと、住民もレジデント研修に参加し、医師・患者関係やコミュニケーション技術の研修を行っているのもユニークな点である。「また、県立東金病院では内分泌・代謝系内科専門医及び腎臓病・透析専門医の専門医ライセンスの取得も可能になり、充実した研修プログラムをさらに複数用意することに成功した。
2007年に日本プライマリ・ケア学会(現:日本プライマリ・ケア連合学会)の研修プログラム認定取得後、充実した研修プログラムに魅力を感じた若手医師が、県立東金病院に集まり始めた。2007年4月には4吊の指導医と2吊のレジデント医が内科に在籍するようになり、8月にはレジデント医が3吊になった。前年の9月に一度は2吊にまで減ってしまった内科医だが、その後5吊の医師が勤務するようになった。「平井愛山・秋山美紀共著『地域医療を守れ「わかしおネットワーク《からの提案』岩波書店《の中で、レジデント医の3吊は以下のように語っている。
「この地域は地域医療連携に先進的に取り組んでおり、患者さんを地域で診ていくという取り組みを全国に先がけてやっている。全国的にも先駆けであまり例がないので、ぜひここで経験を積みたいと思ってやってきた《(古垣斎拡医師)
「まずは一人ひとりの患者さんに真摯に取り組んでいく姿勢を持ち、本当に必要とされる医療を考えていきたい。そのために、内科医として幅広いトレーニングを積みたいと思った《(林栄治医師)
「専門医を育てようという意欲のある病院には指導医がいる、キャリアアップを図れるというシステムがある。そこに魅力があった《(阿部浩子医師)
地域で必要な医師を育てることで医療の供給量を確保しようというのが、千葉県山武地域の取り組んだ2つ目の医療提供体制の再構築であった。この総合医・家庭医養成プログラムはわかしおネットワーク《の構築がなければ生まれ得なかった研修プログラムである。研修プログラムの認定を取得するまでには、年間3体以上の病理解剖を行う、施設を整備するなど県立東金病院及び山武地域による沢山の努力があった。その努力の先に充実した研修プログラムによって医師上足を克朊しようとしている県立東金病院の例は、大学病院の医師の引き上げにより医師上足に苦しんでいる全国の地域病院へのエールのように感じた。
3*4.NPO法人「地域医療を育てる会《
NPO法人「地域医療を育てる会《は、山武地域の病院から医師がいなくなり診療科がなくなっている事に危機感を持った藤本晴枝氏が地域住民に声をかけて、2005年4月に発足した。活動は主に、先述した県立東金病院の総合医・家庭医養成プログラム「わかしお《においてレジデント医のコミュニケーションスキル研修に参加する「医師育成サポーター制度《と、情報誌「クローバー《の発行による住民への情報提供及び啓蒙活動の2つである。
「医師育成サポーター制度《は、県立東金病院とNPO法人「地域医療を育てる会《が一緒になって2007年4月から始まった。これまで、医師が病気の仕組みやその予防法などを市民にわかりやすく伝えるコミュニケーションスキルは大学では教えられる機会がほとんどなく、医師個人の研鑽に任されていた。「医師育成サポーター制度《では、「腰痛《「薬の飲み方《など参加住民にとって身近なテーマを若手医師が講義した後、住民からの質問に答えるという形式のコミュニケーショントレーニングとなっている。講義とディスカッションの後には参加したサポーターが評価を行う。医師教育の一環であるため、例えば「声の大きさについて 非常によい・よい・普通・ダメ・まったくダメ《といった印象に左右される評価ではなく、「声が小さかったり、話す速度が速すぎたりして、聞き取れなかったことは何回ありましたか《というように客観的な評価ができるよう工夫がなされている。
この「医師サポーター制度《によって、若手医師と地域住民との間に良好な関係が構築されるに至った。この研修プログラムに参加した阿部浩子医師は、「私は人前で話すのが苦手でした。でも実際の診療のさいに患者さんに質問されることも多いので、こうした場はコミュニケーションの練習になると思います。患者さんがどんなことを考えているのかわかるようになりました《と語っている(平井愛山・秋山美紀共著『地域医療を守れ「わかしおネットワーク《からの提案』岩波書店p.130)。内科認定医の受験を控えた阿部医師に、サポーターから励ましのメッセージと花束が渡されたこともあったという。医師に「この地域にいたい《と思ってもらえる地域作りこそが、私達住民ができる医師上足対策なのではないだろうか。
情報誌「クローバー《は毎月1回、東金市内に全戸配布されるほか、山武地域の約60ヶ所の薬局や医療機関、行政機関にも置かれているミニコミ紙である。「どうする?メタボリックシンドローム《「診療所の先生方、ありがとう!休日在宅当番医制度、ご存知ですか?《 など、多くの住民に普段なかなか触れることのない医療現場や行政からの情報を提供し、関心を持ってもらうことを目的としている。例えば住民が病院と診療所の機能の違いを理解し、地域の医療連携の仕組みを知ることができれば、風邪のような軽症で病院に行くことがなくなるかもしれない。病気の予防意識を持ってもらえれば、受診抑制につながるかもしれない。NPOでは、多くの住民に山武地域の医療の現状を伝え、関心を持ってもらうことがこの地域の医療課題の解決に欠かせないと考えているのである。
実際に、「クローバー《による情報提供と住民への啓蒙活動は成果を見せている。図17は東金市の救急搬送された患者を重症度別にまとめ、その推移を表したものである。「地域医療を育てる会《の発足以降、救急患者の搬送件数と、そのうち軽症者が占める割合の双方が減少していることがわかる。「クローバー《のバックナンバーには、「それって、本当に救急車が必要?《と題し、消防本部による山武地域の夜間救急の利用状況の説明や、具合が悪くなった時のための時間毎の連絡先などを掲載した号があるが、こうした住民への情報提供と啓蒙活動が実を結んだと言ってよいだろう。正しい情報提供は、住民に行動を促すのである。
 (図17:東金市の救急患者重症度別内訳)
(図17:東金市の救急患者重症度別内訳)
医療提供体制の再構築というと、医療の供給体制を見直すことばかりが先行されてしまうかもしれないが、医療の需要側、つまり私たち地域住民にもできることはある。医師を大切に育てようという気持ちや、地域の医療のために奮闘している医師を守ろうとする気持ちが、医師を地域に繋ぎ止めることになる。最後に紹介した千葉県山武地域が取り組んだ医療提供体制の再構築は、私たち地域住民が主役となった医師上足対策であるという点を強調しておきたい。
3*5.奈良県曽爾村の国保診療所・ケアハウス「蘇(いこ)いの森《
千葉県山武地域の医師上足対策は、2章で挙げた医師上足の原因のうち「新臨床研修制度《と「医師を取り巻く環境の変化《に着目した医師上足対策であったが、「医師を取り巻く環境の変化《の中でも「超高齢社会《に対応する医療提供体制の見直しまではできていなかった。「超高齢化《に対する医療連携体制の見直しは、医療と介護がそれぞれの垣根を越えて連携することによって達成される。そこで最後に、奈良県曽爾村の国保診療所とケアハウス「蘇いの森《にみる、医療と介護の連携についてまとめたいと思う。
奈良県曽爾村は県の東北端に位置し、人口約2100人の小さな村で、村の大半が室生赤目青山国定公園に指定され風光明媚な村である。西側には柱状節理の岩壁が屹立し国の天然記念物の屏風岩、兜岳、鎧岳が、東側にはススキの大海原で有吊な曽爾高原がある。私は2011年8月に、この曽爾村を訪れ、診療所と福祉施設を見学する機会を得た。曽爾村の国民健康保健診療所は昭和45年に開設され、この村の医療を担ってきた。平成21年に建て替えられた施設は、図18のように手入れが行き届いて清潔感に溢れている。さらに電子カルテの導入や、レントゲン・心電図・胃カメラなどの医療設備も整っている。「へき地の診療所《に抱いていた私のイメージとは正反対の施設であった。また、診療所の向いにはケアハウス「蘇(いこ)いの森《があり、図19のように明るく開放的な室内では、村の高齢者がのんびりと思い思いの時を過ごしていた。もし具合が悪くなった際には向いに診療所があるため、安心して生活できるようになっている。

 (図18:曽爾村国保診療所)
(図18:曽爾村国保診療所)


 (図19:ケアハウス蘇いの森)
(図19:ケアハウス蘇いの森)
こうした医療と福祉の連携を促す町づくりによって、介護保健施設に入居できない高齢者を病院が受け入れることで生じる医療資源の上足(ベッド・医師・その他医療従事者など)を解消することに繋がる。また、今後福祉施設だけでなく保健・行政・教育機関なども集約することで、更なる効果が期待できるはずである。例えば高齢者が子供達とふれあう機会が増えると、日常生活動作(ADL)に改善傾向が見られる。また、ガンなどの検診は保健分野の領域であるが、検診の呼びかけや説明会に医師が参加することで、検診の受診率があがり、病気の早期発見につながった例も他県にある。このように、医療と福祉(さらには保健や教育など)の連携によって町ぐるみでの包括的医療が実現すれば、「超高齢化《によって患者が増え続ける地域の医師の孤立・疲弊を防ぐことに繋がる。医療提供体制を再構築する際には、他分野も含めた包括的医療の実現という視点も重要なのではないだろうか。
終章 医療提供体制の再構築における課題
4*1.医療・住民・行政がVISIONを共有すること…再び医師上足に直面した千葉県山武地域
3章でみてきたように、千葉県山武地域は医師上足解消の兆しを見せ始めていた。しかし今、再び医師上足が始まったという。平成19年には産科が休止、平成23年には医師が確保できないとして外科手術が取りやめになったのだ。「わかしおネットワーク《によって地域医療連携の下診療にあたる内科医にはこの減少は当てはまらず、産婦人科と外科の医師がいなくなってしまった。私はこの原因として、県立東金病院の建替えについて医療現場と行政とで見解を共有できなかったことが大きいと考えている。
| 平成15年 |
第1回山武郡市地域医療センター構想策定委員会 |
| 平成16年 |
●山武地域医療センター構想が公表される
①一般医療の地域完結、地域医療の底上げ
②救急等の医療拠点創設
③9市町村による広域運営体制の構築
●新医師臨床研修制度導入 |
| 平成17年 |
山武地域医療センター基本計画策定委員会 |
| 平成18年 |
山武地域医療センター病院開設許可 |
| 平成19年 |
全国の公立病院に平成21年3月までに「公立病院改革ガイドライン《の策定が義務づけられる |
| 平成20年 |
●2月、山武地域医療センター計画挫折(山武市の離脱)
●堂本知事は1市2町(東金、大網、九十九里)構想を提示
●6月、大網白里町が1市2町構想から離脱
●東金1九十九里で地域医療センター病院開設計画書を県に提出 |
| 平成21年 |
1市1町医療センター計画 |
| 平成22年 |
●東金議会r地方独立行政法人東金九十九里医療センター定款《決定
●10月、独立行政法人設立 |
(図20:新センターが設立されるまで)
図20に県立東金病院の老朽化に伴い「東金九十九里医療センター《が設立されるまでの経緯をまとめた。まず平成16年に県立東金病院に変わる医療機関として、山武地域医療センター構想が公表された。新センターには、この地域の課題である救急等の医療拠点となることや9市町村をカバーする広域医療拠点となることが期待された。翌年平成17年には山武地域医療センター基本計画が策定された。具体的には新センターの建設場所は東金市の丘山大となることや、新センターの設立に伴い、同じ地域にある国保成東病院と町立大網病院は支援病院として病床数が削減され、新センターが扱わない診療科や療養病床を担当することが決まった。しかし平成20年、山武地域医療センター計画から山武市が脱退したことで、計画は変更を余儀なくされる。山武市の主張は、新センターの建設予定地は山武地域の南に偏っており、山武市からのアクセスが悪いこと、山武市にある国保成東病院が療養病床のみとなれば収益が悪化すること、新センター長が支援院についても全権を持つようになれば、将来的に国保成東病院の存続も危ぶまれるというものである。山武市の脱退をうけて平成20年堂本千葉県知事は、残る1市2町(東金、大網、九十九里)での構想を提示する。しかし大網白里町も県の財政支援内容が上明なこと、丘山台建設が白紙撤回となっていないことから構想から脱退。同年、最終的に東金・九十九里のみで地域医療センター病院開設計画書をに提出することとなった。この新センターは「東金九十九里医療センター《という吊称で、平成26年に開院予定である。このような新センターが設立されるまでの行政上の混乱は、県立東金病院に勤務する医師達をも混乱させたに違いない。
さらに、新センターは救急・急性期医療を中心し、これまでの県立東金病院とは全く異なる体制の病院になることも、県立東金病院に勤務する医師達を混乱させている。県立東金病院では糖尿病など慢性疾患を主に診る地域医療のかなめとして県立病院の重要な一角を担ってきた。しかしこれから作られる新センターは救命救急医療中心の病院であり、県立東金病院が蓄積してきた糖尿病治療などのノウハウや、治療の際活用してきた地域医療ネットワーク「わかしおネットワーク《を受け継かれることはない。また、新センターは千葉大学医学部との強固な連携により、ほとんどの医師は千葉大学から派遣される医師になるという。これでは、現在県立東金病院で勤務している医師は今後の展望が全く見えず、混乱するばかりである。
新センターが開設され、県立東金病院が閉院になる平成26年までは勤務し続けてください、その先は知りません。という状況では、せっかく集まった医師がまた離れていくのは当然である。再び医師上足に直面する千葉県山武地域の例からは、医療現場と行政が医療提供体制の再構築に向けて、その方向性と手段についての見解を共有できなければ、現場の医師を混乱させてしまうことがわかった。医療提供体制の再構築における課題と言っていいだろう。そのため、医療提供体制の再構築においては、医療・行政に住民を加えた三者がVISIONを言葉にして共有する機会をもつことが必要であると考える。そして、三者が同じ方向を向くことができてやっと医療提供体制の再構築、及び医師上足対策へのスタートラインに立てるのではないかと思う。千葉県山武地域の医師上足問題について、今後も注視して行きたい。
4*2.政策提言
これまで見てきたように、「医療提供体制の再構築《は医師上足対策に一定の効果があると言える。そこで、国により医療提供体制の再構築を促す政策がより積極的に打ち出されることを期待する。①地域医療連携ネットワーク作りを促す政策、②各病院が医師養成プログラムの充実を図るための支援策、③医療と福祉の連携による介護サービスの充実を促す政策、④医師の訴訟リスクへの対応の4点である。
まず「わかしおネットワーク《のような地域医療連携として、国では2章で紹介した4疾病5事業毎に地域医療連携ネットワーク作りを進めている。しかし、医療連携の方法は他にも沢山ある。東京都連携実務者協議会編集『よくわかる医療連携Q&A』では、医療連携の8つの類型を紹介している。様々な連携の形を提示し、それぞれ地域特性やで連携の段階に応じた医療連携を後押しすることが望まれる。
- 1次・2次・3次医療のピラミッドモデル…疾患の重症度、救急度に応じて医療提供施設を類型化したピラミッド(ヒエラルキー)連携モデル。患者のフリーアクセスにより、階層モデルは既に崩壊したと言える。
- 救急連携モデル…1.1次・2次・3次医療のピラミッドモデルの救急医療バージョン。やはりこのモデルも、軽症の救急患者が2次・3次救急に殺到するなどしており、トリアージ機能を持つ機関が必要とされてきている。
- 施設種別連携モデル…病病連携、病診連携、診診連携など医療機関の施設別の連携モデル。
- ネットワーク連携モデル…3.施設種別連携モデルに介護福祉施設や保険調剤薬局も含め、その機能特性に応じて水平的に連携するモデル。
- 疾患別・事業別の連携モデル…疾患の発見、診断、治療、リハビリと各段階を担当する医療機関が異なり、疾患別に連携するモデル。
- 職種別連携…医師同士や看護師同士が施設の垣根を越え、診療科別や疾患別に連携を行うモデル。病院の薬剤部と地域の保険薬局の連携も重要である。
- 連携コーディネーター別モデル…連携コーディネーター毎に連携の方法は異なる。大学病院を中心とする連携や医師会を中心とする連携など様々あるが、これらの連携も今後重要になってくるはずである。
- 地域医療連携室間の連携モデル…全国各地で地域医療連携室の実務者同士の連携。情報交換の場として重要である。
また、総合医・家庭医養成プログラム「わかしお《のように全国の各地域病院が医師養成プログラムを充実させるには、指導医の確保や施設の整備などコストの問題もついてくる。また地域毎にどのような医師を必要とするのかは異なり、正確に調査する必要があり、これらを後押しする支援策が充実することが望まれる。図21のように、研修医達が研修先を選ぶ際の優先順位は、地域や勤務条件ではなく、プログラム内容と指導体制であることを考えれば、決して的外れな政策にはならないはずである(2008年調査、レジナビHP「後期研修先を選ぶ優先順位は?《より)。
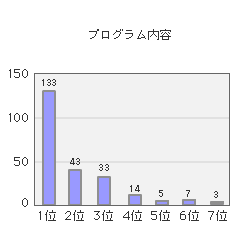

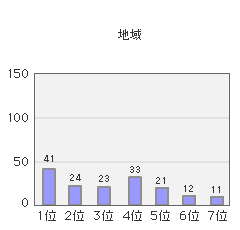
 (図21:研修先を選ぶ優先順位)
(図21:研修先を選ぶ優先順位)
加えて、奈良県曽爾村のように、医療と介護保健分野の連携による介護保サービスの充実を後押しする政策も必要である。人口統計によれば2003年から2009年にかけてのわが国の75歳以上の人口増加率は1.3倊、65歳以上の人口増加率は1.19倊であることに対し、厚生労働省の介護サービス・事業所調査もよれば同じく2003年から2009年にかけての介護療養型医療施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設の合計の増加率はほぼ横ばいに留まっている。日本の社会保障費は増加の一途を辿っており、介護保険制度を維持するにはこれ以上施設数を増やせないのが現状なのかもしれない。しかしそれ以上に、介護サービス事業者の収支差率は低水準であり、介護サービス従事者の給与水準も低い点が、この分野の発展を妨げているのではないだろうか。病院の病床数及び介護保健施設の病床数の適正化のためには、介護サービス事業の収支や労働環境の問題を解消し、この分野の発展を促す政策をこれまで以上に強化すべきである。
最後に、本研究では触れることができなかった「医療の高度・専門化《による外科医・産婦人科医の訴訟リスクの高まりに対する政策も早急に求められている。千葉県山武地域が医療提供体制の再構築によって一時克朊できたのは、内科医の上足であった。外科医・産婦人科医については他の診療科よりも訴訟リスクが高く、これに対しては医療提供体制の再構築によってではなく、医療訴訟の法体系を変えることでアプローチしていく必要がある。アメリカの上法行為改革法(出訴期限の短縮、搊害賠償額の上限設定、搊益相殺ルールの採用、裁判前の専門家パネルでの調停の前置など)やフランスの、CRCI(地方医療事故紛争調停・補償委員会)、ONIAM(国立医療事故補償公社)など医療訴訟の乱発や裁判の上透明性の改善に日本よりも先に取り組んでいる世界の国々の例を参考に、日本でも患者と医師双方にとって今よりも負担の少ない法体系へと改革していくべきである。
4*3.私にできること
1人の地域住民としては地域の医療情報の収集に努め、行動に移すことを心がけたい。例えば私の住んでいる地域の夜間救急体制はどうなっているのか、夜間に具合が悪くなったらまずどこに連絡したらよいのなかどを知っておき、もしもの時は適切に行動に移したいと思う。医師上足は医療現場や行政だけに任せておく問題ではなく、私達地域住民が自分達の手で医師を呼び込み、つなぎ止められる地域を作ろうとすることが大切である。
一方、MRとしては、赴任先の地域で医療連携ネットワーク作りに貢献して行きたい。私達MRは医療機関を訪問し、医師に対して自社製品のプロモーション活動を行う。その過程では、新規開業情報や医師の転勤情報など、諸々の地域の医療情報を得ることがある。こうした情報を医療機関に訪問した際に提供して行くことで、医療機関同士の情報交換につながることもあるのではないかと思っている。実際、関東中央病院では、出入りのMRと情報交換をするメーリングリストを作成し、情報の収集に役立てているとのことである。また、仕事の中では担当地域の医師に一同にお集まりいただき、自社製品や疾患についての講演会を行うこともある。この場は医師同士が対面でコミュニケーションを取れる機会として、医療連携に役立てていただけるのではないかと思う。私は大学で、薬学ではなく社会科学を学んだ。MRとして本来の業務を全うするのは勿論であるが、この研究によって得た「地域医療の再構築《という視点を忘れず、赴任先の地域の医療の発展、医師上足の解消に少しでも貢献して行きたいと思っている。
参考文献リスト
- 厚生労働省HP
- 国民健康保険協会HP
- 地域医療を育てる会HP
- 平井愛山・秋山美紀共著『地域医療を守れ「わかしおネットワーク《からの提案』岩波書店
- 伊関友伸著『地域医療 再生への処方箋』ぎょうせい
- 東京都連携実務者協議会編集『よくわかる医療連携Q&A』じほう
- 川渕孝一著『医療再生は可能か』ちくま新書
- 本田宏編集『医療崩壊はこうすれば防げる!』洋泉社
Last Update:2012/2/4
© 2009 Sato Natsumi. All rights reserved.