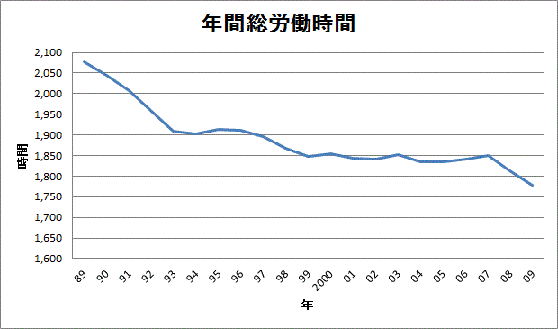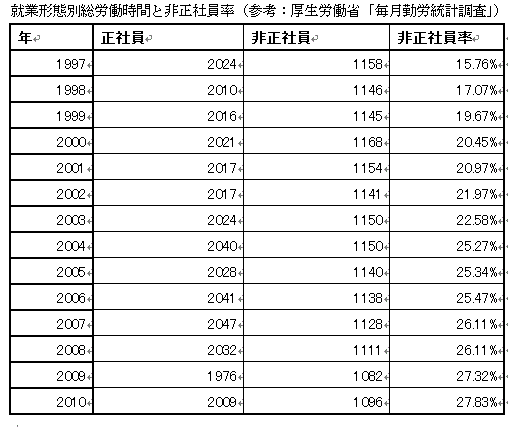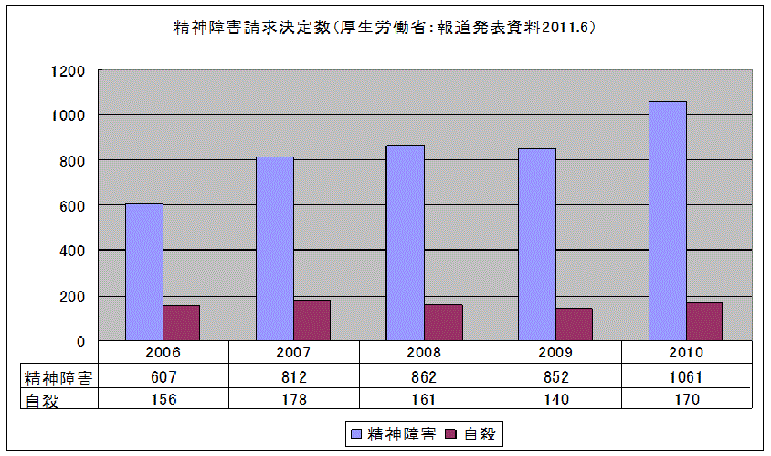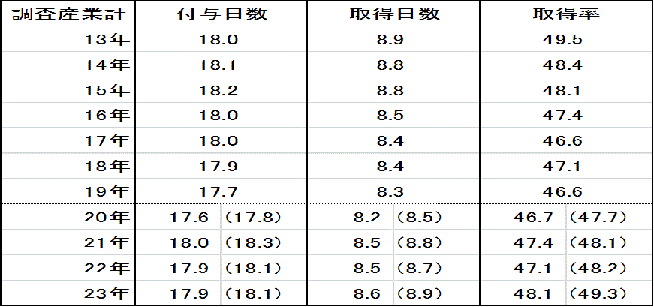以上、過労問題への日本の対策について考察してきたわけであるが、どうも経営側に重きを置いた政策となっているのではないか。おそらく過労問題をコスト問題としてしか捉えていないのではないだろうか。そのため、労働時間を直接的に規制するのではなく、割増賃金といった金で操作する間接的な対策しか行われていなかったのである。確かに、労働者に有利な政策をとれば企業側にとっても政府財政にとっても負担が増えることになり、国を支えてきた経済成長に影響を及ぼし兼ねない。しかし、長時間労働は生産性を低くする要因の一つでもある。また、今後労働人口が減少していくと予想される中で、過労問題が労働力の活用を阻害し、国力の活性化の妨げとなる恐れがある。そのような意味でも、現行制度をもう一度見直し、過労問題に取り組むべきではと考える。
章立てへ
1:増加する過労自殺の背景
過労問題を取り扱う上で難しいのが、労働者の内面に起因した問題である。近年では肉体的な問題による過労死よりも、精神的に追い詰められ自殺してしまう過労自殺が増加している傾向にある(図2-1)。
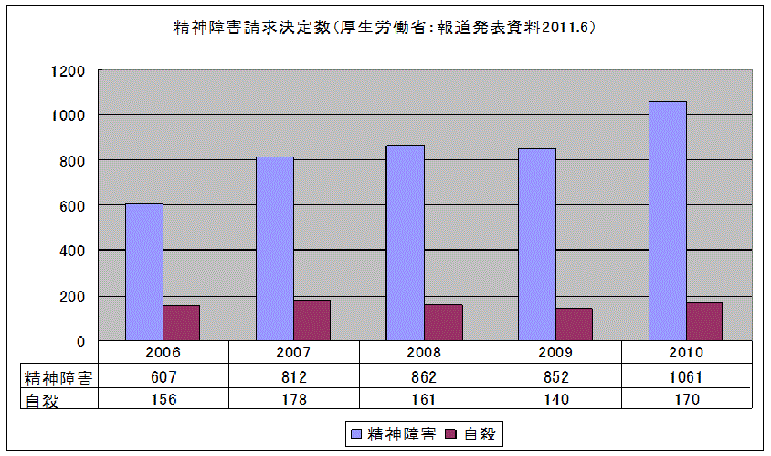
精神的なストレスなどによって過労死に至った場合、もし労働者本人がストレスを打ちに抱えたまま周りの人が気付かなったのであるなら、その原因を特定するのは困難である。それどころか、過労死として取り扱われずに終わってしまう可能性もあるため、統計では現れていない過労自殺者がいると推測される。
基本的に、精神的なダメージを受ける背景として日本人らしい労働者の性質があげられる。企業は帰属意識が強く、責任感があり真面目な人材を欲しがる傾向にある。彼らは企業の期待通りに仕事に打ち込むが、前章でも述べたが、日本の仕事では境界線があいまいなため、個人の仕事量及び領域は熱意によってそれがどこまでも無限に広がる(大野 2003)。企業は彼らにより多くの、重要な仕事を任せるようになり、彼ら自身も断る事ができず労働強化に陥ってしまうのである。また、江頭は「仕事上のノルマや納期の強制による不規則・長時間労働だけが過労死・過労自殺の要因ではない。労働の自由裁量度の高い管理職などでも過労死・過労自殺が多発している。」(江頭 2008)と指摘している。これは、管理職の人間はたいていが企業に忠誠を持ち、仕事熱心な人が多いからだと考えることができ、大野の指摘にあるような状態になり働きすぎてしまった結果だと考えられる。
さらに、ワーカホリックという問題も存在する。ワーカホリック(Workaholic)とは、英語のアルコホリック(alcoholic)=アルコ-ル依存症をまねて創った造語であり、「仕事中毒」や「仕事依存症」と呼ばれるもので、私生活に犠牲を払うまで仕事に打ち込んでいる様子を表す言葉である。仕事をしていないと落ち着かない、定時で帰るのが怖いといったことが代表的な症状で、その原因としては、リストラに対する恐れや仕事・ノルマに対する不安・焦り・プレッシャーからくるもの、強い責任感(生真面目さ)やプライドの高さ、自尊心の強さといった人格から生じるものなどがある。人格から生じる場合、「好きなことを仕事にしてしまった」がために仕事一筋になってしまい自主的なワーカホリックになるケースもある。
これらの内面の問題にも、第一章で考察した過労問題の原因、特に情報化社会が大きな影響を与えている。情報機器の普及で仕事が効率化されたことはすでに述べたが、それは一人の仕事量が増えることを意味するだけでなく、一人で仕事をする時間の増加も増えることを意味する。つまり、自分ひとりで仕事のノルマや責任を背負い込む孤立化が進んでいる。また、IT技術の普及により生じる精神的な失調症状を「テクノストレス」と呼ぶが、現代ではこれがさらに加速しているのではないだろうか。アメリカの心理学者である。クレイブ・ブロードは、テクノストレスを、コンピューターが苦手な人が無理して使用しているうちに体調を崩す不安症と、コンピューター好きが没頭しすぎたあまりに失調を引き起こす依存症の二つに分類している。現代の社会人はそのどちらでもなく、パソコンや携帯といった情報機器が膨大な仕事量を携えて常にそばにあるため、好き嫌い関係なく情報機器に没頭するしかない、より強制的な依存症だといえる。
章立てへ
2:日本の古い体質
肉体的、精神的な過労に対しては休息をとる事が一番効果的である。しかし、日本には残業することが当たり前という半ば暗黙のルールがある職場が多い。「残業しないとやる気がないと思われる」や「残業の有無がそのまま人事考査に影響する」などといった考えが労働者の中で広まり、休憩を取りづらくなっている。もちろん、この考えは古いステレオタイプのものである。だがしかし、いまだにこの考えが消えていない職場がある事もまた事実である。そのような職場環境では、誰かが残業をしていた場合、その日の仕事が終わっているのにも拘らず残って別の仕事をしようとしてしまう。これは特に上司が残っている場合に多く見られる傾向である。また、表向きは残業を抑えて早期退社を宣伝している企業であっても、仕事が減るわけではないので、結局のところ家に持ち帰り作業をせざる負えないケースもある。この場合は一章で述べたサービス残業にあたるが、企業側が特に強制をしているわけでなく、いわば「自主的」に労働者が仕事をしているととらえられることがほとんどである。しかし、そもそも労働者が残業するのは、それが自発的にするのであれ、渋々するのであれ、そうしなければ終わらないような仕事量があるか、達成できないノルマが課されているからであり、仕事の配分の問題でもある。また、社員が居残り残業をすることや持ち帰り残業をすることを、会社がたとえ奨励しなくても容認しているとすれば、それはそれで働きすぎを誘発する要因の一つとなる(森岡 2005)
では、これらの問題に対して、どのような対策がなされてきたのだろうか。前述したように、過労問題に対しては割増賃金など労働時間に関する取り組みが中心となっている。これは、医学的に厳密な定義が存在しないため、「長時間労働」という分かり易い問題にしか目を向けていない(大野 2003)という現状があるからだ。当然、過労について請求する場合も、働きすぎを立証するため裁判でポイントとなるのは長時間労働の有無になる。そのため、企業側としては長時間労働の緩和に向けて努力していたと主張する。そして、労働者個人の性格が「真面目で仕事熱心」であったり「義務感や責任感が強い」であったりという理由で、自発的に働きすぎ、不幸な結果になってしまったという言い逃れすら可能となるのである。
章立てへ
3:裁判例に見る健康配慮義務
このような状況に対し、一つの転機となる考え方が2000年の裁判で出された。いわゆる電通事件と呼ばれるものだが、以下に、厚生労働省のHPと森岡の著書を参考に事件の概要を示す。
- 本事件は、新入社員のA(男性・24歳)が、慢性的な長時間労働に従事していたところ、うつ病に罹患し、自殺するに至ったことから、遺族である両親が会社に対して損害賠償を請求した事案である。Aは、1990年4月に入社し、6月の配属以来、長時間労働で深夜の帰宅が続いたが、当初は意欲的で、上司の評価も良好であった。1991年1月以降、帰宅しない日があるようになり、同年7月には元気がなく顔色も悪い状態となった。さらに、8月に入ると、「自信がない、眠れない」と上司に訴えるようになったほか、異常行動もみられ、遅くともこの頃までにうつ病に罹患した。Aは,入社してからの1年5カ月間,日曜日も必ず仕事に出掛け,この間に取った有給休暇は半日だけであった。特に後半の8カ月は,午前2時以降の退社が3日に1度、午前4時以降が6日に1度で,睡眠時間は30分から2時間30分だった。そして、わずか入社1年5か月後の1991年8月27日、自殺に至った。
(厚生労働省)
- 会社側は、過労自殺したAの仕事熱心で義務感が強いという性格を自殺の要因だと主張し反論した。一審判決で会社側は、約1億2,600万円の賠償金の支払が命じられたが、これを不服とした会社は控訴。続く二審でも会社側に非があるとしたが、Aの性格などを理由に賠償額が減額され約8,900万円の支払いが命じられた。これに対しさらに会社は上告し、最高裁で取り消しを求めた。
- 最高裁では、Aの真面目で責任感が強く、また物事に取り組むにあたっては、粘り強くいわゆる完璧主義の傾向がある性格を認めたうえで、それでもAの性格は通常想定される「労働者の個性の多様さ」の範囲内にあるものとして、会社側の主張を退け、遺族側の訴えを全面的に認め、労働者に過重労働を強いて、心身に対する健康配慮義務を怠った会社側を厳しくとがめる判決を出した(森岡 2005)。
ここで重要となるのが、健康配慮義務という概念である。最高際の判決文では、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきであると指摘した。電通事件ではまさに、Aの健康状態が悪化していることを知りながら何も対応をしなかった会社側の罪が問われたのである。
この判決により、今まで長時間労働ばかりに目が向いていた過労問題にも、労働者の健康という根本的な問題に対して注目されるようになったのではないだろうか。実際、その後の政策では、個人の内面の問題に取り組むため「面接指導医制度」を導入したり、仕事と生活の調和を目指すことで個人の生活の質と仕事の成果の両方の向上を目指す「ワークライフ・バランス(Work-life balance)」や働きがいのある人間らしい仕事を目指す「ディーセント・ワーク(Decent work)」などの新しい概念などが議論されるようになった。これらについては、四章で詳述したい。
この章では、長時間労働だけでは語れない過労問題の側面について考察した。真面目、責任感や帰属意識が強いといった日本人らしさを活かして企業は成長を果たしてきた。しかし、情報化などによる働き方の変化によって、この日本的な労働観が過労死や過労自殺といった問題を引き起こす一つの要因となってしまった。IT技術によって仕事は個人化されたが、それと同時に仕事領域の曖昧な働き方・労働観が依然として残っているため、熱意ある人ほど仕事量が増え労働強化に至るケースが増えてしまっている。これに対して、最近になってようやく、労働者個人の健康に配慮しなければならないという考え方が公の場に出るようになった。だがしかし、この考えのもとで対策をとる企業は全体のわずかな割合にしかない。今後、長時間労働だけでなく、健康配慮の観点からも具体的な政策が必要だと考える。
章立てへ
第三章:過労問題に対する海外の政策と日本との比較
1.欧州の労働制度
過労問題を引き起こす要因として本論では3つの要因を挙げて説明してきた。そのうちの情報化社会と消費社会はグローバル経済とともに全世界に広まっている。こうした状況の中で、他国では過労問題はどのように起きているのだろうか。結論から先の述べると、過労問題が深刻化している国は主にアメリカ・イギリス・韓国である。一方、いまだ過労問題が存在しない、あるいはそれほど目立たない国は主にイギリスを除くヨーロッパ諸国である。図3-1からわかるように、過労問題が深刻な国に比べ、それほど問題とされていない国の労働時間はやはり短くなっている。一番長いのが韓国の2256時間で、一番短いのはオランダの1389時間となっている。この章ではまず、ヨーロッパ諸国の労働政策について、次に過労問題が深刻化している3か国の労働政策についてそれぞれ考察していきたい。

図3-1:独立行政法人 労働政策研究・研修機構(2008)
ヨーロッパでは、ILOによって厳格に定められている労働基準の条約を採択している国が多く、それに加えて独自の法律を制定している。ILOでは、週の労働時間を時間外の労働時間も含めて四十八時間としている。これは一見すると日本の四十時間よりも多いように思えるが、ILO基準の場合は時間外労働も含めた規制となっている。つまり、日本ではほとんど手放しにされてしまっている残業時間を厳格に規定することで、実労働時間が抑えられているのである。これに加え、1993年に制定され、2000年に改正されたEUの労働時間指令では、「最低一日の休日を設けること」・「一日につき最低連続11時間の休息期間を与えること」・「6時間を超える労働日につき休憩時間を与えること」などを定めている。また、多くの国では一日の残業時間にも規制をしており、一日二時間もしくは残業時間も含め一日十時間労働が限界としている。日本に比べてより厳格に労働時間を規制し、労働者の生活を保護する制度となっている。実際はこれ以上に厳しく時間規制をしている国が多く、ドイツやフランスでは原則週三十五時間とし、労使間の協議によって時間外労働も含め四十時間まで引き延ばすことが可能という制度になっている。
この背景には、労働時間規制のとらえ方の違いが存在する。ヨーロッパでは、労働時間規制は命と健康を守るための必要不可欠の上限とされている。これに対して日本では、余暇を確保し文化生活を保障するためのものとしてとらえており、ヨーロッパに比べると規制の力がやや弱く感じる。確かに余暇を確保する事は大事なことである。だが、余暇よりも収入を選んだ場合はどうなるであろうか。生活のために余暇を犠牲にしてでも働こうと考えだすであろう。日本の現状はまさに労働をお金と天秤にかけている状態である。しかも問題なのは、そのような考え方をする圧倒的多数が、政策を練る国家や経済を支える企業の経営者であるという事だ。そのため、本来は労働者の保護のためになされるべき労働規制も、三十六協定などに見るように、一部経済的な観点に寄り過ぎて作成されていると考える。
労働時間の規制と並んで、もう一つ、日本と欧州とでは大きく違う点として年次有給休暇があげられる。ILOが定める条約では、会社には最低3労働週の休暇を労働者に与えるよう義務付けられており、その休暇は原則継続したものでなければならない。事情により分割する場合でも、2労働週連続した休暇を一度は与えなければならないとしている。そのため、各国では20~30日の年次休暇を取得するのが普通で、二~三週間以上の連続休暇を年に二回程度取得するのが一般的である。これに比べ、日本の休暇取得状況はというと、図3-2からわかるように平均して9日前後である。有給休暇の付与日数は、ILOが定める基準に近い18日前後であるにもかかわらず、その半分以上が取得されずにいる。さらに自由時間デザイン協会が2002年に実施した「休暇に関する国民の意識・ニーズに関する調査」によれば、一年間に二週間以上の連続休暇を取得した者はわずか三.五パーセントにすぎない。全体の四割は四日以上から一週間未満しかとれず、三割は四日以上の連続休暇は一度もないとされている。また、わずかに取得された年休も、労働者本人のための休暇に使われず、病欠や育児・介護といった個人的な事情のために利用される場合が多い。個人的な用事なのだからそれは仕方ないかと思うかもしれないが、病欠は年休とは別の有給にし、介護や育児は短期時間労働や臨時休暇など、福祉制度の充実で対応することが望ましい。事実、ILOでは三十年以上も前に、病欠での休暇は年休に含めてならないと条約の中で定めている。
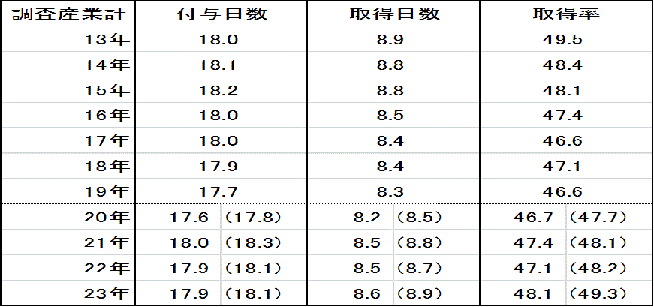
図3-2:厚生労働省 就労条件総合調査 *()内は、本社にいる常時雇用者が30人以上の企業
では、なぜこれほどまでに日本の有給取得率は低いのだろうか。まず考えられるのは、労働の二極化による人手不足である。二極化は一人あたりの仕事量を増やしただけでなく、正社員に100%に近い高い出勤率を促している。企業側は正社員が年休を取得することを考慮に入れず、ほぼ全日出勤することを前提にした業務計画や要員配置を行っている場合が多く、それにより代替要員がいないため休暇が取りにくくなっているのである。次に、依然として残る旧体質によって取得を渋るという事があげられる。もともと日本は勤勉を美徳とする労働観を持っている。それ自体はもちろん良いことであるが、それが歪められ休暇が取りにくい職場環境になってしまう場合がある。労働政策研究・研修機構が2011年に行った『年次有給休暇の取得に関する調査』では有給を取得しない理由として、有給を取ると人事考課でマイナスに査定され賞与や昇進に不利になる、職場の他の人に迷惑をかける、周囲の人が取らないので取得しにくい、などの理由が上位に入っている。また、病気や介護などの突発的事案のために残しておく労働者も多い傾向にある。
このような現状を打開するため、厚生労働省は「労働時間見直しガイドライン」の改正によって取得率向上を呼び掛けている。企業の中でも、ワークライフバランスの観点から様々な対策を講じている企業があるが、ごく一部と言わざる負えない。大竹は「労働者が自分で年休を決定する日本のような制度よりも、使用者が労働者の希望を聞いた上で年休日程を決定するヨーロッパのような制度のほうが、有給取得率は高くなる」(大竹 2010)と指摘している。似たような制度として、日本にも「有給休暇の計画的付与」という制度がある。これは、労働者は有給休暇を会社によって指定された日に消化するという制度である。この場合、最低5日は労働者の自由に取得していい有給休暇を残しておく必要がある。ヨーロッパと違う点は、労働者の希望が勘案されないという点にある。もちろん、企業によっては考慮してくれる場合も考えられるが、基本的には企業の都合により休暇が付与される。それでも有給休暇の取得率向上につながるとして導入されたが、この制度を利用している企業はまだ少ないのが現状である。
ここまでは労働制度のヨーロッパと日本との比較を行ってきたわけだが、その大きな違いは労働のとらえた方であると考える。ヨーロッパでは労働を生活の一部として考え、労働制度は命や健康、生活を守るうえで絶対の規制である。これに対して日本は、労働を経済活動の一部としてとらえ、生活や余暇と収入とのバランスのなかで労働制度を考えている。この違いは、一方にはゆとりのある生活を、もう一方には経済成長をもたらした。日本が戦後、急激に成長した背景には今の労働制度が大きく影響していると考える。だが、環境が変わっていくなかで、その反動が過労問題などといった形で現れているのも事実である。そのため、労働制度の根本的な見直しが必要だと考える。
章立てへ
2.過労問題が深刻な国
過労問題はいまや日本だけでなく、アメリカ・韓国でも深刻な問題となっている。
- アメリカ 近年のアメリカでは日本と同じように労働時間の二極化が進行してきている。ジェイコブスとガーソンの共著『タイム・デバイド―労働、家族、ジェンダー不平等』によれば1970年から2000年の間に短時間労働者の割合が、男性は五%から九%に、女性は一六%から二〇%に増加し、週五〇時間以上の長時間労働は、男性が二一%から二七%に、女性は五%から十一%に増加した。これらの背景には、経済の長期停滞が存在する。1980年以降、不況に陥ったアメリカでは、それまでのゆとりある政策を転換し、人員や人件費を削減するダウンサイジングが始まった。そのため、雇用の安定・余暇時間の確保・企業福祉といった労働者保護の政策がなくなり、日本と同様に長時間労働が蔓延する事態に陥った。
アメリカの労働制度の特徴としては割増賃金とホワイトカラーエグゼプションの2つがあげられる。アメリカでは、日本と同じく四〇時間を超える労働時間に対しては正規給与に対して一.五倍の割増賃金を支払う義務がある。日本と違う点としては、労働時間の上限がないという事である。一応日本では―ほとんど形骸化しているが―週四〇時間、一日八時間が限度と労働基準法で定められているが、アメリカでは割増賃金の支払義務があるだけで、労働時間そのものの規制はない。
ホワイトカラーエグゼプションとは、ホワイトカラーの労働者(主に事務に従事する労働者)に対して労働に関する規制を免除する制度となっている。狭義の意味では、労働時間に対する規制についての緩和を示すが、直接的に労働時間を規制していないアメリカでは、割増賃金の支払い義務の免除を行っている。適用要件として、「原則、週給455ドル以上の固定額の支払いがなされること」とした俸給要件と「部下が存在する管理職、自由裁量が大きい運営業務、または、高度な専門職であること」(労働政策研究・研修機構 国別労働基礎情報)とした職務要件があげられる。
これらの制度が長時間労働や過労問題を促進していると考えられる。日本ほど深刻でない理由としては、個人主義が強いため、企業と労務契約を交わす際にしっかりと主張できるという点、転職が頻繁になされているので、労働条件が合わなかったり過酷だと感じたりする場合には職を辞め、次の職を探すことが日本よりも容易である点の2点が考えられる。
- 韓国 OECD加盟国のなかで韓国の労働時間は最も長いと言われている。図3-1を見ても分かるように圧倒的に長く、唯一2000時間を超えている。韓国の労働時間規制はもともとゆるく、労働時間の上限を週四八時間、残業時間は週十二時間までという規制だ。その結果、過労問題が急激に増えたのだといえる。この結果を受け、韓国政府は2007年の法律改正により法定労働時間の短縮を行い、週の労働時間が四四時間にまで短縮された。だが、依然として長時間労働の問題は解決されていない。その原因として、労働時時間規制の抜け道がある、二交替制の2点が考えられる。
法定労働時間は短縮されたが、時間外労働に関してはいまだ手つかずのままである。むしろ、法定労働時間が短縮によって低下した所得を時間外労働で補おうとする傾向がある。さらに、時間外労働の上限である一二時間に対して、労働基準法の第五九条では「特定の事業で使用者が労働者代表と書面による合意をした場合には、週一二時間を超えて時間外労働させたり、休憩時間を変更することができる」という特例を設けている。これは日本の三六協定と同じで、労働時間規制を無効にし、過労死を誘発する大きな要因になっていると考えられる。
韓国には交替労働時間制度という慣行がいまも残っており、これが長時間労働を誘発すると考えられる。国内企業の一割が交替制度を取っているが、そのうちの六割は人件費などの兼ね合いから二交替制となっている。この二交替制のほとんどが、昼間組に合わせて勤務時間を決めているため、必然的に長時間労働になりやすい。
以上二か国についてみてきたわけだが、日本も含め共通している点は『労働時間を直接規制する手段を持っていない』という点があげられるのではないだろうか。韓国に至っては、規制の無い時間外労働や低い年休取得率など多くの点で共通している。さらに、3か国ともILOの労働時間に関する条約を批准してない。ヨーロッパの規制は、過度に労働者を保護しているのではなく必要に応じて課されている。それに比べ、日米韓は経済状況に重点を置いた制度となっているのではないだろうか。事実、過労問題が深刻化している国とそうでない国の違いは、しっかりとした規制の有無によって分けることができるのである。
章立てへ
3.オランダのワークシェアシェアリング
ここまで労働制度という構造的枠組みを見てきたが、この節では視点を少し変えて、働き方そのものの転換を試みた事例である、オランダのワークシェアリングについて考察したい。
オランダがワークシェアリングを導入した契機は1980年代にさかのぼる。石油ショックによる資源エネルギーバブルが過ぎ去ったあとで、大量の失業者が生まれた。失業率は十四%に達し、経済成長はマイナスに陥った。この状況を打開するために、労使間で賃金削減と雇用確保のための労働時間短縮が行われたのがオランダ版ワークシェアリングである。この時点では、賃金と労働時間の調整による雇用維持型のワークシェアリングが行われていたと指摘できる。
特筆すべきはその後の政府を巻き込んで行われた取り組みにある。まず、政府は賃金削減や労働時間短縮による収入減に対して、社会保障負担の削減と減税を行い生活を保障するとともに、企業投資の活性化に努めた。さらに1996年の労働法改正によって『同一賃金同一労働条件』を定め、ワークシェアリングの基盤を形成した。これは、フルタイム労働者とパートタイム労働者の間で、時間当たりの賃金、年金、社会保障、保険、雇用期間、昇進などの労働条件に格差をつけることを禁じ(森岡 2005)たものである。したがってフルタイムもパートタイムも皆正社員として扱われ、年次休暇やボーナスなどは働く時間に応じ平等に与えられる。そして2000年には労働時間調整法を施行し、雇用主に特別の支障が生ずる場合を除き、労働者が自発的にフルタイムからパートタイムへ、あるいはパートタイムからフルタイムへ移行する権利、および労働者が週当たりの労働時間を自発的に決められる権利(森岡 2005)を保障した。この法律は、男性に柔軟な働き方を提供したというだけでなく、女性がフルタイムで働き、パートタイムで働いた男性が家事労働にも参加するというジェンダーギャップを失くした意味で真に柔軟な働き方を促しが、これが他に類を見ない、オランダのワークシェアリングの大きな特徴といえる。
この結果オランダの失業率は一時二%にまで下がった(その後は四から五%を推移している)。だが、オランダのワークシェアリングがもたらしたのは雇用創出だけではない。ワークスタイルそのものにも影響を与えている。労働時間に関しては、2005年には年間1350時間にまで短縮し、その後も1400時間を推移している。それ以上に効果が現れているのは労働の柔軟性である。日本と同じようにオランダでも労働の二極化が起きているが、それはしっかりとした制度の後ろ楯のもとで進行しており、男女関係なく自らのライフスタイルに合わせてフルタイムとパートタイムを選択した結果である。
もちろん、オランダのワークシェアリングが万能というわけではない。近年の研究では、ワークシェアリングが雇用を創出するという因果関係に疑問が提示されている他、ワークシェアリングだけでは経済成長や生産性の向上にも限界があると指摘されている。それでも過労問題やワークライフバランスという観点から考えれば有効な政策と言えるのではないだろうか。
ただし、このワークシェアリングがそのまま日本で導入できるかと言えば現実問題として無理がある。まず日本の正社員と非正社員の格差は非常に大きいため、均衡待遇の問題が大きな障害となる。また、柔軟な雇用を困難にするものとして日本に特徴的な雇用形態という問題がある。日本では一括して採用し、振り分け、一斉に定年を迎えるという構造のため基本的に職能給または年齢給となっている。そのため、よく指摘されることだが、自由に転職するという習慣がなく一つの企業で一生働くのが基本になっている。これに対しオランダをはじめとする欧米では職務給制度を採用しているため、雇用は職務ごと必要に応じて行われる。そのため、給料の設定も従事する職の価値や難易度などによって決まる。労働者はより良い条件を求めて転職することが頻繁にある。オランダでも職務給が採用されているため、同一労働同一賃金によるフルタイムとパートタイムの格差解消が容易にできたわけである。
では、日本の雇用形態を変え給料も職務給に変更すれば良いのだろうか。確かに構造を変えればワークシェアリングの導入は可能かもしれない。だが、現体制から根本的な構造を変えるのは現実的な政策とはいえず、そのため日本の現状に合わせた労働政策が必要だといえる。
章立てへ
第四章:日本おける新たな取り組み
依然として改善を見ない長時間労働や過労問題に対し、厚生労働省は企業などもここにきてようやく対策を練りはじめてきた。この章では、それらの取り組みのうちいくつかを取り上げ、利点と問題点を考察することで、次章で行う政策提言につなげたい。
1.面接指導制度
2005年、政府は労働安全衛生法を改正し、過重労働やメンタルヘルス対策として一定の時間を超える残業を行った労働者に対しての医師による面接指導を実施しなければならないという面接指導制度を導入した。この制度の概要を、厚生労働省のHPを参考にし、以下に示した。
- 事業者は、労働者の週四〇時間を超える労働が一か月あたり一〇〇時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて、医師による面接指導を行わなければならない。また、基準となる時間の算定は毎月一回以上、基準日を定めて行うこととする。その際、医師は労働者に対し面接したうえで必要な指導を行い、事業者に対しては必要な措置についての助言を行う。これを受けて事業者は、必要があると認めるときは適切な措置を講じ、衛生委員会などに報告しなければならない。
- 上記以外にも、週四〇時間を超える労働が一か月あたり八〇時間を超える労働により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者の申し出を受けた場合、あるいは事前に事業場で定めていた残業基準に達した場合、面接指導を実施するかまたは、それに準ずる措置を講じるよう努めなければならない。
この面接指導制度は、従来の制度のように労働時間に対する措置ではなく、労働者個々人の健康面に関する対策という点で新しい試みだといえる。利点としては、定期的に働きすぎによる弊害をチェックできるという点、今まで効果的な対応ができていなかった労働者のメンタルヘルスに対しても有効だという点、そして、本人が労働強化に気付かない自発的な働きすぎやワーカホリックに対しても健康面のサポートができる点の3つが考えられる。
だが、これらの利点を最大限に生かすためには、現行制度のままではまだ不十分だといえる。まず、面接指導を実施するには労働者の申し出が必要であり、事業者側に対する強制力がないという点だ。極端な話、申し出がなければ一〇〇時間を超えていたとしても面接指導をしなくても良く、そうなれば有給取得の場合と同じく「権利は与えられているが利用はされない」ままで終わってしまう恐れがある。日本人の性格からして、労働者自らが声を上げるとは考えにくく、特に精神面に不安を抱えている場合はなおさら表に出さないようにする傾向があると思われる。また、ワーカホリックや自発的な働きすぎの労働者は自分でコントロールができない場合が多いので、彼らに対しても有効な政策になりきれていない。
また、「疲労の蓄積が認められたとき」や「時間の算定は基準日を定めて行う」といった部分に、事業者任せの曖昧な点が残っているのも問題である。これは企業側のコンプライアンスの問題でもあるが、労務管理がしっかりしている大企業に比べ、規模が小さくなればなるほど曖昧のままにされてしまう可能性がある。その意味でも、やはりある程度の強制力を持たせた制度にすることが望ましい。
最後に、面接指導だけで十分なのか、また月一〇〇時間を超える残業時間という基準はそもそも適切なのかという点である。残業時間が月一〇〇時間という事は一日の残業時間が約五時間という事になる。この場合、相当な労働強化が起きていると考えられることから、面接指導ではなく健康診断を受けさせた方が良いのではないだろうか。また、残業時間が一〇〇時間という適切性はどこからきているのだろうか。医学的見地からみて、一日十時間、週五〇時間を超す労働は健康に支障をきたす場合がある。そのため、ILOの労働基準やヨーロッパでは、残業時間の上限を一日二時間と定めている。
今回の衛生法改正の参考となったのは厚生労働省の「過重労働による健康障害防止のための総合対策」であり、それによると月四五時間を超える残業をさせた場合は、事業場における健康管理について産業医の助言指導を受ける。また月一〇〇時間あるいは二~六か月平均で八〇時間以上の残業をさせた場合は、当該労働者に健康診断を受けさせ、産業医による面接指導を行う(森岡 2005)という二段構想になっていた。最初の四五時間という基準は、一日の残業時間を二時間に抑えるという意図があると考えられる。また、ここでははっきりと健康診断を受けさせるという措置が明記されている。それが、2005年の改正で、二段構えがなくなり、四五時間から一〇〇時間に後退し、健康診断が削除されてしまった。
今回の改正は企業側に配慮した規制緩和であると考えられる。確かに企業側としては労務管理などの負担が増えることになるが、働き手である労働者が倒れてしまっては元も子もない。制度自体は、過労問題に対して有効だと考えられるのでもう一度見直す必要がある。
章立てへ
2.労使間レベルでの取り組み
勤務間インターバル この制度は、仕事が終わってから次の仕事を始めるまでに一定時間の休憩を義務付けるというものである。この制度の基となったのはEUの労働時間指令である。以下ではまずEUの制度について整理したい。
三章でも述べたが、ヨーロッパでは、「EU労働時間指令」(1993年制定)で、最低11時間の休憩を取ることと定めている。例えば、午後11時まで残業した場合、次の日の勤務は11時間後の午前10時まで免除される。決められている始業時刻が午前9時でも、定時に出社する必要はなく、その分の賃金もカットされない。
この制度は、労働時間指令の制定時に、イギリスが主張したオプト・アウトに対するセーフティーネットの意味合いが強い。そもそも、EUでは残業も含め週四八時間を超えてはならないとしている。しかし、ここにも労働時間に関する例外があり、それがオプト・アウトである。これは日本の三六協定に類似したもので、使用者は、あらかじめ労働者の同意を得ている場合にのみ、週四八時間を超えて労働させることができるというものである。これを採用しているイギリスでは、EU諸国の中で圧倒的に労働時間が長くなっていしまっている。しかし、それでも十一時間の休息義務があるため、日本のように無制限の時間外労働になるわけではなく、最大でも一日の労働時間は十三時間、一週間だと七八時間となりそれ以上伸びることはない。
日本では産業別労働組合の情報労連がこの制度に注目し2009年から協議を始めた。2009年のうちにKDDIなどの13社で労使が合意し、インターバル規制を既に導入している。2010年の春にも新たに2社が加わり全部で15社が導入するに至った。ただし、現在制度を導入している15社が合意した休息時間は、EUの11時間に比べればどれも短い。7時間が1社、8時間が10社、8時間プラス通勤時間が2社、10時間が2社だった。それでも、通建連合には組合員から「だらだらと時間外労働をしなくなった」「休息時間が翌日の勤務時間に食い込んでも、気兼ねなく出勤できる」と歓迎する声が届き、従来は1人で対応した深夜工事を複数で分担するなどの改善が進んだという。(朝日新聞 2010年6月2日 朝刊)。
従来の規制は割増賃金による間接的なものしかなく、賃金を巡る綱引きにしかならず効果的な対策とは言えなかった。今回情報労連が導入したインターバル制は、労働時間を直接規制するという点で新しく、また労働者の健康確保やワークライフバランスという観点からも効果的だと考えられる。
現制度の問題点としては、休息時間が短い、導入範囲が狭いという二点があげられる。つまり制度自体には問題がないため、あとは政労使がどれだけ協調し、この制度充実させていけるかが問題となる。
日本型ワークシェアリング 三章でオランダのワークシェアリングについて触れ、日本で実施するには現実的ではないという意見を示した。しかし近年では、再びワークシェアリング導入の議論が活発化してきている。もちろん、すでに指摘したように、オランダのモデルをそのまま導入することは現時点で不可能なため、議論に上っているのは日本に合わせた「日本型」のワークシェアリングである。
自治体でワークシェアリングを試みた例として群馬県の太田市があげられる。太田市では2009年1月から既存職員の残業を減らし、地元の自動車工場などを解雇された市内在住者を対象とし、土木現場や窓口業務での臨時職員として20人ほどを採用した。新規雇用の財源は職員1500人の残業を減らすことで、その浮いた時間外手当からねん出している。他にも、富士通マイクロエレクトロニクスは、従来二日で十二時間勤務するところを八時間に減らし、約五千人の従業員で仕事を共有している。
上記の二つの例からわかるように、「日本型」のワークシェアリングとは雇用を維持するために行われており、増加した人件費を補うために労働時間と賃金を削減するいわゆる緊急避難型のワークシェアリングとなっている。厚生労働省でもこの動きを後押ししており、2009年には助成金制度を創設した。この制度では、残業の削減、休業、教育訓練、出向などにより雇用維持を図ることを「日本型ワークシェアリング」とし、この取り組みを行った企業に対して助成金を支給するとしている。支給要件として、「一人一か月あたりの残業時間が、従来の平均時間と比べ半分以上かつ五時間以上削減されていること」また支給届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇などをしていないこと(厚生労働省)を挙げ、以上の要件を満たせば労働者一人当たり10万円(中小企業事業主は15万円)の支給をすると定めた。
日本のワークシェアリングは雇用問題の文脈で語られ、解雇しない代わりに給料を下げるという、結局お金の問題に終始してしまっている。結果として労働時間が短縮されるのは良いが、今度は生活の維持に支障が出てきてしまう。企業側は賃下げや雇用維持の観点からしかみていないので、ワークシェアリング後の保障を考えていないからである。もちろん、企業としても自社の存続をかけているわけだからそこまで手が回らない。そのため本来ならその保障は政府が行うべきところであるが、現状はわずかばかりの助成金を企業に支給する制度のみに留まっている。ただ、ワークシェアリングは一部ではなくある程度の範囲で均一的に行わなければ効果が薄いのだが、果たして政府がそこまで広範囲な支援ができるのだろうか。国の財務状況や他の問題との兼ね合いから、やはりワークシェアリングを効果的に実現するのは難しいのではと考える。
メンター制度 この制度は企業において新入社員の育成・サポートを行うために近年、大企業を中心に導入されるようになったものである。会社や配属部署における直属の上司とは別に指導・相談役となる先輩社員を付け、仕事における不安や悩みの相談であったり、業務におけるスキルや仕事に対する心構えなどの指導・助言を行う。
もともとこの制度は企業の人材育成戦略にもとづいて導入されたものであるが、これをうまく利用すれば、二章で触れたような労働者の内面の問題への対応策となるのではないだろうかと考える。過労自殺やうつ病、精神疾患などは仕事におけるプレッシャーや責任を一人で抱え込むことで発生する。もしメンターなど、身近に相談できる人がいれば、その発生リスクを減らすことができるのではないか。また、長時間労働に対しても、それが自発的なものであろうがなかろうが、仕事の抱え込みを外からチェックできるので、労働強化に対する予防策としても期待できる。
もちろん、現行制度は人材育成を目的としてものであり、これがそのまま過労問題の対策として効果が発揮するとは限らない。ここで指摘したいのは、労働者の孤立した働き方を防ぐために、労働者同士でチェックし合える、あるいは相談できるような環境づくりが必要になるのではないかという事だ。他人に相談事を持ち込むためには、それなりの関係を構築するコミュニケーション力と時間が必要であり、それを制度で強制するのも可笑しな話だ。だが、少なくとも一人で仕事を抱え込みことで長時間労働や労働強化が起きるような事態にならないよう、お互いにチェックし合える体制は整えることが可能ではないだろうか。
章立てへ
第五章:まとめと政策提言
ここまで、過労問題の背景を整理し、それに対する日本と海外の対応策について考察してきた。その結果、本論文としては、労働の二極化・情報化社会・消費社会の3つの要素が長時間労働と労働強化を生み、これらに対してしっかりとした対応が取れていない国(日本、韓国、アメリカ)では過労問題が深刻化するという見解を示した。対応の違いは労働規制に対する価値観の違いであり、規制を健康と命を守る衛生安全の手段としてとれているかどうかで、政策内容も実施状況も変わってくる。そしてまたそれは、経済成長をとるか生活のゆとりを取るかの選択の問題でもあった。事実、アメリカや日本は経済大国であり、韓国もまた近年急激な経済成長を遂げている国の一つである。以上の事から考えれば、過労問題の対策として一番有効なのは、経済成長に一度歯止めをかけてスローライフへと転換することである。
だが、もちろんこのスローライフを国全体で実施するには現実問題として無理がある。資源の乏しい日本では、成長を追い求めることが生活水準の向上と維持を可能にしてきたが、一度上がった生活水準を放棄することは難しいのである。そこで以下では、日本の現状の勘案したうえで取るべき過労問題への対応策をまとめた。これを本論文の政策提言としたい。
労使間でなすべきこと
1:仕事の根本的な見直し 意識を変えるだけで効果がでる問題もある。文具やオフィス家具などの製造・販売を行うコクヨでは、人事コンサルティング会社「ワークライフバランス」の協力のもと、社内にワークライフバランス推進する部門を置き、仕事の在り方について見直しを行った。その結果、従来よりも月間の総労働時間を約27%短縮することに成功した(朝日新聞「凄腕つとめにん」)。企業側だけでなく、労働者自身が働き方についての意識を変える必要がある。
2:年休取得率の向上 過労に対しては休むことが一番の対策であるため、連続した休暇の取得を確保することは過労問題解決への第一歩であると考える。取得率向上のために、企業側は要員配置の見直しを行う必要がある。休暇を取りたくても代替要員がいなくて休めないという事態は避けなければならない。また、病欠や介護・育児などは年次休暇と区別しなければならない。若手社員は自ら年休を申し出ることができないような場合があるが、上司や先輩社員などが積極的に休暇を取る、もしくは若手社員に取得を促すなど、労働者側の配慮も必要である。
現段階での妥協策として、計画年休制度の推奨が考えれる。強制的で自由な休暇ではないという問題もあるが、企業としてはある程度休暇をコントロールできるので、より休暇を承認しやすくなる。労働者としても、周りに気兼ねしなく休めるというメリットがある。もちろん本来は、ヨーロッパのように労働者の希望を考慮した計画的な年休制度が好ましいが、ひとまず取得率を向上し、過労を解消するために有効だと考える。
政府がなすべきこと
1:労働基準監督署の役割を強化 労働基準監督署は厚生労働省の出先機関として各都道府県の労働局に設置されており、労働基準法に基づいて、労働条件の順守や労働者の保護が適切に行われているかを監督している。近年では厚生労働省の「賃金不払残業総合対策要綱」が出されたために、サービス残業への是正指導が強化されている。しかし、森岡は監督の実施率は違法行為の広がりに比べてあまりにも低すぎると指摘している。労働基準監督官の人数は2003年度時点で3623人いるが、監督適用事業場数はそれ以上に急激に増加した。そのため、労働基準法制定直後の1948年に36%あった監督実施率は、最近では5%を割り込み、年によっては4%を切るまでになっている。4%の実施率では全事業場を一通り回るのにも25年を要することになる(森岡 2005)。つまり、いくら制度を作ろうとも、それをチェックする体制が整っておらず、抜け道が依然として存在するのである。このことはサービス残業の取締りに限らず、ほかの違法行為に対する監督にも支障が出ることを意味する。また、後で述べる面接指導制度や勤務間インターバル制度のチェック体制としても効果が期待できるため、役割の強化、具体的には監督官の増員が必要だと考える。
2:労働時間の直接的規制 一章でも述べたように、割増賃金による労働時間の間接的な規制は過労問題の根本的な解決策とはならない。そこで労働時間そのものを直接規制する制度が必要となる。そのためにはまず、三六協定を見直し、野放しとなっている残業時間の絶対的な上限を定めることが必要になる。本来なら、ヨーロッパ諸国と同じく一日二時間までの規制が望ましいが、経済状況などの事情があるため、その基準は政労使の三者の協議で決めるしかない。その結果が二時間以内にならなかったとしても、無制限に近い現状から考えれば、規制が設けられたという点で前進であり、あとは段階を踏んで改善していけばいいと考える。
もう一つの規制策として勤務間インターバル規制の全事業均一の実施があげられる。この制度については四章で、労使間レベルの取り組みとして考察したが、これを政府が主体となり、情報通信産業内だけでなく全事業に導入するべきだと考える。もし三六協定が見直されなかった場合でも、インターバル規制があれば、物理的に残業時間はある程度の上限までに規制されるので、有効であると考える。この場合のインターバル時間はやはり11時間が望ましい。というのも、疲労回復や健康に考慮すると、最低でも6時間の睡眠が必要であり、この時間に食事や入浴、行き帰りの通勤時間などを加えると11時間ほどになるからだ。もちろん、残業規制と同じく、最初の段階ではまず導入することが重要であり、情報労連内でも見られるように企業間でのばらつきが生じても仕方がないと考える。
そして、以上二つの法令が制定(改正)されたところで重要となるのが、労働基準監督署の役割である。残業規制は守られているか、勤務間インターバルの規制時間は業務実態に対して適正かどうかなどを監督官がチェックすることで、この2つの制度がより充実したものになると考える。
3:労働者個人の健康管理 全体に対する労働時間の規制だけでなく、労働者個人の健康配慮対策も必要だと考える。といのも、二章で触れたように真面目や責任感が強いなどの日本人らしさや、ワーカホリックなどの労働者の内面の問題が過労問題につながる可能性があるからだ。そのために必要となるのがより充実させた健康面接制度の実施である。この制度を充実したものとするためにはまず、面接実施の基準時間を見直す必要がある。一〇〇時間という一つだけの基準ではなく、衛生法改正のもととなった厚生労働省の総合対策を参考にし、二段構えにすべきだある。具体的な修正としては、「残業時間が月四五時間を超えた場合は、産業医による面接と、健康管理についての助言・指導、月八〇時間を超えた場合には健康診断を受けさせ、即座に労働条件を改善する」の二段階が望ましいと考える。月八〇時間という基準の根拠は、2001年に厚生労働省が発表した脳出血や心筋梗塞などによる過労死を労災認定する際の基準、いわゆる「過労死ライン」を参考にした。ちなみにこの基準では、発症前の一から六カ月間に時間外労働が一カ月あたり約四五時間を超える場合は業務と発症との関連性が徐々に強まり、発症前一カ月間に約一〇〇時間、または発症前二から六カ月間に1カ月あたり約八〇時間を超える時間外労働があった場合は「業務と発症との関連性が強い」としている。
この制度を導入した際のチェック体制としては、やはり労働基準監督官が望ましい。だが、前述の通り、少ない人数でここまで監督するのもなかなか難しいものがある。そこで、従業員士でお互いの労働時間をチェックできる体制の構築が必要になると考える。近年ではIT技術を応用して労働時間の管理を行う企業も出てきているので、それほど負担にならないのではないだろうか。また、定年延長制度の導入が段階的に進められているが、本来ある程度まとまって減るはずだった人員を、この労働時間管理の充てるというのはどうだろうか。いずれにせよ、労働者個人に対する健康を維持するという点で、この面接指導制度を導入すべきであり、同時にそのチェック体制の構築も早急になされる必要があると考える。
以上5つの施策を本論文の政策提言としたい。基本的に労働者側によった政策となっているが、これはもともとの制度が経営者側や政府側によって設計されており、それを修正しようと試みたためである。日本が成長重視の制度設計をしたために経済大国になったのは肯定すべきだと考えるが、低成長時代においては、本当の意味でゆとりある生活とは何かを考えなければならない。そのために、政労使三者によるバランスのとれた制度設計が必要だと考える。
章立てへ
おわりに
今回の研究を通して感じたことは、過労問題は非常に見えにくい問題であるという事だ。自殺大国日本と言われているが、過労問題の深刻さを実際に知る機会はなかなかない。ほとんどの人がすこし厳しいなと感じながらも日々の労働をこなしているのが普通である。では、過労問題はごく一部の問題なのだろうかと言えば、もちろんそんなことはない。自動車事故と同じで、今回はたまたま無事で済んだがいつ事故が起きるとも限らないのである。というのも、過労を誘発する情報化と消費社会は経済・生産活動の中に組み込まれており、現代の生活に深く入り込んでいるからだ。
研究期間中にもいろいろな変化が起こった。3月11日の東北大震災や定年の延長。過労問題の防止のための法律制定を求める遺族の署名活動。本論文にも参考事例として多く取り上げたが、安定しているように見えていたEUの不信。これらの変化のなかで、当然過労問題への対応も変わってくるだろう。基本的に、政策提言で挙げたものは企業や政府の負担を増やすものである。震災による復興支援などで、財政や経営状態はかなり厳しいものとなっている。そのため当分は過労問題に対して根本的な改善がなされることはないと予想できる。
だがしかし、これから先を考えるといつかは現制度に対してテコ入れをする必要があるのではないだろうか。つい最近発表された人口予測では、日本の人口は減少の一途をたどり、今度50年で約4132万人減り、なおかつ65歳の高齢者の割合が40%近くになると予測された。人口変動はそのまま労働環境の変化につながる。こうした変化に対して、労働の在り方考えた制度構築が必要だと考える。
章立てへ
last update:2012/1/31
© 2009 suzuki tomoya. All right reserved.