

厚生労働省は、
「固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から
・営業職に女性はほとんどいない
・課長以上の管理職は男性が大半を占めている
等の差が男女労働者の間に生じている場合、このような差を解消しようと、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組」
と定義している。
また、女性の能力発揮促進に関する研究会が、1997年に発表した「女性労働者の能力発揮推進のための企業の自主的取り組みのガイドライン」において、ポジティブ・アクションが取り上げられており、
ポジティブ・アクションを
「企業が法に基づき、差別扱いを撤廃することに加え、さらに、女性の能力発揮を促進し、その活用を図る積極的な取組」
と定義し、具体的には
①女性の採用拡大
②女性の職域拡大
③女性の管理職の増加
④女性の勤続年数の伸長(職業生活と家庭生活との両立)
⑤職業環境・風土の改善(男女の役割分担認識を解消する)
といった取り組みが必要であるとしている。
①労働意欲、生産性の向上━性にとらわれない公正な評価により活力を創出する━
…男性優位の企業風土がある場合に、そのような風土を見直し、能力や成果に基づく公正な評価を徹底することは、女性社員の労働意欲と能力発揮を促すきっかけとなる。また、女性の活躍が周囲の男性にも良い刺激を与え、結果的に生産性の向上や競争力の強化をもたらすことにつながる。
②多様な人材による新しい価値の創造━多様な個性による新たな発想━
…市場が多様化する中で、これからの新しいニーズに対応した商品、サービスを提供するための新しい発想が求められている。男女に関わりなく、多様な個性をもった人材を確保し、その能力を最大限に発揮させることは、これまでにない新しい発想を生み出す可能性がある。
③労働力の確保━労働者に選ばれる企業へ━
…少子・高齢化が進んでいる我が国においては、労働力不足が見込まれており、女性の活躍が大いに期待されている。ポジティブ・アクションを積極的に実施する企業は、働きやすい企業、男女に関わりなく公正に評価される企業として認知され、選ばれることになり、幅広い高質の労働力を確保することができる。
④外部評価(企業イメージ)の向上━人を大切にするというイメージの獲得━
…ポジティブ・アクションを実施し、社員の能力発揮と育成に積極的に取り組む企業姿勢は、経営の持続的発展が期待できる企業として、顧客や株主、取引先等の利害関係者からの信頼や好意的な評価を得ることができる。
平成22年度雇用均等基本調査によると、ポジティブ・アクションについて、各企業は
「取り組んでいる」…28.1%
「今後、取り組むこととしている」…10.6%
「今のところ取り組む予定はない」…60.4%
と答えた。
しかし、企業の規模によって割合が異なり、「取り組んでいる」企業割合は、規模が大きい企業ほどその割合が高く、「今のところ取り組む予定はない」とする企業割合は、規模が小さい企業ほどその割合は高くなっている。
第四条
1.締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなつてはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。
2.締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条約に規定する措置を含む。)をとることは、差別と解してはならない。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(国の責務)
第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(女性労働者に係る措置に関する特例)
第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
第十四条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。
一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成
三 前号の計画で定める措置の実施
四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備
五 前各号の措置の実施状況の開示
三度の改正により、募集・採用・配置・昇進・教育訓練・福利厚生・定年・退職・解雇において男女差をつけることが禁止されたほか、ポジティブ・アクションの推進や、差別禁止範囲が拡大されたことで、男女双方の差別が禁止となった。
男女雇用機会均等法が社会的に与えたインパクトは強く、そのため明白な男女差別は許されないという認識が広く浸透した。しかし、法律の施行と同時に、女子社員を二分する「コース別雇用管理制度」を導入する企業が出てきた。
具体的には、「一般職」と「総合職」に職務を分け、「一般職」では事務職をはじめとした補助的労働で転勤がないこと、「総合職」では営業をはじめとした基幹的業務を行い転勤がある、といった違いがある。
これにより、ごくわずかな女性総合職と、圧倒的多数の女性一般職という女性間の職域分離が進行した。規模の大きい企業ほど導入している割合が高く、また男女雇用機会均等法は雇用管理区分内の均等を指針としているため、一般職と総合職で区分が異なることで格差が生まれる。
また、1997年に男女雇用機会均等法が改正されたと同時に、女性労働者に時間外・休日労働、深夜業を規制していた労働基準法も改正され、女性労働者は母性保護以外には男性と同じ扱いを受けることとなった。男性と同じ扱いを受けるということは、長時間残業する男性と同様に残業しなければならないということになり、家庭をもつ女性にとっては働き続けることが困難となった。
このことから、法律の限界が明確となり、企業の自主的な取組がより一層求められるようになった。
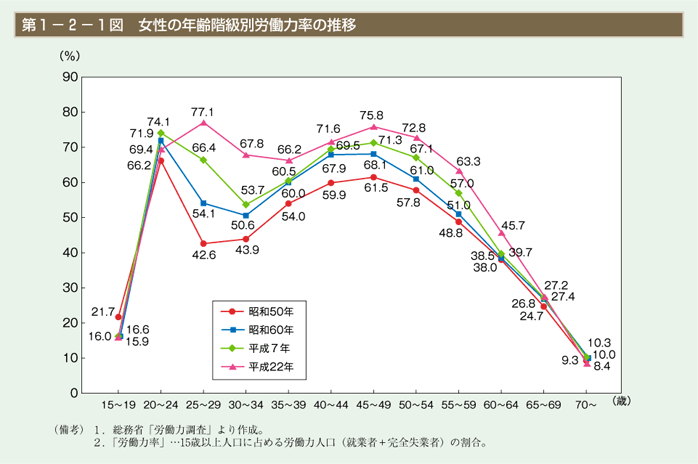
②勤続年数階級別一般労働者の構成割合の推移(性別)
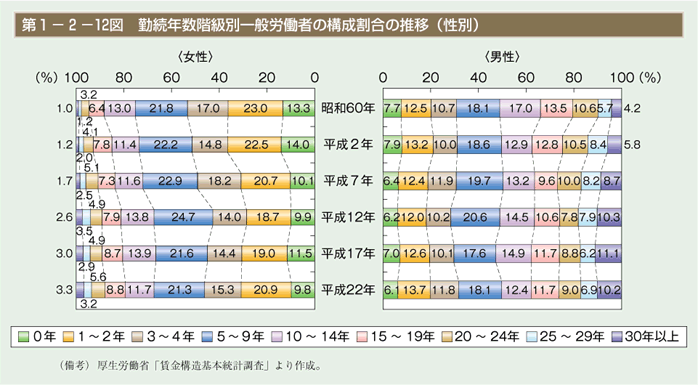
③役職別管理職に占める女性割合の推移
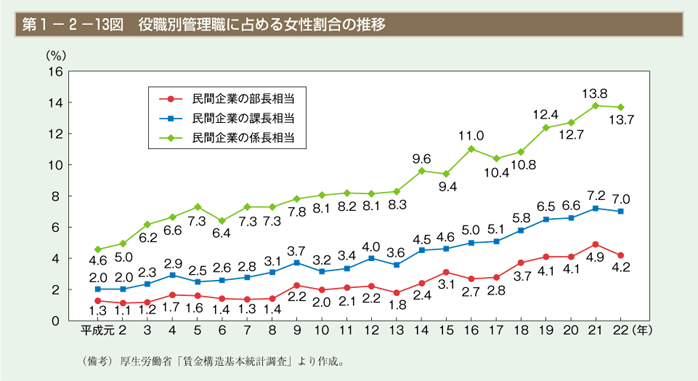
④男女間所定内給与格差の推移(男性の所定内給与額=100)
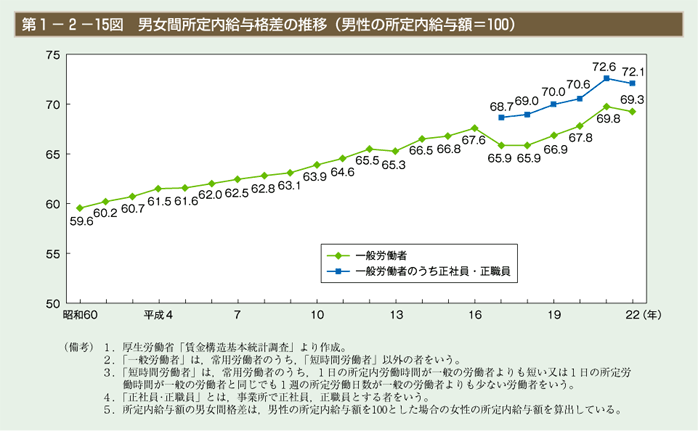
⑤「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」といった考え方について
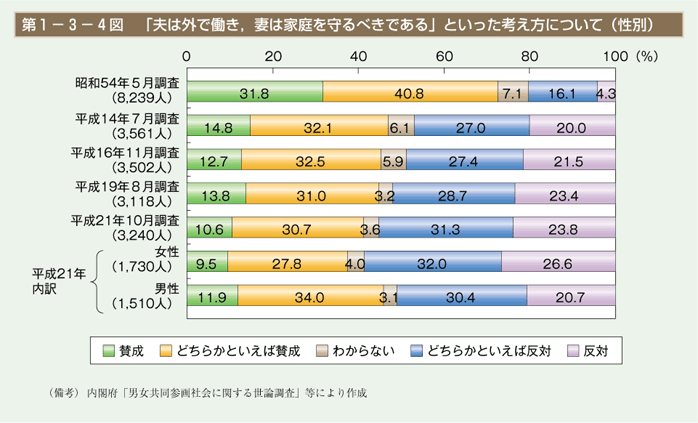
⑥配偶関係・年齢階級別女性の労働力率の推移
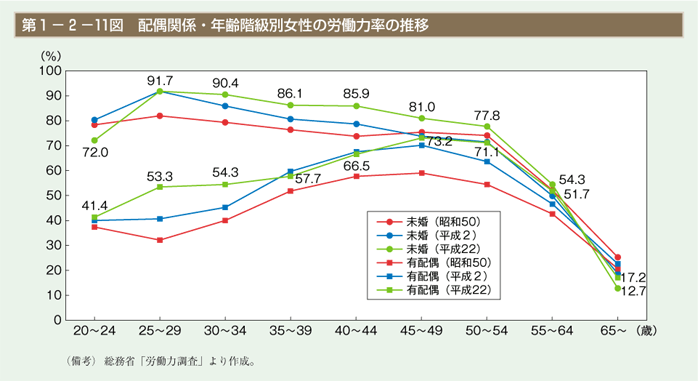
⑦女性のライフステージに応じた働き方の希望と現実
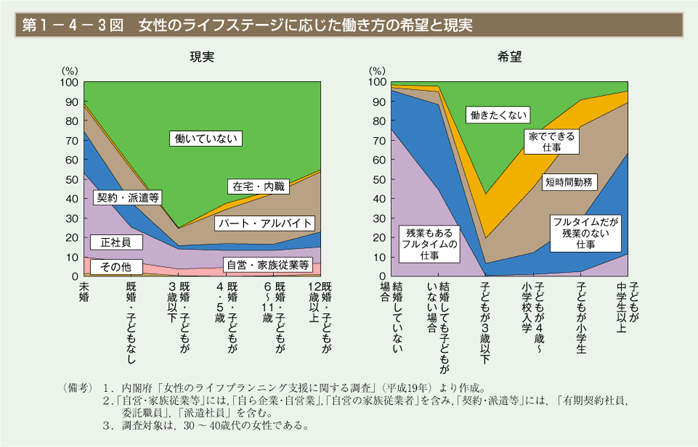
⑧女性の参画や能力発揮を阻む要因
男女共同参画局専門調査会「女性の活躍による経済社会の活性化」中間報告によると、女性の参画や能力発揮を阻む要因として、
・夫の収入が高い層では妻の就業率が低い
・固定的な性別役割分担意識を前提とした社会制度や慣行
・現状をベターと考え、あえて変化を望まない意識があるとの指摘
・先進国中で低い日本の女性の高等教育在学率
・正社員以外の雇用の場合、教育訓練を受ける機会が少ない
以上の5点を挙げている。
Ⅳ.政府の取り組み
平成22年12月17日 第3次男女共同参画基本計画(閣議決定)
…政策・方針決定過程への女性の参画の拡大について、「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度になるように期待する」という目標(平成15年6月20日男女共同参画推進本部決定。「『2020年30%』の目標」)の達成に向けて、政治、司法、行政、雇用、農林水産、教育、科学技術・学術、地域・防災の分野における成果目標(24項目)等を設定。
平成23年2月 男女共同参画会議 基本問題・影響調査専門調査会を設置
…ポジティブ・アクションの推進方策をテーマの一つとする。
平成23年3月 基本問題・影響調査専門調査会 ポジティブ・アクション ワーキング・グループを設置
…政治、行政、雇用、科学技術・学術分野に重点を置いて、実効性のあるポジティブ・アクションを推進する具体的な方策を検討。
平成23年7月 中間報告の取りまとめ
…最終報告に向けた検討事項として、①政治分野におけるクオータ制等の検討に資する具体的事例等の提示、②公共契約を通じた雇用分野の女性の参画拡大の更なる推進方策の検討の二点を挙げた。
平成23年12月 ポジティブ・アクション ワーキング・グループ 最終報告の取りまとめ
①ポジティブ・アクションの必要性
・高い緊要度
…日本における女性の参画は徐々に増加しているものの、先進国の中で低い水準であり、しかも差は拡大している。これまでの延長線上の取組を超えた効果的な対策として、暫定的に必要な範囲において、ポジティブ・アクションを進めていくことが必要である。
・実質的な機会の平等の確保
…固定的性別役割分担意識や女性の能力に関しての偏見が根強く、過去からの経緯などにより、現状では男女の置かれた社会的状況において個人の能力・努力によらない格差があるのが現状である。よって子どもの頃から固定的性別役割分担意識の解消を図ることが必要となる。また、形式的な機会の平等の付与だけでは困難である。
・多様性の確保
…多様性の確保は、政治分野においては民主主義の要請であり、行政分野においては、バランスのとれた質の高い行政サービスの実現にもつながる。民間企業の経済活動や研究機関の研究活動においても、多様な人材の発想や能力の活用は、組織・運営の活性化や競争力の強化等に寄与する。
②ポジティブ・アクションの考え方
・概念
…一般的には、社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機会を提供することなどによって、実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定的な措置である。
・手法と推進方策
…ポジティブ・アクションには、多様な手法や国の方策があり、各機関・団体の特性に応じて最も効果的なものを選択することが重要。
多様な手法:①クオータ制、プラス・ファクター方式など、枠などを設定することによって、その実現を確保する方式
② 達成すべき目標と達成までの期間の目安を示してその実現に努力するゴール・アンド・タイムテーブル方式
③研修の機会の充実、仕事と生活の調和など基盤整備を推進する方式
国の方策:①各機関・団体に取組を義務付け
②インセンティブの付与によって各機関・団体の自主的な取組を政策的に誘導
③各機関・団体に自主的な取組を要請
・能力主義との関係
…企業、大学などにおける採用・登用はいわゆる「能力主義」の下で行われるのが一般的であるが、能力の評価基準が必ずしも客観的とは限らないことや、評価基準が男女で同じように適用されない場合などもある。
このような場合には、
・採用・登用のプロセスの中で固定的性別役割分担意識を解消する取組の推進や、女性に対する実質的な機会の平等が確保されるよう、評価方法の見直しが必要である。
・その他、女性に対する機会の平等を実質的に担保するポジティブ・アクションの検討も有効である。
・理解の浸透
…ポジティブ・アクションによって登用されることに「スティグマ(劣性の烙印)」の意識を持つ女性がいることに対する配慮が必要である。また、ポジティブ・アクションは、女性本人だけでなく、社会全体にとってもメリットがあり、女性にとっても男性にとっても生きやすい社会である男女共同参画社会を実現する最も効果的な施策の一つであることをアピールすることも必要である。
③各分野における推進方策
1.政治分野
<女性の政治参画に関する社会的気運の醸成及び政党への働きかけ>
⇒・日本と世界の状況を平成23年版白書の特集等を活用し、広く周知させる
・調査会で整理した諸外国の事例を提示しつつ、政党に対し女性候補者の増加とポジティブ・アクションの導入の検討を更に働きかける
・その際、各党各会派における選挙制度の検討において、政治分野における女性の参画の拡大も論点の一つとして考慮することも重要である
<ポジティブ・アクションの検討に資する具体的事例の提示>
⇒・政党関係者の間で具体的な議論が喚起されるよう、87か国で導入されているクオータ制の取組等の中から、日本の参考になりうる事例等を整理する
<選挙制度と女性の政治参画>
⇒・小・中・大選挙区制、比例代表制、更には定員・区割りといった選挙制度は女性議員の選出されやすさに大きく影響する。選挙制度等の在り方の検討の際には重要な論点として考慮が必要である。
2. 行政分野
<女性国家公務員の採用・登用の促進>
⇒・各府省における「女性職員の採用・登用拡大計画」を着実に実施する
・第3次男女共同参画基本計画の成果目標を確実に達成する
<国のあらゆる施策における男女共同参画の視点の反映>
⇒・私的懇談会等において女性の参画を拡大する
・国家公務員制度改革の推進
・採用から幹部までの各段階に応じた人事制度改革において、女性登用のためにも官民人材交流、職員公募を一層推進させる
3. 雇用分野
<具体的な目標の設定の促進等>
⇒・ゴール・アンド・タイムテーブル方式等を取り入れた企業の具体例・成功例を公表し、情報共有する
・ポジティブ・アクションに取り組む企業を表彰等により積極的に評価する
<公共契約を通じた推進方策>
⇒・内閣府から地方公共団体に対し、
①競争参加資格設定において社会性等を評価する審査項目を設定する場合、
②調査、広報、研究開発事業等において総合評価落札方式を適用する場合で
男女共同参画等に関連する事業を実施する際は、男女共同参画等に関する項目設定の検討を依頼する
・内閣府において、地方公共団体における上記取組状況や事例を調査し、その成果を広く情報発信する
・現在、国において総合評価落札方式が適用されている、調査、広報、研究開発事業のうち、男女共同参画等に関連する事業を実施する際は、内閣府から各府省に対し、男女共同参画等に関する評価項目の設定を依頼するとともに、その取組状況を調査する
<補助金等における推進方策の積極的な活用>
⇒・先進的な事例としての男女共同参画を要件とするクロスコンプライアンスの積極的な活用を検討・推進する
4. 科学技術・学術分野
<具体的な目標の設定の促進>
⇒・ゴール・アンド・タイムテーブル方式やプラス・ファクター方式等に取り組む研究機関等の具体例・成功例を公表し、情報共有する
<女性研究者の参画の拡大に向けた環境づくり>
⇒・コーディネーターの配置、出産・子育て期間中の研究活動を支える研究・実験補助者等の雇用の支援など、環境整備の取組を支援する
・研究費の申請等に際し、出産・育児を考慮した年齢制限の緩和や業績評価、任期等の弾力化などの研究を続けやすい環境整備を充実・促進する
・日本学術会議に対して、科学者コミュニティにおける女性の参画を拡大する方策についての検討を要請する
女性の活躍推進協議会「ポジティブ・アクションのための提言」(最終アクセス:2012/04/13)
厚生労働省 ポジティブ・アクションの取組事例集(最終アクセス:2012/04/13)
「平成22年度雇用均等基本調査」結果概要|報道発表資料|厚生労働省(最終アクセス:2012/08/05)
男女共同参画白書(概要版)平成23年度版(最終アクセス:2012/08/05)
男女共同参画局 ポジティブ・アクションの推進について(最終アクセス:2012/08/05)
外務省:女子差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)(最終アクセス:2012/08/05)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(最終アクセス:2012/08/05)
田中哲樹 金井篤子 『ポジティブ・アクションの可能性 男女共同参画社会の制度デザインのために』 ナカニシヤ出版 2007年
杉本貴代栄 『女性学入門 ジェンダーで社会と人生を考える』 ミネルヴァ書房 2010年
伊藤公雄 樹村みのり 國信潤子 『女性学・男性学 ジェンダー論入門』 有斐閣 2011年
辻村みよ子 稲葉馨 『日本の男女共同参画政策━国と地方公共団体の現状と課題』 東北大学出版会 2005年