研究テーマ「廃棄物減量化にむけて私たちができること」
早稲田大学 社会科学部
政策科学ゼミナール4年
青木崇通
目次
- 研究動機
- 日本のゴミ処理の現状
- 廃棄物に関しての問題点
- ゴミを減らす行政の取り組み
- 外国の取り組み
- 企業の取り組み
- 地域の取り組み
- ICTの可能性
- ごみエネルギー
- 政策提言
1 研究動機
そもそも「ごみ」とはいったい何を指し示しているのか。
「ごみ」を「ごみ」として処しているのは、社会や個々人の価値観であるとも指摘される。社会や時代、また人によって、同じものでも「ごみ」として捨てる場合もあれば、価値のあるものとして生かしている場合もある。 一方で、「ごみ」の処理についてさまざまな問題が発生し、また深刻化してきている背景には、その排出量と質の問題を抜きに考えることはできない。もともと自然の中で、生物・非生物を含めた物質が過不足なく循環している時代や社会では、「ごみ問題」はないといえる。私たちの暮らす現在の社会で、これほどまでにごみの問題が深刻化している背景には、自然循環の中で対処しきれない膨大な量のものが、安易に廃棄され、しかもその中身がプラスチックを代表とする自然界にはなかった、つまり自然の循環に入りにくい性質のものであるという現状を押さえることが重要といえる。そんな中で、未来を担う我々世代が廃棄物の問題に関して研究することに意味があると感じたから。
2 日本のゴミ処理の現状
・一般廃棄物と産業廃棄物
廃棄物処理法では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物の二つに分類している。
・一般廃棄物�
一般廃棄物とは産業廃棄物以外のすべての廃棄物であると定義されているが、具体的には主に家庭から排出される生ごみや粗大ごみ、オフィスから排出される紙くずなどである。
�
→市町村の責任で適切な処理が行われている。
・産業廃棄物�
産業廃棄物とは製品の製造などの事業活動に伴って工場などから排出される廃棄物のうち、大量に排出されたり、質的に処理が困難であるもので、その性状により燃えがら、汚泥、廃プラスチックなど19種類が定められている。
�
→排出した者が自ら処理するか、都道府県知事などによって許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。
3 廃棄物に関しての問題点

なぜ日本にゴミが多いのか・・・最大の理由は物の売り方!
食品トレーや牛乳パックなどの食物包装物を多く出してしまう。
だから、日本は 他の国に比べて一人当たりの排出するゴミが圧倒的に多い。また、毎月の一家庭でゴミ処理費を3万円以上負担している。
↓
廃棄物処理場の不足
一般廃棄物最終処分場の残余容量と残余年数の推移
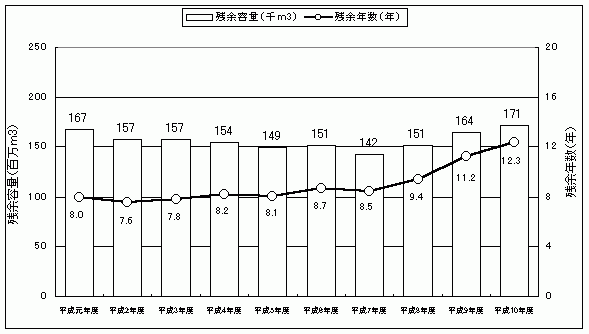 出典:一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成10年度実績)について(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課)
出典:一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成10年度実績)について(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課)
このままいくと数十年で最終処分場がいっぱいになってしまう!
4 ゴミを減らす行政の取り組み
・容器包装リサイクル法
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
ペットボトル,ガラスびん,スチール缶やアルミ缶,牛乳などの紙パック生鮮食料品や惣菜のトレー,段ボールを各家庭で分別してごみ出しし,自治体が収集し,企業が再商品化するというリサイクルに関するそれぞれの役割を明確にしました。

スチール缶リサイクル協会HPより出典
・家電リサイクル法
今まで廃棄物として処理されていた家電製品の再資源化を図るために制定された。 家電製品のうち,エアコン,テレビ,冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機を消費者は,適正な引き渡しを行うとともに,リサイクルの費用を負担するようになった。小売店はこれらの対象商品の収集と運搬を行い,メーカーはリサイクルを行う。リサイクル処理によって,鉄,銅,アルミニウム,ガラス等が回収されています。また,エアコン,冷蔵庫等に用いられているフロン類も回収され破壊されています。
5 外国の取り組み
5−1 ドイツ
・日本との意識の違い
日本・・・ゴミが出てしまったらとりあえずリサイクル。
ゴミを出さないという意識が低い。
ドイツ・・・reuse,reduse,refuse,この3つをした後それでも出てくるゴミをリサイクルする。リサイクルは最終手段という意識。
・具体的な取り組み
ドイツでは、野菜や果物がスーパーで量り売りされていたり、リユースカップで飲む自動販売機が置かれていたり、町によっては飲食店で使われる使い捨ての容器や食器に税金をかけたりとゴミの出ない工夫がされている。
また、フライブルク市では、黒、緑、茶色、黄色という4色のゴミ回収容器を使って、各家庭で丁寧な分別が行われる。黒は紙おむつなどリサイクルできないゴミで、埋め立て処分される。緑は紙のゴミで、専門のリサイクル会社に運ばれ、古紙として再利用される。茶色は生ゴミで、これも肥料にするため専門のリサイクル会社に運ばれる。黒も緑も茶色も、回収は有料となっている。� ユニークなのは黄色い容器。ここには、「緑のマーク」のついたペットボトルやプラスチック容器、牛乳パック、そしてお菓子の包み紙などを入れる。ここに入れたものは、DSD(ドイツ・デュアルシステム)社という会社が無料で回収して、リサイクルをする。
このように、使い捨て容器に高額の税金、ゴミの完全分別、生ゴミの堆肥化、デポジット制の導入などが整然と実施することで
ゴミを作らない、売らない、買わない社会システムの基盤がしっかり整備されている。
5−2 スウェーデン
・スウェーデンのゴミ事情
約100年前から環境系NGOが設立されるなど、環境先進国と言える北欧スウェーデンでは、驚くべきことに、国内のゴミの99%が再利用されている。そればかりか、他のヨーロッパ諸国からわざわざゴミを買い取ってさえいる。
スウェーデン政府は、全国民に平等にゴミ問題に関する厳格なルールを適用している。例えば、生産者は、製品の回収やリサイクルなどに関する費用を全て負担しなければならない。こうした取り組みもあり、スウェーデンのゴミ排出量は、ヨーロッパ諸国の平均よりも少なくなっている。
・ゴミ処理の仕組み
回収されたゴミは、リサイクルできるものはリサイクルされる。問題はそうでないものだ。スウェーデンでは、リサイクルできないゴミを廃棄物発電施設で燃やし、発生した蒸気でタービンを回し、電力にかえているのだ。同国では、3トンのゴミは約1トンの石油燃料に匹敵するとされているのだ。
効率的な燃焼により発電された電力は、スウェーデンの寒い冬を暖める、家庭の暖房燃料の約半分を担っている。スウェーデンでは、別のエネルギーに変換することで効率がよくなり、埋め立て地に行くゴミは全体のたった4%といわれている。
6 企業の取り組み
・江崎グリコ
1.工場での廃棄物を削減するために、江崎グリコグループ取引先と協力して原材料の品質を損なわない限界まで包装材を削減する取り組みをしている。
2.食堂で出る生ごみをすべて肥料に変えている。
イオン
1.reduseの例:ハンガー納品で輸送用の段ボール箱やハンガーを減らしている。
2.reuseの例:リターナブルコンテナで段ボールの使用を減らしている。
3.recycleの例:廃油も100%リサイクルしている。
日本自動車工業会
2005年1月より自動車リサイク法が施行された。同法によって、自動車メーカー、輸入業者にフロン、エアバック、ASR(シュレッダーダスト)の引き取りとリサイクル・適正処理を義務づけています。これによりリサイクル率は施行前の80%程度から90%以上まで向上した。
また、リデュース・リユース・リサイクルの観点からは、自動車を設計する際に軽量化や原材料の工夫等を図るとともに、製造過程で発生する特定副産物の発生抑制及びリサイクルに取り組んでいる。
 日本自動車工業会調
日本自動車工業会調
7 地域の取り組み(徳島県上勝町)
上勝町は、平成15年9月19日に、未来のこどもたちにきれいな空気や美味しい水、豊かな大地を継承することを目的とし、「ごみゼロ(ゼロ・ウエイスト)宣言」を日本で初めて発表しました。その宣言に盛り込まれている内容は、以下のとおり。
宣言文� 1. 地球を汚さないひとづくりに努めます!� 2. ごみの再利用・再資源化を進め、2020年までに焼却・埋め立て処分なくす最善の努力をします!� 3. 地球環境をよくするため世界中に多くの仲間を作ります!
そして、上勝の分別数はなんと34!分別数の多さ、日本一!


グリーンズHPより出典
上勝百貨店
パスタもシャンプーも量り売りする、「ごみを出さない売り方」にこだわるお店。買い物袋も新聞紙でできている。
ものを買うことは、ごみを増やすことではない。

グリーンズHPより出典
8 ICTの可能性
ICTとは?
ICTとは、情報処理および情報通信、つまり、コンピュータやネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設備・サービスなどの総称である。IT(情報技術)のほぼ同義語。2000年代半ば以降、ITに替わる語として、主に総務省をはじめとする行政機関および公共事業などで用いられている。
社内ペーパーレス計画
ソフトバンクグループでは社員全員にiPhone、iPadを貸与し、ペーパーレスに取り組んだ。紙資料の削減に向かって、社内インフラを積極活用しつつワークフローを確立。総務関連の書類はデータ上で承認まで完結できるようにしたり、会議の資料や報告書の確認はiPadとPCを併用してペーパーレスで行うスタイルを徹底したりなど、推進委員会やそれぞれの組織・部門の社員が知恵を絞りながら、全社共通と組織特有の施策を並行で展開した。その結果、5カ月後には、目標にしていた社内業務ペーパーゼロをほぼ達成した。
9ごみエネルギー
一般廃棄物を対象とした廃棄物発電は,その施設数・発電量ともに年々増加する傾向にあります。一方で,焼却処理施設の数は年々減少する傾向にあり,1施設当たりの処理量が増加している。実は,この傾向は廃棄物発電と密接な関係があり,ある程度大きな規模を持った焼却処理施設でないとなかなか効率的な発電ができないことが理由の一つとなっている。これに対し,産業廃棄物を対象とした廃棄物発電はあまり行われておらず,廃棄物発電施設数で69ヵ所,総発電量で204 MW(平成15年度 資源エネルギー庁のデータに基づく)となっている。これは,産業廃棄物の再生利用量が多いことや,「燃えるごみ」の割合自体が小さいことなども理由として考えられますが,一般廃棄物が主に自治体など公的機関により処理されるのに対し,産業廃棄物は主に民間で処理されるため大規模化が難しいこともその一因となっています。規模が小さい焼却施設に見合う発電設備は,効率の面で大規模な設備よりも劣りますし,発電設備そのものを付け加えることでその分コスト高になるので,結果的に廃棄物発電を増やすことが難しい状況にあります。そこで,このような小規模でも高い発電効率が期待できる,「廃棄物ガス化発電」技術が注目されるようになってきている。
ガス化によるエネルギー有効利用に向けた技術開発
「燃えるごみ」の持つエネルギーを有効に利用するための技術の一つである廃棄物ガス化技術は,国内外を問わず幅広く研究されています。国立環境研究所においても,循環型社会研究プログラムにおいて「廃棄物系バイオマスのWin-Win型資源循環技術の開発」の一部として研究が進められています。具体的には,廃木材,紙ごみ,廃プラスチック,都市ごみ等を対象として,650〜850℃に加熱しつつ水蒸気を同時に供給すると,これら廃棄物が蒸し焼き状態になり,水素を多く含む燃料ガスが生成します。さらに改質触媒という材料を用いることで,燃料ガス中に含まれる有機物も分解され,水素,一酸化炭素が大半を占める燃料ガスに変換されます(図5)。この時,ダイオキシンや多環芳香族炭化水素等の有害な物質も同時に分解されるため,環境負荷低減という意味においても優れた技術と言えます。これまでの研究成果から,非常に高い濃度の水素を作り出せることや,ガスエンジンによる発電が可能な発熱量を持つ燃料ガスへの変換が可能であること等を明らかにしています。現在は,改質触媒の耐久性を向上させるための検討や,さらに有害成分を低減するための方法について研究を進めています。
10政策提言
1ゴミの有料化
2012年1月現在、全国810市区に占める比率53.6%の地域において実施されている。そして、有料化が実施された地域どの地域でもではある程度の成果は出ている。また、ドイツにおいても成果は出ている。この点において、まだ実施していない地域もゴミの有料化をすることは得策であると考えられる。また、このゴミの有料化は国民に対して、ゴミは出してはいけないものという意識付けをする役割を担うであろう。
2量り売り
日本と外国で大きく異なるのがやはりモノ売り方だ。そしてこのモノの売り方が日本のゴミが多い原因となっているわけだ。そう考えると量り売りは衛生面の問題のなどの問題があるが、廃棄物減量化に関していえば、かなり有効な手段であると思われる。上勝百貨店のような店は買う側からしてみれば効率の悪いかもしれない。しかし、もう効率が悪くても量り売りのような対策をしなければいけない状況にあることを自覚しなければならない。
3ICTの活用
主に、企業に関してであるがICTを導入する。そうすることで膨大なオフィス書類をゼロとわ言わないまでも、確実に減らすことができるのではないだろうか。また、各家庭でも紙媒体の新聞ではなく、電子新聞を推奨することでゴミを減らすことができると思う。
4ごみ=資源
かつてはごみの焼却処理とは最終埋立処分のための減量化を主な目的としていましたが,近年の地球規模での環境問題・エネルギー問題の観点から,ごみも資源として見直されるようになってきた。もちろん,資源回収や効率を優先するあまり有害な成分を排出してしまっては本末転倒です。廃棄物を適正に処理しつつ,可能な限り資源として再利用するためのWin-Winなシステムを構築すべき。また、韓国や中国にしか行っていないゴミ輸出をヨーロッパにまで拡大するべき。
上記の行政、企業の取り組みを見るとわかるようにある一定の成果は出ている。しかし、抜本的な解決に至っているわけではない。本当に、国民一人一人がゴミ問題に対して意識することで問題の解決が見えてくると私は思う。結果を出している国(ドイツ、スウェーデン)、地域(上勝町)は対策が効果を成しているのもあるが、やはり一人一人の環境意識が高い。精神論のようで私はあまり好まないが、上記の政策提言プラス、皆がゴミ問題に対しての危機感を高めることが一番効果的な政策であると思う。意識が変われば行動が変わる、行動が変われば環境が変わる。
参考資料
『フライブルク環境レポート』中央法規出版
スチール缶リサイクル協会HP(アクセス日2014年1月23日)
日本自動車工業会HP(アクセス日2014年1月23日)
IT用語辞典バイナリ(アクセス日2014年8月5日)
環境省HP(アクセス日2014年8月9日)
ソフトバンクHP(アクセス日2014年8月9日)
ネットワーク地球村(アクセス日2014年8月9日)
グリーンズHP(アクセス日2015年1月18日)
TABI LABO(アクセス日2015年1月26日)
エコライフガイド(アクセス日2015年1月26日)
Last Update:2015/02/04
© 2012 Aoki Takamichi.All rights reserved.

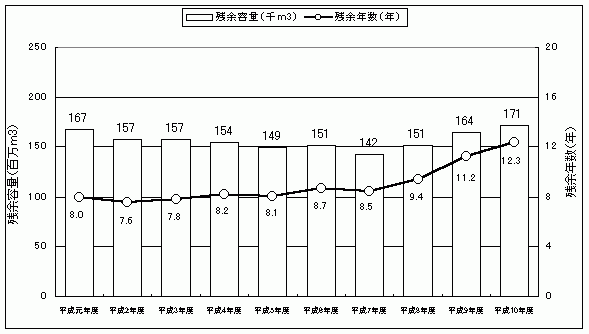 出典:一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成10年度実績)について(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課)
出典:一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成10年度実績)について(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課)
 日本自動車工業会調
日本自動車工業会調


