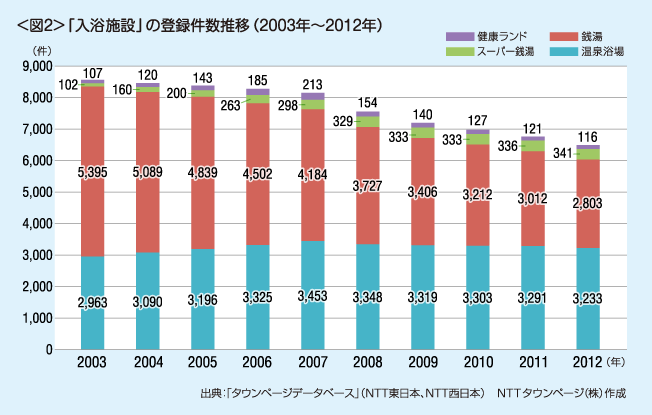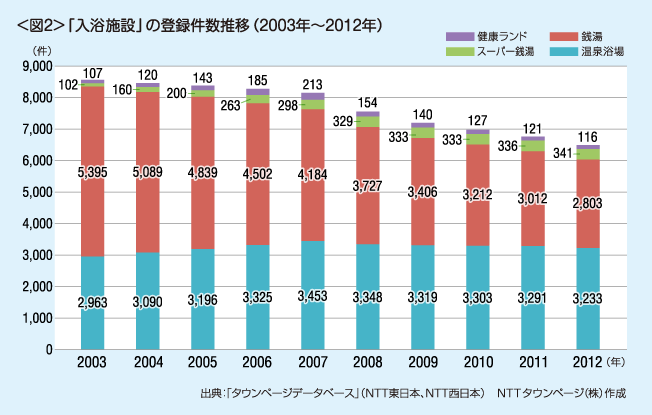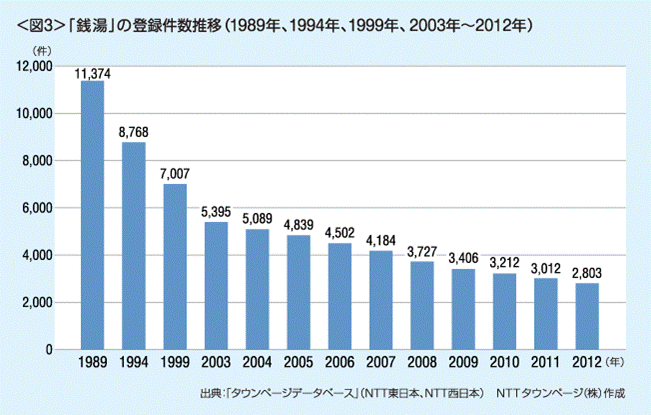銭湯の活用策について考える
社会科学部4年
政策科学ゼミナールⅢ
遠藤将
章立て
- 研究動機
- 第1章 銭湯について
- 第2章 銭湯の現状、減少の主な原因
- 第3章 新しい銭湯
- 第4章 銭湯の存在意義
- 第5章 新たな活用策
- 参考文献
研究動機
自分は銭湯に行ことが好きでよく地元の銭湯などを利用するのだが、利用者も少なくも少なくどうして成り立っているのだろうと疑問に思うことも多かった。
実際に銭湯の数が減ったという話を聞くことはとても多い。
自分が今までに行ったことがある場所も昔も今も何も変わらず営業努力をしているといった様子もあまり見られない。
ほとんどの家にお風呂がある現在、自分が行っているところも含め今後銭湯はさらに減っていってしまうと思う。
しかし、銭湯による地域コミュニティーの形成など銭湯だからこそ出来ることもあると思った。
銭湯は日本のひとつの大事な文化でもあり、どうにか残していくため具体的な方法や銭湯の活用法について研究してみたいと思ったためこのテーマにした。
第1章 銭湯について
まず、銭湯とは物価統制令に基づく条例により料金規定がある風呂屋を指し、いわば普通公衆浴場のことである。
現在東京ではその料金を上限460円と定められており、料金が自由設定となっている、スーパー銭湯 や健康ランドとは異なる。
銭湯の価格は戦後に制定された「物価統制令」によって決められている。
これは闇市などによって値段が不当に上がってしまうことを防ぐために制定されたものであるが、今の日本に残っているのは銭湯の料金にのみである。
銭湯は終戦後、市民の生活衛生を目的とした施設として都市部を中心に多くの現れ出す。
当時は家に風呂が無いのが当り前の時代であったため、銭湯は1970年代まで30年近くの間、盛況が続いた。
第2章 銭湯の現状、減少の主な原因
銭湯の数は1989年から2012年の23年間で、 11,374件から2,803件と4分の1以下にまで減少している。
東京都内で一週間に一軒、全国で一日一軒のペースでなくなっている。
減少の主な原因としては、一般家庭への浴室の普及によって利用客が減少したこと、経営者の高齢化および後継者の不足、また、オイルショック以降ずっと続いている燃料費の高騰、スーパー銭湯等の類似代替施設の台頭、そして、施設の老朽化などが挙げられる。
→中でも浴室の普及が最も大きな原因であり現代では9割以上の家庭に風呂はあるため、銭湯が減っていったのは自然な流れであるといえる。
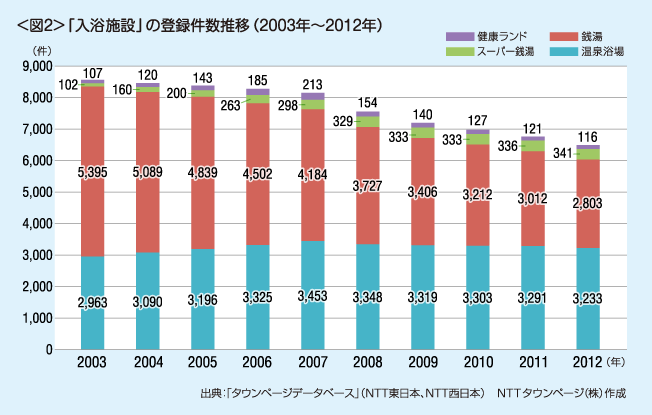
※ NTTタウンページ より抜粋
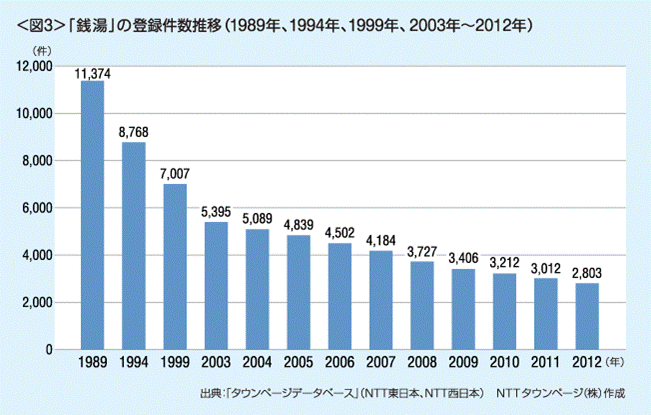
※NTTタウンページより抜粋
第3章 新しい銭湯
各家庭にお風呂があるのが当たり前になったことを背景に、年々銭湯が減少しているという中、銭湯をリニューアル等によって新たな客を呼び込む動きが行なわれている。
- デザイナース銭湯
古くからの銭湯を改装し展開するというもので、リノベーション物件の一例として話題となっている。
従来の銭湯とは一線を画す内装を施すなどの工夫がされていて、束の間のひとときを違った雰囲気で過ごせるという点で老若男女問わず支持されている。
例としては、千駄木ふくの湯(昭和47年創業の老舗。温泉旅館を感じさせる和モダンな雰囲気が魅力)、南青山清水場(昭和47年創業の老舗。温泉旅館を感じさせる和モダンな雰囲気が魅力)、品川区天神湯(様々な種類のタイルを使った高級感が魅力。
バリアフリー設計やエレベーターの設置によって高齢者などに使いやすい配慮もされている)、などが挙げられる。
- 銭湯カフェ
もともと銭湯だった建物を利用して銭湯の雰囲気を残しつつカフェにしたもの。
銭湯とカフェが一緒になっているところも存在する
長時間くつろげるような雰囲気が人気につながっている。
→このように今までの銭湯とは違い、リノベーションによって高級感などの新たな価値を加えた銭湯が成功している。
第4章 銭湯の存在意義
3章で新たな価値を加えた銭湯について述べたが、戦後の銭湯が市民の生活衛生と言う目的が薄れた現代では、銭湯の存在意義や目的を明確にしておく必要がある。ここで、銭湯の歴史を含めた定義や存在理由について述べたいと思う。
銭湯は「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」により、「住民の日常生活において欠くことのできない施設」とされている。
ビジネスとしてではなく主にお風呂がない人たちへの公衆衛生のため、また、高齢者の外出を促し、地域コミュニティを活性化させるためといった福利厚生の一部として存在しているため、今でも物価統制令が残っている。
補助がなければ著しく減少、もしくは消滅してしまう可能性があるため、国や地方公共団体がしっかり管理してサポートしなければならない、という大義名分があるため、自活できない分を国や地方公共団体からの多額の補助金でまかなわれている。
銭湯は自由競争になれば、ほとんどの自宅にお風呂がある現代、ほとんどの銭湯は淘汰されていくこととなる。
銭湯の存在意義としては実際にお風呂がなくて困っている人たちを助ける他にも、地域コミュニティとしての役割や伝統文化としての継承といった点が大きい。
→温泉宿とは違い、遠くから客を呼び込むことには限界があるということもあり銭湯は消滅しないためには地域密着型のサービスを展開していくことで残していくことが必要である。
第5章 新たな活用策
4章で地域密着型のサービスを展開していくことが必要であるということを述べたが、そのような銭湯が持っているコミュニケーションの場という特性や広いスペースなどを活かした例について述べる。
- 防災拠点としての活用
都内で最も多くの銭湯がある大田区で銭湯を防災に活用しようという動きが広まっている。
大田区では住宅が密集している地域が多く、火災等の災害が起こった際に消防車が駆けつけるまでに時間がかかってしまう場所があるため、消防車が到着するまでの間、地域の人たちに銭湯の水で消火活動をしてもらおうという試みである。
さらに、緊急時の避難所としても利用できるよう、食料や毛布などを用意している銭湯も存在する。これにより銭湯が防災拠点の一つになっているといえる。
また大田区では首都直下地震が起こった際の新たな避難先として銭湯を活用できないか検討が進められている。
→地域コミュニティが見直されてきている中で、町の銭湯が持っている地下水やコミュニケーションの場という資源が有効活用されている。
銭湯は地下水等を利用しているため災害時などにも水の確保ができ、またスペースも広いので、人も集まりやすい。ガスが止まってしまうとお湯は沸かせないが、薪でやっている銭湯ならお湯も沸かせる。
大田区では自治会と銭湯とが、災害時に協力する協定を結んでおり、他の地域も行政も一体となった取り組みを考えていく必要がある。
-
介護としての取り組み
東京都品川区「新生湯」では2003年からデイサービスセンターとして活躍している。
営業時間外の銭湯を活用したデイサービス(介護サービス)である。
自力ではなかなかお風呂に入ることができない高齢者に、ゆっくりと広いお風呂に入ってもらいたいという目的からできたものであり、この施設では営業が始まるまでの間、地域の高齢者に施設を提供している。
具体的には介護スタッフによる利用者の入浴のサポートの他、広い脱衣所を利用した健康体操、個人の体調に合わせたリハビリテーション、レクリエーションを実施している。
最近では銭湯の隣接地にサービス付き高齢者向け住宅の開設など、銭湯を中心とした総合的な介護サービスが行なわれている。
身近な銭湯でデイサービスが行なわれることで自分ひとりではなかなか入浴できない高齢者が入浴することが可能になり、また顔なじみも増えることで生活感を取り戻せるなどといった効果もある。
また介護なしの入浴が可能な場合でも、自宅での入浴に不安を感じる高齢者は多い。
そういった人にも公衆浴場に通うことで、外出のきっかけにもなるため高齢者の健康維持につなげていく効果が期待できる。
→銭湯の地域に密着しているという特徴を最大限活かしたサービスであり、特に設備改修費はかからない。
そのため衰退を辿っている銭湯業界にとって銭湯とデイサービスの組み合わせによって地域密着を目指す新しい形の介護現場を作っていくことは非常に有効な活用法であるといえる。
第5章 今後の研究
- 防災や介護としての活用法を他の地域での例も掘り下げて研究する
- 介護のように他の業界との協力した地域密着型の取り組みについて研究する
- 行政の取り組みや財政などについて調べる
- 銭湯の現状や存在意義をしっかり分析して政策提言につなげる
参考文献
Last Update:2015/07/27
© 2014 Sho Endo. All rights reserved.