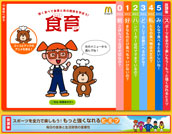学校給食と食育
早稲田大学社会科学部
上沼ゼミ4年
川村友里子
研究動機
日本の食問題について研究を進めていくと、食糧を大量に輸入している一方で、大量に廃棄しているという現状を知りました。なぜそのような事態に陥ってしまっているのかを考えていたところ、日本人の倫理観が関わっているのではないかという意見をいただきました。そこで、食への倫理観に影響を与える幼少期の食育の取り組みについて調べてみました。また、家庭でできる取り組みの例も紹介する。
章立て
- 第1章 学校給食の仕組み①
- 第2章 学校給食の仕組み②
- 第3章 栄養教諭
- 第4章 食育で何が変わるのか
- 第5章 各地域での食育推進と学校給食
- 第6章 学校給食の課題
- 第7章 家庭でできる取り組み
- 第8章 食糧廃棄物の有効活用
第1章 学校給食の仕組み①
学校給食は、学校給食法によって、「教育の目的を実現させるためのもの」と位置付けられ、義務教育諸学校の生徒に対して行われます。義務教育に位置付けられているものの、学校給食法は学校給食の実施を義務付けていません。学校給食の実施を促し、実施する場合の指針や規則、国の支援などを定めるにとどまっています。
学校の設置は義務ですが、学校給食の実施は義務ではないところが特徴です。公立の小中学校の設置所は主に市町村ですので、学校給食の設置所も市町村になります。学校給食は、市町村の住民が自らの判断で実施するかどうかを決めることができ、どんな学校給食を行うか、どのくらいの税金を投入するかなども決めることができます。そのため、運営方法によっては、学校と地域をつなぎ、教育に地域の考え方を入れることもできます。
第2章 学校給食の仕組み②
<自校方式>
自校方式は、学校の敷地内に調理場があり、そこで調理する方法です。この場合、給食の時間ぎりぎりにあわせて調理をするため、できたての食事を子供達に提供することができます。また、子供達に調理の現場を見せたり、調理中の匂いを感じさせられたりするほか、強化や学校行事とからめた給食を組み立てやすいなど、高い教育効果があります。しかし、それぞれの学校に調理場を設置するため、建設や運営コストが高くなってしまいます。
<センター方式>
これは、給食センターで、いくつかの学校の給食をまとめて調理し、配送する方法です。この方法は、多くの学校でいっせいに学校給食を導入できることや、自校方式に比べて設備費や人件費のほか、大量買付によるコスト削減が見込めるという利点があります。しかし、学校に配送する必要があるため、食べるまでの時間によっては、汁物がさめたり、麺が伸びたりなど、味が落ちてしまいます。
<親子方式>
自校方式の調理場が、近隣の学校一、二校分も調理し、供給する、自校方式とセンター方式の折衷的な方式です。
ほかにも、学校からはおかず、牛乳のみを提供し、主食は家庭から持参させる捕食方式、牛乳だけを提供し弁当を持参させるミルク給食、民間の弁当サービスを利用する外注弁当方式などがあります。
第3章 栄養教諭
2005年に導入された制度です。文部科学省は、「生徒の食生活のみだれが深刻化する中で、学校における食に関する授業を充実し、望ましい食習慣を身に着けられるよう栄養教諭制度を設ける」と発表しました。従来の栄養士などの学校栄養職員とちがい、栄養教諭は教員なので、ひとりで教壇にたち授業を行えるだけでなく、食育の担いてとして、学校の食育指導計画を推進したり、地域と結びついた食育を実施することができます。
第4章 食育で何が変わるのか
<学校給食と日本人の食生活>
農林中金研究所という機関が、学校給食と食生活への意識調査を行っています。それによると、子供は学校給食で覚えた料理を親に希望し、親がその料理を出す比率が高いことや、子供の頃に学校給食で覚えた料理を親になってからも家庭でよく出していることがわかりました。このように、学校給食は家庭の食生活に影響を与えており、子供を通じて家庭に入った新しい料理が次世代にも引き継がれていることが明らかになっています。さらに利点としては、バランスの良い食事が提供されることで食生活の改善されること、食の安全性について、正しい知識を得られることなどが挙げられます。
<食育推進と学校給食>
食をめぐる問題を総合的に解決するため、2005年には食育基本法が、2006年には食育推進基本計画が策定されました。この基本計画では、子どもへの食育に重点が置かれています。具体的な内容は、自校方式の学校給食の推進や、生産者の顔が見える地場産物の使用を推進しています。子供達に、いつどこで誰がどのように作ったかを伝えることで、学校給食は食育になるという考えです。
<企業と食育>
食育が法制化されたことから、企業も食育に力をいれはじめました。菓子メーカーのカルビーでは、2004年からカルビースナックスクールと題して、全国の小学校に出張授業を行っています。同社の社員が教壇に立ち、スナック菓子や、パッケージを使って教員と共に授業をします。マクドナルドでは、食育の時間という食育学習専門のサイトを立ち上げたり、教材の無料配布や貸し出し、出張授業を行っています。

カルビーHP
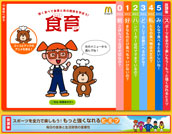
食育の時間HP
第5章 各地域での食育推進と学校給食
2006年に、学校給食法が改定されました。改定の目的は、学校給食の普及、充実と、学校での食育の推進です。栄養や食事についてだけでなく、文化や伝統、自然についての理解を深めることが目標に加えられたほか、栄養教務の職務の明記が加えられました。これにより、学校給食の教育としての位置づけが明確になりました。
<東京都の日野市>
ここでは、30年ほどまえから、地場産の野菜を学校給食に積極的に利用しています。給食にでてくる野菜が近くの畑で作られていることを生徒に話すと、それまで食べ残しが多かった野菜がよく食べられるようになったそうです。地場野菜の使用は、学校と生産者の結びつきを作りました。この輪は開始から年をかされるごとに広がり、今では市内すべての小中学校に広がりました。
そして、市内の平山小学校では、さらなる取り組みが行われています。総合の時間に、全学年が野菜やコメを、つくります。学校農園ではなく、農業指導者の畑や田んぼを借り、生産者が先生となって育て方を教えます。農作業すべての工程を体験することで、食べ物をつくる大変さや大切さを学びます。6年生になると、歴史の授業で縄文土器を学び、土器作りをします。そして、その土器で前年に栽培した古代米を炊いて食べるところまで実体験します。総合と社会の授業、歴史、農業が結びついています。
<神奈川県横須賀市>
大塚台小学校の調理員の発案で、おにぎり隊というら取り組みがはじまりました。給食の時間に、調理員が教室に出向くことで、子供達と教室とのつながりを強化します。おにぎり隊は、残しているご飯をその場で小さなおにぎりにしてくれます。食べきれなかった子供も、目の前でご飯を握ってもらうことで残さず食べるようになり、残食が減りました。この取り組みは、全国に広がりつつあるそうです。
第6章 学校給食の課題
・学校給食の合理化
・調理コストの切り下げ
・安全性の追求
第7章 家庭でできる取り組み
日本の食品ロスは、年間500~800万トンと言われています。そしてその内の200~400万トンは、家庭からのものです。この家庭からの食品ロスを減らす方法の一つとして、農水省などは冷蔵庫や冷凍庫の活用を進めています。近年は、自然解凍でもおいしく食べられる冷凍食品が普及している。朝、冷凍庫から取り出したお惣菜を凍ったままお弁当に入れると、お昼にはうまく解答されて食べごろになってくれる仕組みだ。このような冷凍庫の活用で、食品ロスが減るのではと期待されています。
第8章 食糧廃棄物の有効活用
これまで学校給食の現場においての食育について見てきたが、どうしても食糧廃棄をゼロにすることは出来ない。そこで以降は、どうしても出てしまう廃棄物を活用する方法を探っていきたい。
<スウェーデンの取り組み>
現在、スウェーデンでは家庭ごみの99%が再利用されている。家庭から出た食糧廃棄物も例外ではなく、生ごみをバイオ燃料として活用している。これにより発電された電気によって公共機関の電気を賄っているのだ。このような取り組みを日本全体でも取り入れていきたい。
参考文献
牧下圭貴(2009)『学校給食 食育の期待と食の不安のはざまで』岩波書店
カルビーHP(最終アクセス 2015.1.28)
食育の時間HP (最終アクセス 2015.1.28)
日野市HP
(最終アクセス 2015.1.28)
学校給食ニュースHP
(最終アクセス 2015.1.28)
『朝日新聞』 2015年1月28日 夕刊 6ページ
Last Update:2015/07/27
© 2014 Yuriko Kawamura. Allrights reserved.