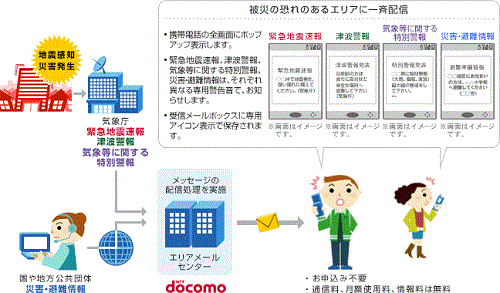災害とメディア
~多くの命を救うために~
政策科学研究ゼミⅢ
社会科学部4年
宮本直毅
研究動機
筆者がこの研究に取り組むことを決意したことには、2つの理由がある。
1つ目は、筆者は熊本県出身であり、2016年4月14日に発生した熊本地震を家族や友人が被災した。その際、食料や飲料水などのような支援物資が必要であった。しかし、支援物資は、新聞やテレビ・ラジオなどのマスメディアが報道をする、1番の災害地であった益城町を中心に届けられた。
そのことにより、被害こそ益城町ほど大きくなかったが、1番人口が密集していた熊本市には、十分な食料が届けられていない様子を目の当たりにした。
今回は、餓死者こそ出なかったものの、多くの人が食料・飲料水を求めてSNSなどの投稿を頼りに行動をする様子を見て、緊急時にこのような様子では非常に危険であると思い、この題材に興味を持った。
2つ目は、筆者がインターネットが好きである点である。幼少期を熊本県ですごし、新しいものに興味をもった。そこで、IT業界などでの複数のインターンシップの経験を活かし、SNSやWebという新しい角度から、現状のメディアに加えた、新しい情報提供方法を探りたいと考えた。
洪水・台風・地震・火山噴火というように、世界でも有数の災害大国の日本。1年を振りかえっても、大規模な災害は後を絶たず、毎回のごとく死傷者が多発している。そこで緊急事態に際して多くの人に迅速かつ正確な情報を伝える手段はないか?それは、世界の災害時にも役立つのではないか?と筆者は考え、今回の研究に取り組む事を決意した。
その際、筆者は、特に、近年使用者が増加しているスマートフォンに注目した。近年ではTwitterやFacebook、instagramをはじめとして多くのユーザー数を持つsocial network survice(以下SNS)を中心として、多くのユーザーが使用している。SNSを活用して、2次災害を防ぐことはできないのか?
テレビ・ラジオ・新聞といったマス・メディアと、スマートフォン・パソコンなどのソーシャルメディアの両者を使い、支援物資や被害状況などを伝えるネットワークを作り上げることができれば、二次災害を防ぐことができると考えた。
その方法を模索していきたい。
章立て
- 第一章 日本における災害対策の現状分析
- 第二章 現代におけるソーシャルメディアとマスメディアの定義と役割
- 第三章 過去の震災時におきたソーシャルメディアの活用例
- 第四章 緊急地震速報の情報拡散方法
- 第五章 ソーシャルメディアとマスメディアの融合例
- 第六章 この研究における重要な課題点
- 第七章 重要な課題点に対する政府の見解と対応策
- 第八章 その他災害に関連する対策を行うステークホルダー
- 第九章 政策提言
- 第十章 研究を通して感じたこと
第一章 日本における災害対策の現状分析
ここでは現状の日本の災害防止策について記述する。
現在、政府の災害防止策としては、津波に対する防波堤の設備など一次災害に対するものが多い。これまでにも複数の大規模災害(地震/台風/火山噴火/水害など)を経験しつつ、様々な予測こそされている。
一方で、二次災害に対する対応策は少ないように感じられる。特に、東日本大震災/熊本震災/北海道震災など、頻繁に大規模な震災が起こっているのに対して、毎度正確な指示などは伝わらず、全くと言っていいほど進展が見られない。
以下では、この二次災害に関して記述をしていきたい。
第二章 現代におけるソーシャルメディアとマスメディアの定義と役割
現代には、2つのメディアが存在すると考えられている。それが、ソーシャルメディアとマスメディアである。マスメディアとは、主に明治時期より発達し始めて、戦時中や戦後復興の際にも使用されたテレビ・ラジオ・新聞・雑誌といった大衆媒体の通称である。
一方で、ソーシャルメディアとは、ITが発達し始めた1990年代より活発になり、近年、急速に普及してきているパソコンやスマートフォンのことを指す名称である。
その特徴としては、以下の点に分けられる。
マスメディアの特徴(ポジティブ面)
- 大量発行による情報発信
マスメディア(テレビ/雑誌/ラジオ)とは1度に多くの人に対して訴求をすることができる
- 情報収集に基づいて発行されるため正確性が高い
コンプライアンス等があるためマスメディアは容易な発言をできない。ある程度の質を担保された情報が発信される。
マスメディアの特徴(ネガティブ面)
- 一方通行による情報の発信(ユーザーとの連絡を行うことはできない)
発信元のマスメディアと相互での対応はできない
- 情報発信までの所要時間が長い
得た情報をすぐには提供できないため、災害時などの一瞬を争う状況に弱い
ソーシャルメディアの特徴(ポジティブ面)
- 情報を迅速に伝えることができる(リアルタイム性)
誰でもいつでもどこでも発言ができるため、情報の速度は圧倒的に早い
- お互いに情報を共有することができる(インタラクティブ性)
SNSにはリプライという機能があるため、お互いの情報を交換することができる
- 拡散されるまでの所要時間が短い
見たものをすぐに発信できる
ソーシャルメディアの特徴(ネガティブ面)
- 誰でもどこでも情報発信できるため情報の正確さに問題あり
悪意の有無にかかわらず、情報が正確である可能性は図れない
- デマなどによる誤った情報によって左右されることがある
誰でも発言ができることから信ぴょう性は低い
以上のように、マスメディアとソーシャルメディアには、良い点・悪い点が存在する。
実際に、東日本大震災や熊本震災を見てみると、お互いの良い部分と悪い部分が如実に表れていた。
例えば、マスメディアでは、発信の速度が遅すぎるため、時間単位で情報を更新する必要性がある、食料/飲料水などの配給情報、また、ケガや病気をしてしまった緊急度の高い情報や行方不明の少年の身元などの連絡手段とはなりえない。
一方で、SNSでは、そもそも配信の難しい内容がある。つまり、人の住所/生年月日を配信することは、それだけでプライバシーの侵害になりえる。また、誰でも発信できるということは、そもそもその情報が正しいのかどうか、という点で信用に足らない。
しかし、この2つのメディアの良い点と悪い点をかけ合わせることで、二次災害に対応するネットワークを作ることができるのではないか。
そう思い、以下の段落では、実際に取り組まれている、マスメディアでの災害予防/ソーシャルメディアでの災害予防/両者を組み合わせた事例を紹介していきたいと思う。
第三章 過去の震災時に起きたソーシャルメディアの活用例
ここでは、東日本大震災でソーシャルメディアが活用された例を、紹介したいと思う。主に、震災で活躍したソーシャルメディアのアプリとしては、TwitterとFacebookである。この2つのアプリは、若者を中心に多くのユーザーがおり、震災時にとても役に立った。
インフルエンサーの存在
インフルエンサーとは、influence(影響を与える)からとられているもので、主に、著名人や公式アカウントといった、フォローの数と比較してフォロワーの数が圧倒的に多いアカウントを指す。
近年では、その情報伝達をうまく行うことができる点などを活かして、主に、広告ビジネスなどにも登場する、アカウントが10000人を超えるユーザーである。
東日本大震災の時には、堀江貴文氏や津田大介氏というような著名人が、安否を確認したい人の情報を手に入れる(後述するがおもにハッシュタグという機能で調べることができる)。
そのあと、そのインフルエンサーのフォロワーネットワークに対して、安否確認などの情報を、フォロワーから集めて再発信することで、多くの人に情報を拡散することができた。
熊本地震の際には、大西一史市長が震災が起こった後、インフルエンサーとして活躍をした。具体的には、地震後に水道管等の断裂が発生したあと、水不足で悩む県民の為に水道管が断裂しているポイントをSNS(Twiiter上)で募集をして、すぐに復旧作業に取り掛かるということを行った。
Googleのパーソンファインダー
ここではおもにWeb/ソーシャルメディアでの情報を提供/獲得する事例を紹介したい。
大手情報検索エンジンサイトGoogleが、パナマ沖震災の時に開発したサイト。現在、グーグルは、全世界で最もユーザーが活用するITサービスであり、その膨大なデータベースには、年齢/職業/性別/おおまかな住所などを特定することができる。(Cookieと呼ばれるサービスでその人物が訪れたサイトなどから、その人にとって必要な情報を如何に最適化して届けるかを分析している)
つまり、スマートフォンやパーソナルコンピュータを通して、所有者の人物を特定することができるということだ。そのため、情報を入力することで、災害時にその人の安否を確認することができる。
具体的なサービスとしては、検索ページに①人を探す②安否情報を提供するという2つのタブがあるため、そちらに情報を提供する/そこから情報を獲得するという仕組みである。名前を記入するだけで情報を得ることができるのは、非常に簡易的、かつ、わかりやすい仕組みであると思う。

出所:・・・・
また、グーグルは、全世界に数多くのユーザーを持ち、世界各国の言語に翻訳されていて、アクセスもスムーズで、東日本大震災の時も大いに役立った。(国内外の人を問わず、情報にアクセスできるため、例えば海外から留学してきた人の安否を海外にいながらすることができるなど)
第四章 緊急地震速報の情報拡散方法
ここでは、政府が行っている緊急地震速報の方策を確認したい。
理由は、災害対策を行っている政府が、どのような方法で災害時に人に情報を届けるのか、また、その情報の精度などはどのように担保をしているのか、を確かめる為である。
緊急地震速報とは、政府が行う巨大地震が起こった際の情報拡散システムである。
「地震が発生すると、震源からは揺れが波となって地面を伝わっていきます(地震波)。地震波にはP波(Primary「最初の」の頭文字)とS波(Secondary「二番目の」の頭文字)があり、P波の方がS波より速く伝わる性質があります。一方、強い揺れによる被害をもたらすのは主に後から伝わってくるS波です。このため、地震波の伝わる速度の差を利用して、先に伝わるP波を検知した段階でS波が伝わってくる前に危険が迫っていることを知らせることが可能になります。」(気象庁緊急地震速報より)
この測定方法で大規模な地震が予測された場合、以下の方法を活用して国民に広めることになる。
国土交通省気象庁が行うシステム。震度4以上の震災を感知したとき、パソコン・携帯電話に地震発生を伝えるメールを自動的に送る。携帯電話ではau・docomo・ソフトバンクの大手三社が参加しており携帯電話を持つ人々には確実に情報発信することができる。
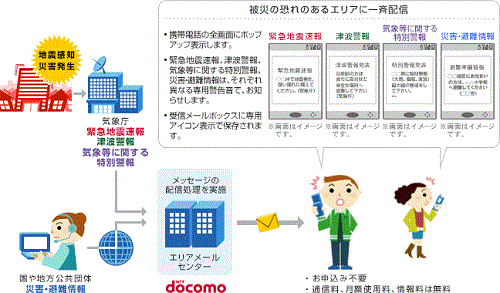
出所:docomoホームページ(https://www.nttdocomo.co.jp/service/areamail/)
上の図のような形式で行われている。気象庁の感知器で地震を感知すると、エリアメールセンターに情報が行き、そこから各個人へ情報が伝わるようになっている。
つまり、国が情報元として正確なデータを導く、その後は、民間の情報伝達機能を使うことで、広く国民に届ける事を可能にしている。
現在では、これがau・docomo・ソフトバンクの3社の携帯キャリア・テレビなどが担っているが、それでは災害時の全ての人に情報を届けることはできない。
災害時に電波などが届かない状況になった際には、誰も確認することができないからだ。しかし、この方法は、とても参考になる。さらに、このような状況をまねることができればよいのではないかと思い、このエリアメールセンターのようなものを作ることができれば、より情報の伝わりが早くなるのではないかと考える。
第五章 ソーシャルメディアとマスメディアの融合
UstとNHK
Ustとは、ニコニコ動画のようにストリーミング放送(簡単にいうとライブ動画)を行うことのできるシステム。ストリーミング放送というのは、動画や音声を一部受信して、その受信したものから、どんどん流していくという放送方法のことで、音声や動画をほぼ同時刻に流すことができる、というメリットがある。
東日本大震災の時に、ある少年がテレビのNHK放送に映っていた津波の映像を、そのままUstに流したことで、ほぼ同時刻に、東北地方で起きていた津波や震災の映像を日本各地や世界各地に放送した。それを受けたNHKは、その少年の行動を引き継ぎ、ストリーミング放送を続けた。
これによって、世界中に東日本大震災の惨劇を、ほぼリアルタイムで提供した事例である。これは、ソーシャルメディアのリアルタイム性と、マスメディアの信頼度の高い情報とを、組み合わせた事例だと思われる。
特務機関NERV
特務機関NERVとは、もともとは新世紀エヴァンゲリオンに登場する機関。その機関名を使った、Twitterのアカウントがある。
そのアカウントは、先ほども述べた、緊急地震速報や気象庁の災害情報を、そのままツイートすることで、たくさんの人に情報を拡散することができる。2017年2月6日現在で、約40万人のフォロワーが存在しており、一度のツイートで40万人に情報を拡散することができる。
さらに、Twitterには、リプライと呼ばれる返信機能も存在するため、この特務機関NERVは、インタラクティブ性・リアルタイム性とマスメディア融合事例だと思われる。
第六章 この研究における重要な課題点
SNSやWebを用いて二次災害を予防することには、大きく2つの問題がある。
1つ目は、プライバシーの問題である。
現代のSNSなどでは、その匿名性から、あることないことを記述して広めることすら可能となった。つまり、全国全ての人が、情報を発信できるのである。とくに、緊急度の高い災害時において、悪意の有無にかかわらず、発信した情報が人の人権を侵害することにもなりかねない。
例えば、熊本県の事例では、震災後の仮設住宅の前にたくさんの報道陣が群がり、その様子を伝えようとした。また、急病者/身元不明な子どもの情報を、WebやSNS上に書き込みをする事は許されるのか。通常時では非難されることではあるが、これが、プライバシーの問題と如何に折り合いをつけるのか、が1つ目の問題である。
2つ目は、情報の精度の問題である。
災害時によく見られた○○の地域に水や食料がありますという情報。これ自体をつぶやく人に悪意はない。しかし、この情報が正しくまた普遍的なものではないため、時にその情報は嘘にすらなりえる。緊急事態に如何にこの情報を精査するのかが、問題として挙げられる。この嘘が浸透すれば、関東大震災の時に韓国人が井戸に毒物を入れたなどのような虚偽情報にさえ、人は真偽を確認なければならない。以上が2つ目の問題である。
第七章 重要な課題点に対する政府の見解と対応策
以上の2つの問題を解決することで、この施策は解決される。
プライバシーの権利
まずは、1つめのプライバシーの権利である。
災害時における主なプライバシーの権利としては、①人権侵害②プライベートの発信③個人情報の発信の3つである。
①例えば、民間のテレビや新聞会社が、被災地の仮設住宅を訪れて、写真を撮ったり動画を回したりしていることで、人々の生活に影響を与えてしまうなどがある。
②また、仮設住宅内で人の個人情報や生活環境をSNSなどに投稿する人がいるがその対策をどのようにするのか
③例えば、急病者が出たさいに、家族はその情報を提供することができる。しかし、民間企業はそれをできるのか、さらには、友人はそれをできるのか、が議論になるかと思う。
その中で、私が今回研究している災害時に、傷病者などの手当てを行うためのネットワーク作成は、③に該当するのではないかと思う。そこで以下では③に絞って研究を進めることにする。
様々な文献を調べた結果、大きく3つに分類をされることがわかった。地方自治体/法人格/個人である。
地方自治体では“町内会が名簿を作成・共有することで、災害発生時等の緊急時に身体の不自由な方、介護を要する方などの避 難誘導を適切に行うことが可能である。”(改正個人情報保護法の概要と 災害・危機管理対応より)という個人情報保護法の観点から情報を提供することができる。
次は法人格に関してであるが、“JIS Q 15001のA.3.4.2.8(個人データの提供に関する措置)の例外事項 g)に規定されている“A.3.4.2.3(要配慮個人情報)のただし書きb)”に該当する”(一般財団法人日本情報経済社会推進協会より)から災害時のデータとして活用することができる。
しかし、様々な文献を探しても、このような場合に、とある個人が救急隊などに調べるために、個人情報をSNS等に活用することができないということである。この施策を検討するにあたり、やはり家族が基準となる場合が多い為、家族が提供をするのが筋ではないかと考える。
情報の精度
次に、2つ目の情報の精度であるが、こちらも非常に重要な問題である。
総務省のデータによると、日本では、マスメディアを信用し、SNSやWebの情報は信頼しづらいという傾向にある。そのSNSやWebを使用する本政策提言では、この問題は回避できない。さらに日経新聞の調査によると、災害時には86%の人がSNSを活用するということだ。つまり、信用できないと思いながらも、100人に86人は使用することになる。
これに対して、政府は、「dissana」というシステムを作成した。これは、簡単にいうと、Twitterにある災害時の情報を全て拾い出し、そこから情報の精査を行う。例えば、熊本県であった動物園からライオンが逃走した、のような案件では、デマツイートに対してそのデマを否定するツイートもある。
このデマ/事実のツイートを見極めて、正しい情報を提供するという方法である。個人がツイートをすることができるため、Twiiterには多くの情報が集まる。そのメリットを活用した情報の精査方法である。これは非常に役立つ方法であると考え、非常に参考になる。
第八章 その他災害に関連する対策を行うステークホルダー
その他にも、このような災害時に、活用できるサービスが存在した。
例えば、「eST-aid」と呼ばれる災害時の医師/薬局会と連動したサービスである。
災害時の緊急診療所で、医師/看護師/薬剤師またはその治療に必要な器具や道具などが不足した場合、その地方自治体を経由して不足した部分を補うことができる、というサービスである。こちらは、Webこそ使われていないものの、非常に様々なステークホルダーが融合した事例である。
また、「SNSダッシュボード」と呼ばれる自分が持つSNSアカウント(Twitter/instagram/facebookなど)を同時に見ることができるサービスも存在する。このサービスを活用することで、自分自身でも、この情報が正しいものなのかをセルフチェックすることができる。
また、最後の政策提言にもつながるのだが、「Bousai Tech」というWebメディアについて紹介したい。これは、災害時に役立つ情報のまとめ記事と、自治体の災害時に役に立つコンサルをしており、このようなビジネスモデルが成立することで、二次災害予防がマネタイズする?ことができる。それによって、さらなる加速が期待できると考える。
第九章 政策提言
筆者は、この研究のゴールを「政府/マスメディア/ソーシャルメディアが融合した二次災害予防専門のメディア作成」にしたいと考える。この政策を提案するのには、3つのステークホルダーがお互いの強みを補強し、弱点を補いあうことができるからである。マスメディアの強みである情報の「精度」と、インターネットの強みである「速さ」を活用できる。それぞれがお互いの弱点であるため、信用に値するメディアができるのではないかと思う。これに加えて、政府の信頼と最先端のdisaanaのような政府の最先端のシステムを活用することで、今後のさらなる発展にも期待できる。そのためこの政策を提言する。
第十章 研究を通して感じたこと
この研究を通して、筆者は2つ目のことを考えた。
1つ目は、様々なステークホルダーがかかわりあう解決策が、非常に難易度が高いものであること。
2つ目は、全ての国民に対して、等しく情報を届けることが難しいことである。
1つ目、この政策は、国/民間企業/そして全ての国民など、多くの関係者によって成立する政策である。全ての国民を統制することが難しいように、全てのステークホルダーが、同じ論理で行動をするとは限らない。そこを解決する必要があると強く実感した。
2つ目、全ての被災者に、情報を届ける難しさである。例えば、災害時にスマートフォンを持ち忘れた人・お年寄りでそもそもスマートフォンを持っていない人・充電がなくなって確認ができない人。スマートフォン関連でも、これだけの条件で等しく情報を与えることができない。まして、緊急度の高い災害時において、これ以外の例外ケースが発生するのは間違いない。その場合に、如何にして情報を届けることができるのかは、必ず考えるべきであると思う。そして、最後になるが、この災害大国の日本において、毎年、何かしらの大規模災害が発生している。この研究が、その被災をされた人が二次災害に合わないような情報提供ができることを、こころより願い、この研究を終わりにする。
参考文献
Last Update:2019/01/31
© 2016 Naoki MIYAMOTO. All rights reserved.