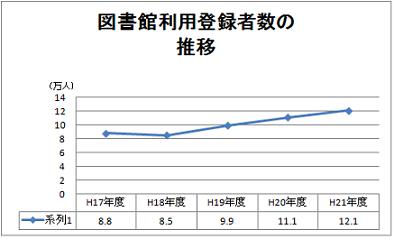【3】豊島区の事例
①豊島区の概要
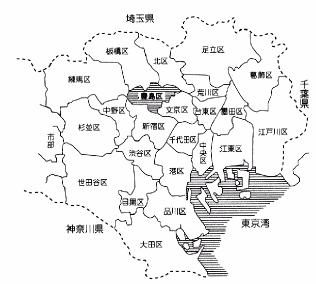
【豊島区地図:豊島区HP出典】
以下、豊島区HPより引用




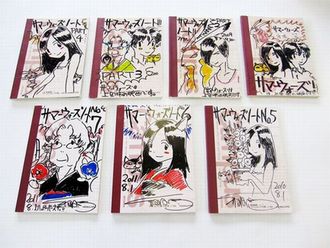
【3】豊島区の事例
①豊島区の概要
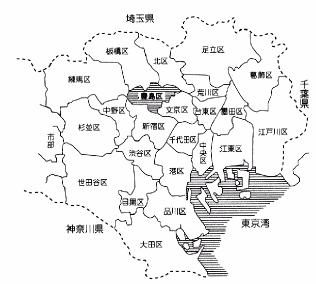
【豊島区地図:豊島区HP出典】
以下、豊島区HPより引用
【位置】 豊島区は東京23区の西北部に位置し、東は文京区、南は新宿区、西は中野区・練馬区、北は板橋区・北区に隣接しています。区の中央部は、東経139度43分、北緯35度44分にあたっています。
【地勢】 東西に6,720メートル、南北に3,660メートルと「鳥が羽を広げたかたち」をしており、東京湾の平均海面を水準として、高地が36メートル、低地が8メートルとおおむね台地状をなしています。
【面積】 面積は13.01平方キロメートルで、23区中18番目の広さです。 これは、東京都総面積の0.595%、区部面積の2.1%にあたります。
土地利用区分を立地条件や集積している機能などを考えて類型に区分し、それぞれに対応した地区レベルでまちづくりを進めていきます。
住宅地 ・ 商業業務地・都市型混在地の3つの類型に区分します。
さらに、商業業務地は以下の3つに分類できます。
(ア)副都心商業業務地
池袋駅周辺、サンシャインシティ及びその周辺で、広域的な商業・業務機能と副都心機能の拡充をはかる区域
(イ)地域中心商業業務地
目白、大塚、巣鴨、駒込の駅周辺で、商業・業務機能等の充実をはかる区域
(ウ)地区中心商業地
私鉄及び地下鉄の駅周辺で、住民の日常生活を支える商業・地域サービス機能の充実をはかる区域